
発売日: 2024年8月16日
ジャンル: インディーロック、ドリームポップ、フォーク・ロック、Y2Kリバイバル
⸻
概要
『This Is How Tomorrow Moves』は、Beabadoobeeが2024年に発表した3作目のスタジオアルバムであり、内省と希望、喪失と再生を行き来するような「移動」をテーマにした作品である。
これまでの彼女のキャリアは、ローファイなベッドルームポップから始まり、『Fake It Flowers』では90年代オルタナティヴ・ロック、『Beatopia』では幻想的な内面世界と、多彩な変遷を遂げてきた。その延長線上にある本作は、そうした音楽的実験を統合しながら、より成熟した視点から「変化」と「未来」を描き出している。
本作は、プロデューサーにRick Rubinとの共作で知られるJacob Bugdenを再び起用し、ミックスにはPhil Ek(Fleet Foxes, Band of Horses)が加わるなど、フォーク・ロックからY2Kポップ、ドリーム・サウンドまでを織り込んだ豊かなアレンジが特徴的。Beabadoobeeはこのアルバムについて、「今の自分の感情と、これからの私自身の予感を繋ぐ“地図”のようなもの」と語っている。
リリース当時、Z世代の不安やデジタル疲れ、エモ再評価といった文化的文脈とも共鳴し、批評家からは「もっとも人間らしいBeabadoobeeがいる」と高く評価された。
⸻
全曲レビュー
1. Take a Bite
鮮烈なオープニング。タイトルの“かじる”という行為は、未知の世界への一歩を象徴しており、リズミカルで鋭いギターがその決意を支えている。
2. California
流麗なストリングスとともに、喪失と旅の記憶を描くバラード。心の風景を地名に仮託する手法は、Joni Mitchell的でもあり、Beaの詩的進化を感じさせる。
3. The Things That Make You Beautiful
一見するとラブソングだが、実は自己肯定とセルフラブをテーマにした楽曲。シンプルなギターコードに乗る言葉が、聴く人の胸にじんわりと染み込む。
4. Ever Seen
エフェクトを抑えたボーカルと、ポストロック風のギターが特徴。誰かを“ちゃんと見た”瞬間の、静かな衝撃がテーマとなっている。
5. Take It Easy
Beabadoobeeらしい優しさに満ちたトラック。ベースラインとコーラスの絡みが、曲全体を“ゆったりとした運び”へ導いている。
6. Girl Song
友人やシスターフッドへのオマージュ。複数の女性ボーカルを重ねることで、“私たち”という連帯感を生み出している。
7. You’ll Be
Bea自身が「子どもの頃の自分に向けた歌」と語る。フォーク的な構成の中に、未来へのメッセージが穏やかに響く。
8. Flash Bang
最もロック色の強い楽曲。歪んだギターとドラムが“感情の爆発”を象徴しており、ライブでの定番曲となる予感を孕んでいる。
9. Post
SNSや手紙、言葉にまつわる現代的なテーマを扱った曲。ミニマルな構成が、言葉が届かないもどかしさを逆説的に伝えている。
10. When The Rain Falls
雨音のサンプリングが印象的な、アンビエント・フォーク的トラック。Beaの囁くような歌声が、聴く者を優しく包み込む。
11. Everything I Want
現実と理想のズレを描くメランコリックな一曲。ギターとピアノの掛け合いが、“揺らぎ”を巧みに演出している。
12. This Is How Tomorrow Moves
表題曲にしてアルバムの核心。静かな導入から徐々に盛り上がる構成は、まるで夜明けを迎えるような感覚を想起させる。未来への歩みを、“動き”として肯定する姿勢が眩しい。
⸻
総評
『This Is How Tomorrow Moves』は、Beabadoobeeの音楽的成熟を象徴する作品である。
感情の複雑さ、未来への不安、そして過去との和解。それらが全体を通して丁寧に織り込まれており、「移ろうもの」をそのまま肯定するような美学が感じられる。アルバムタイトルの“明日が動く”という表現は、未来は待つものではなく、自分で動かすものだという意思の表れとも解釈できる。
また、サウンド面でもベッドルームポップ、フォーク、ドリームポップ、ロックの要素が織り成すバランス感覚が秀逸で、Beaがどのジャンルにも還元されない独自の居場所を築きつつあることがよく分かる。
リスナーにとってこのアルバムは、“成長しながらも立ち止まることを恐れない”姿勢に、そっと寄り添ってくれるような存在になるだろう。何気ない日常の中で、自分の「明日」の歩き方を見つめ直すきっかけになるアルバムである。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Phoebe Bridgers『Punisher』
繊細なリリックと空気感のあるアレンジが、Beaの本作と響き合う。 - Big Thief『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』
フォークと内省、実験性のバランスが取れた名作。 - Alvvays『Blue Rev』
ギターポップと内向性の融合。『Take a Bite』などのトラックに通じるものがある。 - Boygenius『The Record』
友情、セルフラブ、自己理解といったBeaのテーマと地続きの女性的視点が印象的。 - Billie Marten『Drop Cherries』
自然との距離感、静けさの中にある感情のうねりが、『When The Rain Falls』などと共振。
⸻
歌詞の深読みと文化的背景
本作で特筆すべきは、「自己肯定」や「移ろい」に対する態度が、過去のBeabadoobeeよりも柔らかく、そして開かれている点である。
たとえば“Everything I Want”では、願いが叶わないことに対して嘆くのではなく、叶わないことすら人生の一部として受け入れていく視点が示されている。“You’ll Be”のように、自分の過去を癒そうとするアプローチもまた、Z世代が抱える「過去の自分との対話」文化の表出とも言えるだろう。
また、“Post”ではSNS世代の「言葉の行き違い」や「フィルタリングされた関係性」が扱われており、デジタルネイティブとしてのBeabadoobeeのリアリティが音と言葉の両方で表現されている点が興味深い。
このように、歌詞と音像、そしてBea自身の成長とリンクしたテーマ性が、本作の魅力をより深く支えている。


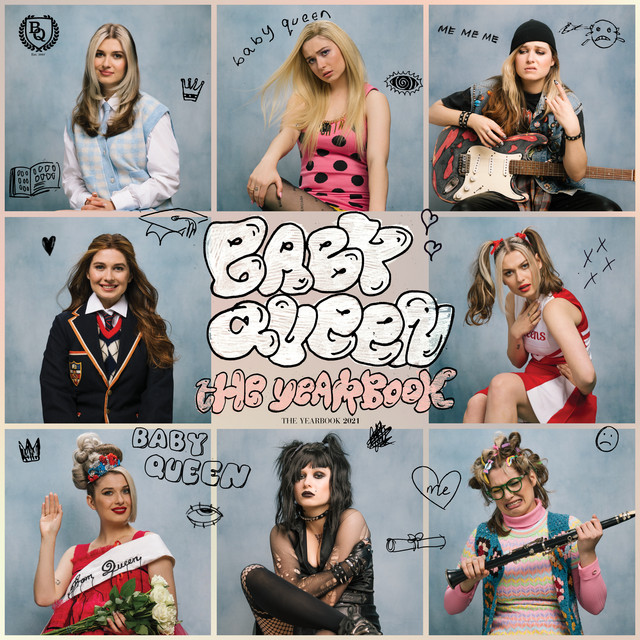
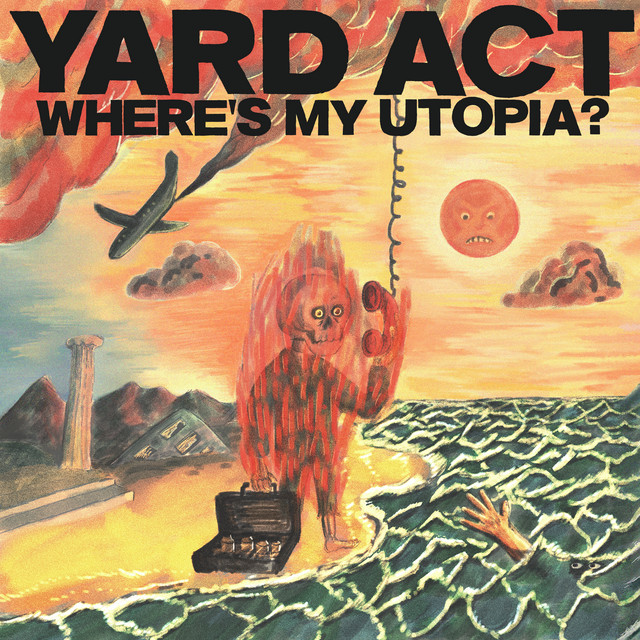
コメント