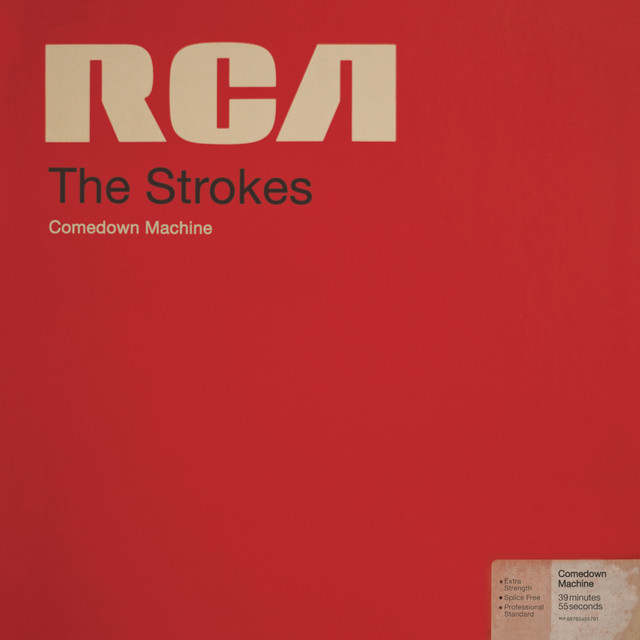
発売日: 2013年3月26日
ジャンル: ニューウェーブ、シンセポップ、インディーロック
バンドの名を伏せた匿名性の中で——欲望と疲弊、そのどちらでもない場所へ
『Comedown Machine』は、The Strokesが2013年に発表した5作目のスタジオ・アルバムであり、
前作『Angles』で顕在化した“分裂”と“再構築”の延長線上に位置する作品である。
特徴的なのは、その匿名性である。
ジャケットにはRCAのアナログテープ風デザインが施され、バンド名の表記も控えめ。
まるで“期待”や“神話”を拒否するかのように、The Strokesというバンドの名前そのものから距離を置いた構成となっている。
サウンドは80年代のニューウェーブ/シンセポップから強い影響を受けつつも、
それをノスタルジーではなく“冷たい質感”として現代に再構築している。
Julian Casablancasのヴォーカルも多くがファルセットやエフェクトで加工され、
“バンドが前に出ない”音作りが一貫している。
まるでポップとアンチポップの狭間に浮かぶ、奇妙に曖昧な存在。
それが『Comedown Machine』というアルバムの姿なのだ。
全曲レビュー
1. Tap Out
ファルセット・ヴォーカルとファンキーなギターが印象的なオープニング。
従来のStrokesらしさとは異なるが、洗練されたグルーヴが新しい。
2. All the Time
初期Strokesを思わせるストレートなガレージロック・ナンバー。
唯一と言っていいほど“いつもの彼ら”を感じさせる楽曲で、逆に浮いて聴こえるほど。
3. One Way Trigger
カサブランカスによるシンセ主導のメロディとファルセットが特徴の異色作。
まるで80年代のチープ・シンセポップとラテン調メロディの融合。賛否を呼んだ問題作でもある。
4. Welcome to Japan
エロティシズムと皮肉、クールさが混ざったナンバー。
「で、昨日は誰と寝たの?」というセリフ的リリックが耳に残る。
5. 80’s Comedown Machine
タイトル通り、80年代的美学の残響と虚無をサウンドで描いたようなバラード。
まるで深夜のテレビCMのような、冷めた夢のような雰囲気。
6. 50/50
アルバム中最も激しくノイジーなガレージ・ロック。
ラフなヴォーカルと歪んだギターが初期の衝動を呼び戻す。
7. Slow Animals
スロウコア的なテンポと、語りかけるようなリリックが印象的。
アルバム中でもっとも情緒的で、余白の多い一曲。
8. Partners in Crime
ニューウェーブのクールさを感じさせる、抑制されたポップ・チューン。
冷淡なメロディの中に仄かな熱が宿る構造。
9. Chances
ファルセットを多用した内省的ナンバー。
タイトル通り、失われたチャンスへの未練や諦念を漂わせる。
10. Happy Ending
アップテンポなリズムとノスタルジックなギターが交錯する。
ポップながらどこか儚く、まるで幸せの“後”を描いているような空気感。
11. Call It Fate, Call It Karma
アルバムの終幕に置かれた、夢のようなローファイ・バラード。
ジャズ的コード進行とアンティークな音像が、過去との和解を予感させる。
総評
『Comedown Machine』は、The Strokesがかつての“ロック・アイコン”としてのイメージから逃れ、
自らを匿名化し、実験的で匿名的な音楽へと向かった試みである。
この作品に“バンドの情熱”や“ライブの一体感”を求めると、拍子抜けするかもしれない。
だが、“音楽という商品”を冷静にパッケージングする姿勢や、ポップと距離を取る構えには、
現代的な潔さと皮肉が込められている。
『Comedown Machine』とは、“夢のあと”を描いたような作品だ。
すべてが終わったあとに、それでもなお音楽を鳴らすという選択。
そこには、過去にも未来にも属さない、今だけのStrokesが息づいている。
おすすめアルバム
-
Angles / The Strokes
本作の前作。バンドの分裂と再構築が始まった作品。音楽的流れをつかむうえで必聴。 -
The New Abnormal / The Strokes
次作。匿名性を脱し、成熟と回復を目指した傑作。『Comedown Machine』との対比が興味深い。 -
Room on Fire / The Strokes
初期の緊張感と疾走感を確認するならこちら。『Comedown Machine』とのギャップが明確。 -
Random Access Memories / Daft Punk
80sエッセンスの再解釈という点で共通するコンセプト・アルバム。 -
In Colour / Jamie xx
冷静で洗練された“夜のポップ”。『Comedown Machine』の内省性と美学を拡張したような世界観。


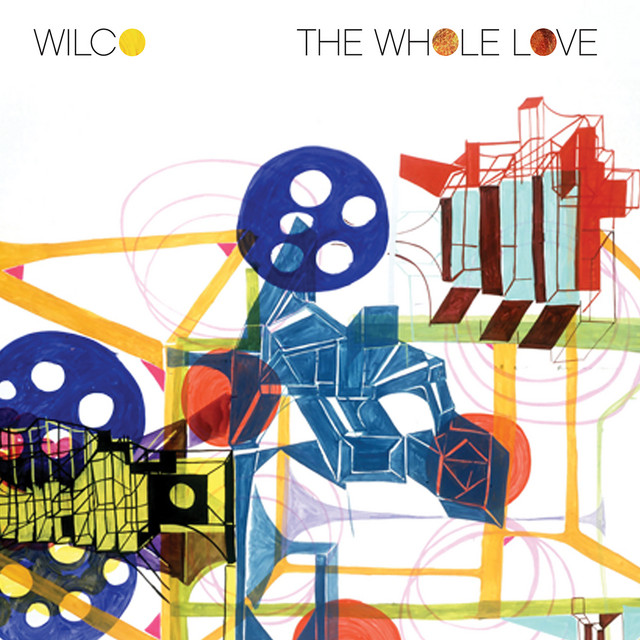

コメント