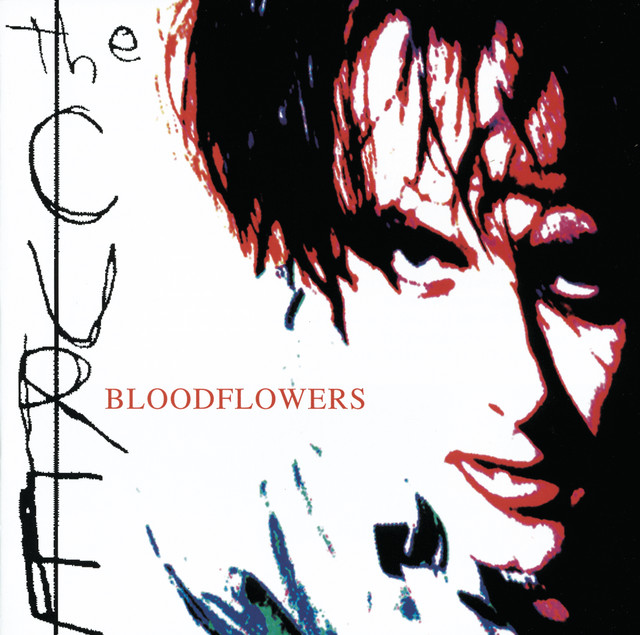
発売日: 2000年2月15日
ジャンル: ゴシックロック、オルタナティヴ・ロック、アートロック
時を超えて咲く“血の花”——終わりを受け入れるための音楽
2000年、The Cureは9作目となるBloodflowersを世に放った。
この作品は、ロバート・スミス自身が「Pornography(1982年)、Disintegration(1989年)と並ぶ三部作の完結編」と語るように、
内面の深い悲しみと崩壊を音として結晶化した“最後の叙情詩”とも呼べるアルバムである。
この時期のスミスは40代に差し掛かり、キャリアの総括的な位置にいた。
そんな中で彼が選んだのは、「現代的なエレクトロニカやリズムトラックの導入」ではなく、
むしろ時間の流れを否定するかのような、じっとりとした静謐と長尺構成だった。
ポップ性は抑えられ、感情表現は抑制され、代わりに広がるのはゆっくりと滲んでくる哀しみと、受容の静けさである。
このアルバムにあるのは、もはや嘆きではない。
終わってしまったものたちに、静かに祈りを捧げるような境地なのだ。
全曲レビュー:
1. Out of This World
ゆったりとしたテンポと、淡く重なるギターのレイヤーが、アルバム全体のトーンを決定づける。
「ここではないどこか」への憧れと別れの感情が、冒頭から静かに波紋を広げる。
2. Watching Me Fall
11分を超える大曲で、内的崩壊を壮大なスケールで描き出す。
愛と依存、自己否定が螺旋のように絡まり、ギターが断続的にうねる。
この“堕ちていく”というイメージが、アルバムの核心にある。
3. Where the Birds Always Sing
「鳥たちがいつも歌っている場所」——つまり、変わらない理想や自然への憧れ。
しかしスミスは、それがいかに幻想であるかを冷静に語り、あくまで現実にとどまろうとする。
4. Maybe Someday
本作では数少ないアップテンポのナンバー。
それでもポジティブさではなく、「いつかそうなれたらいいのに」という諦めと未練が主題である。
軽やかな響きの裏に、虚無が見え隠れする。
5. The Last Day of Summer
そのタイトルだけで、すでに切なさが漂う美しいスロウバラード。
過ぎ去った季節、過ぎ去った愛を悼むように、淡く霞んだ音像が広がる。
6. There Is No If…
語りかけるようなヴォーカルと、ミニマルな構成。
若いころの関係性や約束が、時の流れの中でいかに脆くなるかを描いている。
“If(もしも)”という言葉が意味を失う瞬間が、じわじわと迫ってくる。
7. The Loudest Sound
アルバム中でもっとも静かな曲の一つ。
だがその“静けさ”こそが“最大の音”であり、無言によって語られる別れの痛みが心に刺さる。
8. 39
本作で最もアグレッシブなトラック。
ギターが炎のように荒ぶり、内なる怒りと消耗が爆発する。
しかしそれは解放ではなく、やがて訪れる終焉への予兆に過ぎない。
9. Bloodflowers
タイトル曲にして、アルバム全体の精神を凝縮したような9分超の大作。
「花は咲き、枯れる。だからこそ美しい」という受容と赦しの物語。
スミスの声が、諦めと愛情を等しく内包しながら、静かに語りかけてくる。
総評:
Bloodflowersは、The Cureというバンドが「年齢を重ねること」「喪失を受け入れること」に真正面から向き合った作品である。
このアルバムにはヒット曲もない。
キャッチーなメロディもない。
だが、一人で過ごす夜、失った誰かを思い出す瞬間、人生が静かに過ぎていく実感の中でこそ、この作品は輝きを放つ。
スミスが語るように、これは三部作の終章であり、「死」ではなく「変化」を受け入れるための祈りなのだ。
音楽という形を借りて、ただ“それでも花は咲く”ことを信じるために。
おすすめアルバム:
-
Talk Talk / Laughing Stock
静寂と崩壊のあわいを描く、孤高のポストロック名作。 -
David Bowie / Heathen
喪失と成熟の中に祈りを込めた、後期ボウイの傑作。 -
The National / Trouble Will Find Me
人生の痛みを知る大人のための、繊細なモダン・ロック。 -
Sigur Rós / ( )
言葉を超えた感情を描く、北欧のポストロック幻想。 -
The Cure / Disintegration
本作と対をなす、若さゆえの破壊と祈りのアルバム。


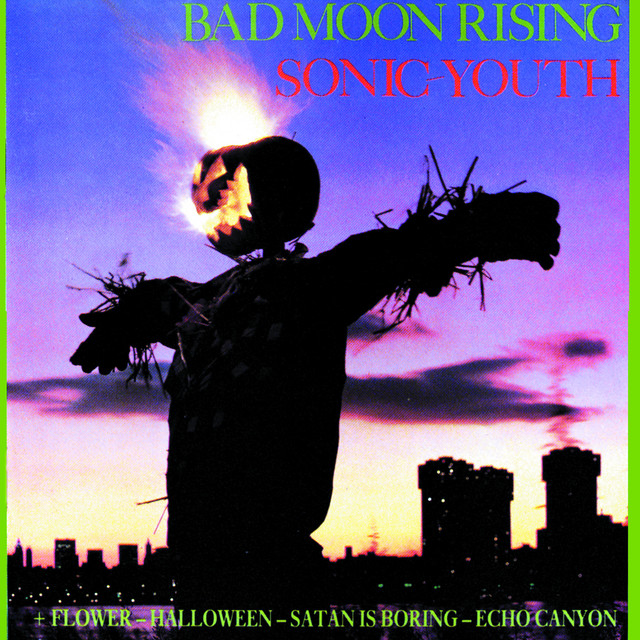
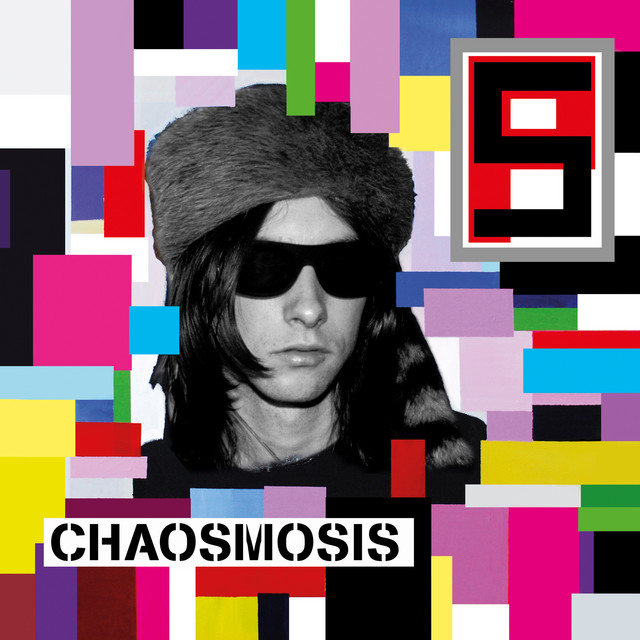
コメント