
発売日: 2018年2月9日
ジャンル: ダンス・ロック、アートポップ、ニューウェーブ
上昇し続けるという不穏な欲望——変容と継承の“新生フランツ”宣言
『Always Ascending』は、Franz Ferdinandが2018年に発表した5作目のスタジオ・アルバムであり、
ギタリストのニック・マッカーシー脱退後、初の新体制(5人編成)で制作された作品である。
タイトルが示すように、「常に上昇し続ける」という言葉には、
前向きさと不安、自己拡大の快感と限界の狭間にあるような、皮肉めいた二重性が漂っている。
音楽的には、従来のポストパンク/ダンスロックに加え、よりシンセティックで流麗なサウンドスケープが採用されており、
プロデューサーにはカサビアンやフィービー・ブリジャーズを手がけたPhilippe Zdar(Cassius)を起用。
クラブカルチャーとアートロックの美学を架橋するような、エレガントな進化を遂げている。
“失われたもの”の余白を、変容によって埋めようとする——
そんなバンドの姿勢が、全編に通底している。
全曲レビュー
1. Always Ascending
7分超えのタイトル曲で幕を開ける異例の構成。
ピアノとシンセの重なりが幻想的に広がり、
“昇るほどに不安定になる”という逆説的快楽がサウンドに宿る。
2. Lazy Boy
シンプルなリフと繰り返しのフレーズが中毒性を生む、ストレートなダンス・ロック。
「僕はレイジーなボーイさ」と開き直るようなユーモアが、裏にある空虚さを際立たせる。
3. Paper Cages
軽快なリズムの裏で、“紙の檻”という繊細なメタファーが語られる。
自由を手にしたと思った瞬間、それが幻想だったことに気づくような、現代的な閉塞感を描く。
4. Finally
「ついに分かったよ」というフレーズで始まる、軽やかな脱力ポップ。
その裏には、何かを“手遅れで理解する”という皮肉が潜んでいる。
5. The Academy Award
映画的スケールと甘美なメロディが融合した異色のバラード。
アカデミー賞=仮面と演技をめぐる、現実逃避とアイデンティティのドラマ。
6. Lois Lane
スーパーマンの恋人になぞらえたラブソング。
ポップな比喩を通じて、現代における男女関係やヒロイズムを再解釈する。
7. Huck and Jim
マーク・トウェインの小説『ハックルベリー・フィン』の登場人物を用いた社会風刺ソング。
アメリカ的価値観への揶揄と、旅というモチーフが交錯する異色作。
8. Glimpse of Love
ニューウェーブ感あふれるビートと、淡く甘いメロディ。
“恋の気配”にときめきながらも、それが蜃気楼であることを知っているような曲。
9. Feel the Love Go
フロア向けの強烈なファンク・ナンバー。
ホーンやシンセの重なりがゴージャスで、アルバム中最もグルーヴィな楽曲。
10. Slow Don’t Kill Me Slow
終幕にふさわしいスロウ・チューン。
“ゆっくり殺してくれ”というフレーズが示すように、快楽と死の境界線を漂うような、
耽美的で不穏な美しさを持つ一曲。
総評
『Always Ascending』は、Franz Ferdinandが“変化すること”そのものをテーマにしたようなアルバムである。
主要メンバーの脱退という危機を越えて、彼らは新しい構成と音の方向性を模索し、
その過程を“永遠の上昇”というアイロニカルな姿勢で音に刻みつけた。
サウンドは洗練され、演奏も引き算の美学に基づいて構築されており、
どこかクラブライクでありながら、同時に文学的な湿り気を残しているのが特徴だ。
“踊れるロック”というジャンルを深化させ、
理性と快楽の境界を遊ぶFranz Ferdinandは、
この作品において、“変わり続けるバンドの美学”を明確に示したのである。
おすすめアルバム
-
Everything Now / Arcade Fire
クラブ・カルチャーと皮肉を融合させたカナダ産アートロック。主題性とスタイルの共通点が多い。 -
Mirror Traffic / Stephen Malkmus and the Jicks
インディーロック的距離感と知性を感じさせる、軽妙な進化形。 -
Gone Now / Bleachers
80年代的ポップと現代的内省の融合。『Always Ascending』のロマンチシズムと響き合う。 -
A Brief Inquiry into Online Relationships / The 1975
現代の愛と孤独をテクノロジーの文脈で描く、ポストモダンなポップの傑作。 -
Sound of Silver / LCD Soundsystem
ダンスと内面の間で揺れる都市の肖像。Franz Ferdinandの目指す知的快楽の先輩格。


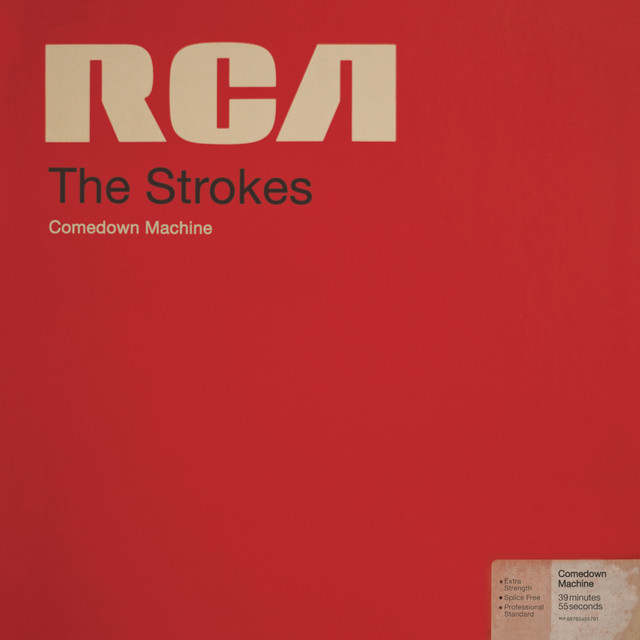
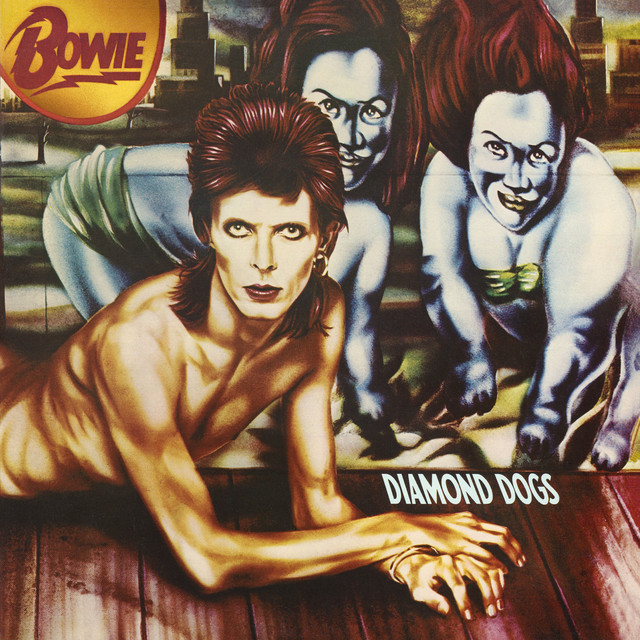
コメント