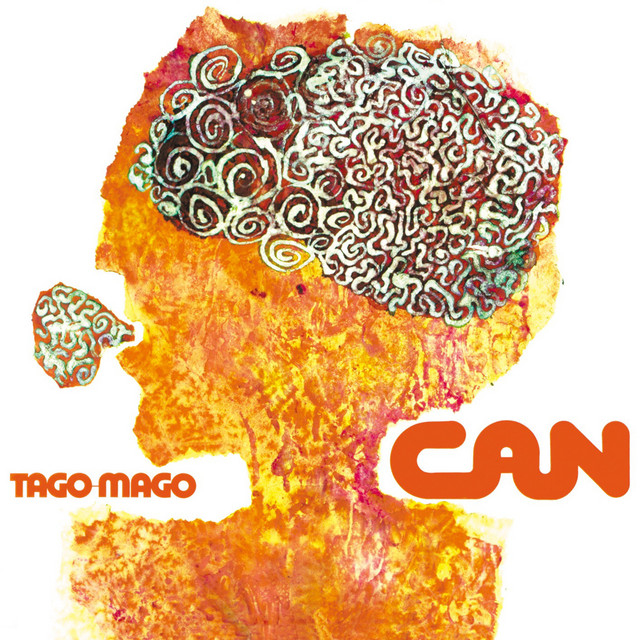
発売日: 1971年2月**
ジャンル: クラウトロック、アヴァンギャルド、エクスペリメンタル・ロック
音は崩壊し、再構築される——“Tago Mago”は異世界から届いた音響の魔道書
『Tago Mago』は、1971年にリリースされたCanの3作目のスタジオ・アルバムであり、クラウトロックというジャンルを決定づけ、後世の実験音楽すべてに影響を与えた伝説的作品である。
ドイツの小島“イビサのタゴ・マゴ洞窟”にちなんだタイトルには、“外界から隔絶された異界のような音楽世界”という意味が込められている。
この2枚組アルバムには、従来のロックの構造はほとんど存在しない。
代わりにあるのは、リズムの執拗な反復、非線形的展開、偶発性、そして音響による意識の変容。
ダモ鈴木による即興的な歌唱はもはや“ヴォーカル”という概念すら逸脱し、まるで音霊のように漂う。
Canはここで、“演奏された楽曲”ではなく、“生成される現象”として音楽を提示してみせたのだ。
全曲レビュー
1. Paperhouse
穏やかなイントロから始まり、徐々にテンションを上げていく構成。
ギターとベースが渦を巻き、ダモの声が霧のように現れては消える。
Canの“動的ミニマリズム”が確立された序章。
2. Mushroom
短い曲ながら強烈なインパクトを残す、呪詛のような一曲。
「I’m gonna give my despair to mushroom, mushroom, mushroom…」というフレーズが何度も繰り返され、聴く者の感覚を催眠に誘う。
3. Oh Yeah
テープ逆再生のようなイントロと、ファンクにも似たグルーヴが融合する不可思議なトラック。
ダモのヴォーカルは意味を超えて“音の質感”として響き、時間感覚を狂わせる。
4. Halleluhwah
18分を超えるアルバムの中核にして、Canを語るうえで避けて通れない大作。
ヤキ・リーベツァイトのドラムが永遠に回り続けるかのようなリズムを刻み、その上を各楽器が有機的に変化しながら漂う。
「ハレルワー」というフレーズの呟きが時に暴力的に、時に滑稽に繰り返され、無意識の旅路を導いていく。
5. Aumgn
『Tago Mago』の“アヴァンギャルド領域”への突入点。
19分に及ぶこのトラックは、もはや“楽曲”というより儀式的な音響空間そのもの。
断片的な言葉、地を這うようなベース、歪んだ残響——聴く者の精神を試す、音の迷宮。
6. Peking O
さらに狂気が加速する。
電子音とヴォイスマニピュレーションによる極端な分裂音響。
前衛ジャズ、ダダイズム、音響彫刻といったジャンルが交差する“カオスの実験室”。
ラスト近くで突如現れる狂ったピアノが、現実と幻想の境界を破壊する。
7. Bring Me Coffee or Tea
アルバムを締めくくるのは、意外にも静謐で内省的な一曲。
反復のなかに疲労感と祈りのような優しさが宿る。
旅を終えたリスナーにそっと現実への扉を開くような、脱力と余韻のフィナーレ。
総評
『Tago Mago』は、ロックの構造を破壊し、音そのものを“現象”として再構築した、前人未到の音響実験である。
この作品が示した“ロックの先にある何か”は、その後のポストパンク、インダストリアル、テクノ、ポストロック、アンビエントなど、あらゆる実験音楽の土壌となった。
ここにあるのは、ジャンルでも、曲でもない。
意識の変性装置、あるいは音の儀式——それが“Tago Mago”というアルバムなのである。
一度聴けば、あなたも戻ってこられなくなるかもしれない。
それでも、この“怪物の中の怪物”と対峙する価値は、確かにある。
おすすめアルバム
-
Faust『Faust Tapes』
編集と即興、構造破壊の美学が極限まで突き詰められたカルト作品。 -
Miles Davis『Bitches Brew』
ジャズの領域から音の解体と再構築を実践した先駆的エクスペリメンタル。 -
This Heat『Deceit』
ポストパンク時代の“Tago Mago的精神”を継承した唯一無二の音響。 -
Amon Düül II『Yeti』
サイケデリックと即興演奏が織り成す、もうひとつのクラウトの深淵。 -
Swans『Soundtracks for the Blind』
重厚で破壊的、そして精神的。Tago Mago以後の“音による叙事詩”。


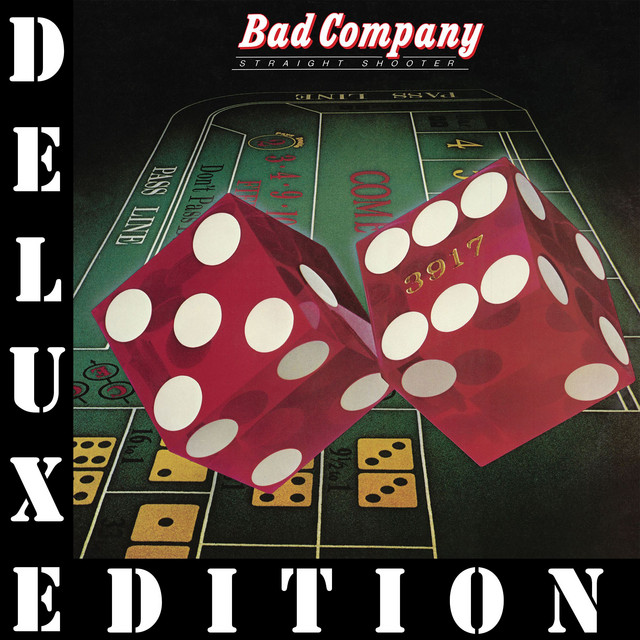
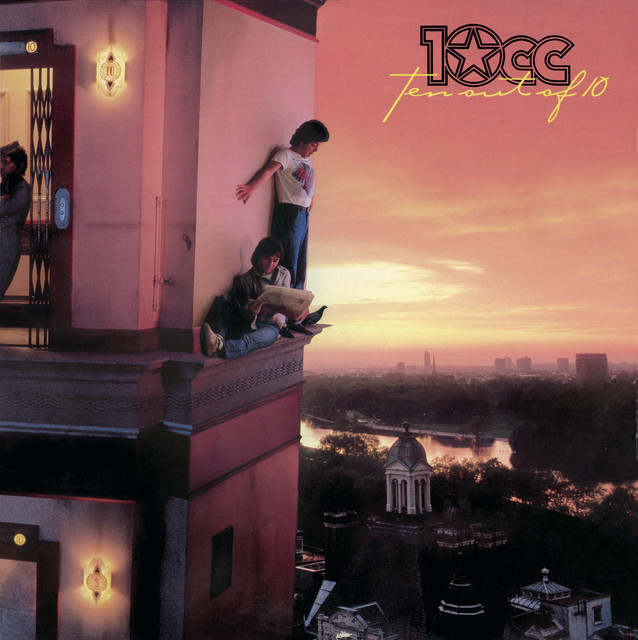
コメント