
発売日: 2022年10月21日
ジャンル: ポップ、ドゥーワップ、レトロ・ソウル、モダン・ポップ
- “昔の私を取り戻す”という再誕——ポップの原点回帰が未来を照らすとき
- 全曲レビュー
- 1. Sensitive (feat. Scott Hoying)
- 2. Made You Look
- 3. Takin’ It Back
- 4. Don’t I Make It Look Easy
- 5. Shook
- 6. Bad for Me (feat. Teddy Swims)
- 7. Superwoman
- 8. Rainbow
- 9. Breezy (feat. Theron Theron)
- 10. Mama Wanna Mambo (feat. Natti Natasha & Arturo Sandoval)
- 11. Drama Queen
- 12. While You’re Young
- 13. Final Breath
- 総評
“昔の私を取り戻す”という再誕——ポップの原点回帰が未来を照らすとき
2022年、Meghan TrainorはTitle以来となるドゥーワップ回帰のポップ・アルバムであるTakin’ It Backを発表した。
タイトルが象徴するように、本作は「過去の自分を取り戻す」だけではない。
それは、成熟した今だからこそ再び“初期衝動”を信じることができるという、
ポップ・アーティストとしての自己再発見の記録なのである。
Treat Myselfで示された自己ケアの姿勢はそのままに、
本作ではTrainorらしい色彩感とユーモア、そして“明確なメッセージ性”が復活している。
往年のMotownや60年代ポップを思わせるホーンやコーラス、
ファットなビートに乗せて、母であり、妻であり、表現者である“Meghan Trainor”の現在地が生き生きと描かれる。
全曲レビュー
1. Sensitive (feat. Scott Hoying)
アルバムの幕開けは、控えめでチャーミングなコーラス・ポップ。
“私は敏感な人間なんだ”という一言に、すでに本作のテーマが集約されている。
力強くなる前に、弱さを認めるという選択。
2. Made You Look
本作最大のヒット曲にして、ドゥーワップ・ポップ復活の狼煙。
鏡の前で自分を見つめ直し、視線を武器に変えていくプロセスが明るく軽やかに描かれる。
“ハイブランドより私のほうが視線を集める”という自信とユーモアの交錯。
3. Takin’ It Back
アルバムタイトル曲。自身のキャリア初期の音楽性と、
今のパーソナリティが自然に結びつくバランスの取れた一曲。
ここでの“Back”は後退ではなく、“再起動”を意味している。
4. Don’t I Make It Look Easy
華やかさの裏にある疲労とプレッシャーをポップに描いた名曲。
「簡単そうに見えるけど、実は必死なの」という、
SNS時代に響くリアルな叫びが、キャッチーなリズムと共に広がる。
5. Shook
60sファンク×TikTok世代的アティチュードの融合。
恋のときめきと身体的リアクションをコミカルに描写しながらも、
ポジティブなボディイメージが貫かれている。
6. Bad for Me (feat. Teddy Swims)
恋愛や人間関係における“優しい毒”をテーマにした、繊細なデュエット。
“君を愛してるけど、君は私に悪い”という逆説的な愛のかたちを、
スウィートなハーモニーで切なく包む。
7. Superwoman
母となった彼女の“戦う女性像”を、
自虐も交えつつ描いたリアルなフェミニン・アンセム。
誰かのために頑張る日々の中で、「私も私のヒーローでありたい」と歌う。
8. Rainbow
一転してピアノ主導のスロウ・バラード。
悲しみの後に虹がかかるように、回復と受容の詩が静かに広がる。
9. Breezy (feat. Theron Theron)
レゲエ調の軽やかなグルーヴが特徴。
一日中踊っていたいような、“心に風が吹く瞬間”の描写。
10. Mama Wanna Mambo (feat. Natti Natasha & Arturo Sandoval)
ラテン・フィーリング全開のダンス・チューン。
キューバの伝説トランぺッター、サンドヴァルの参加も話題に。
異文化へのリスペクトが感じられる華やかな一曲。
11. Drama Queen
セクシャルかつコメディカルな歌詞で構成された、ポップな風刺曲。
“ドラマクイーン”というラベルを、ポジティブに転換する試み。
12. While You’re Young
自分自身への手紙のようなバラード。
“若いうちに自分を信じること”の大切さを、
静かなメロディとともに丁寧に紡ぐ。
13. Final Breath
エンディングはまるで子守唄のような優しさに満ちている。
“最後の息”というタイトルにもかかわらず、
その歌声はむしろ「新しい朝」のように聴こえる。
総評
Takin’ It Backは、過去を懐かしむだけのアルバムではない。
それは“今の自分のために、あの頃の自分をもう一度信じてみる”という再出発の音楽である。
レトロなスタイルに立ち戻りながら、
現代的な感性と人生経験を加えた本作は、
ポップ・アイコンMeghan Trainorの成熟と再覚醒を高らかに告げている。
彼女の音楽は、外向きの“キラキラした自信”から、
内向きの“本当の意味でのセルフラブ”へと進化した。
そのプロセスを一緒に歩めるという点で、本作は極めてパーソナルであり、
そして同時に誰にでも響く普遍性を持ったポップ・アルバムなのだ。
“`
ご希望があれば、全アルバムのレビューをまとめた記事形式にも対応可能です。お気軽にお申しつけください。


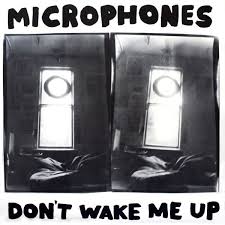

コメント