
発売日: 2020年4月17日
ジャンル: ポップ、オルタナティブR&B、ニューメタル、エレクトロポップ
『Sawayama』は、Rina Sawayamaが2020年に発表したフルアルバム・デビュー作であり、ジャンルの壁を超えた実験精神とアイデンティティの探求を融合させたポップ・ミュージックの革新的傑作である。
日本生まれロンドン育ちというバックグラウンドを持つRinaは、本作を通じて「東洋と西洋」「個と社会」「記憶と未来」といった二項対立の狭間を縦横無尽に駆け抜け、自身の内なる分裂と調和の物語を語っている。
アルバムには、プロデューサーとしてクラレンス・クラリティ(Clarence Clarity)を中心に、Danny L HarleやKyle Shearerなど新進気鋭の才能が集結。
ポップ、R&B、メタル、EDM、Y2Kリバイバルといった様々なスタイルを取り込みながらも、緻密な構成とサウンド・デザインによって「Rina Sawayama」というひとつの世界観へと統合されている。
本作は、音楽的な驚きに満ちているだけでなく、歌詞のテーマにおいても「家族」「帰属意識」「ジェンダー」「資本主義」など現代的かつ個人的な問題意識が通底しており、社会的なメッセージを内包した“ポップでありながら鋭い”作品として注目を集めた。
また、批評家やファンの間で大きな支持を受け、The GuardianやPitchforkなどの年間ベストに名を連ねるなど、グローバルな成功を収めたことでも話題となった。
全曲レビュー
1. Dynasty
ストリングスと歪んだギターで幕を開けるドラマティックな1曲。
家族のトラウマを引き継ぐ「王朝」というメタファーを使い、個人史と歴史の重なりを歌い上げる。
エモーショナルでありながら構築的な展開が見事。
2. XS
90年代のR&Bとニューメタルを融合させた代表曲で、資本主義批判をキャッチーに包んだアイロニックな楽曲。
“Excess(過剰)”をテーマに、欲望と贅沢への皮肉をビートとギターリフで表現している。
3. STFU!
ラウドロックとJ-POP的な甘さが交錯する挑発的なトラック。
アジア人女性へのステレオタイプや人種差別への怒りを、轟音と共にぶつける。
シャウトと囁きのコントラストが激しく、緊張感に満ちている。
4. Comme des Garçons (Like the Boys)
ディスコとヴォーグ文化を掛け合わせたクラブ・トラック。
「男性的な自信」を皮肉交じりに模倣し、ジェンダー観への挑戦を繰り広げる。
ファッションブランドの名を冠したタイトルも、演出として機能している。
5. Akasaka Sad
ロンドンの都会的サウンドと東京の郷愁が交差するミドルテンポのナンバー。
帰属意識の希薄さ、アイデンティティの分裂と孤独を歌った楽曲で、タイトルの「赤坂」が示すように、個人的な原風景が影を落とす。
6. Paradisin’
2000年代初頭のJ-POPやアニメソングを思わせるシンセポップ。
十代の反抗心と自由をテーマに、音楽的には遊園地のような楽しさとスピード感がある。
サックスのソロも印象的。
7. Love Me 4 Me
セルフラブをテーマにしたR&Bナンバーで、90年代のMariah Careyを彷彿とさせる。
“愛されるためには、まず自分を愛さなきゃ”という普遍的なメッセージが込められている。
8. Bad Friend
ピアノ主体のバラードで、友情の喪失と罪悪感をしっとりと描写。
東アジア的な旋律を思わせるスケールが入り込み、文化横断的なサウンドが強く印象を残す。
9. Fuck This World (Interlude)
重苦しいストリングスとともに世界への幻滅を語るインタールード。
短いながらも、全体の中で陰影と深みを与える重要な役割を果たしている。
10. Who’s Gonna Save U Now?
アリーナロックのようなスケール感を持ったアンセム。
自己救済と逆境からの復活を高らかに歌い、ライブでの高揚感を想像させる1曲である。
11. Tokyo Love Hotel
“東京”をメタファーに、消費される文化や愛について歌う。
メロウなサウンドの中に、観光的視点から見た日本への葛藤がにじむ。
12. Chosen Family
LGBTQ+コミュニティに向けた愛と共感のバラード。
生まれによらない「選ばれた家族」の存在を優しく描写し、共感の輪を広げている。
13. Snakeskin
クラシック音楽の引用と電子音が融合した終曲。
自らの「皮を剥がす」ことで再生しようとする姿を、音楽的にも破壊と再構築で表現。
混沌の中から静かに幕を閉じる。
総評
『Sawayama』は、単なる“ジャンルを横断したポップ”という枠を超えた、21世紀的アイデンティティの表現である。
その核心には、「境界を生きる者のリアル」があり、アジア系ディアスポラとしての視点、女性としての経験、クィアな感性などが複雑に編み込まれている。
特筆すべきは、Rinaのヴォーカルと演出力の振れ幅の広さだ。
ヘヴィなギターの上でシャウトしながら、次の曲では甘いトーンで繊細に囁く。
ジャンル的なスイッチの速さは、現代のリスナーの感覚に寄り添うものでありつつ、それを超えて“私とは何か”という問いを私たちに突きつけてくる。
サウンドプロダクションにおいても、ノスタルジアと未来性の絶妙なバランスが保たれており、2000年代初頭のY2Kポップの美学とポストインターネット世代の断片的な感性とが交差している。
それでいて、単なる引用やリバイバルにとどまらず、個人的・政治的な物語として再構築されている点に深い感動がある。
Rina Sawayamaという存在そのものが、ポップ・ミュージックの新たな地平を切り拓いていることは間違いない。
『Sawayama』はその始まりであり、世界と自分自身に問いを投げかける音楽の力を証明する一作である。
おすすめアルバム
- Charli XCX / how i’m feeling now
ジャンル横断的なエレクトロ・ポップの感性が近く、DIY精神にも通じる。 - Lady Gaga / Chromatica
ポップの王道と社会的メッセージを融合させた姿勢に共鳴する作品。 - FKA twigs / MAGDALENE
身体と感情、傷と再生をテーマにした実験的なR&B。表現のストイックさに共鳴する。 - Grimes / Art Angels
ジャンルレスで混沌としたポップ世界。ビジュアルと音の連動性も共通点。 -
Björk / Homogenic
アイデンティティと自然、テクノロジーの融合。孤高のポップを築いた先達。
歌詞の深読みと文化的背景
『XS』や『STFU!』に込められた怒りや皮肉は、アジア系としての体験に根差している。
とくに『STFU!』では、アジア女性に向けられるステレオタイプ(静か、従順、エキゾチック)に対する怒りが、ニューメタルの暴力性とJ-POPの可愛らしさを意図的に接続することで表現されている。
この組み合わせ自体が「あなたの思う“アジア人”はこれだろう?」という逆説的な問いを内包している。
また『Tokyo Love Hotel』では、観光的視線で消費される日本文化への違和感をメロウなトーンで描いている。
彼女自身が“日本人として見られず、ロンドンでも完全にイギリス人と見なされない”というアイデンティティの宙吊り感が、アルバム全体に濃厚に投影されている。
『Sawayama』というタイトルは、そのまま「名乗ること」であり、「名を取り戻すこと」なのだ。
このアルバムは、Rinaが自己を語るための“舞台”であり、同時に彼女が聴き手に向かって開く“語りの場”でもあるのだろう。


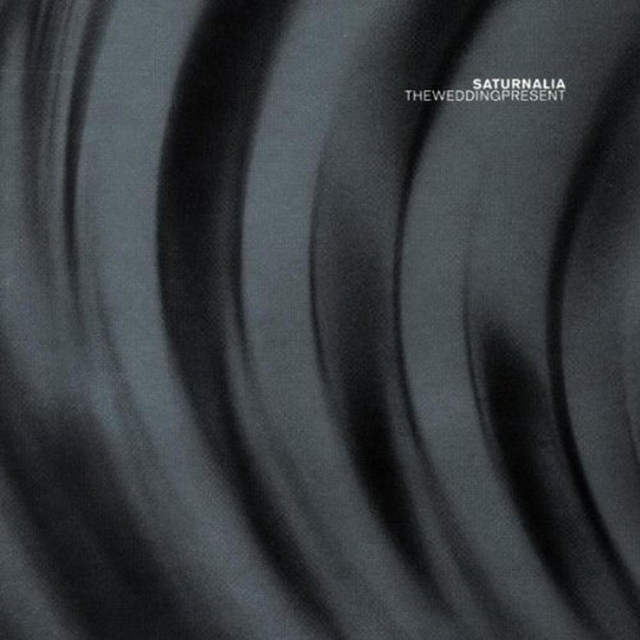

コメント