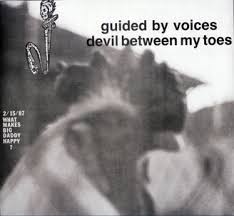
発売日: 1987年2月
ジャンル: ローファイ・ロック、インディーロック、エクスペリメンタル
ノイズと詩とフィードバック——“バンドごっこ”の果てに現れた地下の詩人たち
『Devil Between My Toes』は、オハイオ州デイトンの小学校教師だったロバート・ポラード率いるGuided by Voicesが1987年に自主制作した記念すべき1stアルバムである。
1,000ドル以下の低予算で録音されたこの作品は、後の“ローファイ・ムーブメント”の先駆けとなるものであり、
ガレージ、プログレ、ポストパンク、フォークがごちゃ混ぜになった混沌の音世界を展開している。
録音はメンバーの自宅やバスルームで行われ、雑音、テープヒス、アンバランスなミックスもそのまま収録。
だがそこにあるのは、音楽産業の外側で、夢と音楽に取り憑かれた人々の手作りの神話なのだ。
全曲レビュー
1. Old Battery
いきなりの雑音混じりのギターとエフェクト処理されたヴォーカルが、“まともな音楽”の枠を壊す。
再生と劣化、ノスタルジーと未来。まるで朽ちたバッテリーのように不安定で、しかしエネルギーを秘めたオープニング。
2. Discussing Wallace Chambers
タイトルからして謎めいた一曲。
不穏なテンションで鳴るギターとポラードの変則的なメロディが、言葉の意味ではなく響きの世界へとリスナーを誘う。
3. Cyclops
まるで未完成なまま放置されたデモテープのような音像。
だがそれがむしろ創造の瞬間の生々しさを焼き付けており、“一つ目巨人”という寓話的存在と共に何か原始的な感覚を喚起する。
4. Crux
バンドとしての“核=crux”を示すような、重く不穏なトーン。
ミニマルなアンサンブルが、内向的な不安と集中をもたらす。
5. A Portrait Destroyed by Fire
本作中もっとも“詩的”なタイトルを持つ楽曲。
フォーク的なコード進行に、朽ちていく肖像画のイメージが音に乗る。
Guided by Voicesの“言葉の異化作用”の萌芽を感じさせる瞬間。
6. 3 Year Old Man
荒々しいギターとエコー処理されたヴォーカルが混然一体となる、パンク的エネルギーの噴出。
実験性とナンセンスが共存する、最初期GBVらしさの結晶。
7. Hey Hey, Spaceman
どこかユーモラスでサイケデリックな浮遊感。
ローファイであることが、逆に宇宙的拡がりを持つアイロニカルなトラックへと昇華している。
8. The Tumblers
短くてリズミカル、まるでポラードのノートの切れ端をそのまま録音したような感覚。
“Tumblers”=回転する者たち、というモチーフが音の断片とシンクロする。
9. Bread Alone
宗教的なニュアンスを含んだタイトルとは裏腹に、音はほとんどノイズの海。
しかし、ローファイという形式が信仰と孤独の距離を逆説的に近づけている。
10. Contact High
最もポップでキャッチーな一曲。
だがGBVのこと、“高揚感”はすぐに反転し、幻のように消えていく。
総評
『Devil Between My Toes』は、音楽的完成度や録音の美しさを一切追求していない。
それどころか、音楽というものが“完成”していなくても成立し得るという、逆説的な強さに満ちている。
ロバート・ポラードの詞と声は、時に意味不明で、時に異様なほど叙情的。
それらがローファイという枠組みの中で“現実感”を喪失し、
むしろイメージと幻想の断片としてリスナーの脳内に焼きつく。
この作品を聴くことは、“ロックバンド”の物語ではなく、
音楽という概念の解体と再構築の物語に触れることでもある。
それはDIYでもあり、ノイズでもあり、詩の破片でもある——
Guided by Voicesは、ここからすべてを始めたのだ。
おすすめアルバム
-
『Bee Thousand』 by Guided by Voices
ローファイ美学の完成形。本作の精神的続編にして代表作。 -
『Alien Lanes』 by Guided by Voices
切れ味と断片性をさらに推し進めたGBV流ポップアート。 -
『Wowee Zowee』 by Pavement
ポスト・ローファイの金字塔。実験とポップの理想的衝突。 -
『We’re Only in It for the Money』 by The Mothers of Invention
ザッパ流の分裂的な美学と、DIY精神の始祖的存在。


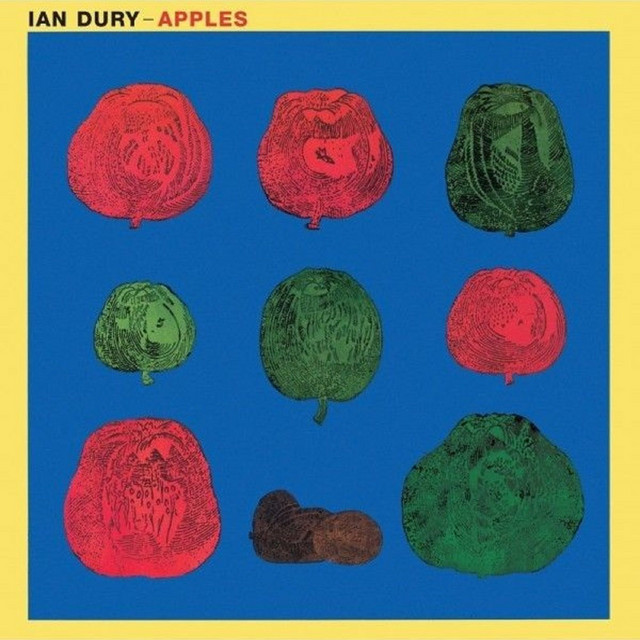
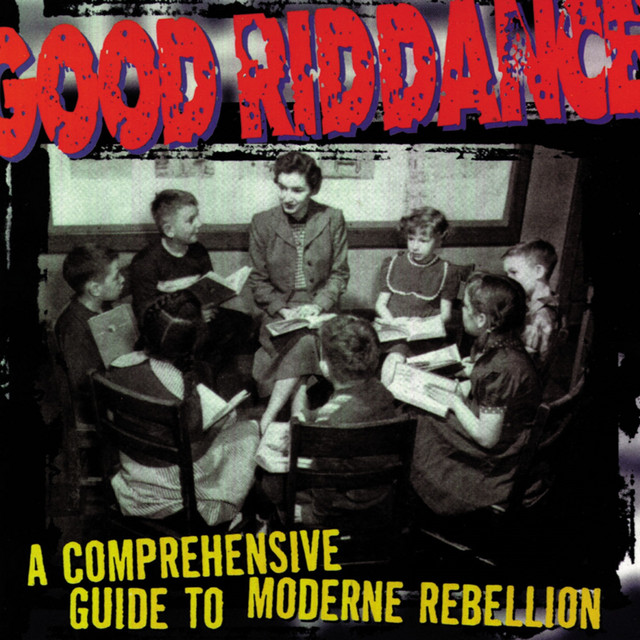
コメント