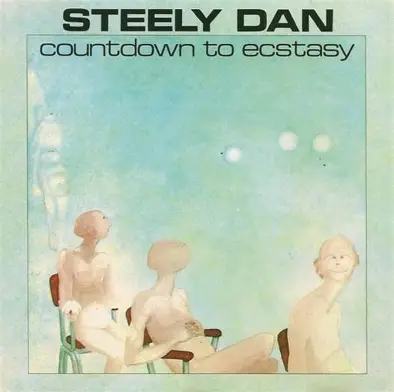
発売日: 1973年7月
ジャンル: ロック、ジャズ・ロック、ポップ
2. 概要
『Countdown to Ecstasy』は、アメリカのバンド Steely Dan が1973年に発表したセカンド・アルバムである。
デビュー作『Can’t Buy a Thrill』のヒットで一躍注目を集めた直後に制作された本作は、ポップス寄りだった前作から一歩踏み込み、ジャズ的な和声と複雑なアレンジを前面に出した “バンド時代の頂点” のような作品なのだ。
録音はロサンゼルスの The Village Recorder とコロラド州の Caribou Ranch を中心に行われた。
当時 Steely Dan はまだツアーを行う「実働バンド」で、ステージで鳴らせるアンサンブルをそのままスタジオに持ち込む、という発想で曲作り・アレンジが進められている。後年の “スタジオ完結型ユニット” へ移行する前夜の、バンドらしいダイナミズムが閉じ込められている点が本作の大きな特徴である。
また、デビュー時に一部のリード・ボーカルを取っていた David Palmer が脱退し、本作から Donald Fagen が全曲でリード・ボーカルを担当することになった。
ナイーヴさと毒気を同居させるFagenの声が、冷笑的な歌詞世界とジャズ・ロック寄りのサウンドに強く結びつき、のちの Steely Dan 像を決定づけることになる。
ただし商業的には、前作ほどのヒット・シングルを生み出せなかった。
「Show Biz Kids」や「My Old School」といったシングルはFMラジオで支持を集めたものの、全米アルバム・チャートは最高35位止まり。しかし批評家の評価は高く、のちに “必聴アルバム” の一枚としてたびたび挙げられるなど、再評価が続いている。
サウンド面では、ロックを軸にしながらもビバップに着想を得たソロや、テンションを多用するコード進行が印象的である。
リズム隊はタイトで音数が少なく、上に乗るギターやキーボードが緻密に絡み合う。
のちに “ヤット・ロック” と呼ばれる洗練されたAORの源流として語られるのも、こうしたジャズ的な語彙と、乾いたシニカルさが奇妙なバランスを保っているからだろう。
歌詞のテーマも、ラブソングにとどまらず、ショウビズ界の腐敗、大学キャンパスの混乱、ポスト・アポカリプス的な世界観までをさらりと描いてみせる。
アメリカ社会がベトナム戦争後の倦怠と不信感に包まれていた70年代初頭、その空気を直接的なスローガンではなく、皮肉と寓話に置き換えて提示している点で、本作は“時代の記録”としても機能しているアルバムだと言える。
3. 全曲レビュー
1曲目:Bodhisattva
アルバムの幕開けを飾るのは、アップテンポなブギー調のロック・チューン「Bodhisattva」である。
ギターが左右に飛び交い、ピアノも高速でフレーズを畳みかける、その勢いはジャズ・ギタリストのソロをロック・バンドで再現してしまったかのようだ。
歌詞では、東洋思想や悟りに憧れる西洋人の姿が、どこか滑稽なまでの熱狂として描かれている。
“悟りをもたらしてくれ” と必死に求めるが、その姿自体がすでに消費主義的であり、Steely Dan 特有のブラックユーモアが立ち上がってくる。
霊性への欲望と資本主義的欲望が、同じ場所でねじれていることを、痛快なロック・ナンバーとして提示したオープニングと言えるだろう。
2曲目:Razor Boy
「Razor Boy」は、パーカッションやビブラフォンが柔らかく揺れる、ラテン〜ジャズ風味のミディアム・チューンである。
エレキ・ギターよりもアコースティック寄りの質感が前に出ており、アルバムの中でひとつの小休止のような役割も果たしている。
しかし歌詞を追うと、老いと死、そしてお金ではどうにもならない不安が静かに語られていることに気づく。
タイトルに登場する “Razor Boy” は、時間や死のメタファーとしても読める存在で、どれだけ財産を積み上げても最終的にはすべて持っていかれてしまう、という諦念がにじむ。
穏やかなサウンドと、冷ややかなテーマのギャップこそが、この曲の不思議な後味を作り出しているのだ。
3曲目:The Boston Rag
「The Boston Rag」は、静かなイントロから、徐々にバンド全体が荒々しく立ち上がっていく構成が印象的な一曲である。
ジャジーなコード進行に乗せて、ギターがディストーションを効かたソロを繰り出し、AOR的な洗練とガレージ・ロック的なラフさが同時に存在している。
歌詞は、過去の学生時代や若気の至りを回想するような内容で、ノスタルジーと後悔が入り混じる。
当時のアメリカ東海岸の大学文化、薬物やアルコールにまみれた青春の記憶が、どこか距離を置いた語りで描かれる。
“あの頃” をただ美化するのではなく、むしろやり直しのきかない傷として振り返ることで、Steely Dan らしい冷静な視線が浮かび上がる。
4曲目:Your Gold Teeth
アルバム前半のハイライトとも言えるのが、「Your Gold Teeth」である。
6分台の長尺を使い、ジャズ寄りのコード進行とポリリズミックなグルーヴ、長めのインスト・パートが展開される。鍵盤とギターがソロを交換し合い、リスナーをじわじわとトランス状態へ誘うような構成である。ウィキペディア+1
歌詞には、ギャンブルやカジノのイメージ、運と確率、そして人間関係の駆け引きが重ねられている。
タイトルに登場する “金の歯” は、富や魅力、あるいは危うい誘惑の象徴とも読める。
人を惹きつけてやまない存在が、同時に破滅への入り口でもあるという、Steely Dan流の “甘くて苦い” 人間観察が表現されているのだ。
5曲目:Show Biz Kids
「Show Biz Kids」は、重たいビートとスライド・ギターがうねる、ブルージーなファンク・ロックである。
Rick Derringer によスライド・ギターが暴れ回り、コーラス隊の反復するフレーズが、退廃的な都会の風景を強調する。
テーマはタイトル通り “ショウビズ界の子どもたち”、つまり特権階級の放蕩息子・娘たちだと言える。
金とコネに恵まれ、労働と無縁の生活を送りながら、退屈しのぎに享楽を積み重ねる人々を、鋭い皮肉とともに描き出している。
当時のロサンゼルス音楽産業への嫌悪と諦めが、そのままリフになって鳴っているようにも聴こえる。
6曲目:My Old School
「My Old School」は、ホーン・セクションとピアノが躍動する軽快なロック・ナンバーで、アルバム随一のキャッチーさを持つ楽曲である。
しかし、その明るいサウンドとは裏腹に、歌詞は大学時代の大規模な薬物摘発をモチーフにしていると
キャンパスを襲った突然の逮捕劇、そこに絡む裏切りや政治的思惑を経験した語り手が、母校に対して複雑な感情を抱いている様子が伝わってくる。
軽快なメロディの裏で、権力と若者文化の衝突、60年代末から70年代初頭にかけてのアメリカ大学社会の混乱が暗示されている点が興味深い。
“懐かしのスクール・ソング” に聞こえながらも、実は苦い記憶の告白なのだ。
7曲目:Pearl of the Quarter
「Pearl of the Quarter」は、カントリーやニューオーリンズR&Bの要素を感じさせる、しっとりとしたミディアム・バラードである。
スライド・ギターの甘い響きと、ゆったりとしたグルーヴが、夜の街角のムードを丁寧に描き出す。uDiscover Music+1
歌詞に登場する “Pearl” は、フレンチ・クォーターの娼婦、あるいはバーで働く女性として描かれている。
彼女のもとに通う語り手は、そこに恋愛とも依存ともつかない感情を抱いており、どこか報われないロマンスとして物語が進む。
これまでの曲で見せてきた社会批評の鋭さとは少し違う、哀愁と優しさが同居する楽曲であり、アルバム終盤の大きな支えとなっている。
8曲目:King of the World
ラストを飾る「King of the World」は、未来の終末世界を舞台にしたディストピア・ソングである。
シンセサイザーとギターが絡むタイトなグルーヴの上で、核戦争後の荒廃した世界からラジオで呼びかけるような視点が描かれている。
新聞には暗いニュースばかりが並び、人々は暴力と犯罪に支配されている。
その世界で語り手は、もはや希望を見出すことすら難しい状況を淡々と報告するだけである。
アルバム全体を通じて描かれてきた、倦怠と腐敗、シニシズムの行き着く先を象徴するようなエンディングであり、1973年という時代の不安心理を鋭く反映した楽曲と言えるだろう。
4. 総評
『Countdown to Ecstasy』は、Steely Dan のキャリアの中でも特に “バンドらしさ” と “知性” が高いレベルで同居した作品である。
まだツアーを行っていた時期に作られたため、全曲がバンド・アンサンブルを前提に書かれており、後年の作品に見られるような、超分業化されたスタジオ・プロジェクト的な冷たさはまだない。
その代わり、ジャズ的なコードやリズムを駆使しながらも、ロック・バンドとしての勢いやアドリブ感が随所に残っているのが魅力である。
同時に、本作は Steely Dan が単なる “おしゃれなロック・バンド” にとどまらないことを示したアルバムでもある。
「Show Biz Kids」で描かれるショウビズ界の堕落、「My Old School」での大学社会への苦い視線、「King of the World」における終末的な世界観など、その歌詞は一貫して現実社会への不信とシニカルなユーモアを携えている。
それでも説教臭くならないのは、彼らがいつも人間の弱さや滑稽さを、どこか自分たち自身にも向けているからだろう。
同時代のアーティストと比べてみると、その独自性はよりはっきりする。
たとえば Pink Floyd がコンセプト・アルバム形式で社会や精神世界を描いたのに対し、Steely Dan は一曲ごとの短編小説のようなスタイルで人間ドラマを切り取っていく。
また、同じくジャズの要素を取り込んでいた Chicago や Blood, Sweat & Tears といったブラス・ロック勢に比べても、Steely Dan の音作りはよりミニマルで、フレーズやコードの “選び方” そのものにジャズの感覚を宿らせているのが特徴である。
のちの名作『Aja』や『Gaucho』では、さらに洗練を極めたAOR的サウンドへ到達するが、そこに至る途中段階としての『Countdown to Ecstasy』は、構造的にはすでにかなり複雑でありながら、演奏にはまだ生々しい熱量が残っている。
特に「Bodhisattva」「Your Gold Teeth」といった曲では、ギターやキーボードのソロが長く展開され、ライブ・バンドとしての瞬発力をそのまま封じ込めているように感じられる。
制作面でも、クリーンで歪みの少ない録音、音数を抑えたミキシングによって、各パートのニュアンスがはっきりと聴き分けられるよう設計されている。
全体のバランスは非常に整理されているにもかかわらず、どこか乾いた空気感があり、“完璧すぎるがゆえの冷たさ” と “バンドの熱” が同じフレームの中に同居しているのが面白いところだ。
商業的には前作ほどの成功を収めなかったものの、長い時間をかけて評価を高めてきたタイプのアルバムである。
“わかりやすいヒット・ソング集” ではないが、じっくり聴き込むほどに歌詞の伏線やアレンジの妙が見えてきて、リスナーの耳が育つほどに味わいが増す。
その意味で、『Countdown to Ecstasy』は Steely Dan 入門の次のステップとして、あるいは70年代ロックの中でも “知的なサウンド” を好むリスナーにとって、避けて通れない一枚だと言えるだろう。
現在でも本作が聴き継がれている理由は、時代性と普遍性の両方を備えているからだ。
70年代アメリカの倦怠や不信感という文脈を背景にしながらも、そこで描かれるのは、金や名声への執着、青春への後悔、権力への不信、そして世界の終わりへの怯え――どれも現代にも通じる感情である。
その感情を、ただ嘆くのではなく、ユーモアと高度な音楽性によって乗りこなしてみせるところに、Steely Dan の真価があるのだと思う。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Pretzel Logic / Steely Dan
本作の次にリリースされた3作目のアルバム。
ジャズ要素をさらに凝縮しつつ、よりコンパクトでポップな楽曲構成へと進んでいく、Steely Dan の “転換点” を知る一枚である。 - Can’t Buy a Thrill / Steely Dan
デビュー作にしてヒット・シングルを多数生んだ、よりポップ寄りのSteely Dan。
『Countdown to Ecstasy』との聴き比べによって、バンドがどのようにジャズ・ロック路線へ踏み込んでいったかがよくわかる。 - Aja / Steely Dan
1977年作。ジャズとポップの融合が極限まで洗練された、彼らの代表作。
『Countdown to Ecstasy』で見られたジャズ寄りの感覚が、ここでスタジオ精度の高いAORとして結実している。 - Silk Degrees / Boz Scaggs
西海岸のスタジオ・ミュージシャンを多数起用したAOR名盤。
洗練されたグルーヴと都会的なメロウネスは、Steely Dan のサウンドが好きなリスナーにも自然に響くはずである。 - The Nightfly / Donald Fagen
Steely Dan の中心人物 Donald Fagen のソロ・アルバム。
50年代アメリカ文化へのノスタルジーとハイエンドなサウンド・デザインが融合し、『Countdown to Ecstasy』で芽生えたシニカルな視線が、よりパーソナルで映画的な形で表現されている。
6. 制作の裏側
『Countdown to Ecstasy』の制作は、ツアーの合間にスタジオへ出入りするという、かなりハードなスケジュールの中で進められたと言われる。
まだバンドとして各地を回っていた時期だったため、ライブで鍛えられたアレンジを一旦スタジオに持ち帰り、そこからさらにハーモニーや構成を練り直す、というサイクルが繰り返されていた。
録音の中心となったロサンゼルスの The Village Recorder は、当時からジャズ〜ロックのアーティストが行き交うスタジオで、Steely Dan もその豊富な機材とエンジニア陣をフル活用している。
一方、「Show Biz Kids」のスライド・ギターはコロラド州 Caribou Ranch で録音されており、山間のスタジオで生まれた粗削りなテイクが、都会的なミックスの中にあえて残されている点も興味深い+
プロデュースは、以後も Steely Dan 作品を手がけることになる Gary Katz。
彼は、Walter Becker と Donald Fagen が持ち込む緻密なアイデアを整理しつつ、当時のロック・アルバムとしては異例なほど “抜けの良い” サウンドを作り上げた。
リズム隊をタイトに録り、必要以上にエフェクトで加工しないことで、ジャズ的なニュアンスを損なわないよう配慮されているのがわかる。
アートワーク面では、ジャケット・ペインティングを Donald Fagen の当時の恋人 Dorothy White が担当している。
抽象的な女性像と幾何学的なテーブルが描かれたシュールな画面は、アルバムの知的で少し不気味な世界観を視覚化したような印象を与える。
レーベル側は当初このアートワークを好まず、レイアウトを巡ってバンドと激しく対立したというエピソードも残っており、最終的には Becker と Fagen が校正紙を “持ち去る” 形で決着したと伝えられている
こうした制作の裏側を知ると、『Countdown to Ecstasy』は単なるジャズ・ロックの名盤というだけでなく、アーティストがレーベルの期待や時代の空気とせめぎ合いながら、自分たちの美学を貫こうとした記録でもあることが見えてくる。
8. ファンや評論家の反応
リリース当時、『Countdown to Ecstasy』は批評家から高い評価を受けたものの、シングル・ヒットが出なかったこともあり、セールス面ではやや伸び悩んだ。
前作でポップなヒット曲を期待していたレーベル幹部たちは、この知的で皮肉っぽい作品を前にして、露骨に落胆したとも伝えられている。
しかし時が経つにつれ、アルバム全体を通しての統一感やアレンジの完成度、ジャズとロックのバランス感覚が再評価されるようになった。
音楽誌や批評サイトでは、Steely Dan のディスコグラフィーを語る際に、しばしば本作を “隠れた最高傑作” と位置づける声も多い。
また、ロック史のガイドブックや「死ぬまでに聴くべきアルバム」リストにも選出されるなど、長期的な評価は確実に上昇している。
ファンの間でも、『Aja』『Gaucho』のような後期の完璧に磨き上げられたサウンドを好む層と、この『Countdown to Ecstasy』や『Pretzel Logic』のような、バンド感が残る時期を愛する層に分かれることが多い。
とりわけミュージシャンやエンジニアからの支持が厚く、「Bodhisattva」や「Your Gold Teeth」の構成、コード進行、ソロの組み立ては、現在でも分析の対象として語られている1
2020年代に入ってからは、高音質リマスターやアナログ盤の再発が続き、新世代のリスナーにも再発見されつつある。
ストリーミング世代にとっても、一曲ずつシャッフルで聴くより、アルバム通してゆっくり浸ることで良さが開く作品であり、“アルバム文化” の豊かさを伝える教科書的な一枚にもなっていると言えるだろう。
参考文献
- Wikipedia: “Countdown to Ecstasy”ウィキペディア
- Session Days: “1973 – Steely Dan – Countdown to Ecstasy”Session Days
- PopMatters: “Just Growing Old? Steely Dan’s ‘Countdown to Ecstasy’ at 50”PopMatters
- uDiscoverMusic: “Show Biz Kids: Steely Dan’s ‘Countdown To Ecstasy’ At 50”uDiscover Music
- Apple Music Album Description – Countdown to EcstasyApple Music – Web Player



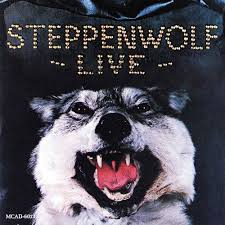
コメント