
発売日: 2022年7月15日
ジャンル: インディーポップ、ドリームポップ、フォーク、ネオサイケデリア
⸻
概要
『Beatopia』は、Beabadoobeeが2022年にリリースした2作目のフルアルバムであり、彼女自身が7歳の頃に想像した空想世界「Beatopia(ビートピア)」をコンセプトに描かれた作品である。
このアルバムは、前作『Fake It Flowers』での90年代オルタナティヴ・ロック路線から一転し、より内省的かつ幻想的な音像へと舵を切った内容となっている。BeabadoobeeことBeatrice Lausの音楽性は、単なるノスタルジーを超えて、ジャンルを横断する多層的な表現へと深化を遂げた。
本作では、ドリームポップ、ボサノヴァ、サイケデリック・フォークといった柔らかなサウンドスケープが中心となり、個人的なトラウマや成長過程、夢と現実のあわいを詩的に表現。参加プロデューサーにはJacob Bugden(Dirty Hitの若手プロデューサー)が名を連ね、現代のベッドルームポップ以降の文脈を保ちつつも、より緻密で洗練されたアレンジが施されている。
文化的には、Z世代特有の内向性と癒しへの希求を映し出す作品であり、特にパンデミック以降の「逃避としての音楽」の一つの到達点と位置づけることができるだろう。
⸻
全曲レビュー
1. Beatopia Cultsong
アルバムの扉を開く静謐な短編。タイトルは架空のカルト宗教風だが、実際には「自分だけの世界」への儀式的導入として機能している。
2. 10:36
スラップベースとエッジの効いたリズムが印象的な一曲。共同生活者との曖昧な距離感を歌ったリリックは、Z世代の人間関係の空気を如実に反映している。
3. Sunny Day
ボサノヴァの影響を受けた軽やかなグルーヴが特徴。心の曇りを「晴れの日」にたとえるリリックが、日常と非日常の境界線を溶かしていく。
4. See You Soon
LSD体験を元に書かれたと言われる一曲で、リリックには多幸感と不安定さが共存する。浮遊感のあるアレンジがその幻覚的な感情を増幅させる。
5. Ripples
アコースティックギターが主体の繊細なフォークトラック。心の波紋をテーマに、自己受容と変化のプロセスを静かに語る。
6. The Perfect Pair
ソフトなギターとストリングスが調和するドリーミーなラブソング。理想と現実のギャップを抱えながらも、相手との繋がりを肯定しようとする優しさに満ちている。
7. Broken CD
「傷ついたCD」が比喩するのは、繰り返す記憶や言葉の断片。Bea特有の壊れかけた美しさが、サウンドにもリリックにも滲み出ている。
8. Talk
アルバム中もっともロック色の強い楽曲。生き急ぐような日常とその反動の虚しさを描いたリリックは、『Fake It Flowers』の延長線にもある。
9. Lovesong
ストレートなタイトルとは裏腹に、リリックには「愛の不完全さ」が語られる。優しい旋律の中に、どこか諦念と祈りが共存している。
10. Pictures of Us
The 1975のMatty Healyが共作したことで話題に。エレガントで物憂げなアレンジと、過去の記憶を巡る内省的な歌詞が、極めて叙情的な空気を生み出している。
11. Fairy Song
子どもの空想世界のようなタイトルと裏腹に、夢と現実の境界が曖昧になるような不思議な音像。トリップ感と素朴さが同居する。
12. Don’t Get the Deal
エレクトロニックな要素が強く、Beabadoobeeにしては異色の構成。SNS時代の疎外感を反映したリリックが、冷たさと痛みを伴って響く。
13. tinkerbell is overrated
ジェンダー観や成長に対する複雑な想いを童話に仮託して描く曲。フェアリーテイルの終わり方を、別の角度から見つめ直すような内容。
14. You’re Here That’s the Thing
アルバムを閉じるにふさわしい、静かな希望を感じさせる曲。誰かが「いてくれること」そのものの価値を、Beaは素朴に、でも確かに歌い上げている。
⸻
総評
『Beatopia』は、Beabadoobeeの音楽的変遷を象徴する作品であり、90年代オマージュの枠を超え、彼女独自の「内的宇宙」を確立したアルバムである。
ビジュアル的な世界観や架空の地名を導入することで、まるで一冊のファンタジー小説のような連続性を持った構成となっており、Beaが自分の過去と向き合うための“再構築された夢”のようにも感じられる。
音楽的にはグランジやオルタナの荒さを抑え、より洗練されたポップス、フォーク、サイケデリックへと移行。音の密度は増しているが、空間的余白も丁寧に残されており、聴き手はまるで浮遊しているかのような感覚に包まれる。
Z世代の不安や孤独、他者との微細な距離感、そして「自分の物語を語る」ことの重要性が、本作では明確に可視化されている。それゆえ、本作はただの夢想的な作品ではなく、リスナーにとっての避難所ともなりうる力を持っているのだ。
Beabadoobeeの音楽は、進化と拡散の過程にある。『Beatopia』はその重要な通過点として、彼女の可能性をさらに広げていくであろう。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Clairo『Sling』
Bea同様、ベッドルームポップから内省的フォークへと移行した作品。癒しと孤独の質感が共通する。 - Mazzy Star『So Tonight That I Might See』
幻想的で幽玄なサウンドスケープ。『Beatopia』のドリームポップ的要素と響き合う。 - Faye Webster『I Know I’m Funny haha』
ゆるやかなリズムと感情の揺らぎ。Beaのソフトな表現と重なる感性がある。 - Men I Trust『Oncle Jazz』
ミニマルでチルな空気感。心の内側を音で表現するスタイルが共通点。 - The Japanese House『Good at Falling』
Beaと同じDirty Hit所属。透明感あるポップと内省的世界観の融合が秀逸。
⸻
ビジュアルとアートワーク
『Beatopia』のジャケットは、Beabadoobee自身が描いた幻想的な絵をもとにしたアートで構成されており、アルバム全体の「夢の中の世界」というテーマを視覚的にも体現している。
また、MVやライブパフォーマンスにおいても、「Beatopia」という概念世界を一貫して表現。ステージセットや衣装も、ファンタジーと内省性を融合させたビジュアルコンセプトで統一されており、視覚と音楽の両面から没入感を提供している。
この世界観の徹底が、Beabadoobeeというアーティストの信頼性と想像力の高さを象徴していると言えるだろう。


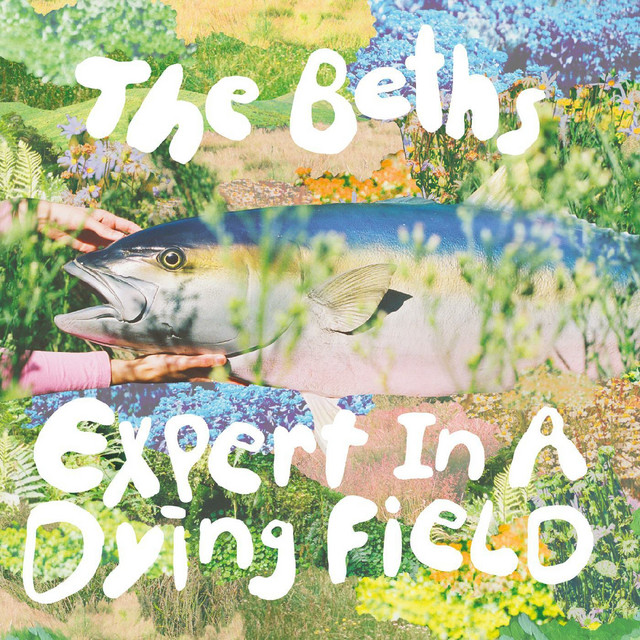

コメント