
発売日: 1976年5月31日
ジャンル: ジャズ・ロック、ファンク・ロック、ポップ・ロック
2. 概要
『The Royal Scam』は、アメリカのロック・バンド Steely Dan が1976年に発表した5作目のスタジオ・アルバムである。
前作『Katy Lied』で本格的なスタジオ専念体制へ舵を切った彼らが、その路線をさらに推し進めつつ、よりダークでギター主導のサウンドへ踏み込んだ作品なのだ。
録音は1975年11月から76年3月にかけて、ロサンゼルスのABCスタジオとニューヨークのA&Rスタジオで行われた。
ギターには Larry Carlton、Denny Dias、Elliott Randall、Dean Parks、そしてWalter Becker 自身が参加し、ドラムには Bernard “Pretty” Purdie や Rick Marotta、ベースにはChuck Rainey など、当時の超一流セッション・ミュージシャンが集結している。
その結果、本作は Steely Dan 作品の中でも「もっともギター色の強いアルバム」として語られることが多い。
サウンド面では、ジャズ・ロックの複雑なコードと、ファンク由来のグルーヴ、そして70年代中盤の硬質なロックの要素が混ざり合う。
『Katy Lied』での繊細でソフトな質感に比べると、リズムはよりタイトで、ギターは歪みを増し、全体にギラついた印象が強い。
同時に、アレンジやミキシングは従来通り緻密で、音数自体は決して多くないのに、情報量の多いサウンドスケープが構築されている。
歌詞世界はさらに一段ダークになり、麻薬王、武装犯、亡命的な移住者、観光客による“離婚ツーリズム”など、社会の裏側で生きる人物たちが次々と登場する。
アルバム・タイトルにある “Royal Scam(王家級の大ぼったくり/壮大な詐欺)” が示すように、本作は一枚丸ごと「搾取」「詐欺」「裏切り」といったテーマを変奏していくコンセプト・アルバム的性格を持っている。
全米チャートでは最高15位を記録し、のちにプラチナ認定を受けるなど、商業的にも堅実な成功を収めた。
ただし、シングルとしては「Kid Charlemagne」「The Fez」「Haitian Divorce」がチャートインしたものの、派手な大ヒットには至らず、当時のアメリカではやや“渋い人気”に留まった面もある。
一方イギリスでは「Haitian Divorce」がトップ20ヒットとなり、アルバム人気の牽引役となった。
2020年代に入ると、本作は高音質アナログやSACD、UHQRなどでリマスター再発が進み、改めて再評価されている。
『Aja』に代表される滑らかなAOR路線とは対照的に、『The Royal Scam』は“最もハードで毒の強い Steely Dan” を記録した作品として、コアなファンから熱い支持を集めているのである。
3. 全曲レビュー
1曲目:Kid Charlemagne
オープニングを飾る「Kid Charlemagne」は、ジャズ・ファンクとロックが高密度で融合した代表曲である。
Bernard Purdie のグルーヴィなドラミングと、Larry Carlton による名高いギター・ソロが、冒頭から最後まで緊張感を途切れさせない。
歌詞は、伝説的なLSD製造者 Owsley “Bear” Stanley をモデルにした人物の興亡を描いているとされる。
60年代カウンターカルチャーの頂点に立った“ドラッグの王様”が、時代の変化とともに逮捕され、役割を終えていく。
「お前は街でいちばんだった」というフレーズに込められた栄光と失墜のニュアンスは、サイケデリック時代全体の終焉を象徴するものでもある。
サウンドの面でも、フェンダー・ローズとギターが複雑なフレーズを投げ合いながら、緊張と解放を繰り返す構成は、Steely Dan のアンサンブル美学の到達点のひとつと言える。
アルバムの入り口にして、“The Royal Scam 的世界観” のすべてが凝縮された一曲なのだ。
2曲目:The Caves of Altamira
「The Caves of Altamira」は、ホーン・セクションとサックス・ソロが印象的なミディアム・チューンである。
柔らかいグルーヴと温かいコーラスが、どこかソウル〜R&B寄りの質感を生み出している。
歌詞のモチーフになっているのは、スペイン北部のアルタミラ洞窟壁画。
少年時代にそこを訪れ、原始の絵画に圧倒された語り手が、その後の人生で“あの瞬間”を繰り返し思い出す――そんな「記憶」と「喪失」の物語である。
Becker と Fagen は、この曲について「無垢さの喪失を描いたストーリー」だと語っており、子どもの驚きが、やがて世界の複雑さを知る入り口となる様を寓話的に描いているのだ。
穏やかな音像の裏側で、“Before the fall(堕落の前)” というフレーズが示すように、人類全体の原罪や文明の歩みさえも重ね合わせているように思える。
ポップで耳触りが良い一曲でありながら、Steely Dan らしい哲学的な深みを持つ楽曲である。
3曲目:Don’t Take Me Alive
「Don’t Take Me Alive」は、アルバム随一と言っていいほどロック色の強いナンバーである。
鋭いギター・リフとハードなビートが印象的で、「Steely Dan史上もっともハードロッキンな曲」と評されることもある。
歌詞は、爆弾を抱えた武装犯が警察に包囲され、「生きたまま捕まえるな」と叫ぶ一瞬のドラマを切り取っている。
彼は父親(あるいは“おやじ”と呼ぶ存在)を裏切り、もう後戻りができない地点まで追い詰められている。
ニュース映像のような冷静さと、当事者の狂気が同時に存在する視点は、まさに Steely Dan 的な“他人事の残酷さ”と言えるだろう。
音楽的には、ギターとキーボードが作る緊張感の高いコード進行と、Fagen のやや歪んだボーカルの組み合わせが、極限状態の心理を音として表現している。
ロックバンドとしての攻撃性と、ジャズ由来の精度の高さが共存した、アルバム中盤のハイライトである。
4曲目:Sign In Stranger
「Sign In Stranger」は、ゆったりとしたシャッフルに近いリズムと、エレピのフロウが心地よいナンバーである。
どこか酒場のピアノのようなゆるいムードと、巧妙なコード進行が同居している。歌詞では、“異国の惑星”のような場所に集まるアウトローたちの姿が描かれる。
犯罪者やインチキ医者、怪しげな商売人たちが、過去を置き去りにして新たな名前で生き直そうとする“亡命者の楽園”のような光景である。
そこに漂うのは自由さと同時に、どこへ逃げても自分からは逃れられないという諦念であり、聴き手はいつの間にかこの奇妙な街の空気を吸わされている。
Steely Dan に特有の、ディテール過多な固有名詞とスラングの応酬も魅力で、歌詞カードを追いながら聴くと、架空都市の地図が頭の中に立ち上がってくるような一曲なのだ。
5曲目:The Fez
「The Fez」は、ディスコ〜ファンク寄りの4つ打ちビートと、反復するシンセ・リフが特徴的なダンス・チューンである。
ここではキーボーディストの Paul Griffin が作曲クレジットに加わっており、彼のアイディアがメロディやリフの核になっていると言われる。
歌詞は、表面上かなり意味不明なフレーズを並べているが、“I don’t wanna lose your fez(あの帽子を失いたくない)” というラインは、しばしばコンドームや性的な暗喩として解釈されてきた。
安全なセックスを巡るコミカルなやり取りを、あくまで比喩のレベルに留めたまま転がしていくスタイルは、露骨さを避けつつも現実的なテーマを扱う Steely Dan らしい手法と言える。
音的には、繰り返しの多い構成とミニマルなリフで、アルバムの中にクラブ感覚を持ち込んだような役割を果たしている。
重いテーマの曲が多い本作にあって、奇妙な軽さをもたらす、“毒のある箸休め” のような位置づけの一曲である。
6曲目:Green Earrings
「Green Earrings」は、ファンクとジャズ・ロックの要素が混ざり合ったグルーヴィなインプロ風ナンバーである。
ギターとキーボードがモチーフを投げ合い、ホーンがアクセントを入れながら、緊張感のあるリフをひたすら磨き上げていく。
歌詞は断片的で、緑のイヤリングを巡る奇妙な執着と、犯罪の気配を匂わせるだけで詳細は語られない。
盗まれた宝石なのか、かつての恋人の象徴なのか、あるいはドラッグの隠語なのか――聴き手は手がかりだけを渡され、自分なりの物語を組み立てることになる。
この曲では Larry Carlton をはじめとするギタリスト陣のプレイが前面に出ており、『The Royal Scam』が“ギター・アルバム”と呼ばれる理由がよく分かる。
フックの強いサビというより、グルーヴそのものを楽しむタイプの曲で、アルバムの流れを一段ハードな方向へ押し上げている。
7曲目:Haitian Divorce
「Haitian Divorce」は、トーク・ボックスとレゲエ風リズムを取り入れたユニークな一曲である。
ギターのカッティングとゆるやかなビートが、カリブ海の熱気とどこか退廃的なムードを漂わせる。
歌詞は、結婚生活に疲れたアメリカ人女性 Babs が、簡単な離婚手続きが売りの“ハイチ離婚ツーリズム”に乗ってカリブへ向かう、というストーリーになっている。
しかし現地で出会った男との一夜と、ゾンビ・カクテル、音楽とダンスの渦に巻き込まれた結果、帰国後には予期せぬ子どもが生まれ、関係はさらに複雑なものになってしまう。
観光地として消費される“エキゾチックな他者”と、それを利用する先進国の中産階級――その二重の搾取構造を、軽妙な物語として描いた曲だと言える。
耳に残るトーク・ボックスのギターと、のんびりとしたリズムの中で展開される皮肉なストーリーは、まさに Steely Dan の真骨頂であり、本作の中でも特に人気が高い。
8曲目:Everything You Did
「Everything You Did」は、ミディアム・テンポのややブルージーなロック・ナンバーである。
ギターのオブリガートとコーラスが控えめに絡み、どことなく冷えた空気をまとっている。
歌詞は嫉妬と監視に取り憑かれたパートナーの視点から描かれており、“お前がやったことは全部知っている”という執拗な言葉が並ぶ。
有名な行として、Eagles へのメタな言及とされるフレーズ(ラジオのバンド名を挙げる部分)があり、当時同じロサンゼルス・シーンで活動していたバンド同士の軽いジャブのようにも受け取られてきた。
ただし、曲の核心はイースターエッグ的なネタではなく、「関係を支配しようとする視線の気味悪さ」にある。
穏やかなサウンドの裏で、所有欲と不信がじわじわと侵食していく感覚を描くことで、本作の“暗い人間模様”をさらに補強している。
9曲目:The Royal Scam
ラストを飾るタイトル曲「The Royal Scam」は、重く反復するリズムと、不穏なコード進行が印象的な長尺ナンバーである。
テンポはそれほど速くないが、ベースとドラム、ギターがじわじわと圧力をかけてくるような構成で、アルバム全体のダークさを凝縮したエンディングになっている。
歌詞は、プエルトリコ移民たちが“アメリカン・ドリーム”を信じて本土に渡るも、結局は劣悪な住環境と低賃金労働に閉じ込められ、都市開発の犠牲になっていく、という物語として読まれてきた。
華やかな摩天楼は、実は彼らの上に建設された“巨大な詐欺(Royal Scam)”の象徴であり、当時のアメリカ社会に根深く存在した人種差別と経済格差を鋭く暴き出している。
音楽的には、同じモチーフを粘り強く反復することで、逃げ場のない閉塞感を作り出している。
アルバムの最後に、この重く長い曲を置くことで、聴き手は“詐欺の構造”から簡単には抜け出せない感覚を味わわされるのだ。
4. 総評
『The Royal Scam』は、Steely Dan のキャリアの中でも、特に“ギターのアルバム”として位置づけられる作品である。
Larry Carlton を中心に、Elliott Randall、Denny Dias、Dean Parks、そして Walter Becker 自身が入れ替わり立ち替わりプレイし、そのどれもが洗練されたフレーズと鋭い音色で楽曲を彩っている。
同時に、ドラムには Bernard Purdie や Rick Marotta、ベースには Chuck Rainey が参加しており、リズム・セクションの安定感も抜群である。
『Katy Lied』までの作品が、ソフト・ロックやポップス的な側面とジャズ和声を折衷していたのに対し、『The Royal Scam』は一歩踏み込んで“ファンクの肉体性”と“ロックの攻撃性”を強く押し出している。
「Don’t Take Me Alive」や「Green Earrings」、タイトル曲のようなトラックは、Steely Dan に対して“インテリでクールなAOR”というイメージを持っているリスナーにとって、かなり意外なほどハードな側面を見せてくれるはずである。
一方で、歌詞世界はこれまで以上に暗く、社会批評的である。
LSD時代の終焉を描く「Kid Charlemagne」、無垢さの喪失を扱う「The Caves of Altamira」、爆弾犯の立てこもり劇「Don’t Take Me Alive」、離婚ツーリズムと観光的搾取を描く「Haitian Divorce」、都市開発と移民搾取の構造を暴く「The Royal Scam」――いずれも、アメリカ資本主義の裏側に潜む“詐欺”を多角的に描いた短編小説のような曲である。
同時代のバンドと比較すると、その異質さはさらに際立つ。
たとえば Eagles や Fleetwood Mac が、同じ西海岸の空気を吸いながらも恋愛や人間関係の葛藤を比較的ストレートに歌っていたのに対し、Steely Dan はあくまで“皮肉な語り手”の位置を崩さない。
主人公たちに対して共感を示すこともあれば、冷笑を浴びせることもあり、その感情の揺らぎこそが本作の魅力のひとつである。
制作面でも、『The Royal Scam』は重要な分岐点にある。
ここで確立された「Becker & Fagen +精鋭セッション陣」というスタジオ志向は、次作『Aja』で極限まで洗練され、究極のAORサウンドとして結実する。
つまり、本作は『Aja』の前夜にあたり、まだ生々しい歪みやハードさが残る段階で、すでにアンサンブルと録音の精度が極めて高い、という稀有なバランスの作品なのだ。
ジャケット・アートも、そのダークな世界観を決定づけている。
ベンチで眠るホームレスの男の背後に、獣のように変形したビル群がそびえ立つこのイメージは、都市そのものが人々を食い物にする怪物であることを象徴しているように見える。
ここにも、“Royal Scam”=壮大な詐欺の構造に取り込まれた個人の無力さが反映されていると考えると、本作全体がひとつの大きなコンセプチュアル・アートとして立ち上がってくる。
批評的にも、リリース当時から高く評価されてきたが、近年では「Steely Dan で一番好きなアルバム」と挙げるファンも多く、ディスコグラフィーの中での位置づけがじわじわと上がっている。
『Can’t Buy a Thrill』『Aja』といった分かりやすい代表作に比べるとやや陰気でクセが強いが、そのぶん聴き込むほどに中毒性が増し、“沼”のように抜け出せなくなる作品なのだ。
Steely Dan を初めて聴くリスナーにとっては少しハードルが高いかもしれないが、『Aja』や『Pretzel Logic』で彼らの世界観に慣れてきた頃にじっくり向き合うと、その真価が一気に開けてくる一枚である。
ギター、リズム、歌詞、アレンジ――そのすべてが高いレベルで連動し、“知的でブラックな70年代ロック”の極北を示した作品として、『The Royal Scam』は今後も聴き継がれていくに違いない。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Aja / Steely Dan
『The Royal Scam』の次作にあたる代表作。
よりジャズ寄りで滑らかなAORサウンドへと到達した姿を確認でき、両作を続けて聴くことで、ハードなギター・アルバムから洗練の極みへの流れがはっきり見えてくる。 - Pretzel Logic / Steely Dan
コンパクトなソングライティングとジャズ和声のバランスが絶妙な一枚。
『The Royal Scam』のダークさに対して、よりポップでメロディアスな側面を持ち、初期〜中期 Steely Dan の全体像を掴むうえで好対照となる。 - Katy Lied / Steely Dan
本作直前のアルバム。
音質トラブルのエピソードで知られるが、楽曲の質は極めて高く、『The Royal Scam』へ向かう過程での“影と光のバランス”を知ることができる。 - Silk Degrees / Boz Scaggs
西海岸のスタジオ・ミュージシャンが多数参加したAOR名盤。
洗練されたグルーヴと都会的な哀愁という点で Steely Dan と地続きの空気を持ち、70年代中盤の“ラグジュアリーなポップ”の一端を比較して楽しめる。 - The Nightfly / Donald Fagen
Steely Dan の中心人物 Donald Fagen のソロ・アルバム。
50年代アメリカ文化へのノスタルジーと高度なサウンド・デザインが融合し、『The Royal Scam』で描かれたシニカルな視線を、よりパーソナルで映画的な形で味わうことができる。
6. 制作の裏側
『The Royal Scam』の制作は、Steely Dan が完全なスタジオ・プロジェクトとしての形を固めていくプロセスそのものだった。
Becker と Fagen は、自分たちのイメージするサウンドに合わせて曲ごとにプレイヤーを選び、何度もテイクを重ねてベストな演奏だけを残すという方法を徹底している。
その中心にいたのが Larry Carlton であり、彼はアルバムの約半分の曲でギターを担当している。
彼のプレイは、単なる早弾きや派手さではなく、コードの隙間を縫うようなフレージングと、ジャズ寄りの音使いによって、曲全体のハーモニーを立体的に見せる役割を果たしている。
Carlton のギターが本作を“最もギター志向の Steely Dan アルバム”として特徴づけていると言っても過言ではない。
ドラムでは Bernard Purdie が独特の「Purdie Shuffle」をはじめとするフィールでグルーヴを支え、Rick Marotta がタイトで抑制されたビートを提供する。
ベースの Chuck Rainey も含め、リズム隊はあくまで音数を控えめにしながら、微妙なノリとダイナミクスで楽曲の骨格を作っている。
この“控えめだが異様にうまい”リズム・セクションこそが、Steely Dan サウンドの屋台骨なのだと改めて実感させられる。
プロデュースは前作までと同様に Gary Katz が担当しており、彼は Becker & Fagen の緻密な要求を受け止めつつ、ロック・アルバムとしての躍動感を損なわないサウンド作りを行っている。
のちの『Aja』ほどツルツルに研ぎ澄まされてはいないものの、その“わずかなラフさ”が、『The Royal Scam』に特有の生々しい質感を与えているとも言えるだろう。
10. ビジュアルとアートワーク
『The Royal Scam』のジャケットは、Steely Dan のディスコグラフィーの中でもひときわ異様なインパクトを持っている。
ベンチで眠るホームレスの男の上に、高層ビルが獣のような姿でそびえ立ち、今にも彼を飲み込もうとしているかのようなイメージだ。
このビジュアルは、ニューヨークという都市そのものが、弱い者を食い物にする怪物であることを象徴しているように読める。
アルバム・タイトル曲の歌詞が、移民と都市開発の搾取構造を描いていることを踏まえると、ジャケットはまさにそのメタファーを視覚化したものだと言えるだろう。
Steely Dan のジャケットは、ポップでカラフルな『Can’t Buy a Thrill』、シンプルで抽象的な『Countdown to Ecstasy』、写真主体の『Pretzel Logic』『Katy Lied』など、作品ごとに異なる方向性を持っていたが、『The Royal Scam』はその中でも最もダークでシュールレアリスティックな表現である。
ここから、極端にミニマルな『Aja』、無機質でアイコニックな『Gaucho』へと続いていく流れを考えると、本作のアートワークは“都市の悪夢”を描いたピークとして位置づけることもできる。
視覚的にも聴覚的にも、“Royal Scam=壮大な詐欺” の感覚をこれほど一貫して表現したロック・アルバムは多くない。
ジャケットを眺めながらアルバムを通して聴くと、その世界観の重層性がより強く伝わってくるはずである。
参考文献
- Wikipedia: “The Royal Scam”(アルバム概要・制作背景・楽曲情報)ウィキペディア+1
- AllMusic: “The Royal Scam – Steely Dan”(レビュー・ジャンル・スタイル)AllMusic
- Steely Dan 公式バイオ的記事(The Royal Scam〜Aja期の位置づけ)ウィキペディア
- Session Days: “1976 Steely Dan – The Royal Scam”(レコーディング参加ミュージシャン一覧)Session Days
- Far Out Magazine / 各種記事(「Kid Charlemagne」「The Caves of Altamira」のモチーフ解説)Far Out Magazine+2Far Out Magazine+2
- Jukebox Time Machine / MODs ほか(「Haitian Divorce」の背景と離婚ツーリズム)What’s It All About?+2さまざまなものの酔い+2
- Pitchfork: “Steely Dan: The Royal Scam” レビュー(アルバム全体のトーンと批評的評価)Pitchfork


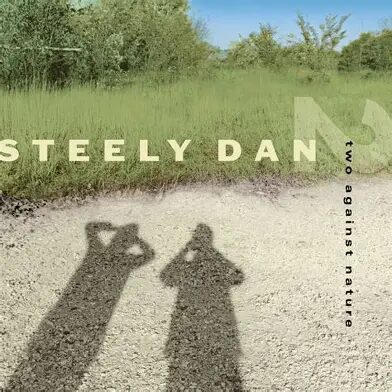

コメント