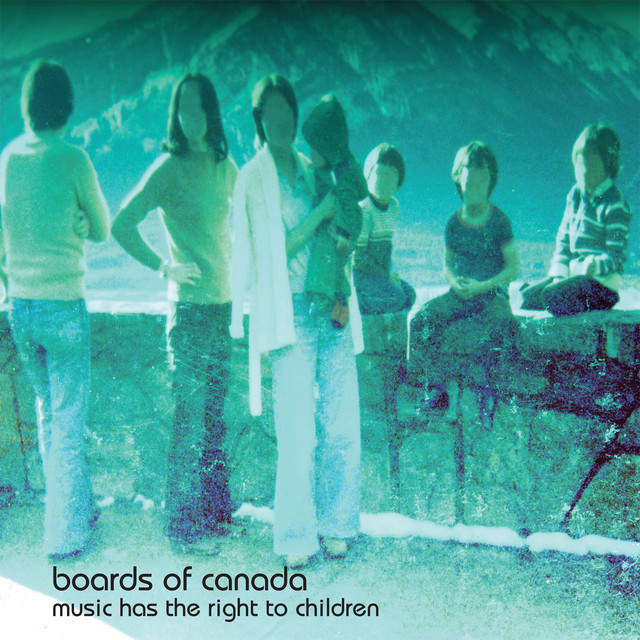
発売日: 1998年4月20日
ジャンル: IDM(インテリジェント・ダンス・ミュージック)、アンビエント、ダウンテンポ、エレクトロニカ
- 記憶の砂漠に残る旋律——“子どもたちの権利”としての音楽と、ノスタルジアの電子詩学
- 全曲レビュー
- 1. Wildlife Analysis
- 2. An Eagle in Your Mind
- 3. The Color of the Fire
- 4. Telephasic Workshop
- 5. Triangles & Rhombuses
- 6. Sixtyten
- 7. Turquoise Hexagon Sun
- 8. Kaini Industries
- 9. Bocuma
- 10. Roygbiv
- 11. Rue the Whirl
- 12. Aquarius
- 13. Olson
- 14. Pete Standing Alone
- 15. Smokes Quantity
- 16. Open the Light
- 17. One Very Important Thought
- 総評
- おすすめアルバム
記憶の砂漠に残る旋律——“子どもたちの権利”としての音楽と、ノスタルジアの電子詩学
1998年、スコットランド出身の兄弟デュオBoards of Canadaが放ったデビュー・アルバム『Music Has the Right to Children』は、電子音楽の歴史における転機となった作品である。
Aphex TwinやAutechreらが主導していた当時のIDM(インテリジェント・ダンス・ミュージック)潮流の中にあって、彼らの音はより内省的で、より感覚的、そして決定的に“郷愁的”だった。
タイトルにある「音楽には子どもたちの権利がある」という言葉は、単なる比喩ではない。
それは、記憶、遊び、教育、自然、感情といった“人間の根源的な体験”に音楽がアクセスする方法を示している。
彼らはその入り口として、ウォーミーなアナログシンセ、VHS的な質感、フィールドレコーディング、そして断片的なメロディを用いた。
その結果、本作は“どこかで聴いたことのあるようでいて、決して知らない風景”を描く電子音のアルバムとなっている。
それは、個人の記憶と集合的な潜在意識を同時に刺激するような不思議な感覚を生む。
まさに「音楽という名の夢の中」。
全曲レビュー
1. Wildlife Analysis
静かな水面のようなオープニング。
ミニマルなコードと揺れるサンプリングが、アルバム全体の“夢の輪郭”を描き出す。
2. An Eagle in Your Mind
断続的なパーカッションと不安定なメロディが交錯する、ポスト・トリップホップ的ナンバー。
電子音の背後に、風景のざわめきが聴こえる。
3. The Color of the Fire
子どもの声の断片と不穏なループが絡み合う、不安定なインタールード。
まるで壊れた教育テレビの幻を見ているような感覚。
4. Telephasic Workshop
本作でもっともビート感の強い一曲。
機械的なリズムと有機的なノイズが混在する、アナログとデジタルのはざま。
5. Triangles & Rhombuses
短くも美しいアンビエントの小品。
タイトルが示すように、幾何学的で抽象的な響きが印象的。
6. Sixtyten
長尺で、変化し続ける風景のようなトラック。
浮遊するメロディと深く沈み込むビートが、夢と現実の境界を曖昧にする。
7. Turquoise Hexagon Sun
後に彼らの象徴的な楽曲ともなる、ノスタルジック・ドローンの傑作。
空想と自然、アナログと幻影が混じり合ったサウンドの万華鏡。
8. Kaini Industries
日本語の企業名から取られたタイトルながら、内容は不可解で幻惑的な断片。
日常と記号の断片化がテーマか。
9. Bocuma
中盤のブレイクのように配置された、柔らかく温かなアンビエント。
子どもの眠る音が聴こえてきそうな静けさ。
10. Roygbiv
本作でもっとも親しみやすく、ファン人気も高いトラック。
“虹の色”を表すタイトル通り、淡くカラフルで、幸福な記憶の断片が滲むような名曲。
11. Rue the Whirl
ミニマリズムと郷愁が交差する、不穏さと心地よさの同居。
通り過ぎた風景が、音になって追いかけてくるような感覚。
12. Aquarius
チルでありながら、不協和音と奇妙なナレーションが散りばめられた、ボーカル・サンプリング中心の実験作。
テレビと夢が混ざり合う電子のサイケデリア。
13. Olson
短くも感情に満ちた、美しいピアノループの小曲。
寂しさと希望が指先で触れ合うような、切実なアンビエント。
14. Pete Standing Alone
ヘヴィなビートと歪んだシンセが絡み合い、後半に向けてグルーヴがうねりを生む。
他曲よりも土臭さを感じる一曲。
15. Smokes Quantity
過去作の音源をリワークしたようなノイズ的断片。
記憶の再編集、というテーマが顕著に表れた曲。
16. Open the Light
その名の通り、音の中に微かな光が差し込むようなトラック。
祈りにも似た、静かな浄化作用を感じさせる。
17. One Very Important Thought
突如として登場する“語り”のサンプル。
一種のメタ構造として、アルバム全体の夢から聴き手を目覚めさせる役割を担う。
総評
『Music Has the Right to Children』は、IDM/アンビエントの枠を超えて、「記憶そのものを音に変換すること」に成功した数少ない作品である。
それはまるで、廃校になった小学校の教室に差し込む午後の光のような、懐かしさと不安の混合物だ。
Boards of Canadaは、シンセサイザーの音色やテープの劣化、断片的なサンプリングを通じて、私たちが言語化できない過去=潜在記憶を呼び覚ます。
その体験は、一種の催眠であり、瞑想であり、そして音楽が本来持っていた“子どものための魔法”の力を思い出させるものでもある。
おすすめアルバム
- Aphex Twin – Selected Ambient Works 85–92
同時代のIDMクラシック。BoCよりも内的だが、世界観の没入度は高い。 - Ulrich Schnauss – Far Away Trains Passing By
ノスタルジックで美しいアンビエント/IDM。BoCの情緒性と共鳴。 - Casino Versus Japan – Go Hawaii
レトロ感とウォーミーなサウンドがBoC的世界を拡張。 - Tycho – Dive
ポストBoC的チルアウト/エレクトロニカ。視覚的に広がるサウンドスケープ。 - The Caretaker – Everywhere at the End of Time
記憶、認知、老いをテーマにした壮大な作品。BoCの“記憶音楽”としての側面をさらに深化。


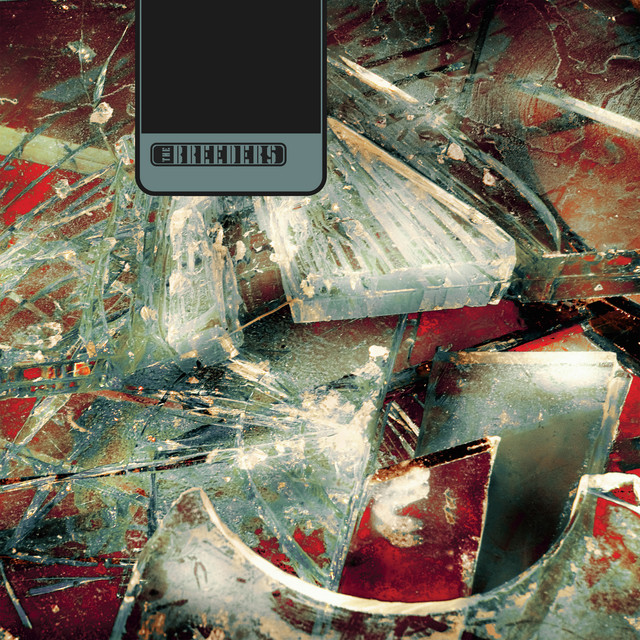

コメント