
発売日: 1981年9月
ジャンル: ニューファンク、ディスコ、ポストパンク、トーキング・ブルース
揺らぐ威厳とファンクの恍惚——ユーモアと猥雑のあいだに立つ“貴族”イアン・デューリーの異色作
『Lord Upminster』は、Ian Dury(イアン・デューリー)が1981年にリリースした2枚目のソロアルバムであり、彼のキャリアにおいて特異かつ実験的な色合いを持つ作品である。
1979年の『Do It Yourself』以降、The Blockheadsとの距離が開いたDuryは、今回初めてブロックヘッズ抜きでの制作に挑み、ニューヨークのCompass Point Studiosにて、Sly & Robbie(スライ&ロビー)らジャマイカ系の超一流リズムセクションと共に録音を行った。
この組み合わせにより、サウンドはパンクやパブロックの荒々しさよりも、ファンクやディスコの肉体性、リズムの躍動感に比重を置いた構成となっている。
だが、リズムが洗練されるほどに、Dury特有のロンドン下町由来の毒舌と庶民的スラング、風刺の効いた語り口が際立ち、ローカルとグローバル、下品と高尚が奇妙に交錯するユニークな音世界が広がっている。
全曲レビュー
1. Funky Disco Pops
冒頭から放たれる陽気なディスコビートと、Duryのくだけたモノローグ。
ダンスフロアへの愛と皮肉が同時に渦巻く、奇妙な魅力を持つパーティー・チューン。
2. Red Letter
官能的なグルーヴと詩的なリズムが交錯するファンク・トラック。
“赤い手紙”というモチーフに込められた社会的・個人的意味が、Duryの語り口により幾層にも響く。
3. Girls (Watching)
アルバム中でも最も知られた一曲。軽妙なディスコ・グルーヴと、女性観察のユーモラスな視点が絶妙に絡む。
女性賛美というよりも“観察と距離”がテーマであり、その曖昧な視線こそがDuryらしさである。
4. Wait for Me
スローでしっとりとしたラブソング。
だが情緒よりも、間の取り方やリズムの繊細さに重きが置かれており、Dury流の“熱くなりすぎない愛の表現”が味わえる。
5. The Body Song
エロティックかつ実験的な一曲。
リズムの解体とボディへの執着が、Dury特有のポエトリー・ファンクとして結実している。
6. Lonely Town
レゲエ〜ラヴァーズロックの影響が色濃く出たスロー・トラック。
孤独というテーマを、リズムの浮遊感と乾いた語りで描き、アルバムの静かな核心をなす。
7. Trust Is A Must
即興性とユーモアに満ちたアップテンポのトラック。
「信頼こそがすべて」というタイトルが示すように、都市社会や人間関係の信頼性に鋭いメスを入れている。
8. Spasticus Autisticus
最大の問題作にして、最大の傑作。
“自閉性/障害を持つ者の声”として歌われたこの曲は、BBCに放送禁止とされるほどの物議を醸した。
だが、これはDury自身の身体障害(ポリオによる半身麻痺)と社会への怒り、そしてアイロニーが込められた抵抗のアンセムである。
「I’m Spasticus, I’m Autisticus」というフレーズは、単なる挑発ではなく、排除される者の誇り高き叫びとして記憶される。
総評
『Lord Upminster』は、Ian Duryというアーティストが“語ること”の本質をリズムの中で探った異色作である。
Sly & Robbieを筆頭とするニューヨーク・ファンク/レゲエのリズム職人たちによって、このアルバムはDuryの語り芸を世界的グルーヴの上に乗せるという試みに成功している。
一方で、当時のファンからは「パンクの激情が薄れた」「ブロックヘッズ不在で温度が違う」と評された側面もある。
だが、これは怒りを内に秘めた知性と、猥雑な人生観を冷静なビートに載せた“老獪なる戦略”とも言えるだろう。
特に「Spasticus Autisticus」に象徴されるように、マイノリティの声を堂々と語るためのユーモアと挑発が、ここにはある。
おすすめアルバム
-
Ian Dury – New Boots and Panties!! (1977)
Duryの原点。パブロックとポエトリーの最初の融合点。 -
Grace Jones – Nightclubbing (1981)
同じCompass Point Studios録音。スライ&ロビーのグルーヴとアート感覚の見事な結晶。 -
Talking Heads – Remain in Light (1980)
ファンクと知性、語りと実験が融合したポストパンク名盤。Duryの方向性と交差する。 -
Linton Kwesi Johnson – Bass Culture (1980)
政治的ポエトリーとレゲエの融合。Duryの社会的語りに共鳴する作品。 -
Jona Lewie – On the Other Hand There’s a Fist (1978)
脱力ポップと語り芸を武器にした異端のシンガー。ユーモアと皮肉のバランス感が共通。



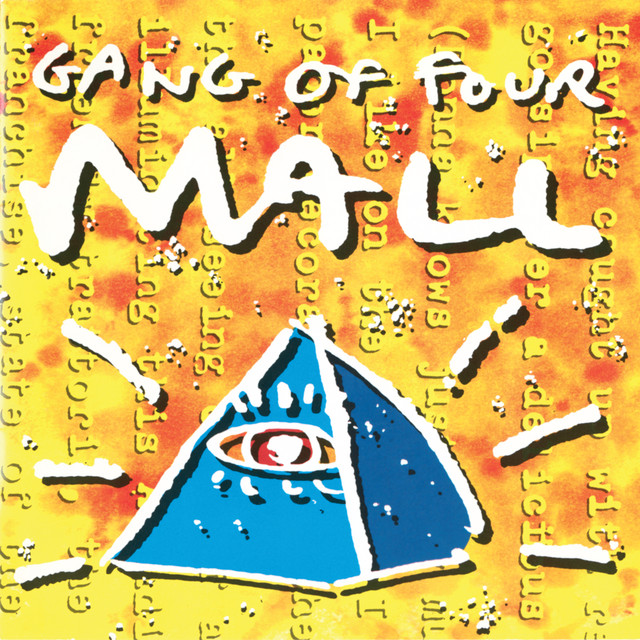
コメント