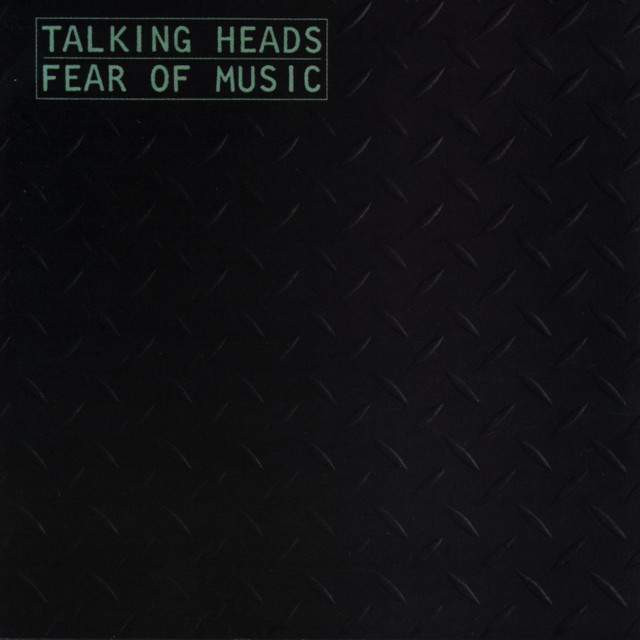
1. 歌詞の概要
「Life During Wartime」は、Talking Headsが1979年に発表したアルバム『Fear of Music』に収録されている楽曲であり、彼らの作品の中でも最も緊張感と切迫感に満ちた一曲である。タイトルを直訳すれば「戦時中の生活」となるが、この“戦時”とは、実際の戦争を指しているわけではない。ここで描かれているのは、都市で生きる人間たちが、社会的不安、監視、暴力、そして内面の分裂といった、目には見えない“戦争状態”の中でどうにか日々をやり過ごしている姿なのだ。
歌詞には、地下に潜って身を隠す主人公が登場する。彼はレコードを買うこともなく、クラブにも行かず、電話線を切り、仲間と連絡を取りながら物資を確保し、自らの痕跡を消し去ることに腐心している。これは明らかに、パーティを楽しむような通常の生活とは対極の、“サバイバル”を描いたものだ。そしてそのサバイバルの中には、1970年代末のアメリカ社会に対する不信感、パンク以降のアートの冷笑、そして情報化社会への警戒心が見え隠れする。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Life During Wartime」が書かれた1979年という時代は、アメリカがポスト・ベトナム戦争とウォーターゲート事件後のアイデンティティ危機に直面していた時期である。社会には虚無感が広がり、一方でパンク・ロックやニュー・ウェイヴが、既存の価値観や音楽形式を打ち壊すムーブメントとして若者たちの支持を集めていた。
Talking Headsはその文脈の中で、インテリジェンスと皮肉を武器に新たな音楽表現を試みていた。『Fear of Music』は、タイトルからして「音楽への恐れ」や「感覚の不安定さ」をテーマにしており、その冒頭から終わりまでが緊張の連続である。「Life During Wartime」はその中核を成す楽曲であり、バンドにとってもパフォーマンスの中心に置かれることが多かった。1984年のライブ映画『Stop Making Sense』でもこの曲は重要な場面で使用され、メンバーが楽器を持って舞台上を歩き回り、まるでパトロール中の軍隊のような振る舞いを見せることで、視覚的にも“戦時中”の世界観を強調している。
さらに興味深いのは、バーン自身がこの曲について「当時のニューヨークの状況を少し誇張したつもりだったが、後年それが現実になってしまった」と述べている点である。現代の監視社会や分断された都市の風景を思えば、彼の予言的感性に驚かされる。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に印象的なリリックをいくつか紹介し、日本語訳を併記する。
Heard of a van that is loaded with weapons
武器を満載したバンの話を聞いたPacked up and ready to go
荷物をまとめて、もう出発準備はできてるHeard of some gravesites, out by the highway
高速沿いの墓地の話も聞いたA place I never go
絶対に近づかない場所だThis ain’t no party, this ain’t no disco
これはパーティじゃない、ディスコでもないThis ain’t no foolin’ around
ふざけてる暇なんかないNo time for dancing, or lovey dovey
踊ってる場合じゃない、いちゃついてる暇もないI ain’t got time for that now
今はそんなことしてる時間はないんだ
引用元:Genius – Talking Heads “Life During Wartime”
4. 歌詞の考察
「Life During Wartime」の歌詞は、黙示録的な都市風景と、地下活動者のモノローグを融合させたような構成を持っている。そのリズミカルなフレーズは、淡々とした報告のようでもあり、逆説的に感情のない語り口が、かえって不気味さと緊張感を増幅させている。
注目すべきは、「This ain’t no party, this ain’t no disco」というフレーズである。それは、70年代の享楽的なカルチャーへの明確な拒絶であり、バンド自身の芸術的立場を示すものでもある。ここには、ただの娯楽では済まされない現実と向き合う決意がある。そして「This ain’t no foolin’ around」という一節は、状況が切迫しており、選択肢のない中での自己防衛を強くにじませている。
一方で、主人公は自分が“普通の生活”を捨てたことを多少の皮肉と共に語る。「もうレコードは買わない」「ディスコに行かない」と語るその語り口には、サブカルチャーとの決別を宣言しながらも、どこかでそれらへの未練も感じられる。
都市生活者の孤独、逃避、監視、そして反抗——この楽曲が内包するこれらのテーマは、単なるフィクションを超えて、80年代以降の都市文化やポスト・インターネット時代の我々の実感とも響き合っている。
※歌詞引用元:Genius
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Burning Down the House by Talking Heads
同様に都市生活とパニックをテーマにした名曲。緊張と爆発力のあるリズムが共通している。 - Psycho Killer by Talking Heads
個人の中に潜む狂気と都市の疎外感を描いた代表曲。 - The Guns of Brixton by The Clash
都市の暴力と緊張感をテーマにした、社会的メッセージの強いパンク・レゲエの名作。 - What’s Going On by Marvin Gaye
ベトナム戦争とアメリカの社会的混乱を背景にした、優しくも痛烈な問いかけ。 - Watching the Detectives by Elvis Costello
メディアと暴力、日常の中の狂気に焦点を当てたニュー・ウェイヴの一曲。
6. サウンドと構成——ファンクと都市の緊張
音楽的にもこの楽曲は独特である。ファンクのグルーヴを基調としながらも、ギターは尖ったリフを繰り返し、シンセサイザーやパーカッションが緻密に絡み合う。そのサウンドは、まるで神経を尖らせながら街を走り抜ける逃亡者のような疾走感を持つ。ティナ・ウェイマスのベースラインは常に動き続け、クリス・フランツのドラムはリズムの骨格を正確に刻みつつも、どこか落ち着きのなさを演出している。
また、デヴィッド・バーンのヴォーカルは、感情の起伏を抑えた“冷たい語り”として機能しており、それが逆に緊迫感を増幅させる要因となっている。この語りのトーンは、まるで秘密警察からの逃亡者が心の中でつぶやいているような印象を与える。
「Life During Wartime」は、ただの警告でもプロテストでもない。むしろ、それが“日常になってしまった”ことを淡々と歌っている。その冷静さこそが、最も不気味で、そして時代を映す鏡として今も輝きを放っているのである。




コメント