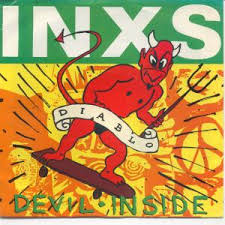
1. 歌詞の概要
「Devil Inside(内なる悪魔)」は、オーストラリアのロックバンド**INXS(インエクセス)**が1987年に発表したアルバム『Kick』に収録されたシングルで、バンドの持つセクシーかつダークな側面を前面に押し出した代表曲である。
この楽曲では、人間の中に潜む二面性──善と悪、光と闇、天使と悪魔──をテーマとして扱い、繰り返されるフレーズ「The devil inside(内なる悪魔)」が、その二重性を印象的に表現している。
表面的には、クールでグルーヴィーなダンスロックナンバーとして成立しているが、その裏には、理性の皮を被った本能の衝動や、人が持つ道徳的矛盾への問いかけが潜んでいる。愛や欲望、宗教、社会の規範といった概念を“内なる悪魔”というメタファーで包みながら、本当の自己とは何か?という根源的なテーマが浮かび上がってくる。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Devil Inside」は、INXSのギタリストであるアンドリュー・ファリスとボーカリストのマイケル・ハッチェンスの共作によって誕生した。彼らが制作したアルバム『Kick』は、ファンク、ロック、ポップを融合した画期的な作品であり、世界的な成功を収めることとなった。この曲はその中でも特に危険な色気と哲学的な問いを同時に内包する楽曲として異彩を放っている。
アメリカではBillboard Hot 100で2位まで上昇し、INXSにとって「Need You Tonight」に次ぐ大ヒット曲となった。しかし、宗教的な理由で一部地域では放送禁止になるなど、その挑発的なテーマ性が議論を呼んだ曲でもある。
楽曲のプロダクションには、当時の最先端だったダンスビートやエフェクトが用いられ、80年代後半の“ナイトクラブと心理の狭間”のような音像を創り出している。ハッチェンスのボーカルは、囁くようでありながら挑発的であり、まさに“内なる声”のように聴こえる。
3. 歌詞の抜粋と和訳
引用元:Genius Lyrics – INXS “Devil Inside”
Here come the woman
With the look in her eye
女がやって来る
その目つきに何かがある
Raised on leather
With flesh on her mind
レザーに育てられ
頭には“肉欲”が渦巻いている
この冒頭部分では、誘惑的で危険な女性像が描かれており、彼女自身もまた“内なる悪魔”を体現する存在であることが暗示されている。ここでは性的象徴性と力の逆転が同時に提示されている。
Words as weapons sharper than knives
Makes you wonder how the other half die
言葉はナイフより鋭い武器
お前はきっと考えるだろう、もう片方の人間がどう死ぬのかと
この部分は、言葉の暴力や感情の切れ味の鋭さを描くと同時に、“半分の人間”という概念によって、**人間の中の二面性──理性と本能──を浮き彫りにしている。
The devil inside, the devil inside
Every single one of us, the devil inside
内なる悪魔、内なる悪魔
すべての人間の中に、悪魔はいるんだ
このサビ部分は、曲の核心であり、人間誰もが持つ暗黒面の存在を肯定する宣言である。それは非難ではなく、“自分を偽るな”という問いかけであり、道徳や宗教に縛られた社会に対する皮肉や挑発としても受け取れる。
4. 歌詞の考察
「Devil Inside」は、そのタイトル通り、人間の本質に潜む“制御できない欲望”や“社会が抑圧しようとする本能”をテーマにしている。ここで語られる“悪魔”は、サタン的な存在ではなく、むしろ人間の自然な一部である本能的衝動や、抑えきれない感情の象徴である。
INXSはこの楽曲を通して、表面上は礼儀正しく、善良に生きているように見える人々の裏に潜む暗部を暴き出している。そしてそれを「恥」として隠すのではなく、「誰にでもあること」として受け入れようとする態度にこそ、この曲の革新性がある。
このようなテーマは、当時としては挑発的でありながらも、現代の心理学やフェミニズム、社会批評と強く接続している。とりわけ、“誰の中にも悪魔がいる”というメッセージは、道徳的理想像や清潔な自己像に疑問を投げかけ、もっと複雑で多面的な人間理解を促すものとして機能している。
また、音楽的にはミニマルな構成と重たいビート、そしてハッチェンスのダークなヴォーカルが、抑圧された情念の爆発寸前の緊張感を表現しており、まさにサウンドそのものが“内なる悪魔”を表現する装置となっている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “People Are People” by Depeche Mode
人間の内面の矛盾と社会的対立を鋭く指摘するエレクトロ・ロックの金字塔。 - “Strangelove” by Depeche Mode
快楽と罪の狭間で揺れる人間心理を描いた官能的でダークなラブソング。 - “Sweet Dreams (Are Made of This)” by Eurythmics
欲望と幻想、アイデンティティの探求をポップな装いで描いた一曲。 -
“Closer” by Nine Inch Nails
性的・精神的な深層を剥き出しにした90年代以降の“悪魔の末裔”。 -
“Sympathy for the Devil” by The Rolling Stones
“悪魔の語り手”を通じて人類の歴史と暴力を批評したロックの古典。
6. 欲望は罪ではない──“内なる悪魔”を肯定するロックの哲学
「Devil Inside」は、80年代という時代の中で、ロックが“本能”と“道徳”の境界を問う手段であることを明確に示した曲である。それは単なるセクシーなダンスロックではなく、人間の中にある矛盾や欲望を恥じることなく認めることこそが、自分を生きる第一歩であるという、ある種の生き方の提示でもある。
マイケル・ハッチェンスはその表現を通して、優雅でありながらも危険な、内面の真実と向き合う姿勢を体現した。
そしてINXSというバンドは、こうした音楽によって、“クールで踊れる”だけではない、深く思索的なロックの可能性を提示したのである。
「Devil Inside」は、すべての人の中に眠る衝動を、美しく、妖しく、肯定するロックの黙示録である。


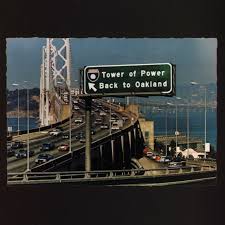
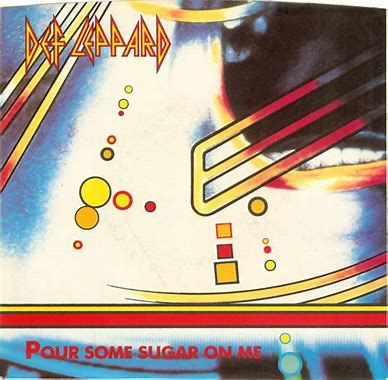
コメント