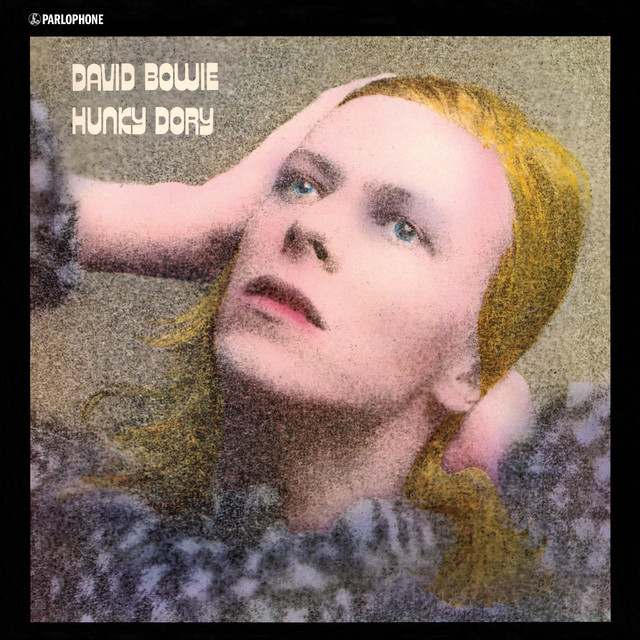
発売日: 1971年12月17日
ジャンル: グラムロック、アートポップ、フォークロック
“変化する者”の誕生――ボウイという神話のプロローグ
『Hunky Dory』は、David Bowieが1971年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、彼のキャリアにおける最初の“明確な覚醒”を刻んだ作品である。
前作までのフォークやブルース色を残しつつも、ここでボウイはアートポップ、演劇性、そして知的なリリックを伴って、変身の旅へと足を踏み出す。
プロデューサーはKen Scott、ピアノには後に重要なコラボレーターとなるRick Wakeman(Yes)が参加。
ビートルズ以降のポップ感覚と、ルー・リードやアンディ・ウォーホルら当時のアート・カルチャーからの影響が交差し、音楽と視覚、思想と感情が複雑に絡み合う作品となった。
このアルバムにおいてボウイはまだ「Ziggy Stardust」ではない。
だが、“変身”という彼の芸術の核が、すでに鮮やかに芽吹いているのだ。
全曲レビュー
1. Changes
「変化」をテーマにしたボウイの代表曲。
軽快なピアノとメロディに乗せて、“自己変革”をポップに、しかし決意を込めて歌い上げる。のちのZiggyやベルリン時代をも予見する宣言的なナンバー。
2. Oh! You Pretty Things
ニーチェ思想をベースにした歌詞では、新たな人類(Homo Superior)の台頭が語られる。
家庭的なメロディとの対比が不穏さを強調し、ボウイの知的側面が色濃く出た一曲。
3. Eight Line Poem
シンプルな詩の構造と、浮遊感のあるギターが特徴の短編的トラック。
都会の倦怠と個の孤独を静かに描く。
4. Life on Mars?
本作の頂点とも言える壮大なバラード。
退屈な現実とポップ・カルチャーにまみれた夢想とのギャップを、映画的アレンジで昇華した名曲。まさに「不条理な現代を生きる少女のための国歌」である。
5. Kooks
息子ダンカンへのラブレターのような、家庭的でユーモラスな一曲。
ボウイの柔らかな父性とポップ職人としての手腕が光る。
6. Quicksand
オカルト、宗教、哲学的イメージが複雑に織り込まれた、内省的な名バラード。
「I’m sinking in the quicksand of my thought(思考という流砂に沈んでいく)」というフレーズが示すように、自我の深淵を覗き込むような感覚がある。
7. Fill Your Heart
ポジティブで明るいトーンのカバー曲。
陰鬱な前後の曲との対比が、むしろこの明るさを不気味に映すというボウイ的構成。
8. Andy Warhol
ウォーホル本人に捧げたアコースティック曲。
“芸術”と“偶像”の関係を、乾いたリフとストップ&ゴーの構造で表現する。
9. Song for Bob Dylan
ディランに影響を受けたことを公言していたボウイによるオマージュ。
だがそれは単なる礼賛ではなく、「新しい声」を求める呼びかけでもある。
10. Queen Bitch
ルー・リードやVelvet Undergroundへの敬愛を込めたグラム・ナンバー。
Ziggy期のプロトタイプとも言える疾走感と性的曖昧さを含んだ歌詞が魅力。
11. The Bewlay Brothers
ボウイ自身が“意味を明かしたくない”と語った、謎めいたラストトラック。
彼の兄テリーとの関係を象徴しているとも言われ、夢と狂気が交錯する音の迷宮。
総評
『Hunky Dory』は、“David Bowie”という存在が本格的に輪郭を持ち始めたアルバムである。
知性と感情、演劇性と音楽性、ポップとアート。すべてが未完成ながらも高密度に詰め込まれている。
音楽的にはピアノ主体のアレンジが印象的で、Ziggy期のロックとは対照的に、室内楽的な親密さが漂う。
一方でリリックは大胆かつ哲学的で、当時の若者が抱える孤独や焦燥、芸術への渇望を代弁するようでもある。
『Hunky Dory』は、ポップの形式を借りて詩と思想を届けるという、ボウイの根源的な方法論の起点なのだ。
ここから始まる変身の旅を知っている我々にとって、この作品はまさに“序章にして核心”とも言える。
おすすめアルバム
-
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars / David Bowie
『Hunky Dory』の直後に発表された代表作。キャラクター性とロックが融合したグラムの頂点。 -
Transformer / Lou Reed
ボウイがプロデュースしたルー・リードの代表作。性的曖昧さとアート感覚が色濃い。 -
Aladdin Sane / David Bowie
Ziggyの続編的作品。アメリカをテーマに、狂気と派手さが炸裂する。 -
Bryter Layter / Nick Drake
同時代の内省派シンガーソングライター。繊細なアコースティックと憂いの美学が共鳴。 -
Electric Warrior / T. Rex
グラムロックの源流。ボウイのグラム期に多大な影響を与えた名盤。


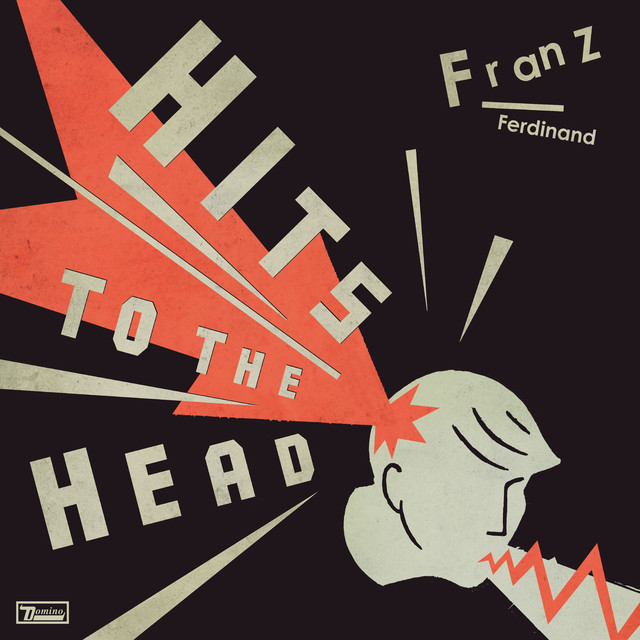

コメント