はじめに
Babyshambles(ベイビー・シャンブルズ)は、2000年代イギリスのロック・シーンにおいて、特異な存在感を放ったバンドである。
フロントマンのピート・ドハーティは、The Libertinesでの活動を経て、ドラッグ問題やスキャンダルにまみれながらも、言葉とメロディで魂を震わせる表現を追い続けた。
彼らの音楽には、危うさと脆さ、そしてそれを突き抜けるような一瞬の光が確かに刻まれている。
バンドの背景と歴史
Babyshamblesは、The Libertinesを脱退したピート・ドハーティによって2003年にロンドンで結成された。
The Libertinesの頃から続く喧噪と混乱、そして友情と破綻の物語を引きずりながら、彼は自身の言葉と向き合う場所としてこのバンドを立ち上げたのだ。
初期のメンバーは流動的であったが、ドラマーのアダム・フォークナーやベーシストのドリュー・マクコーネルらが徐々に定着。
スタジオ録音とライブのテンションの落差、そしてたびたび中止されるツアーは、彼らの音楽活動をより神話的なものにしていった。
音楽スタイルと影響
Babyshamblesの音楽には、パンク、フォーク、ガレージロック、さらにはレゲエやジャズの断片までもが混ざり合っている。
その中心にあるのは、ピート・ドハーティの詩情と声である。
彼の歌詞は、ウィリアム・ブレイクの詩を思わせる幻想と、ロンドンの街角の退廃を同時に孕んでいる。
イギリス的メランコリーと美的破滅が同居するサウンドは、BlurやThe Clashの系譜にありながらも、より切実で生々しい。
代表曲の解説
Fuck Forever
Babyshamblesの代表曲にして、世代のアンセムとも言えるのがこの曲である。
「未来なんてクソくらえ」という言葉が何よりも鋭く、そして切実に響く。
一見挑発的なこのフレーズは、希望を見失った若者たちの無言の祈りにも聞こえる。
パンクの攻撃性とポエトリーリーディングのような言葉の連なりが、絶妙に交錯する。
Albion
「アルビオン」とはイギリスの古称。ピートの心象風景を旅するような、美しくも哀しいバラードである。
彼の歌うイギリスは、もはや地図には存在しない幻想の国だ。
アコースティックギターのシンプルな伴奏に乗せて、夢と現実の境界を彷徨うように語られるリリックは、まるで個人的な祈りのようでもある。
Delivery
この曲は、Babyshamblesにしては珍しく、ポップなキャッチーさと勢いを持った一曲である。
だが、その明るさの裏にはやはりどこか空虚な響きがある。
「君に伝えたいことがある」という繰り返しの中に、伝えきれない想いがこぼれ落ちていく。
アルバムごとの進化
Down in Albion(2005)
デビュー作にして混沌の極み。スティーヴン・ストリートがプロデュースを担当しているが、音の粗さや録音のブレはむしろ魅力として機能している。
ピートの詩的な衝動と混乱がそのままパッケージングされ、まるで日記を読むような生々しさがある。
Shotter’s Nation(2007)
より洗練されたプロダクションで、音の輪郭が明瞭になった作品。
ミック・ジョーンズ(The Clash)がプロデュースに関与しており、パンク的ダイナミズムと繊細なアレンジが共存している。
このアルバムでは、Babyshamblesが単なる破滅の象徴ではなく、音楽的な成熟を見せるバンドであることを証明している。
Sequel to the Prequel(2013)
前作から6年の空白を経て発表されたアルバム。
ジャズやシャンソンの要素も取り入れられた音作りが印象的で、ピートのヴォーカルもより柔らかく、円熟味を帯びている。
衝動よりも余韻、破壊よりも再構築といった印象の強い作品である。
影響を受けたアーティストと音楽
ピート・ドハーティの音楽的ルーツには、The Jam、The Smiths、そしてThe Poguesのような英国の詩情派ロックがある。
また、ブレイクやオスカー・ワイルドといった文学からの影響も色濃く、彼の言葉には一種の文学的憧憬が漂う。
彼の美意識は、単なるロックスターの破天荒さを超えて、耽美と頽廃のあわいにある。
影響を与えたアーティストと音楽
Babyshambles、そしてピート・ドハーティの生き様と音楽は、The ViewやThe Kooks、さらにはArctic MonkeysといったUKロックの次世代にも影響を与えた。
彼らの「どうしようもなさ」にこそロックの真実があるとする姿勢は、後のインディーシーンにおいてひとつの美学として共有されたのだ。
オリジナル要素
Babyshamblesの魅力は、ライブの不安定さにも表れている。
ステージに現れない、酔って演奏が成立しない――そんな逸話も枚挙に暇がないが、それすらも観客にとっては“儀式”のようなものだった。
ピートの姿を一目見るために、ファンたちは不確かな夜を共有した。
また、ピートが描くアート作品や詩の出版も、音楽以外の表現手段として注目されている。
そのすべてが、彼の「表現せずにはいられない」衝動の延長線上にあるのだ。
まとめ
Babyshamblesは、音楽的な完成度や技巧よりも、生き様そのものを鳴らすようなバンドであった。
その音楽には、絶望も希望も、夢も現実も、すべてが混ざり合っている。
それは決して完璧ではないし、しばしば聴く者を混乱させる。
だが、だからこそ胸を打つ。
ピート・ドハーティというひとりの詩人が、この世界をどう見つめていたか。
Babyshamblesの音楽は、その答えの断片であり、いまもなお聴く者の心に爪痕を残し続けている。



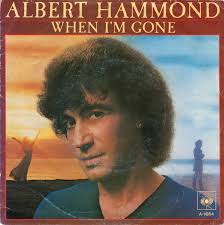

コメント