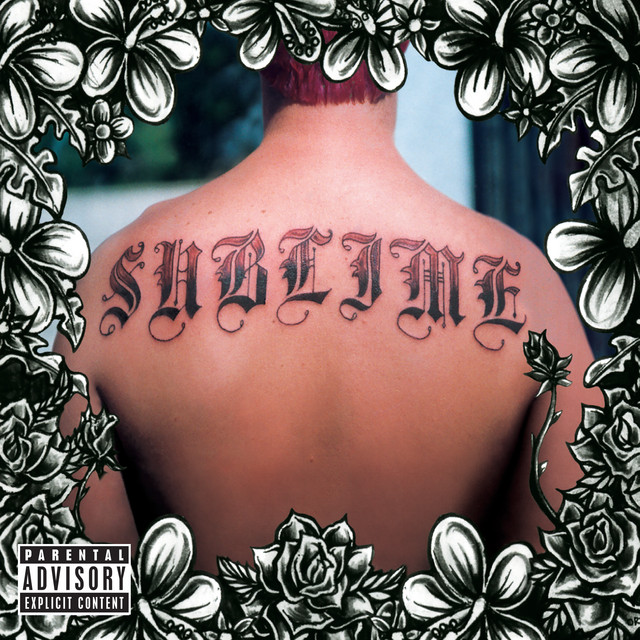
1. 歌詞の概要
「April 29, 1992 (Miami)」は、アメリカ西海岸のレゲエ・ロックバンド、Sublimeが1996年に発表したアルバム『Sublime』に収録された楽曲であり、そのタイトルが示す通り、1992年4月29日にロサンゼルスで発生した**ロサンゼルス暴動(LA Riots)**を題材とした、強い社会的メッセージを含んだ一曲である。
暴動の発端は、ロサンゼルス市警の警官による黒人男性ロドニー・キングへの集団暴行事件であり、それに対して陪審員が無罪評決を下したことが市民の怒りを爆発させた。「April 29, 1992」は、まさにその暴動の現場を、**市民の目線で赤裸々に描いた“ストリート・ドキュメント”**であり、商店の略奪、放火、警察の無力さ、混乱の熱気を、淡々とした語りとともに再構築している。
語り手は、暴動を傍観者としてではなく、能動的に参加した者として描かれており、正義への怒りと同時に、それが自己破壊や略奪として表出する矛盾を象徴的に体現している。その語りは決して道徳的でも、英雄的でもなく、混乱と暴力のなかで生まれた“生々しいリアリズム”に満ちている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「April 29, 1992」は、SublimeのフロントマンであるBradley Nowellが、ロサンゼルス暴動に触発されて制作した楽曲であり、彼自身の体験とフィクションを交差させながら、アメリカ社会に潜む人種差別、警察の腐敗、経済的格差、そして若者たちの怒りを描き出している。
興味深いのは、実際に暴動が始まったのは4月29日だが、曲中でノウェルが最初に歌っているのは「April 26, 1992」。これは当初のレコーディングで間違った日付を使用したデモテープを元に、バンドがそのまま楽曲を発展させたという裏話があり、曲の混沌と即興性を象徴する一要素にもなっている。
この曲は、ミュージシャンが“政治を歌う”ことの意味を再定義した一例であり、怒りをロックでもヒップホップでもない“レゲエ/スカ”という陽気なビートに乗せることで、暴力と音楽の二重構造が浮き彫りとなっている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「April 29, 1992」の印象的なフレーズとその日本語訳を紹介する。
“April 26, 1992 / There was a riot on the streets, tell me, where were you?”
1992年4月26日 通りで暴動が起きてた おまえはどこにいた?
“You were sittin’ home watchin’ your TV / While I was participatin’ in some anarchy”
おまえはテレビの前に座ってただろ そのとき俺は無政府状態の中にいたんだ
“‘Cause everybody in the hood has had it up to here / It’s getting harder and harder and harder each and every year”
街のやつらは皆もう我慢の限界だった 年々、生きてくのがきつくなってた
“It’s about comin’ up and stayin’ on top / And screamin’ 1-8-7 on a motherfuckin’ cop”
のし上がってトップに立ちてえんだよ くたばれクソ警官、って叫びながらな
“Let it burn, wanna let it burn / Wanna let it burn, wanna wanna let it burn”
燃やせ、全部燃やしてしまえ 焼き尽くせ、何もかも
歌詞引用元:Genius – Sublime “April 29, 1992 (Miami)”
4. 歌詞の考察
この曲は一見すると“犯罪の正当化”に聞こえるかもしれないが、実際にはもっと複雑なメッセージが込められている。ノウェルが描く“暴徒の視点”は、正義や倫理という枠組みでは収まらない、“生存のための怒り”であり、貧困層の若者が社会から排除され、法や秩序に裏切られた末に辿り着いた“暴力による表現”の形だ。
「略奪したのはテレビだった」「次は銃屋に行くつもりだった」という歌詞は、物欲だけではなく、“力を取り戻す”という衝動の象徴であり、アメリカの深層にある階級と権力の非対称性を浮き彫りにするものだ。
また、「riot(暴動)」という言葉を、政治運動でも革命でもなく、“anarchy(無政府状態)”として表現することで、これは“統制なきエネルギー”の発露であり、行き場を失った者たちの叫びであることを暗示している。
その暴力性を、怒鳴るのではなく、スローで陽気なサウンドで描くことで、Sublimeは聴く者の“倫理的判断”を停止させ、あえて“暴力の中にある理由”を考えさせようとする。音楽による批評とは何かを問い直す、非常に挑戦的な作品である。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Date Rape by Sublime
社会的問題を風刺とブラックユーモアで描いた、Sublimeならではの問題提起ソング。 - Killing in the Name by Rage Against the Machine
警察暴力への抗議を激しい怒りで表現した90年代のプロテスト・ロックの金字塔。 - Sound of da Police by KRS-One
警察権力と人種差別をテーマにしたヒップホップの古典。“ワオワオ!”の掛け声が有名。 - White Man in Hammersmith Palais by The Clash
レゲエとパンクの融合によって階級と文化の矛盾を暴いた、英国パンクの社会派代表作。
6. “暴動”を音楽に昇華した異色のドキュメント
「April 29, 1992 (Miami)」は、暴動というタブーに真っ向から向き合い、正義と破壊、怒りと享楽の間で揺れる若者の魂を描き出したSublime屈指の社会派トラックである。この曲は、ただのレポートでもなく、英雄譚でもなく、**“何が正しくて、何が間違っているのか分からない世界で、人はどうやって声を上げるのか?”**という問いかけそのものだ。
Bradley Nowellはこの曲で、“正しさ”の定義そのものを揺るがせる。リスナーは、心地よいビートに身を委ねながらも、その中に隠された怒りと矛盾に気づいたとき、初めてこの曲の“核心”に触れることになる。
「April 29, 1992」は、90年代アメリカの混沌と怒りを、軽やかなスカのリズムで覆い隠しながら、深い問いを突きつける“音楽による暴動”である。それは、聴く者に倫理ではなく、想像力を求めてくる。



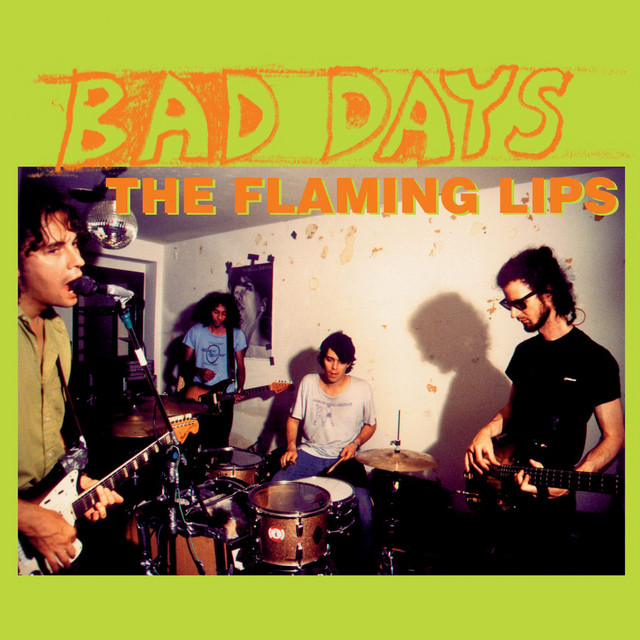
コメント