
発売日: 1978年11月10日
ジャンル: ロック、ハードロック、アートロック、グラムロック
概要
『Jazz』は、クイーンが1978年に発表した通算7作目のスタジオ・アルバムであり、ジャンルやテーマの壁を大胆に飛び越えた“ごった煮”とも言うべき作品である。
タイトルに“Jazz”と冠してはいるが、実際にジャズ的な要素は極めて限定的であり、むしろその“文脈を無視した命名”自体がアルバムの姿勢を象徴している。
すなわち、ジャンルや形式を超え、自由奔放に音楽を拡張していくという姿勢そのものである。
本作は、フランスのマウンテン・スタジオとミュンヘンのミュージックランド・スタジオで制作され、プロデュースには再びロイ・トーマス・ベイカーが参加。
メンバーそれぞれの楽曲が色濃く個性を放ち、ポップ、ロック、エキゾチック、風刺、エロスといった多様な要素が所狭しとひしめき合っている。
特に話題となったのは、「Fat Bottomed Girls」「Bicycle Race」といった性的なユーモアに富んだ曲群。
ミュージックビデオにおけるヌード女性の自転車レース映像や、物議を醸すリリックなど、クイーンの過剰さと挑発性が最も過激に表れたアルバムとも言える。
しかしそれらの裏にあるのは、音楽的探求心と遊び心、そして聴き手との“距離の遊び”である。
高尚さと軽薄さ、シリアスさとナンセンスが混在したこの作品こそ、クイーンというバンドの本質を語るうえで欠かせない1枚なのだ。
全曲レビュー
1. Mustapha
アラビア語風のフレーズで始まる異国情緒あふれるロックナンバー。
宗教的な言葉遊びと爆発的なボーカルが交錯し、オープナーから“常識破り”を宣言しているかのよう。
ライブでもサビのみ引用されるなど、観客との“共通言語”のように扱われる存在。
2. Fat Bottomed Girls
ジョン・ディーコンの粘っこいベースラインとメイの重厚なリフが光る、ブルージーなロック。
女性の肉体美を称えるユーモラスな歌詞が物議を醸しつつも、骨太なサウンドが印象に残る。
「Bicycle Race」との連動性も含め、バンドの茶目っ気が全開。
3. Jealousy
フレディによるピアノ主体のバラード。
チェンバロのようなエフェクトを施したアコースティックギターの装飾が美しく、愛における嫉妬心を繊細に描き出している。
静かながら感情の奥行きが深い一曲。
4. Bicycle Race
“私はレースがしたい、でもツール・ド・フランスではなくて人生の”──というような、社会風刺とナンセンスが混在した奇曲。
サーカス的なアレンジ、擬音的なコーラス、ギターによる自転車ベル模倣など、実験精神が詰まった名物曲。
5. If You Can’t Beat Them
ディーコン作のストレートなハードロック。
“敵わぬなら仲間になれ”というテーマを、明快なメロディとサビでロックアンセム化している。
クイーンの中では比較的“普通”な一曲だが、だからこそ心地よく響く。
6. Let Me Entertain You
ライブでのオープニングを意識した、自己言及的なショウ・ナンバー。
“我々はあなたを楽しませるためにやってきた”という宣言と共に、フレディのスター性が爆発する。
7. Dead on Time
ブライアン・メイによるスラッシュ寸前の高速ロック。
ギターの切れ味、ロジャーの怒涛のドラムが炸裂し、“時間との戦い”を文字通り音にしたようなテンション感が支配する。
雷鳴のSEで締める演出も象徴的。
8. In Only Seven Days
ディーコンによる、日常の恋愛模様を描いたささやかなバラード。
過剰な装飾のない端正なアレンジが、アルバム中に一瞬の静けさをもたらしている。
9. Dreamer’s Ball
エルヴィス・プレスリー追悼曲とされる、スウィング調の作品。
管楽器を模したギターエフェクトが印象的で、時代を遡るようなノスタルジックさに満ちている。
10. Fun It
ロジャー・テイラー作のファンクロック。
ミニマルな構成とルーズなビートが心地よく、のちの「Another One Bites the Dust」への流れを予感させる実験的側面も強い。
11. Leaving Home Ain’t Easy
メイの繊細なボーカルによる叙情曲。
旅立ちと喪失をテーマにしたナンバーで、声の多重録音により内省的な美しさが漂う。
12. Don’t Stop Me Now
本作最大のヒット曲にして、現在ではクイーンを代表するアンセムのひとつ。
「今の僕を止めないで」と自信と自由を高らかに歌い上げるこの曲は、ポジティブさと躍動感が圧倒的。
ピアノロックとギターソロの見事な融合、そしてフレディのエネルギーがアルバムを最高潮に導く。
13. More of That Jazz
断片的に前曲のフレーズを再利用しながら展開する、ロジャーのサイケデリックなクロージングナンバー。
疲労感や反復への倦怠といったテーマが感じられ、アルバムのカーテンコールとして意外に重い余韻を残す。
総評
『Jazz』は、ジャンル、文脈、そして“ロックらしさ”という固定観念への痛快な挑発であり、クイーンの音楽的多面性が最も極端に振り切れた作品である。
多彩すぎる楽曲構成は、アルバムとしての統一感を欠くという批判もあるが、それすらも“意図的な混沌”として楽しめるのが本作の醍醐味だ。
フレディ・マーキュリーの表現力とジョン・ディーコンのポップセンス、ロジャー・テイラーの実験志向、ブライアン・メイの構築美が、それぞれ異なる方向へと拡張されながらも、最終的にはクイーンという器の中でひとつのショウとして成立している。
この作品はまさに“サーカス”であり、“カーニバル”であり、“演劇”であり、そして“日常への風刺”でもある。
それを理屈で整理すること自体が野暮であり、むしろこの作品を“楽しむ”という姿勢こそが最もふさわしい鑑賞態度なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Electric Light Orchestra / Discovery
ポップとディスコ、ロックの境界を遊ぶという意味で通じる作品。 - David Bowie / Lodger
ジャンル混成と実験性において『Jazz』と共鳴する。 - Talking Heads / More Songs About Buildings and Food
ファンクや変拍子の導入、アート性のあるポップスという点で比較的近い。 - 10cc / How Dare You!
ポップの形を借りた風刺と実験精神の両立という点で相似している。 - Roxy Music / Manifesto
ナイトクラブ的耽美とロックの混交という意味で、『Jazz』の世界観に呼応する作品。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Jazz』のレコーディングは、クイーンがかねてより所有したいと考えていたスタジオ——スイスのマウンテン・スタジオにて実施され、さらにミュンヘンのミュージックランド・スタジオでも一部が録音された。
プロデューサーには久々にロイ・トーマス・ベイカーが復帰。彼はクイーンの初期3作品にも携わっていた人物で、音の密度や空間処理に優れた技術を持っている。
また、「Bicycle Race」のミュージックビデオ撮影時には、ヌードモデルを大量に自転車に乗せたという大胆な演出が行われ、撮影用のレンタル自転車が“返却拒否”される騒ぎになるなど、周辺でも話題が絶えなかった。
こうした“音”と“演出”を同時にプロデュースするスタイルは、後のMTV時代を先取りするような感覚でもあり、クイーンが時代の先端を走っていたことを象徴するエピソードである。


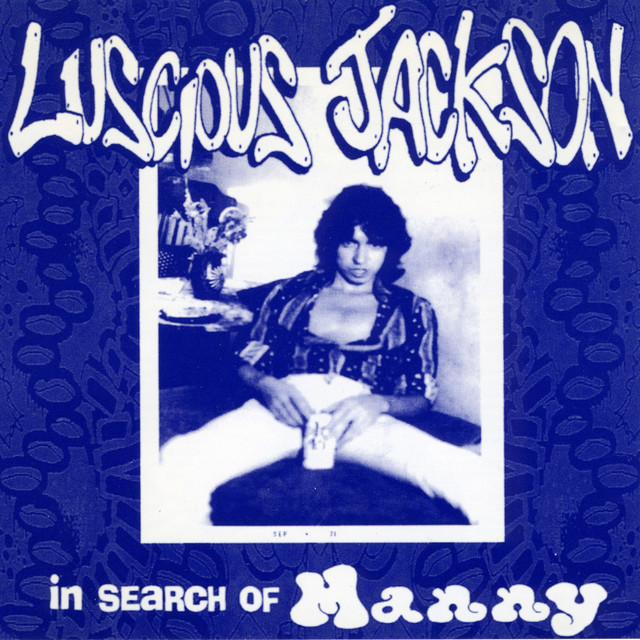

コメント