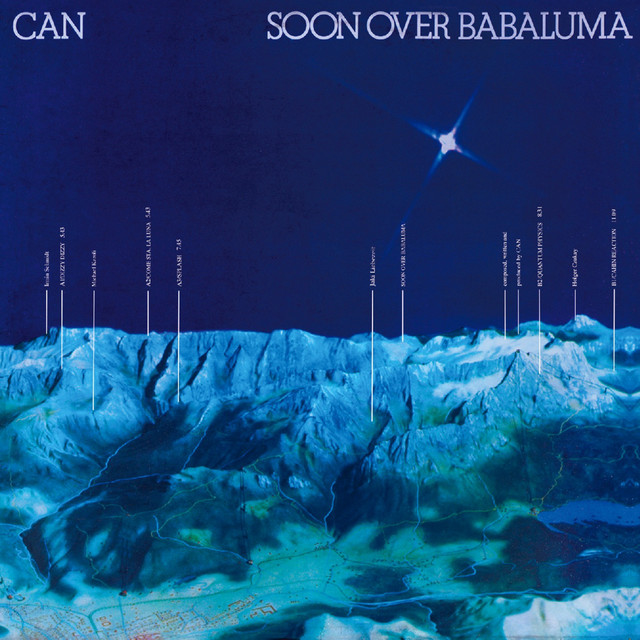
発売日: 1974年11月**
ジャンル: クラウトロック、アヴァンギャルド、ジャズロック
ババルマの向こう側——声なき世界に響く、リズムと夢想の余白
『Soon Over Babaluma』は、1974年にリリースされたCanの6作目のスタジオ・アルバムであり、ヴォーカリストのダモ鈴木脱退後、初のアルバムとして位置づけられる転換点である。
本作ではマルチ・インストゥルメンタリストであるマルコム・ムーニー以来、初めてヴォーカル不在の体制が本格化し、
メンバーであるミヒャエル・カローリとイルミン・シュミットが交代でヴォーカルを担当するという形式が採用された。
この変化によって、Canのサウンドはより“内面化”し、リズムと音色の流動性が前面に出る構成へとシフトしていく。
ジャズ、アンビエント、エスニックな要素がミックスされ、“即興の力”がより洗練された響きへと変容したアルバムである。
全曲レビュー
1. Dizzy Dizzy
カローリによるファルセット気味のヴォーカルと、ひしゃげたヴァイオリンのようなギターが絡み合う、浮遊感と脱力感に満ちたオープナー。
リーベツァイトのドラムがタイトにグルーヴを刻む一方で、音全体はどこか頼りなく、不思議な不安定さが癖になる。
2. Come Sta, La Luna
シュミットがイタリア語で歌うこのトラックは、カンタベリー系にも通じる耽美と皮肉の入り混じったジャズ・ナンバー。
柔らかなエレピ、幻想的なパーカッション、そして朧げな声。
“月の調子はどう?”という問いかけが、現実と夢の狭間へと導いていく。
3. Splash
リズムセクションが暴れ回るインストゥルメンタルで、Canの演奏力と即興的緊張感が極限まで発揮される一曲。
ギター、キーボード、ベースが絶えず変化するモチーフを出し入れし、
水飛沫のように音が跳ね、散り、また戻ってくる。
タイトル通り“飛び跳ねる音”のダンス。
4. Chain Reaction
アルバムの中核にあたる10分超のトラック。
反復するリズムとミニマルなフレーズが、まるで機械の中で何かが徐々に暴走していくようなスリルを生む。
リーベツァイトのドラムが狂気的に美しく、後のテクノやクラブ・ミュージックにも明確に連なるプロトタイプ的楽曲。
5. Quantum Physics
アルバムの終幕は、シンセと残響音がゆっくりと拡張し続ける、静かな音響瞑想。
「量子物理学」というタイトルが示す通り、音の粒子が空間を満たしていくような、非人称的で宇宙的な感覚。
ヴォーカルもビートもなく、ただ振動だけが存在する。
それはもはや“音楽”というより、“存在の反映”である。
総評
『Soon Over Babaluma』は、Canが“歌”という伝達手段を放棄した先で見出した、新たな音楽の地平を記録した作品である。
ここにあるのは、メッセージではなく質感、構造ではなく流動、表現ではなく感応。
それはまさに、“音が音であること”だけを追求した、ミニマルでアブストラクトな旅だった。
『Tago Mago』や『Ege Bamyasi』で見せた混沌やファンクとは異なり、
本作には夜の静けさ、内省の深度、そして音に委ねる無重力感が満ちている。
Canはここで、爆発の次にやってくる“透明な残響”を描いたのだ。
おすすめアルバム
-
Tortoise『Millions Now Living Will Never Die』
ポストロックの金字塔。『Chain Reaction』のリズム構築美を受け継ぐ現代的再解釈。 -
Brian Eno『Before and After Science』
ポップと実験、静けさと知性の同居。Can後期の音響的延長線。 -
Cluster & Eno『Cluster & Eno』
内省的な電子音楽の親密さと即興性。『Quantum Physics』と共鳴。 -
Miles Davis『Get Up With It』
リズムと音の空間化という観点で非常に近い。 -
The Notwist『Neon Golden』
ドイツ発のエレクトロ・ポップ+ポストロック。Can的精神を21世紀に受け継いだ形。


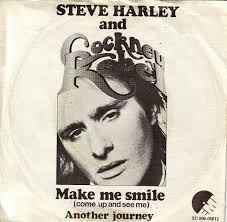

コメント