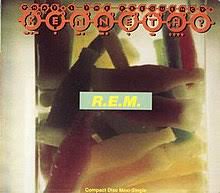
1. 歌詞の概要
「What’s the Frequency, Kenneth?」は、1994年のアルバム『Monster』の冒頭を飾るR.E.M.の代表的ロックナンバーであり、歪んだギターと社会風刺が融合した、90年代的“混乱”を体現する一曲である。
タイトルに使われているこの奇妙なフレーズは、実際に1986年に起きた事件から採られている。CBSのニュースキャスター、ダン・ラザーがニューヨークで暴漢に襲われた際、犯人が繰り返し口にしていたのがこの「What’s the frequency, Kenneth?(周波数を教えろ、ケネス)」という言葉だったのだ。意味不明で、脈絡もなく、まるで都市の雑音のようなこの問いは、90年代アメリカの“情報過多”と“認識の歪み”の象徴としてR.E.M.に引用された。
歌詞は、「君たちの世代はわからない」「アイロニーの使い方を理解しない」「メディアが作った感情を生きている」といった、若い世代とメディア消費社会に対する皮肉と困惑をユーモラスに描写している。一見意味の取りにくい断片的な表現で構成されているが、その混沌とした語り口こそが、時代のノイズを音楽に変換したR.E.M.らしさでもある。
2. 歌詞のバックグラウンド
この楽曲は、R.E.M.が商業的・芸術的な頂点にあった時期に発表されたアルバム『Monster』のリードトラックとして書かれた。前作『Automatic for the People』で静謐な音世界を構築したあと、バンドは意図的によりラウドでラフな“ロック回帰”を志向した。結果として、「What’s the Frequency, Kenneth?」は、グランジやオルタナティブロックの潮流に呼応するかのような歪みと混乱をそのままサウンドに変換した一曲となった。
タイトルの由来は前述のとおり、実際の事件に基づいており、その奇妙さと不条理性が、90年代という時代の象徴的モチーフとして非常にフィットしていた。バンドはこの事件を通して、「意味を持たない問い」「情報の断絶」「現実と虚構の混在」といったテーマを掘り下げ、ポップ・カルチャーのアイロニーと戯れながら、自らの存在意義を問い直した。
加えて、この曲のビデオではマイケル・スタイプがギターをかき鳴らすという演出がなされており、それまでの“内省的で詩的”というR.E.M.のイメージとは一線を画す新たなパブリック・フェイスの提示でもあった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下は印象的なフレーズの一部(引用元:Genius Lyrics):
“What’s the frequency, Kenneth?” is your Benzedrine, uh-huh
「周波数を教えろ、ケネス?」──それが君のベンゼドリン(覚醒剤)なんだな
I was brain-dead, locked out, numb, not up to speed
僕は脳が死んだようで、閉ざされていて、麻痺していて、ついていけなかった
You wore a shirt of violent green, uh-huh
君は毒々しい緑のシャツを着ていた
You said that irony was the shackles of youth
君は言った、「アイロニーは若さを縛る鎖だ」と
You said that sarcasm is all I have left
「皮肉しか自分には残っていない」とも君は言った
Now I’m not looking for absolution / Forgiveness for the things I do
僕は今、赦しを求めてはいない
自分がしてきたことへの免罪を欲しているわけじゃない
これらの断片的なフレーズには、自意識過剰なポップ文化、理解されない世代間の溝、言葉が“機能しなくなった”社会の滑稽さが織り込まれている。特に「アイロニーは若さを縛る鎖」という一文は、若者たちが本心を表すことよりも皮肉や反語に逃げてしまう時代精神を批判的に捉えているとも読める。
4. 歌詞の考察
「What’s the Frequency, Kenneth?」は、意味不明な言葉の連なりの中にこそ、現代社会の不条理とメディア汚染の本質を見出そうとする作品である。
冒頭の問いかけが象徴するのは、“周波数=理解のチャンネル”のズレである。情報に溢れた社会において、誰もが何かを“受信”しているようでいて、実は本当に通じ合っている人は少ない。誰かが叫んでも、その“周波数”が合っていなければ、何も届かない。この曲は、その現代的孤独と断絶感を、エッジの効いたロックサウンドに乗せて提示しているのだ。
また、歌詞にはメディアとポップカルチャーの疲労感が見え隠れする。毒々しいファッション、冷笑的な若者言葉、薬物、テレビ、情報の洪水──これらはすべて90年代における“無力な自意識”のカケラたちである。それを掻き集めて組み合わせ、パズルのように並べ直すことで、R.E.M.は不完全な時代の断面をあぶり出している。
そして、この曲におけるマイケル・スタイプのボーカルは、叫ぶでもなく、説くでもなく、まるで“冷笑的な語り手”のように世界を眺めている。それがまた、曲全体に皮肉とリアリズムのバランスをもたらしている。
(歌詞引用元:Genius Lyrics)
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Smells Like Teen Spirit by Nirvana
アイロニーと怒り、疎外感の炸裂。90年代の若者文化を象徴するグランジの金字塔。 - My Iron Lung by Radiohead
商業的成功と創作の間で揺れる自己認識を描いた、皮肉に満ちたロックナンバー。 - Celebrity Skin by Hole
ポップカルチャーとメディアを笑い飛ばすような、強烈で鮮やかなパンキッシュな一曲。 - Basket Case by Green Day
不安と自意識過剰をポップに描き出した、90年代的“狂気のエンタメ”。 - Perfect Situation by Weezer
メディアとの関係性、誤解、疎外といったテーマをキャッチーに仕上げた名曲。
6. “意味不明”という時代の言葉:R.E.M.が映した90年代のノイズと自意識
「What’s the Frequency, Kenneth?」は、90年代という“意味の霧”の中で、自分の位置を確かめようとするすべての人に向けた、アイロニカルでエネルギッシュな問いかけである。
この曲は、時代の周波数が狂ってしまったとき、人はどうすれば“真実”を受信できるのかを、答えのないまま提示する。叫びではなく、皮肉で。熱狂ではなく、ノイズで。
それはR.E.M.というバンドが、単なるロックグループではなく、社会と文化を同時に映し出す鏡であったことの証左でもある。
この一曲には、理解されたいが、決して迎合したくはない──そんなR.E.M.の矛盾と誠実が、濃密に封じ込められている。
だからこそ、「What’s the Frequency, Kenneth?」は、時代の“受信障害”を体現した、永遠に鮮烈な問いなのだ。


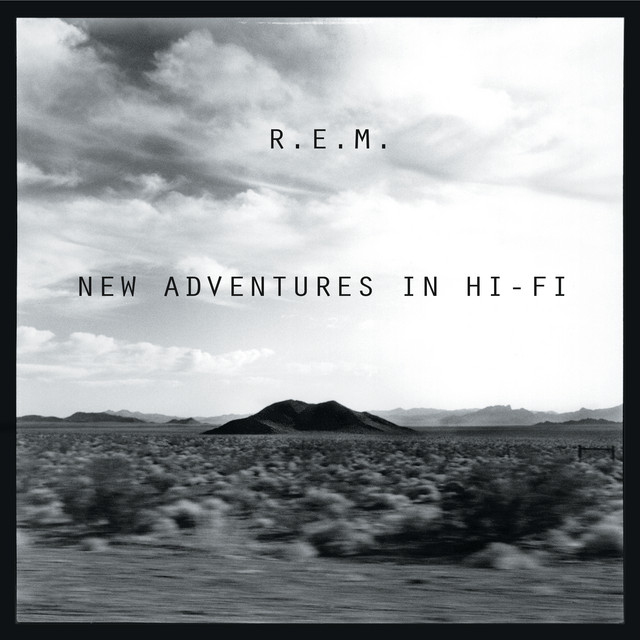
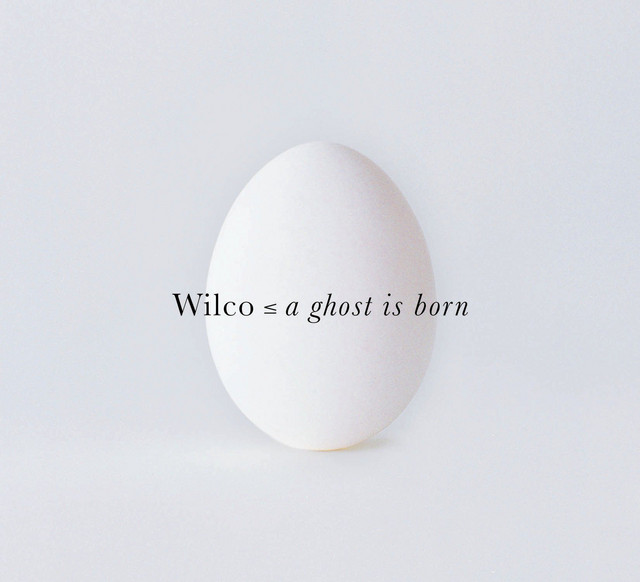
コメント