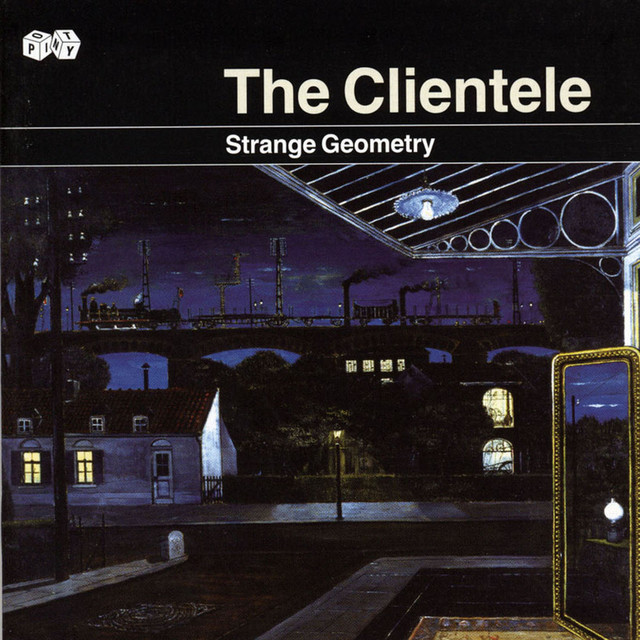
発売日: 2005年8月30日
ジャンル: ドリームポップ、ネオアコースティック、バロック・ポップ、サイケデリック・ポップ
『Strange Geometry』は、The Clienteleが2005年にリリースした3作目のフルアルバムであり、バンドの芸術性とポップセンスが最も美しく交錯した、キャリア中期の代表作である。
プロデューサーにIron & WineやSpoonで知られるBrian Paulsonを迎え、より明瞭な録音と構成の中で、彼らの幻想的なサウンドが一層豊かに響く作品となっている。
前作『The Violet Hour』では、霞がかったギターと囁くようなヴォーカルによって“音の霧”を纏っていたが、本作ではその霧が少し晴れ、より輪郭のあるメロディとハーモニーが前面に押し出されている。
しかし、そこに描かれる情景や感情は依然として曖昧で、夢のようで、手を伸ばしても届かない場所にある。
“Strange Geometry”というタイトルが象徴するのは、規則性のあるようでいてどこか歪んだ心の構造、あるいは都市と自然、現実と記憶の関係性である。
詩的で静謐なリリックと、ジャジーで耽美なアレンジが織りなす本作は、まさに“夜の都市を歩くための音楽”と言えるだろう。
全曲レビュー
1. Since K Got Over Me
アルバムの冒頭を飾る、軽快なギターとメランコリックなメロディが印象的な曲。
“K”という人物の回復と、語り手の取り残された感情のズレが、静かに胸を打つ。
The Clientele流の“失恋ポップ”としての完成度が高い。
2. (I Can’t Seem To) Make You Mine
ソフトサイケ風味のコード進行と、追いかけるようなギターのリフが印象的。
恋愛における距離感、届かない想いを繊細に描写している。
幽霊のようにすり抜けるようなヴォーカルが特徴。
3. My Own Face Inside the Trees
タイトルからして詩的で内省的なこの曲は、記憶と自然の重なりを感じさせるバラード。
木々の中に“自分の顔”を見るというイメージが、都市生活者の孤独や過去との対話を想起させる。
4. Geometry of Lawns
本作のタイトルにも通じる“幾何学”のイメージを象徴する楽曲。
手入れされた芝生、整った日常、その奥に潜む奇妙な違和感を描いているようにも聴こえる。
室内楽のような落ち着いたアレンジが美しい。
5. Spirit
軽やかなリズムとノスタルジックな旋律が特徴的な中盤のアクセント。
“精霊”という言葉が暗示するように、目には見えない感情や記憶の輪郭を描き出している。
6. The Hunger Sisters
リリカルで物語性に富んだ楽曲。
架空の姉妹を描いたこの曲は、語り部的な視点と幻想的なイメージが交錯する。
メランコリーを帯びた旋律が印象的。
7. E.M.P.T.Y.
タイトル通り、“空っぽさ”を主題にしたミニマルなナンバー。
繰り返される言葉と単調なリズムが、感情の希薄さと内面の空洞を浮き彫りにする。
8. When I Came Home From the Party
帰宅後の静けさと、余韻の中に残された孤独や疲労をテーマにした静かな曲。
夜の静けさがそのまま音楽になったような1曲で、アルバム中でも最も内省的な瞬間である。
9. Losing Haringey
ポエトリー・リーディングとインストゥルメンタルが融合した、実験的トラック。
語りによって語られるのは、ロンドン郊外ハリンゲイでの記憶。
記録のようでいて、どこか夢の中の出来事のような語りが印象的。
10. Six of Spades
寓話のような歌詞と、ドリーミーなギターが絡む終盤の楽曲。
タロットカードのような象徴性を感じさせ、ラストへと静かに流れ込む。
11. Step Into the Light
アルバムの締めくくりにふさわしい、穏やかで美しい楽曲。
“光の中へ一歩踏み出す”という希望を含んだイメージで、曖昧な世界からの出口を静かに示している。
総評
『Strange Geometry』は、The Clienteleが初めて本格的なスタジオ録音によって「輪郭のある幻想」を描き出したアルバムである。
それは決してドリームポップの“浮遊感”を失うことなく、むしろ構造を明確にすることで、夢と現実の境界をより美しく際立たせた成果と言える。
特に本作では、リリックの文学性と音の繊細さがこれまで以上に有機的に結びついている。
MacLeanの詩は、風景の中に漂う感情や時間の流れ、記憶の気配を捉えており、それは“言葉による音楽”とでも言いたくなるような完成度を見せている。
同時に、ベースやドラムの躍動、弦楽器の導入によって、バンドとしてのグルーヴも増しており、静かに生きている音楽という印象を強く残す。
『Suburban Light』の霧と、『The Violet Hour』の夕暮れを経て、本作は“夜の街の静かな詩人”としてのClienteleを完成させたと言ってよい。
おすすめアルバム
- Camera Obscura / Let’s Get Out of This Country
文学的でメロディアスなネオアコ作品。哀愁と軽快さのバランスに共通点。 - The Go-Betweens / 16 Lovers Lane
詩的でポップ、都会的な叙情性を持つバンド。語りのような歌詞世界に通じる。 - Trembling Blue Stars / Her Handwriting
内省的なリリックと儚い音像。失われた恋と記憶を音楽にしたような作風。 - The House of Love / The House of Love (1988)
残響系ギターと知的なポップ性が融合。英国らしい湿度が近い。 - The Radio Dept. / Clinging to a Scheme
ノスタルジーと現代性を合わせ持つドリームポップ。控えめな感情表現が重なる。
歌詞の深読みと文化的背景
『Strange Geometry』のリリックは、一見すると日常の断片を静かに綴っているように見えるが、実際には“都市生活者の詩学”とも言えるような深い構造を持っている。
たとえば『Losing Haringey』では、郊外の風景と記憶、時間の重なりが語られるが、そこにあるのはノスタルジーではなく、“記憶のなかでしか生きられない都市”への問いかけである。
また『Since K Got Over Me』や『My Own Face Inside the Trees』では、個人の感情が風景や自然と一体化し、内面と外界の境界が曖昧になっていく。
この感覚こそが“strange geometry(奇妙な幾何学)”の本質であり、Clienteleの音楽が常に“見えるものの向こう側”を描こうとする所以なのだ。
それは、ポップでありながら詩的、具体的でありながら幻想的という、このバンドにしかなしえない独自の構造美と言えるだろう。



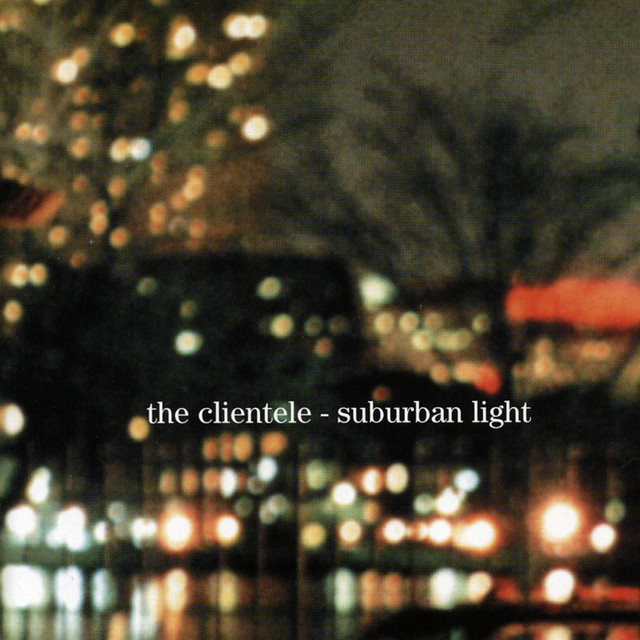
コメント