ロサンゼルスの青い空と、1960年代後半に渦巻くサイケデリックの熱気。
その只中で生まれたバンドSpiritは、ジャズやフォーク、ブルースなど多様なエッセンスを取り込みながら、独創的かつ柔軟な音楽世界を切り開いていった。
結成当初からメンバー間の年齢差や経歴の違いもあり、のちのフォークロックやアートロックの流れにも通じる先鋭性があったのだ。
彼らはヒットチャート上で爆発的な成功を収めたバンドというわけではないかもしれない。
しかし、ギタリストのランディ・カリフォルニアが放つスピリチュアルでサイケデリックな旋律や、エド・キャシディ(ドラム)の静かに燃える技巧は、後世のミュージシャンに深い影響を与えている。
本稿では、Spiritの結成から代表曲・アルバム、そしてその特異な存在感に至るまで、あらためてその軌跡を振り返ってみよう。
結成と背景
Spiritの原型は、ギタリストであるランディ・カリフォルニアと、ドラムを務めるエド・キャシディの親子同然の関係から始まる。
エドはランディにとって義理の父親に近い立ち位置で、ジャズ畑で叩き上げられたキャリアを持ちつつ、1960年代末のロックシーンにも積極的に挑戦しようとしていた。
そこにボーカル兼パーカッションを担うジェイ・ファーガソンやベース担当のマーク・アンデス、キーボードのジョン・ロックなどが加わり、1967年頃にSpiritとして正式に活動を開始する。
当時のロサンゼルスといえば、サーフィンやフォークロックのブームが盛り上がり、同時にドアーズやラヴ、バッファロー・スプリングフィールドなどの新世代バンドも台頭していた。
Spiritはそこにジャズ色をじわりと染み込ませつつ、サイケデリックなムードや先鋭的なアレンジを積極的に導入することで、ほかのグループとは一味違う存在感を放つようになったのだ。
サウンドの特徴
Spiritの音楽を聴いてまず印象深いのは、バンド全体から漂う“折衷性”である。
フォーク調のメロディに、ひらひらと舞うようなギターリフが絡み合い、さらにリズム隊がジャズやブルースのフィーリングを織り交ぜながら、どこか神秘的で浮遊感のあるサウンドを生み出している。
とりわけランディ・カリフォルニアのギタープレイは注目に値する。
彼は若くしてジミ・ヘンドリックスと共演した経験を持ち、そのサイケデリックなアプローチやフィードバックの使い方などを吸収しつつ、より内省的で叙情的な演奏スタイルを育てていた。
一方、ドラムのエド・キャシディはスキンヘッド姿と黒尽くめの衣装で知られ、当時としては高齢(40歳近辺)ながら、しなやかなドラミングとジャズ由来のリズム感でバンドの“柱”となっていたのだ。
加えて、アルバム制作時にはメンバー全員が作詞・作曲に関与し、曲によって色合いがガラリと変わるのもSpiritの面白さのひとつ。
サイケロックの定石を踏襲しながらも、いつのまにかフォークっぽい穏やかさや、あるいはジャズの高揚感が顔を出してくるので、聴くほどに味わいが増していく。
代表曲とアルバム
『Spirit』(1968年)
デビューアルバムは、曲ごとに異なるサウンドアプローチが散りばめられ、バンドの多彩さを見事に示している。
**「Fresh Garbage」は、ジャズロック的ビートの上にサイケ風のギターが舞い、同時代のバンドにはない“クールさ”を放つ名曲。
また、メロディアスで抒情性あふれる「Taurus」**も収録され、後年にレッド・ツェッペリンの「Stairway to Heaven」との類似問題で話題になったことでも知られる。
『The Family That Plays Together』(1968年)
デビューに続けて同年リリースされた2作目。
**「I Got A Line On You」**はエネルギッシュでキャッチーなシングルとして注目を集め、バンドの中でも大衆的ヒットとなった。
ジャズやサイケ風の色彩はそのままに、さらにストレートなロックの勢いが加わり、より聴きやすい仕上がりが印象的だ。
『Clear』(1969年)
3作目の本作は、前2作よりやや実験性が際立つ一方で、コマーシャル路線も狙ったのか、ポップなメロディも並行して見せている。
“クリア”というタイトルが示すように、透明感とミニマルな構成が同居しており、初期Spiritのクロスオーヴァー的アプローチが深化している作品でもある。
『Twelve Dreams of Dr. Sardonicus』(1970年)
多くのファンや批評家がSpiritの最高傑作として挙げるアルバム。
「Nature’s Way」や「Animal Zoo」、**「Mr. Skin」**など、名曲が並び、サイケ・プログレ・フォークのバランスが見事に調和。
デヴィッド・ブリッグス(ニール・ヤングの作品で知られるプロデューサー)とのコラボレーションにより、音像はさらにスケールアップし、“Dr. Sardonicus”なる架空キャラクターを軸にしたコンセプト性もそこはかとなく感じられる。
「Taurus」とレッド・ツェッペリンの論争
Spiritについて語る際、しばしば取り上げられるのが**「Taurus」**とレッド・ツェッペリンの名曲「Stairway to Heaven」との類似問題である。
「Taurus」の冒頭部と「Stairway to Heaven」のイントロが似ていると言われ、バンド側(ランディ・カリフォルニアの遺族)とツェッペリン側の間で法的な争いに発展することもあった。
最終的には裁判が複数回行われたのちにツェッペリン側が勝訴という形になったが、この件を通じてSpiritが再評価されるきっかけにもなったことは皮肉な面もある。
歴史的名曲「Stairway to Heaven」との比較論議は今なおネット上で繰り返されており、そのたびに「Taurus」のサイケデリックな美しさが掘り起こされるという現象が起こっている。
後年の活動とメンバーチェンジ
1970年代前半を過ぎると、メンバーの意向や方向性の相違もあってバンドは何度も分裂や再編を繰り返す。
ジェイ・ファーガソンやマーク・アンデスは別プロジェクトに参加するなどし、ランディ・カリフォルニアとエド・キャシディを中心に名義を存続していく形になった。
その後も『Feedback』(1972年)などの作品を出すが、オリジナルメンバー不在の状態や、時代の潮流がハードロックやディスコへと移り変わることもあり、大きな商業的成功には結びつかなかった。
しかし、バンド自身は断続的に活動を続け、ライヴや一部のアルバム制作を通じて根強いファンを保持してきた。
ランディ・カリフォルニアのギタープレイと音楽的情熱は死の直前まで衰えることなく、その精神をエド・キャシディが支え続けた形である。
影響と再評価
Spiritは驚くほど多様な音楽スタイルを一枚のアルバムでまとめる、実験精神に富んだバンドだった。
このミクスチャー感覚は、のちのアメリカン・プログレッシブ・ロックやアートロック、あるいはジャムバンドのムーブメントにも通じる要素がある。
例えば同郷のスティーリー・ダンが洗練されたジャズ・ロックを模索し、グレイトフル・デッドやフィッシュらがジャム文化を拡大していく上でも、“枠にとらわれない編曲”という点でSpiritの先例は見過ごせないと言えるだろう。
また、サイケデリック・ロックという観点では、ジェファーソン・エアプレインやマザーズ・オブ・インヴェンションにも通じる“奇妙な実験精神”が垣間見えるのがSpirit。
そこにジャズのリズムやブルース、フォークの柔らかさが解け合うことで、独創的なサウンドを確立していた。
彼らの活動が広く再評価されるようになったのは1980年代以降だが、近年ではエド・キャシディやランディ・カリフォルニアへのリスペクトとともに、若い世代のリスナーがアルバムを掘り下げるケースも増えている。
オリジナルエピソードや興味深い逸話
- エド・キャシディの風貌 スキンヘッドに全身黒い衣装という出で立ちから“Mr. Skin”というニックネームを持ち、同名の曲も生まれた。 ジャズドラマーとしての経歴が長く、柔軟かつ確かなテクニックで若いメンバーをリードする父親的存在だった。
- バンド名の由来 Spiritというシンプルでありながら力強いバンド名は、彼らの音楽性にも通じる霊性や自由さを象徴しているとも言われる。 当初はほかの候補もあったが、結局はこの「Spirit」という単語の普遍性がメンバー全員にしっくりきたようだ。
- ランディ・カリフォルニアの名付け親 ランディのステージネーム“カリフォルニア”は、かつて一緒に演奏したジミ・ヘンドリックスが付けたという逸話がある。 ヘンドリックス・バンドにはもう一人“ランディ”というメンバーがいたため、区別のために出身地を付けたのだとか。
まとめ――ジャンルの枠を超えた音楽的冒険
Spiritは、1960年代後半のロサンゼルスから飛び出し、サイケデリックやジャズ、フォークなど多彩な音楽性を大胆に掛け合わせることで、ユニークなサウンドを打ち出した。
ランディ・カリフォルニアの浮遊感あるギターと、エド・キャシディの柔軟なドラミング、そしてほかのメンバーのアンサンブルが生む“ボーダーレス”な世界観は、まさにバンド名が表す“Spirit”のごとき自由と冒険心に満ちている。
大きなヒットこそ多くはないが、**「I Got A Line On You」や「Nature’s Way」**といったロックファンなら誰しもが一度は耳にしたであろう名曲を残し、プログレッシブ・ロックやアートロックにおける重要な架け橋ともなった。
さらに後年の「Taurus」VS「Stairway to Heaven」の論争を通じて、“幻の名曲バンド”として再度脚光を浴びているのも、彼らの音がいかに時代を超え得る魅力を持っているかの証左かもしれない。
もしSpiritを初めて聴くなら、まずは『The Family That Plays Together』や『Twelve Dreams of Dr. Sardonicus』を手に取ってみてほしい。
陽光きらめくLAの空気と、ジャズの薫りが混ざり合う音像に耳を傾けていると、懐かしくも不思議な“自由の息吹”が感じられるに違いない。
それこそがSpirit――文字どおり、ロックの精神を解き放つ原動力だったのだ。




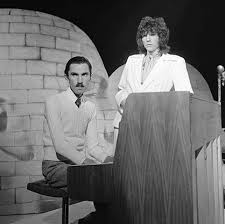
コメント
ニューミュージックマガジンが企画したコンサート出演をドタキャンし、日本ではずいぶんと嫌われたバンドです。