
アルバムレビュー:Simulation Theory by Muse
発売日: 2018年11月9日
ジャンル: シンセウェイヴ、オルタナティヴ・ロック、エレクトロニック・ロック、ポップ・ロック
⸻
概要(約1000文字)
『Simulation Theory』は、Museが2018年に発表した通算8作目のスタジオ・アルバムである。
80年代SF映画やアーケード・ゲームの美学を大胆に取り込み、ネオン、グリッド、クロームの光沢がきらめく視覚世界と、シンセウェイヴ由来のサウンド・テクスチャを統合した。
結果として本作は、ロック・バンドがデジタル時代のポップ表現をいかに自分たちの語法へ翻訳しうるか、その実験の到達点を示す一枚になっている。
背景には、前作『Drones』で復活させたギター主導の強度を維持しつつ、2010年代半ば以降のレトロ・フューチャー再評価の潮流がある。
Museはそこに自身の得意とするアリーナ級の劇性を重ね、アナログ・シンセ、ゲート・ドラム、ヴォコーダー的処理、メタリックなリフを、映画音楽的な和声と巨大なコーラスの中で鳴らし切った。
「現実はシミュレーションなのか?」というポスト・インターネット的な問いを、陰謀、支配、抵抗、癒やしといったモチーフに展開し、テクノロジーと人間の境界が曖昧になる感覚を音で触知させる。
制作面では、長年のコラボレーターであるプロデューサー陣に加え、ポップ畑の人材が関与し、ダンス・ビートとロックの骨格を同居させた。
トラックごとの表情は多彩だが、アルバム全体は「シミュレーションの入口→異常の兆候→感染→反撃→静かな余韻」という物語線で貫かれている。
たとえば「Algorithm」「The Dark Side」で提示される冷たい質感は、後半「Get Up and Fight」「Blockades」での人間的な昂ぶりと対照をなす。
終曲「The Void」では、光の届かない空間に漂うような無重力の抒情が訪れ、聴き手に不安と安堵の混じった後味を残す。
本作は、Museの「過剰」の美学が80s回帰の装いをまとった作品だと言える。
だが単なる懐古ではない。
サイドチェイン的なダイナミクス、ベース・ミュージックの音圧、映画的オーケストレーションを接続し、アーカイヴされた未来像=レトロ・フューチャーを現在のクラブ~アリーナ音響でアップデートしている。
ロックがポップの中心から相対化された2010年代において、Museは「規模」と「演出」の力学で再び大文字の物語を立ち上げようとしたのだ。
⸻
全曲レビュー
1曲目:Algorithm
冷ややかなアルペジオとストリングスが、システムの起動を告げる。
機械音声的な質感と人間的なメロディが衝突し、支配アルゴリズムへの宣戦布告として機能するオープニングである。
2曲目:The Dark Side
疾走するシンセ・ベースとギターが同調。
タイトル通り「暗い側」への引力を、80sバディ・ムービー風の高揚で包み、逃走と追跡のカタルシスを生む。
3曲目:Pressure
ブラス風シンセと跳ねるリズム。
社会的・感情的な「圧」をポップ・ロックの枠組みで前進力へ変換する、ライブ映え必至のアンセムである。
4曲目:Propaganda
ミニマルなビートに艶のあるヴォーカルが絡む。
扇動、偽情報、映像編集のトリックが、官能と嫌悪の狭間でゆらぐ感覚を描写する。
5曲目:Break It to Me
オリエンタルな半音階のギター・リフと、ねっとりとしたベース。
真実を告げる行為の痛みを、粘性の高いグルーヴと遊び心で包み隠す。
6曲目:Something Human
アコースティック寄りの質感とシンセ・パッドの温度感が共存。
ツアー疲労や孤独の回復をテーマに、「人間的な何か」への回帰を穏やかに歌い上げる。
7曲目:Thought Contagion
「思考の感染」という現代的モチーフを、コール&レスポンス的なメロディで増殖させる。
スタジアムで合唱されることを前提に設計された、骨太のミッドテンポ・ロックである。
8曲目:Get Up and Fight
逆境に立ち上がる決意の歌。
キーボードの輝度とギターの壁が重なり、パーソナルな励ましをアリーナ級の広がりに拡張する。
9曲目:Blockades
ストリングスとギターが同時に駆け上がる、クラシカルな高揚。
障壁を突破する感覚を、和声の上昇とリズムの推進で可視化する。
10曲目:Dig Down
ゴスペル的合唱とミニマルなループ。
内面に掘り進む動作を繰り返しの装置で象徴し、希望の芯を掘り当てるような構造を取る。
11曲目:The Void
静寂と残響が支配する終幕。
真空の中で点滅する小さな光のように、脆いメロディがたゆたい、物語を余韻のうちに閉じる。
⸻
総評(約1200〜1500文字)
『Simulation Theory』は、Museがロックの枠に留まりつつ、2010年代のポップ・カルチャーを席巻した“80s的未来像”を、最新の音響圧と舞台演出で再構成した作品である。
サウンド面では、アナログ・シンセの温度とデジタル編集の冷たさ、ギター・リフの手触りとサイドチェインの呼吸がせめぎ合い、バンドの特権である「過剰さ」を新しい形で更新している。
音のレイヤーは厚いが、メロディはあくまで歌えるラインに保たれ、アリーナでの共有可能性が精密に設計されているのだ。
時代的文脈として、2010年代後半はストリーミング普及とレトロ・フューチャー回帰が交差した。
Daft Punk以降の大規模プロダクションが示した“アーカイヴされた未来”の魅力に、シンセウェイヴの映画的想像力が加わり、ポップは別の時間軸を参照しはじめる。
Museはここで、Radiohead的な内向の抽象化ではなく、スピルバーグ~キャメロン~ゼメキス的な“語りの大文字化”へ進んだようにも思える。
つまり、複雑化した現実を寓話に変え、ネオンの光で輪郭を太く描く手法である。
本作の強みは、コンセプトと設計の一体感にある。
「Algorithm」「The Dark Side」が示す“起動~異常”の導入から、「Thought Contagion」「Get Up and Fight」での感染と抵抗、「The Void」の静穏という出口へ至るまで、アルバムは一続きの体験として編まれている。
個別曲のフックが強い一方で、曲順によって意味が上書きされ、緊張と解放の配分がアリーナ規模のダイナミクスで管理されているのだ。
ミキシングは低域を厚く保ちつつ高域のきらめきを強調し、ミドル帯を整理することで、群衆のざわめきの中でも輪郭が溶けないバランスを実現している。
批評的には「過度にポップ」「過去の意匠に依存」といった指摘もありうる。
しかし本作の肝は、過去の意匠を複製するのではなく、現在の音圧とライヴ設計の知恵で“再演出”する点にある。
ギター中心へ回帰した『Drones』直後に、ここまで大胆にポップへ切り返す柔軟性は、Museのキャリアにおける重要な“揺り戻し”であり、ブランドの可塑性を証明した。
結果、『Simulation Theory』はアリーナ・ロックがポップの文法を横取りし、同時にSF的想像力で大文字の物語を更新しうることを示した作品なのだ。
今なおライヴの現場で曲が強く機能するのは、そうした設計思想が的確に実装されているからだろう。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Black Holes and Revelations / Muse
ポップと宇宙的スケールの接合点。メロディの強度が本作と響き合う。 - The 2nd Law / Muse
デジタル処理とオーケストレーションの同居。レトロ・フューチャー以前の布石。 - Absolution / Muse
アリーナ級の劇性と黙示録的テーマの基点。重心の低い参照軸。 - Hurry Up, We’re Dreaming / M83
映画的シンセ・ポップの名盤。80s的抒情の広がりを補完する。 - OutRun / Kavinsky
シンセウェイヴの記念碑。夜の都市を走る感覚をサウンドで体感できる。
⸻
制作の裏側
本作の制作陣は、ロックとポップ双方の現場を知るプロデューサー/エンジニアが中核を担い、楽曲ごとに最適な音響設計を当て込んでいる。
ヴィンテージ/モダン双方のシンセ群(アナログ系ポリ、FM、モノフォニック)が、ギターと同格の“主役”として配置され、音色の立ち上がりや減衰にまで演出的な意味が与えられた。
ドラムはゲート処理やリバーブ・テイルのコントロールで80sの質感を再現しつつ、現代的なローエンドの量感を確保。
ライヴ想定のクリックとトリガー運用を前提に、スタジアムPAでの再現性を高めたセッション設計が採られている。
⸻
歌詞の深読みと文化的背景
「Thought Contagion」は、SNS時代におけるミームや陰謀論の伝播を“感染症”として描く。
群衆の同調圧力とメディア循環の副作用を、コール&レスポンスの形式で増殖させる構造が巧みである。
「Algorithm」「The Dark Side」は、支配アルゴリズムによる世界の“演算可能性”と、その影で肥大する恐怖を対にし、制御と自由の綱引きを露出する。
「Something Human」「Get Up and Fight」は、テクノロジーの疲労の中でなお人間的な共感に救いを見いだす章であり、アルバムの黒い回路に暖色を差し込む役割を担う。
「The Void」は言葉少なに、真空の孤独と微細な希望を点滅させ、物語を余韻へと退かせる。
⸻
ファンや評論家の反応
リリース当時、80s回帰の強さとポップ指向に賛否は割れた。
一方でシングル群は配信時代の文脈で強く機能し、ライヴでは合唱と演出の相乗効果で評価を伸ばしたのも事実である。
アルバム単位の物語設計と、単曲での即時性を両立させたことが、長期的な聴取に耐える鍵になったのだ。
⸻
後続作品とのつながり
『Simulation Theory』でのポップ~シンセ志向は、Museのレパートリーにおいて以後も重要な“引き出し”として残る。
ギター主導の作品へ再度振れても、シンセとポップの演出を自在に出し入れできる体制が整った点が大きい。
本作は、バンドの“可塑性”を制度化したアルバムでもあるのだ。
⸻
ビジュアルとアートワーク
ネオン、ワイヤーフレーム、グリッドが交錯するアートワークとMV群は、80s的未来像を現代に召喚する装置として機能。
紫とシアンのコントラスト、クロームの輝度、ホログラム的処理は、サウンドのきらめきと同期し、音と映像が相互に補完し合う。
アルバム体験が“映画的”に感じられるのは、この視覚設計があってこそである。



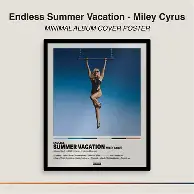
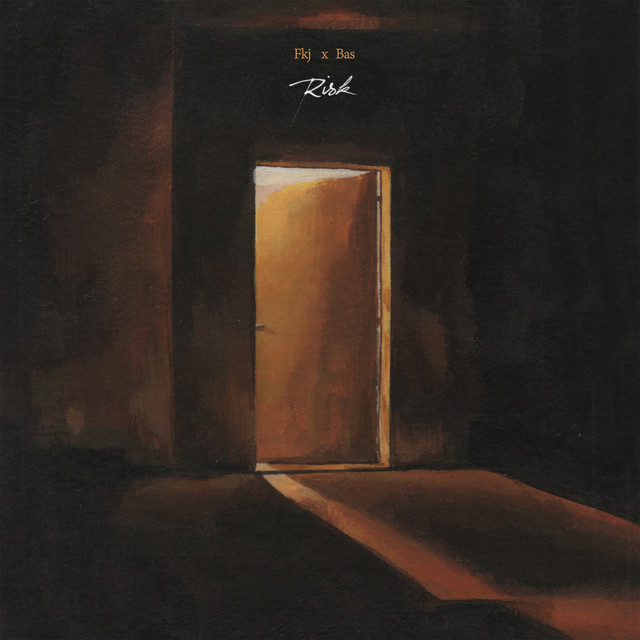
コメント