
発売日: 2020年4月17日
ジャンル: ポップ、オルタナティヴR&B、ニューメタル、Y2Kポップ、エレクトロニカ
⸻
概要
『Sawayama』は、Rina Sawayamaが2020年に発表したデビュー・スタジオ・アルバムであり、ジャンルの壁を大胆に越えながら、個人史とアイデンティティを鋭く掘り下げた21世紀ポップの金字塔である。
日本生まれ・ロンドン育ちのRina Sawayamaは、ケンブリッジ大学で心理学と政治を学んだ異色の経歴を持つアーティスト。本作は、彼女の名字をそのまま冠したセルフタイトル作であり、アジア系としてのルーツ、家族との関係、社会的疎外、ジェンダー、そして自己肯定などをテーマに、自らの物語をポップのフォーマットで語りきった壮大な作品である。
プロデューサーには盟友クラレンス・クラリティが名を連ね、サウンド面ではブリトニー・スピアーズやChristina Aguileraを彷彿とさせるY2Kポップから、ニューメタル、ハイパーポップ、バラード、R&Bまでが縦横無尽に交差する。
その豊かなジャンル横断性と、批評的思考を持つリリックは、音楽メディアやSNSで大きな話題を呼び、The GuardianやPitchforkなどが「2020年代のポップを定義する作品のひとつ」として絶賛した。
⸻
全曲レビュー
1. Dynasty
アルバムの幕開けを飾る壮大なナンバー。ギターリフとストリングスが交差する劇的な構成の中で、「家族の呪縛」と「それを断ち切る自分」が歌われる。自己物語のプロローグとして圧倒的な重みを持つ。
2. XS
バロック調のギターフレーズと、Y2K風ポップが融合した怪作。過剰な消費主義を皮肉たっぷりに描いたリリックと、耳に残る「エクセス(XS)」というフックの中毒性が特徴的。
3. STFU!
ニューメタルとJ-Popが奇跡的に融合したキラートラック。アジア人女性としての差別体験を怒りと皮肉で叩きつける衝撃作。日本語の発話やサンプリングも交え、政治性とパーソナルが融合するRinaの代表曲。
4. Comme Des Garçons (Like the Boys)
ファッションブランド名を引用し、男性的な自信を“借用”して自らを肯定するアイロニックなクラブ・チューン。ディスコとファンク、ハウスを滑らかに接続し、ジェンダー観の再定義に挑む。
5. Akasaka Sad
東京・赤坂を舞台に、アイデンティティの曖昧さと心の孤独を重ね合わせたメランコリックな楽曲。イギリスと日本という二重の文化の間に引き裂かれる彼女の痛みが、美しい旋律に託される。
6. Paradisin’
2000年代のアニメ主題歌のようなノスタルジックなポップ。思春期の記憶と自由への渇望を、キラキラとしたサウンドで包んでいる。サックスの使い方も遊び心に満ちている。
7. Love Me 4 Me
自己肯定をテーマにしたファンク調のポップナンバー。Mary J. Bligeへのオマージュを感じさせる構成で、アルバムの中でも最も“希望”に満ちたトラックのひとつ。
8. Bad Friend
ミニマルなサウンドとエモーショナルな歌声が響くバラード。友情をうまく維持できなかった罪悪感と後悔を、静かに吐露する。電子的な処理が逆に人間味を増幅させる。
9. Fuck This World (Interlude)
わずか1分強のインタールードだが、Rinaの世界観を詩的にまとめた小さな宇宙。静謐な音と怒りの言葉のギャップが印象的。
10. Who’s Gonna Save U Now?
ライブのような歓声を取り入れた壮大なアンセム。敗北と勝利が交差する構成で、サビの爆発力は圧巻。Rinaが自身の“ポップ・スター性”を自覚した瞬間とも言える。
11. Tokyo Love Hotel
“東京ラブホテル”という比喩を通して、アジア的エキゾチシズムに消費される感覚と、文化的空虚を描き出す。浮遊感のあるR&Bビートが痛みを包み込む。
12. Chosen Family
LGBTQ+コミュニティや移民への賛歌。生まれた家族ではなく、選び取った関係性を称えるバラードであり、Beabadoobeeやオルタナ勢とは異なるRinaの“社会的スタンス”が明確に現れている。
13. Snakeskin
クラシック音楽をサンプリングしながら、データ社会とアイデンティティの再構築を語る異色の終曲。変拍子やコラージュ的展開が、最後に新しい混沌へと導いていく。
⸻
総評
『Sawayama』は、ジャンルを越え、文化を越え、アイデンティティの“外側”にまで手を伸ばした、まさにハイブリッド時代のポップアルバムである。
Rina Sawayamaは、「何者にもなれなかった自分」を逆手に取り、「何者にもなれる表現者」として自身を再構成した。このアルバムは、その実践の記録であり、アジア系ディアスポラ、クィア、Z世代など、多様な“周縁の声”に対する共感の磁場となっている。
また、Y2K以降の音楽的資源を見事に再編し、ポップの形式に社会的な“問い”を組み込んだ手腕は特筆すべきで、ポストインターネット世代の新しい“政治的ポップ”として記憶されるべき作品だ。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Charli XCX『how i’m feeling now』
ハイパーポップの爆発力と自己露出の極限がRinaのスタイルと共鳴。 - Lady Gaga『Born This Way』
ポップを通じてマイノリティを讃える思想とスケール感が重なる。 - Poppy『I Disagree』
メタルとポップの融合、そして“ジャンル越境”の先鋭さがRinaのアプローチと類似。 - FKA twigs『Magdalene』
身体性と文化的アイデンティティを表現に昇華したアート性が共通。 - Björk『Post』
ジャンルレスで自己と世界を再構成する意志と感性の先駆者。
⸻
歌詞の深読みと文化的背景
『Sawayama』のリリックは、自己物語の語り直しであると同時に、「西洋的な普遍性」からの逸脱を鮮やかに描く行為でもある。
特に“STFU!”では、アジア人女性としてのステレオタイプへの怒りを、ユーモアと攻撃性で反転させている。また“Tokyo Love Hotel”では、日本という国が他者に消費される空虚さをラブソングに仮託し、“Akasaka Sad”では「日本人であること」と「そうでない自分」の矛盾が吐露される。
“Chosen Family”は、家族という制度を選択的関係へと転換し、ポストモダンな共同体の可能性を示唆する曲であり、本作全体が「新しい居場所の構築」というテーマで貫かれていることが分かる。
Rina Sawayamaの言葉は、その鋭さと優しさの両方において、現代を生きる誰かの「もう一つの声」となるのだ。


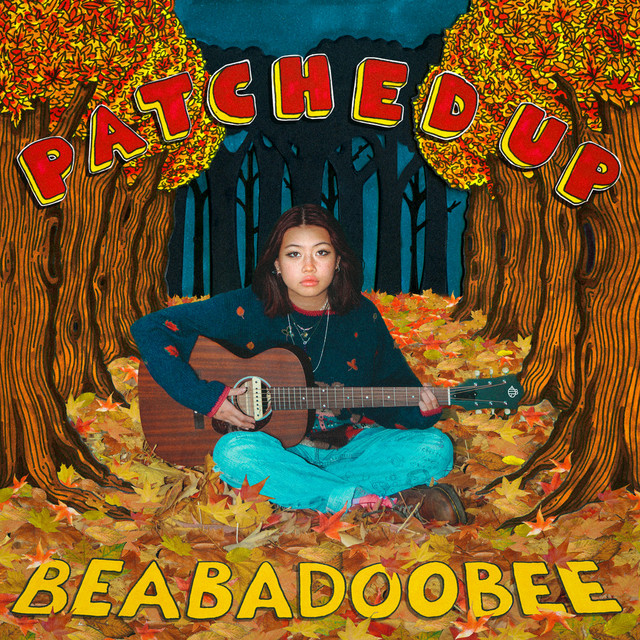

コメント