
発売日: 2017年10月27日
ジャンル: Y2Kポップ、R&B、オルタナティヴ・ポップ、エレクトロポップ
⸻
概要
『Rina』は、Rina Sawayamaが2017年に自主リリースした初のEPであり、彼女の音楽的個性とアイデンティティの基盤を築いた作品である。
日本生まれ・ロンドン育ちという自身のハイブリッドなバックグラウンドを反映しながら、90年代〜2000年代初頭のポップ/R&Bのエッセンスをモダンに再構成。ブリトニー・スピアーズ、Christina Aguilera、宇多田ヒカルなどへの愛情を感じさせつつ、当時のベッドルームポップやハイパーポップと異なる、明確に“構築されたポップ”としての美学を確立している。
本作では、若き日の不安や孤独、承認欲求、デジタル時代の自己イメージといったZ世代的なテーマが、極めてキャッチーなメロディとヴィジュアル志向の世界観で描かれており、Rina Sawayamaというアーティストの“始まり”にして“完成”された宣言的な作品である。
⸻
全曲レビュー
1. Ordinary Superstar
オープニングを飾るY2K風シンセポップ。自分のことを「普通のスーパースター」と形容するセルフアイロニーと、華やかなサウンドのギャップが絶妙。アイドル文化やフェイムへの皮肉も込められている。
2. Take Me As I Am
R&Bを基調としつつ、サビではハウス的な広がりを見せるパワフルな自己肯定ソング。「ありのままの私を受け入れて」というメッセージがシンプルながらも力強い。
3. 10-20-40
恋愛の段階を数字で表現した実験的な構成。リズムの変化とビートの分裂的展開が、感情の不安定さを音で体現している。
4. Tunnel Vision (feat. Shamir)
幻想的でアンビエントなトラック。Shamirとのデュエットが、心の迷路をさまようような内省的世界観をより立体的に演出する。
5. Time Out
一時停止を求める心の叫び。クラシックなポップ構成と、90年代の少女向けアニメ主題歌のような無垢さが交錯する。
6. Alterlife
本EPのハイライトとも言えるナンバー。ギターリフとシンセが混ざり合いながら、自己変容(=オルターライフ)をテーマにしたサウンドが爆発する。過去から脱皮し、別の人生を生きる決意を感じさせる。
7. Through the Wire
Kanye Westの同名曲とは異なり、こちらは通信やデジタル依存をモチーフとした楽曲。ネット越しの人間関係と、それに伴う疎外感を詩的に表現。
8. Cyber Stockholm Syndrome
最終曲にして最大の衝撃作。デジタル社会に生きる者が、ネット空間という“監禁場所”に安心を覚えてしまうという、現代的なアイロニーをテーマにした傑作。2000年代J-Popとクラブカルチャーの融合がここに極まる。
⸻
総評
『Rina』は、Rina Sawayamaが世界に向けて放った第一声であり、彼女の音楽性、思想、そしてヴィジョンがすでに完成されていたことを示す作品である。
本作では、単に懐古的なY2Kポップに終始するのではなく、その懐かしさを「今」の感性でアップデートし、そこに鋭い社会的視点やアイデンティティの複雑さを埋め込むことで、他にはない唯一無二のポップスを生み出している。
Rinaは本作を通じて、グローバルに活躍するポップアーティストとしての可能性を提示しつつ、「アジア人としての私」「ネット時代の私」「不完全な私」といった多層的な自己像を音で編んでいく。
『Rina』は、すべての“名前を持たない違和感”に名前を与えるような作品であり、今聴いてもその先進性と切実さは決して色褪せない。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Utada Hikaru『Exodus』
J-Popと欧米ポップの境界を越えた実験作。Rinaの音楽的ルーツに直接つながる。 - Robyn『Body Talk Pt. 1』
ポップの構築性と感情の複雑さを両立させた傑作。『Cyber Stockholm Syndrome』と通じる世界観。 - Grimes『Art Angels』
セルフプロデュースによるジャンルミックスと、ヴィジュアルへのこだわりが共鳴。 - Janet Jackson『The Velvet Rope』
自己と向き合う内省的ポップの金字塔。『Rina』の内面性にも通じるものがある。 - Charli XCX『Pop 2』
アヴァンギャルドで実験的なポップスの集大成。Rinaの音楽的未来形としても比較される。
⸻
歌詞の深読みと文化的背景
本作のリリックには、Rina Sawayamaが経験してきた文化的断絶、ジェンダー的規範、メンタルヘルス、SNS依存など、現代的でかつパーソナルなテーマが凝縮されている。
“Cyber Stockholm Syndrome”では、監視と依存のはざまで快楽を見出すという、まさにポストデジタル時代の精神構造を見事に描写。また、“Alterlife”では自己再生の物語が語られ、個人的な痛みを“もう一つの人生”というかたちで昇華している。
これらは単なるポップソングではなく、Z世代的な存在論を音楽に落とし込んだ“哲学的ポップ”とも言えるだろう。


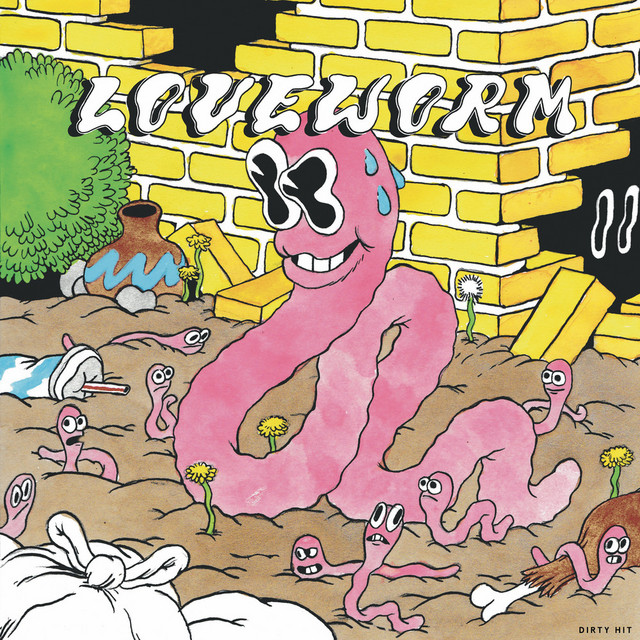
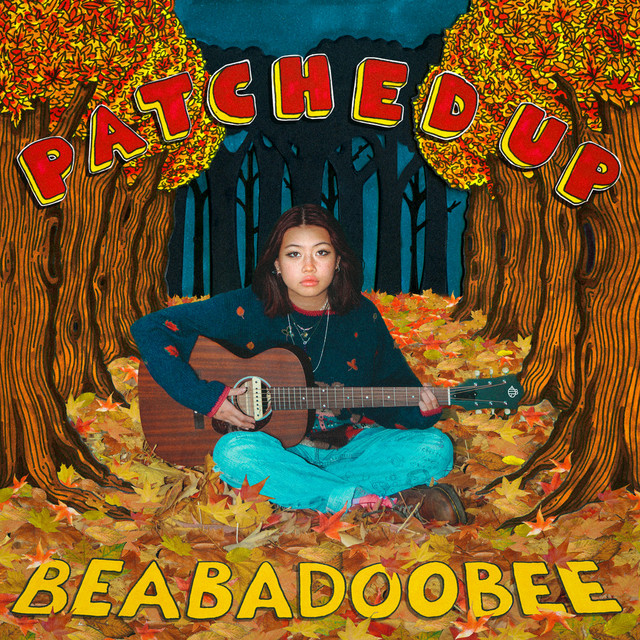
コメント