
発売日: 1974年11月
ジャンル: アート・ポップ、グラム・ロック、バロック・ポップ
概要
『Propaganda』は、Sparksが1974年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、前作『Kimono My House』でのブレイクを経て、より複雑かつ実験的な音楽性へと踏み込んだ意欲作である。
ロンとラッセルのメイル兄弟を中心に据えた本作では、シアトリカルでバロック的な構築美と、シニカルなユーモア、そして現代社会への鋭い風刺がさらに先鋭化している。
クラシカルなコード進行に乗せて展開されるスリリングなポップナンバーの数々は、グラム・ロックの商業的枠組みを軽やかに超え、ニュー・ウェイヴの萌芽をも感じさせる。
シングルヒットした「Never Turn Your Back on Mother Earth」や「Something for the Girl with Everything」に象徴されるように、本作はSparksが“風刺と感傷”を両立させる唯一無二の存在であることを再確認させる作品である。
全曲レビュー
1. Propaganda
1分にも満たないアカペラのイントロ曲。
“Propa-ganda, Propa-ganda”という反復と転調が、すでにただならぬ知性と演劇性を示している。
アルバムのタイトルを冠し、皮肉と崇高さの両極を提示する開幕。
2. At Home, at Work, at Play
めまぐるしい展開と変拍子を繰り返す、超人的ポップ・アート。
「家庭でも職場でも遊びでも支配される人間」の滑稽さと虚無を、躍動的な音像で風刺する。
ロン・メイルのピアノが跳ね回り、ラッセルのファルセットが熱量を加える。
3. Reinforcements
“増援部隊”という軍事的メタファーを用いながら、人間関係の崩壊や救済の不在を描く。
ポップでありながら不安を煽るようなメロディ進行が印象的で、短い中にもドラマ性が凝縮されている。
4. B.C.
“Before Christ”の略語をタイトルに据え、過去へのロマンと現在のアイロニーを重ねる歴史的モチーフの曲。
宗教、文化、恋愛の視点が重なり合い、知的で奇妙な魅力を放つ。
5. Thanks But No Thanks
軽やかなメロディに対して、「感謝するけど、結構です」という曖昧で攻撃的な態度が歌詞に表れる。
受容と拒絶が表裏一体であることを、Sparks流のユーモアで描いた作品。
6. Don’t Leave Me Alone with Her
“彼女と二人きりにしないで”というタイトルがすべてを物語る、ブラック・コメディ的な楽曲。
恐怖と誘惑、嫌悪と愛情の奇妙なせめぎ合いを、極端な展開で表現している。
7. Never Turn Your Back on Mother Earth
本作の代表曲であり、Sparksのキャリアにおいても屈指の名バラード。
母なる大地を擬人化し、人間の自然に対する背信を詩的に描く。
哀愁に満ちたメロディと切実なリリック、シンプルなアレンジが深く胸を打つ。
8. Something for the Girl with Everything
アルバム内で最もキャッチーなナンバーで、軽快なピアノとハンドクラップが印象的。
すべてを持つ少女に“もっと”を贈ろうとする行為が、消費社会の欲望と虚しさを逆説的に示す。
アイロニーの効いた祝祭歌。
9. Achoo
風邪のくしゃみをテーマにした奇抜な楽曲。
“アチュー!”という声がそのままサビに登場する異色作ながら、病を比喩にした人間関係のストレスを描く巧妙さが光る。
10. Who Don’t Like Kids?
“子どもが嫌いなんて人、いる?”という皮肉を込めた風刺曲。
無垢と邪悪の間で揺れる子ども像を、多層的なコードと演奏で描き出す。
11. Bon Voyage
ラストを飾るのは、旅立ちと別れをテーマにした優美なバラード。
“良い旅を”という一見穏やかな言葉の裏に、決定的な断絶や諦念を含ませるのがSparks流。
アルバム全体の奇抜さとは対照的な、静かな幕引きが印象的である。
総評
『Propaganda』は、Sparksが『Kimono My House』で築いた成功のフォーミュラを維持しつつ、それをさらに先鋭化し、複雑化させた知性と演劇性の極地である。
演奏はタイトでアレンジは実験的、リリックは社会風刺と風変わりなロマンスが交錯し、すべての楽曲が“ひと癖もふた癖もあるポップ”として機能している。
グラム・ロックの煌びやかさを残しつつ、より文学的でアート・ロック的な展開を見せるこのアルバムは、Sparksというユニットの“次なる段階”を明確に示した一作であり、のちのニュー・ウェイヴ、バロック・ポップ、オルタナティヴ・ポップの源流としての意義も大きい。
あらゆる“ジャンル”や“常識”へのユーモアある抵抗、それこそが『Propaganda』の本質なのである。
おすすめアルバム(5枚)
-
Brian Eno – Taking Tiger Mountain (By Strategy) (1974)
同年に発表された知性と奇妙さの融合作。ポップの前衛という共通点がある。 -
10cc – How Dare You! (1976)
風刺性と完成度の高さでSparksと並び称される知的ポップの代表格。 -
Roxy Music – Country Life (1974)
美と毒、演劇性と知性の交錯するグラム/アート・ポップの名盤。 -
Kate Bush – The Kick Inside (1978)
声の演劇性と奇妙なリリック世界という点で、女性版Sparks的な作品。 -
Devo – Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! (1978)
風刺、知性、変則性のロック解体的アプローチがSparks以後の文脈を体現。


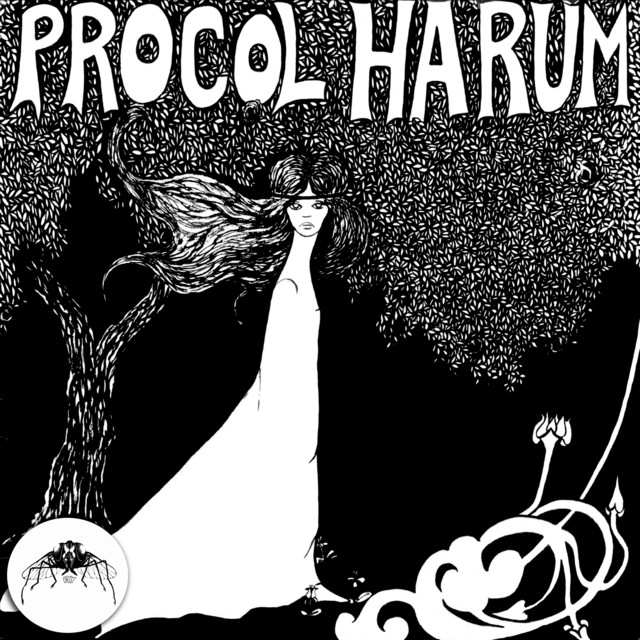
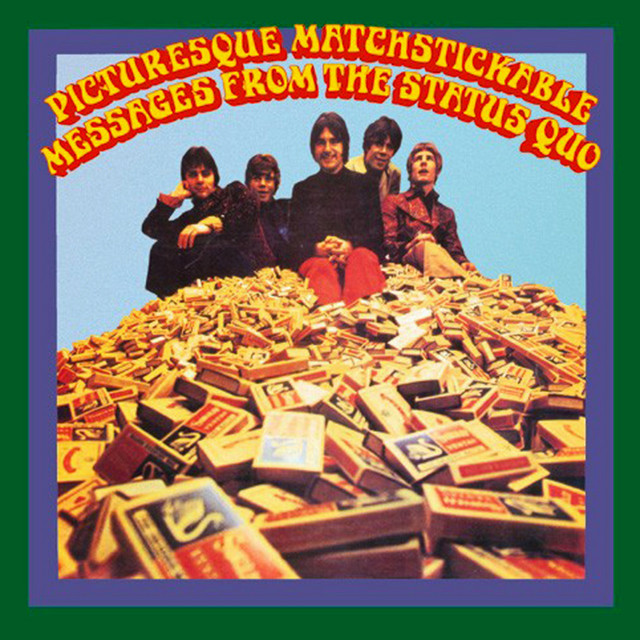
コメント