
発売日: 2000年5月16日
ジャンル: エクスペリメンタル・ロック、ノイズロック、アートロック、ポストロック
亡霊と詩人が徘徊する都市——“音楽”で詩を書くという試みの極北
2000年、Sonic YouthはNYC Ghosts & Flowersを発表する。
これは“バンド史上最も異質で詩的な作品”として知られる一枚であり、
同時に“ギターを盗まれたバンドが、言葉と音の境界を壊しながら作り上げた、都市の亡霊たちのアルバム”でもある。
実際、1999年のツアー中、彼らは使用していた多数のギターとエフェクターを盗難によって失っており、
結果としてこのアルバムでは、即興演奏や詩的朗読、無調ギター、ドローン的展開が強く前面に押し出されることとなった。
かつてないほどに“音”ではなく“声”と“質感”に重きを置いた作品であり、
その挑戦的すぎる内容は、当時批評家の間でも賛否が大きく分かれた。
だが現在振り返れば、この作品こそがSonic Youthの“ポスト音楽的表現”の到達点のひとつであり、
“音楽と詩と都市と記憶”の境界線を、じわじわと溶かしていった風変わりな傑作と見ることもできる。
全曲レビュー:
1. Free City Rhymes
12分に及ぶオープニング。
低速でうねるギターのドローンと、Thurston Mooreのスポークン・ワードが交錯する。
“自由都市”という言葉の皮肉が、漂うような音像の中で重く響く。
2. Renegade Princess
Kim Gordonが囁くように歌い、語り、息を吹きかける。
“裏切りの王女”という名の存在が、都市の闇と性を象徴する。
詩と音のあいだに溜まる“間”が、不穏で艶めかしい。
3. Nevermind (What Was It Anyway)
再びThurstonによるポエトリーリーディング。
何かを“気にしないで”という反語的タイトルが、むしろ喪失感を浮き彫りにする。
ポストビート文学のような構造。
4. Small Flowers Crack Concrete
Kimによる政治的な語りと、硬質なサウンドの対比。
“コンクリートを割る小さな花”は、抑圧と抵抗の象徴。
都市の中のわずかな生命を、破裂音のようなギターが後押しする。
5. Side2Side
リズムもメロディもない。
代わりにあるのは、Kimが語る“意味の断片”と、ギターの断続的な軋み。
スラム詩人のモノローグのようにして、都市の輪郭が浮かび上がる。
6. StreamXsonik Subway(本作には未収録)
※補足:この曲は前作A Thousand Leavesに収録されており、本作には含まれない。混同注意。
7. Lightnin’
ジャンクなビートと歪なリズムが構築する中、Lee Ranaldoが語りを展開。
実在した詩人“Lightnin’ Hopkins”へのオマージュとも取れる、不定形のトリビュート。
8. NYC Ghosts & Flowers
タイトル曲にして、最も象徴的なトラック。
ギターが霧のように立ち込める中、詩人たちの亡霊と都市の記憶が重なっていく。
Leeの語りは祈りのようでもあり、呪文のようでもある。
この街に棲む“音にならないもの”たちが、最後にそっと息を吹き返す。
総評:
NYC Ghosts & Flowersは、Sonic Youthが“ロックバンド”としての枠を完全に脱し、
詩人、アーティスト、亡霊、ジャーナリスト、そして都市の観察者として振る舞った作品である。
ノイズもメロディも意図的に削ぎ落とされ、代わりに立ち現れるのは、
言葉のざらつきと、音の“消える直前”の余韻、沈黙の輪郭だ。
それは決して聴きやすい作品ではない。
だが、音楽が“語られないこと”や“名づけられない感情”に触れるとき、
このアルバムは都市という亡霊たちの記録簿として、しずかにその存在を主張してくる。
おすすめアルバム:
-
Laurie Anderson / Big Science
詩と電子音が交錯する、都市のリリシズムの原点。 -
John Cale / Music for a New Society
沈黙と痛みが共存する、詩的ドキュメント。 -
Patti Smith / Radio Ethiopia
ポエトリーとロックが高次に融合する“語る音楽”。 -
Scott Walker / Tilt
音楽というより芸術行為としてのサウンドの極北。 -
Sonic Youth / Murray Street
本作の詩的方向性にバンド感を取り戻し、再構築した2000年代の傑作。



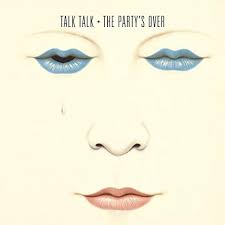
コメント