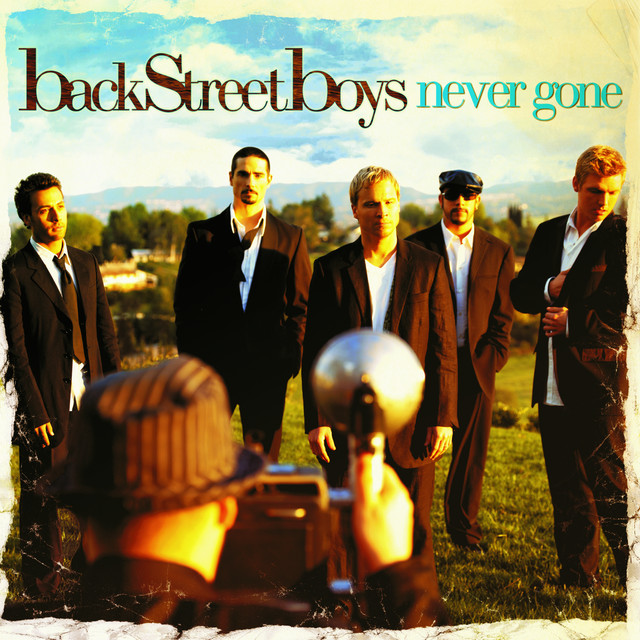
発売日: 2005年6月14日
ジャンル: ポップ、アダルト・コンテンポラリー、ポップ・ロック
『Never Gone』は、Backstreet Boysが2005年に発表した復帰作であり、1990年代後半に世界的ポップ・グループとして頂点を極めた彼らが、成熟したサウンドとバンド的なアレンジへ舵を切ったことを示す作品である。
一世を風靡したデビュー〜『Black & Blue』期から数年が空き、ティーン・ポップのブームも沈静化し、さらにメンバーの体調や私生活の変化も重なった時期に作られたアルバムであり、単なる「再始動」ではなく「成長した姿をどう提示するか」という課題に正面から向き合った1枚なのだ。
本作の大きな特徴は、打ち込み主体のダンス・ポップから、ギター・ベース・ドラムによるバンド的な質感、そして大人向けのメロディを強く押し出したことである。
それまでの彼らは、マックス・マーティンらスウェーデン勢のソングライティングと、R&B寄りのバラードを武器に“声のそろった美しいボーイ・グループ”として機能していたが、2000年代半ばには音楽シーン全体がロック/ポスト・グランジ/アダルト・コンテンポラリー寄りの音への回帰を見せていた。
『Never Gone』は、そうした時代感のなかで「まだ僕らは終わっていない」「でも同じやり方には戻らない」というメッセージを形にしたアルバムなのである。
また、タイトルの“Never Gone(いなくなったわけじゃない)”という言い回しそのものが、活動休止やポップ・ブームの終わりを経た彼らがファンに対して発する、ある種の宣言になっている。
90年代にティーンエイジャーだったリスナーが20代半ば〜後半になっていたことを考えると、このアルバムは「かつてのファンが今の自分でも聴けるBsb」を作ることを最初から意識しているとも言える。
よってサウンドは派手すぎず、歌唱も以前よりも“聴かせる”方向にシフトしている。ハウイーやブライアンの柔らかい高音、AJの深みのあるボーカル、ニックの少年性の残る声が、よりアーシーなバックトラックと絡むことで、グループとしての立体感がはっきりとしたのである。
アルバム全体に通底するのは「後悔」「赦し」「再出発」といった感情である。
失われたものを振り返りながらも、そこに留まらず前へ進もうとする語り口が多くの楽曲で繰り返され、これまでラブソング中心だった彼らの歌詞世界にわずかな陰影と年齢相応のまなざしが加えられた。
この世代のボーイ・グループが2005年というタイミングで出すにふさわしい、成熟と継続のアルバムなのである。
- 全曲レビュー
1曲目:Incomplete
アルバムの象徴的なリード曲であり、Bsbが“バラードの王道”に戻ってきたことを高らかに告げる1曲である。
ピアノとストリングスを軸にしたドラマティックな構成で、サビではメンバー全員のハーモニーが重なり合い、失われた関係を取り戻したいという切実な感情が押し寄せる。
「I am incomplete(僕は未完成のまま)」というフレーズは、この時期のグループ自身の状態をも暗示しているようで、オープニングとして実に象徴的なのだ。
2曲目:Just Want You to Know
ここで一気に80s的なギター・ポップのテンションが上がり、前曲のしっとりしたムードとのコントラストが生まれる。
ややロック寄りのビートに乗せて、忘れられない恋を明るめのトーンで歌い上げることで、アルバムが“バラード一辺倒ではない”ことを早々に提示している。
ミュージックビデオでもコミカルなパロディ感を見せた曲で、当時の彼らがシリアスになりすぎず、ポップ・グループとしてのサービス精神も残していたことが分かる。
3曲目:Crawling Back to You
ややミッドテンポで、2000年代前半のアダルト・コンテンポラリーによく見られたギターとピアノの絡みが印象的な楽曲である。
タイトルどおり「また君のもとへ戻ってしまう」という弱さと執着を描き、歌詞もサウンドも適度に大人びている。
コーラスの重ね方が巧みで、ボーイ・グループとしての強みを新しいサウンドに移植する試みが見える。
4曲目:Weird World
イントロから優しいアコースティック・ギターが鳴り、前の曲までの恋愛中心のムードから少しだけ視野が広がる。
混沌とした世界や変わりゆく状況の中で、支え合うことの大切さを歌う楽曲で、2000年代半ばのポップがよく用いた“世界の異常さを背景にしたパーソナルな愛”という構図に近い。
5人のハーモニーが柔らかい布のように全体を包み、アルバムの中継ぎとして心地よく機能している。
5曲目:I Still…
アルバムの中でもっともロマンティックで、かつセンチメンタルな一曲である。
別れたあとも消えない想いを、過剰に泣き崩れず、淡くにじませるように歌っているのがポイントで、これも“成長したBsb”の表現なのだろう。
メロディは非常に耳に残りやすく、2005年当時のJ-POPリスナーにも通じる歌心がある。
6曲目:Poster Girl
ここで少しテンポが上がり、ポップ寄りの遊び心が戻る。
タイトルどおり“ポスターの女の子”=アイドル的存在への憧れを描きつつ、シニカルに語る部分もあり、グループが長くショービジネスにいたことを感じさせる。
サウンド的には前半のシリアスさを一度ほぐす役割を担っている。
7曲目:Lose It All
ピアノを軸にしたしっとりとした楽曲で、失うことの恐れと、それでも愛を選ぶという決意を歌う。
ブライアンの堂々としたボーカルが中心に立ち、そこに他メンバーのコーラスが重なることで、90年代の彼らを思わせる“多層の声のドラマ”が再現されている。
アルバムの感情線をもう一段階深くするポイントになっている。
8曲目:Climbing the Walls
タイトルから想起されるとおり、閉塞感や出口のなさをモチーフにした一曲。
ギターの歪みがやや強く、ポップ・ロック的なアプローチで、2005年当時にラジオを席巻していたロック寄りポップにも呼応している。
ここでのBsbは“ポップスを歌う5人”というより“5人でロック調の曲をこなすバンド的ユニット”として鳴っており、アルバム全体の音像を広げている。
9曲目:My Beautiful Woman
温かいコード感と優しいメロディが心地よい、ラブソングの王道。
ここではリスナーを特定の年代に閉じ込めず、万人が聞ける普遍的な愛情表現を選んでいるのが特徴である。
中盤以降のハーモニーの重なりがアルバムの中で一番“懐かしいBsbらしさ”を感じさせるかもしれない。
10曲目:Safest Place to Hide
タイトルどおり「君のそばが一番安全な場所」という非常にBsbらしい愛の比喩を用いたバラードである。
しっとりとした導入から、サビで大きく開くという構成が実に彼ららしく、ファンが期待する“泣ける一曲”をここでしっかりと回収している。
終盤に向けてアルバムを落ち着かせる役割もある。
11曲目:Siberia
ややダークで、寒さや距離を感じさせる歌詞が印象的な終盤曲。
失恋の痛みを“シベリア”という極寒の比喩で語ることで、情景と感情を一体化させている。
ここまでの明るさ・成熟・再出発といったテーマの裏側にある“失われたものへの悔恨”を改めて示すことで、アルバムに奥行きを与えている。
12曲目:Never Gone(地域によってはボーナス扱い)
アルバム・タイトル曲として、別れと継続、記憶と現在を架橋するような、最終的なメッセージを担った楽曲である。
“僕たちはいなくなったわけじゃない”というタイトルが示すように、グループの存在証明そのものがテーマになっており、アルバム全体を優しく締めくくる。
この曲があることで、2005年版Backstreet Boysの物語はきれいに円を描く。
- 総評(約1200〜1500文字)
『Never Gone』は、Backstreet Boysのキャリアにおいて明確な転換点を示した作品である。
それは単に“再結成後のアルバム”というだけではなく、“90年代ボーイ・グループが2000年代半ばにどう生き延びるか”という問いに対する、彼らなりの実践的な答えだからである。
ダンス・ポップやR&Bに寄った過去作の路線をそのままなぞることもできたはずだが、当時のUS/UKポップ市場では、マルーン5やクリーンなポップ・ロック、あるいは成人向けACが強く、ティーン向けアイドル・ポップは勢いを落としていた。
『Never Gone』はそうした状況を読み、バラードとポップ・ロックを軸に「大人になったファンが聴いても不自然ではないBsb」を提示してみせたのである。
この“年齢に合わせる”というのは、ポップ・グループにとって非常に難しい課題である。
若さやきらめき、アイドル性だけで成立していた時期を過ぎてしまうと、たいていのグループはイメージを保てずに失速するか、逆に過剰に大人化してオリジナルの魅力を失ってしまう。
だが本作のBsbは、ボーカル・グループとしての最も大きな武器――精度の高いハーモニーと、感情の乗ったユニゾン――を手放さずに、サウンドの質感だけをロック/AC寄りに寄せることで、ブランドの継続とアップデートを同時に成立させた。
これは、同時期に活動していた他の90sボーイ・グループと比べても、構造的にうまい落としどころである。
また、歌詞面でも「ただの恋の歌」に留まらず、失われた関係や、時間の経過、もう一度やり直すことの難しさと希望が繰り返し語られる。
これはグループ自身の歴史――健康問題、ソロ活動、人気の浮き沈み――と深く重なっており、聞き手は無意識のうちに“これは彼ら自身の物語でもある”と感じるはずだ。
こうした“作品の外側の物語”をうまく内側に取り込むことができたのが、本作が単なる復帰盤に終わらず、キャリアの中で特別な位置を占める理由である。
音響的には、90年代のリッチで光沢のあるポップ・サウンドからややマットな質感にシフトしており、ギター、ピアノ、ストリングスが前面に出るミックスになっている。
これは当時のロック/ポップのトレンドと足並みを揃えた結果であると同時に、メンバーの声をより“楽器的に”聴かせるための選択でもある。
プロデューサー陣も、かつてのような“とにかくヒットさせるための最強ポップ”を全面に押し出すのではなく、バンド的な手触りを残したアレンジを採用しており、ここから先のBsb――たとえば『Unbreakable』以降の落ち着いた路線――への橋渡しとしても自然な仕上がりになっている。
2005年という時代背景を考えると、本作は“90年代アイドルの生き残り策”という文脈で語られがちだが、実際には“ボーカル・グループをアダルト・ポップにソフトランディングさせた好例”として評価するべきだろう。
同世代のリスナーが家庭を持ち、仕事をしている中で、かつてのアイドルが過去の栄光だけでなく“今でも聴ける歌”を届ける。
この構図がきちんと成立している点で、『Never Gone』はBackstreet Boysという名前の持つ文化的価値を延命させた重要作なのである。
- おすすめアルバム(5枚)
- Black & Blue / Backstreet Boys
2000年時点でのポップ路線の完成形。『Never Gone』と聴き比べると質感の違いが分かりやすい。 - Backstreet Boys / Backstreet’s Back
90年代黄金期のサウンドを押さえておきたいときの必聴盤。ハーモニーの若々しさが際立つ。 - Millennium / Backstreet Boys
グループ最大の商業的成功作。ここから『Never Gone』までのギャップを埋める文脈として最適。 - Under My Skin / Avril Lavigne (2004)
同じ時期の“ロック寄りポップ”の空気を感じられる1枚。2000年代前半のサウンドトレンド確認に。 - Songs About Jane / Maroon 5 (2002)
ポップとバンドサウンドの中間で成立した代表的アルバム。『Never Gone』の方向転換を理解しやすくなる。 - 制作の裏側
『Never Gone』の制作は、グループの再始動と同時に「サウンドの再定義」を行う作業でもあった。
かつてのように外部ソングライターから一方的に楽曲を提供してもらう形ではなく、メンバーの声質や年齢に合ったキー、より自然に歌えるレンジが吟味されている。
そのため、過去曲のように高音フェイクで押し切る場面は少なく、むしろ中音〜やや低めの音域を気持ちよく鳴らすことに重点が置かれている。
また、ライブでの再現性も意識されており、バンドを従えたステージでもアルバムの雰囲気が壊れないようなアレンジが採用されているのだ。
- 歌詞の深読みと文化的背景
本作における「戻る」「まだ終わっていない」「ここにいる」というフレーズは、2000年代初頭に一度表舞台から退いたポップ・スターたちがよく用いたレトリックと重なる。
ブリトニー、N Sync、5ive、Westlifeらが一斉に登場した時代のあとの、いわば“ポスト・アイドル期”であり、そこで再度自分たちの居場所をつくるためには、恋愛だけでなく“関係性の修復”や“時間の経過”を歌う必要があった。
『Never Gone』はその要請に応えたアルバムであり、だからこそ当時のファンが大人になって聴き直したときにも違和感が少ないのである。
- ファンや評論家の反応
リリース当時、往年のダンス・ポップを期待していた一部リスナーからは「落ち着きすぎている」「もっとアップテンポが欲しい」という声もあった。
しかし長期的には“歌のグループとして生き続けるための重要作”という評価が定着しており、後年のアコースティック寄りのステージや、各メンバーのソロを含むライブ構成にもこのアルバムの影響が見て取れる。
日本でも『Incomplete』を入口として、90年代にハマっていた層がもう一度彼らを聴き始めるきっかけになった作品なのだ。

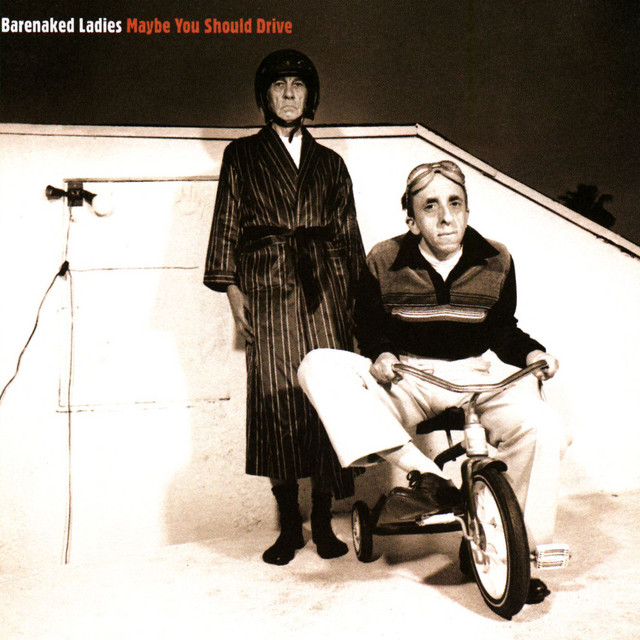

コメント