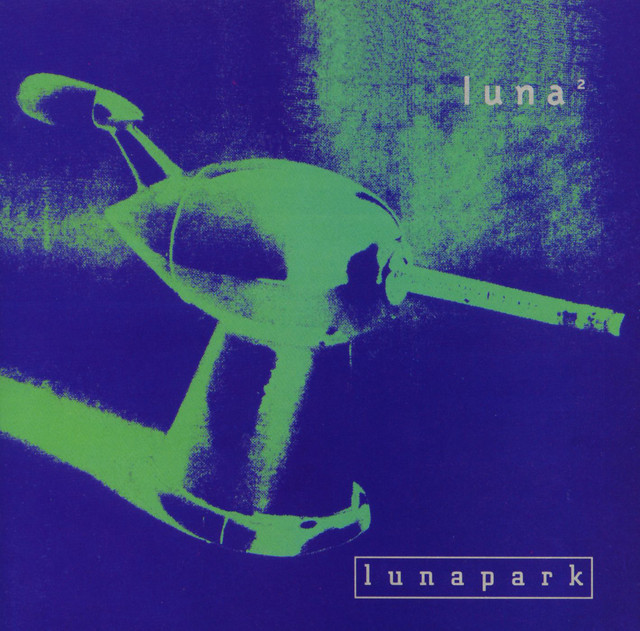
発売日: 1992年6月23日
ジャンル: ドリームポップ、インディー・ロック、スロウコア
概要
『Lunapark』は、Galaxie 500解散後にフロントマンのディーン・ウェアハムが結成したバンド、Lunaのデビュー・アルバムであり、1990年代初頭のインディー・ロックの流れに新たな光と陰影をもたらした静謐な名作である。
プロデュースはフレッド・マー(元Scritti Politti)、メンバーにはThe Chillsのジャスティン・ハレル(ベース)とThe Feeliesのスタンリー・デメスキー(ドラム)という精鋭が揃い、
Galaxie 500のドリーミーな浮遊感を継承しながら、よりリズムに重心を置いた“夜の街角のような”アンサンブルが展開されている。
「Lunapark(ルナパーク)」というタイトルは、“遊園地”を意味しつつも、どこかくすんだメランコリアが漂う。
Lunaというバンドの本質が、まさにこの言葉の中にある――楽しげで、でも心のどこかに影を抱えた音楽なのだ。
全曲レビュー
1. Slide
アルバムの冒頭を飾る、Lunaの世界観を凝縮したような楽曲。
クリーントーンのギターとつぶやくようなヴォーカルが、都会の夜を思わせる滑らかさで進行する。
2. Anesthesia
痛みを和らげるはずの“麻酔”がテーマの、皮肉と抑制の効いたナンバー。
穏やかなサウンドの中に、醒めた視線が滲む。
3. Slash Your Tires
印象的なタイトルとは裏腹に、繊細なメロディが流れる叙情的なトラック。
日常の衝動と倦怠の間で揺れる、Lunaらしい都市の詩。
4. Smile
短く、やさしい曲。
“笑って”という命令形が、逆説的に無感情さを強調するようで、寂しさが際立つ。
5. I Can’t Wait
やや明るめのコード進行と浮遊感あるギターが美しい。
だが“待ちきれない”という言葉には、どこか不穏な焦燥が混ざる。
6. Great Jones Street
ドン・デリーロの小説から引用されたタイトル。
ミニマルな構成で、静かな暴力性を感じさせる一曲。
Lunaの“文学性”が最も強く表れているトラックのひとつ。
7. I Want Everything
欲望と虚無を同時に歌う、内省的スロウナンバー。
ギターのレイヤーが美しく、Luna特有の“過剰ではないエモーション”が光る。
8. Time
アルバム中でもっともグルーヴ感のある一曲。
淡々と刻まれるリズムの中に、時間の経過と変わらぬ心情の反復が響く。
9. Crazy People
語りかけるようなリリックと、ユーモアを滲ませた展開。
狂気を身近なものとして描く、Lunaらしい距離感の楽曲。
10. Goodbye
静かな別れの歌。
感情を抑えたメロディがかえって胸に迫る、アルバムのハイライト。
11. Werewolves
月(Luna)と狼男。象徴的な最終曲として、自己変容と夜の衝動を暗示。
サウンド的にもサイケ寄りで、ドリーミーな締めくくりにふさわしい。
総評
『Lunapark』は、Lunaというバンドが“静かな夜にしか見えない感情”を鳴らす存在であることを、最初から明確に示したデビュー作である。
ここには派手なカタルシスはない。
だが、ささやき、反復、余白の美学によって、聴く者の心の奥底に小さな波を立てる音楽がある。
ディーン・ウェアハムの声は相変わらず感情の頂点に行かず、それが逆に“わかってしまう痛み”をリアルに描く。
それはポスト・ブームの90年代インディーシーンにおいて、グランジとは異なる“もう一つの沈黙”の系譜を切り拓いた。
『Lunapark』は、その最初の一歩として、誰もが心の中に持つ寂しさと静かな希望にそっと手を差し伸べる音なのだ。
おすすめアルバム
- Galaxie 500 / On Fire
ディーン・ウェアハムの前身バンドによる、ドリームポップの金字塔的名作。 - Yo La Tengo / Painful
同時代の知的インディー・ロックとして、Lunaと共鳴する温度感。 - Mazzy Star / She Hangs Brightly
より幻想的でスローな感覚のある女性版Luna的世界観。 - The Feelies / Only Life
本作にも参加しているスタンリー・デメスキーが所属。静けさの中の熱量が通じ合う。 - Red House Painters / Rollercoaster
スロウコア的感傷と都市の孤独感という点で、Lunaと響き合う重要作品。
制作の裏側と文化的背景
90年代初頭、グランジとブリットポップに挟まれるようにして、アメリカ東海岸から静かに広がった“ポスト・ベルベット”な音の潮流があった。
その先頭に立ったのが、Galaxie 500の残響を引き継ぐLunaだった。
『Lunapark』はSub PopやMatadorといった当時のインディー・レーベルの文脈とはやや異なり、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとニューヨーク文学、映画的構成と抑制された感情表現を軸に据えた新しい美学を提示した。
華やかさを拒み、ひとりでいることの強さと弱さを抱きしめるようなこのアルバムは、“静かな革命”として今なお語り継がれるべき名作である。


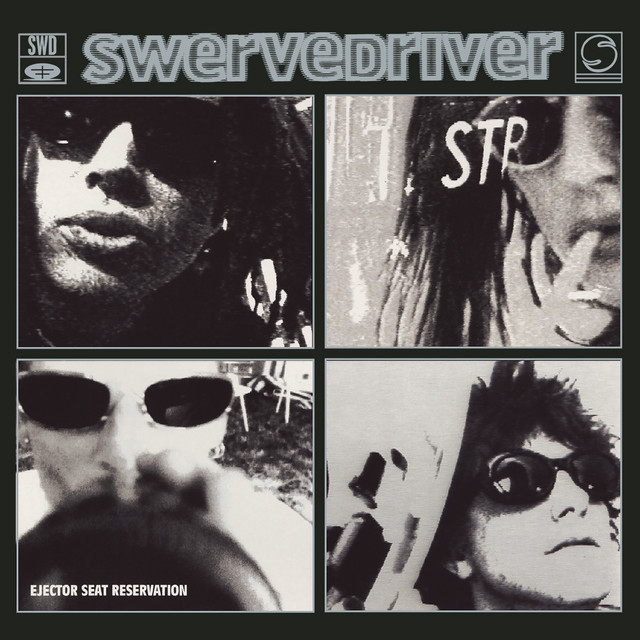
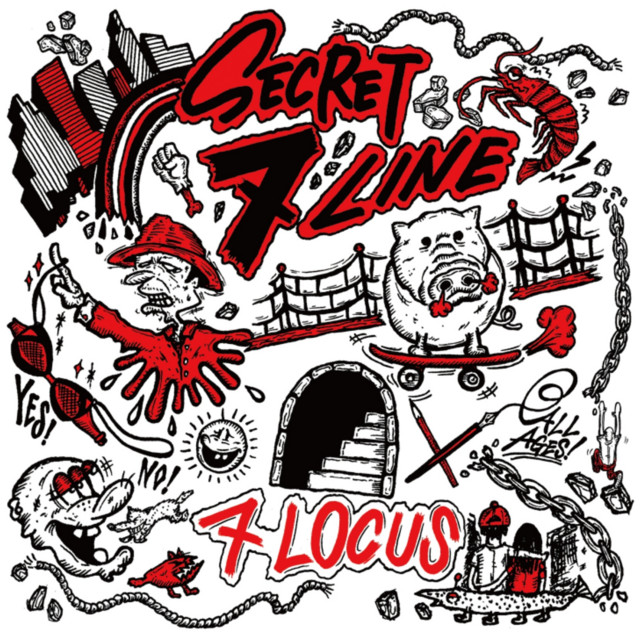
コメント