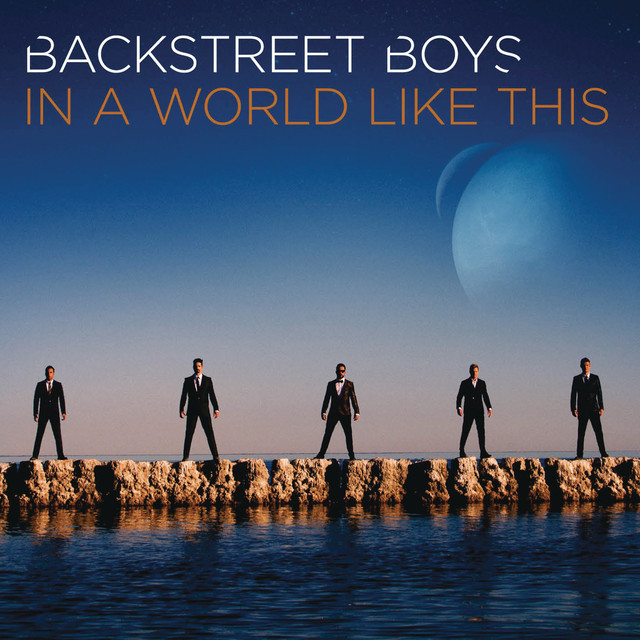
発売日: 2013年7月24日
ジャンル: ポップ、アダルト・コンテンポラリー、フォーク・ポップ
『In a World Like This』は、Backstreet Boysが2013年に発表した8作目のスタジオ・アルバムであり、デビュー20周年を記念した節目の作品である。
本作では脱退していたケヴィン・リチャードソンが復帰し、久々に5人編成での活動が再開された。
デビュー時からのファンにとって、それは「原点回帰」でありながらも、「成熟したBsb」としての再確認でもあった。
タイトルの“In a World Like This(こんな世界の中で)”という言葉が象徴するように、本作は単なるラブソング集ではなく、現代社会の不安や混乱の中で“それでも愛と信頼を信じる”というメッセージを内包している。
サウンド面では、エレクトロやダンス・ポップの要素を抑え、アコースティックやオーガニックな質感を重視。
20年を経た5人の声が穏やかに調和し、成熟したバンドサウンドとしての完成度を高めている。
『Never Gone』や『Unbreakable』で築いたアダルト・ポップ路線を、さらに自然体へと昇華させた本作は、まさに“時を超えて生き残ったグループ”の記録なのだ。
3. 全曲レビュー
1曲目:In a World Like This
アルバムの表題曲にしてリードシングル。
アコースティック・ギターを主体とした軽やかなサウンドに、普遍的な愛のメッセージを乗せたナンバーである。
「こんな世界の中でも、愛は勝つ」というテーマは、単なる恋愛を超えた人間賛歌のようでもある。
透明感のあるサウンドと希望に満ちたメロディが、20周年を迎えたBsbの穏やかな自信を感じさせる。
2曲目:Permanent Stain
キャッチーなリズムと切ないメロディを融合させたミディアム・テンポの曲。
“君という存在は僕の心に消えない染みのように残る”という比喩が印象的で、成熟した恋愛の苦さを描く。
AJのソウルフルな声が中心に立ち、他のメンバーのハーモニーが柔らかく包み込む。
3曲目:Breathe
ストリングスとピアノが美しく絡むバラード。
“息をするように君を思う”という詩的な歌詞が心に残る。
ブライアンの清らかな高音とケヴィンの深みのある低音が対照的に響き、復帰後の5人の調和を感じられる楽曲である。
4曲目:Madeleine
ファンの間で特に人気の高い曲。
孤独や苦しみを抱えた少女“マデリーン”に語りかけるように歌われる。
「君はひとりじゃない」というメッセージは、かつて10代だったBsb世代のリスナーが大人になり、今度は誰かを励ます側に回る――そんな構図を想起させる。
グループの人間的な温かさが滲み出た1曲である。
5曲目:Show ‘Em (What You’re Made Of)
本作を象徴するもう一つの重要曲。
タイトルの意味は“自分の本当の姿を見せてやれ”――つまり自己肯定と誇りの歌である。
AJとブライアンがリードを取り、力強くも穏やかなメッセージを伝える。
ドキュメンタリー映画『Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of』(2015)にも引用されたことからも、グループにとって特別な位置づけの楽曲だ。
6曲目:Make Believe
幻想的なサウンドと甘いメロディが特徴のラブソング。
“君がいると現実が夢のように変わる”というロマンティックな世界観で、穏やかな幸福感を描く。
ハーモニーの完成度が高く、特に中間部のコーラスの展開が美しい。
7曲目:Try
アコースティック・ギターが心地よい、内省的なミディアム・テンポ。
「何度でも挑戦してみよう」という前向きなメッセージを、柔らかいトーンで伝える。
シンプルだが心に残る構成で、アルバム全体の“再生”というテーマを支える。
8曲目:Trust Me
軽やかなポップチューンで、ビートルズ的なメロディセンスが光る。
“信じてほしい”という言葉を、甘く軽快に繰り返すことで、アルバム中でもっとも明るくキャッチーな瞬間を生み出している。
9曲目:Love Somebody
モダンなR&Bのエッセンスを取り入れたナンバー。
“本気で誰かを愛せるか”という問いを、やや切ないメロディで表現する。
ヴォーカルの分担が巧みで、特にニックとAJの掛け合いが印象的。
10曲目:One Phone Call Away
アコースティックを基調にした静かなラブソング。
“たった一本の電話で君のもとに駆けつける”という、Bsbらしい誠実さと優しさに満ちた歌詞。
エンディングに向けて、アルバム全体の温度がじんわりと上がっていく構成が見事である。
11曲目:Feels Like Home
軽快で開放的なサウンドが心地よいナンバー。
タイトル通り“ホーム(居場所)”をテーマに、グループの絆とファンへの感謝を歌う。
5人が帰ってきたことの象徴として、ライブでも人気の高い曲だ。
12曲目:Soldier
“君を守るために戦う兵士になる”という強い誓いを歌うラストナンバー。
ピアノとストリングスが織りなす壮大なアレンジの中で、メンバーの声が一人ずつ浮かび上がる。
最後に「We’re still here(僕らはまだここにいる)」というメッセージが滲み出る、完璧なエンディングである。
4. 総評(約1300文字)
『In a World Like This』は、Backstreet Boysが20年のキャリアを経て“音楽的にも人間的にも成熟した姿”を提示したアルバムである。
ケヴィンの復帰によって声のレンジが広がり、かつての5人のハーモニーが完全復活したことはファンにとって最大の喜びだった。
しかしこの作品は単なる懐古ではない。
90年代の輝きと2000年代の経験を融合し、“現在のBsb”として自然に成立している。
サウンドは全体的にアコースティックで温かく、過剰なプロダクションを避けている。
2000年代のエレクトロ・ポップ路線から一歩引き、声とメロディの力を中心に据えた構成が印象的である。
“年齢を重ねても歌で勝負できるグループ”としての誇りが感じられ、ポップ・グループとしては異例の円熟味をたたえている。
テーマ的にも、恋愛だけではなく“信頼”“再出発”“絆”“感謝”といった普遍的な要素が多く、デビュー当時の若さとは異なる深い情感が宿っている。
特に「Show ‘Em (What You’re Made Of)」に込められた“自分の本当の姿を見せよう”というメッセージは、アイドルとしてのイメージを脱ぎ捨てた彼らの現在地を象徴している。
“完璧さ”よりも“誠実さ”を選んだアルバムなのだ。
また、制作面ではマーティン・テレフェ(Jason MrazやJames Morrisonのプロデューサー)が関与しており、ポップにフォークやアコースティック要素をブレンドするセンスが活かされている。
この方向性は、Bsbの原点である“歌声の美しさ”を最大限に引き出し、メンバー全員がヴォーカリストとして成熟したことを証明している。
同時期のポップ・シーンでは、エレクトロ・ダンスが主流であったが、Bsbはあえてその流れに乗らず、静かな感動と人間味を武器に勝負した。
その姿勢は、もはや彼らが“時代の波に乗る存在”ではなく“時代に寄り添う存在”へと変化したことを意味している。
この立ち位置の変化こそ、長寿グループとしての強さなのだ。
商業的にも、アルバムは日本やヨーロッパで高い評価を得て、ワールドツアー「In a World Like This Tour」ではファン世代を超えた熱狂が再び生まれた。
往年のファンだけでなく、新しいリスナーにも届く“ポップの普遍性”を獲得した点で、Backstreet Boysの第二の黄金期を象徴する作品と言えるだろう。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Never Gone / Backstreet Boys (2005)
アコースティック寄りの路線を初めて本格導入した作品。『In a World Like This』の原型。 - Unbreakable / Backstreet Boys (2007)
4人体制時代の静かな名作。再結集後との比較で進化が分かる。 - This Is Us / Backstreet Boys (2009)
エレクトロ・ポップ路線の代表作。対照的なサウンドの流れを楽しめる。 - Under the Mistletoe / Justin Bieber (2011)
同時期のアコースティック・ポップとの共鳴を感じられるアルバム。 - To Be Loved / Michael Bublé (2013)
成熟したポップ・ヴォーカルの文脈で近しい空気感を持つ。
6. 制作の裏側
『In a World Like This』の制作は、バンド自身がレーベルを離れ独立した状態で行われた。
メジャーの制約から解放されたことにより、サウンド面での自由度が増し、メンバーの意見がより直接的に反映された作品になっている。
レコーディングは主にロサンゼルスで行われ、プロデューサーのマーティン・テレフェが自然な音の広がりを重視した。
その結果、リスナーの耳に“生きた声”として届く仕上がりとなっている。
また、20周年という節目を意識して、歌詞にもキャリア全体を振り返るような内容が多く含まれている。
特に「Show ‘Em」や「Feels Like Home」は、長年支えてきたファンに対する感謝の手紙のようでもある。
7. 歌詞の深読みと文化的背景
『In a World Like This』のメッセージは、2010年代初頭の世界情勢とも密接にリンクしている。
経済危機、災害、紛争など、不安が続いた時代において、“それでも愛と絆を信じる”という姿勢は大きな意味を持った。
“こんな世界の中でも愛がある”というタイトル曲のメッセージは、希望の再確認であり、グループの人生観そのものを反映している。
また、「Madeleine」のように、リスナー自身の苦しみに寄り添う視点も含まれており、Bsbが単なるアイドルを超えて“癒しを届けるアーティスト”として位置づけられた瞬間でもある。
8. ファンや評論家の反応
リリース当時、ファンの反応は非常に温かかった。
ケヴィンの復帰を歓迎する声が圧倒的で、5人の声が再びひとつになったことへの感動がSNSやライブ会場を埋め尽くした。
評論家からも“Backstreet Boys史上もっとも人間的なアルバム”として評価され、声の表情の豊かさが絶賛された。
また、アルバムを引っ提げたツアーではアコースティック演奏を中心に据え、華美な演出よりも“歌そのもの”で魅せる構成が話題を呼んだ。
それは、20年を超えるキャリアの中で“本当に伝えたいこと”を明確に見据えたBsbの姿を示していた。
結論:
『In a World Like This』は、Backstreet Boysが“過去を懐かしむ存在”ではなく、“今も進化し続けるアーティスト”であることを証明したアルバムである。
どんな世界の中でも、彼らのハーモニーは希望の象徴であり続ける。
それは、ポップ・ミュージックの時代を超えた“人間の声”の力を改めて実感させる一枚なのだ。

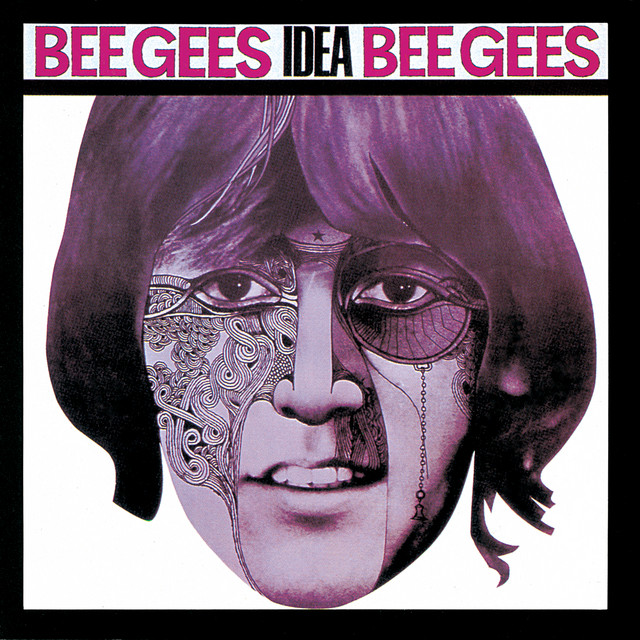

コメント