
発売日: 2022年9月16日
ジャンル: ポップ、オルタナティブ・ポップ、カントリー、Y2Kポップ
『Hold the Girl』は、Rina Sawayamaが2022年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、自己救済とトラウマの克服をテーマにした壮大なコンセプト・ポップ作品である。
前作『Sawayama』でポップの革新者として名を轟かせたRinaは、本作においてより内面的で叙情的な領域へと踏み込み、自らの過去と対峙しながら、癒しの物語を紡いでいる。
音楽的には、2000年代初頭のY2Kポップの香りを色濃く残しつつ、カントリー、ゴスペル、UKガラージ、パワーバラードなど多彩なジャンルを織り交ぜている。
プロデューサーにはPaul Epworth(Adele、Florence + the Machine)をはじめ、Stuart Price、Clarence Clarityらが名を連ね、映画的なスケール感を支えている。
Rina自身が“セラピーのようだった”と語るこの作品は、歌詞と音像が緊密に連動し、聴く者に深い共感とカタルシスを与えるよう構成されている。
本作は、単にジャンルを混ぜ合わせたポップというだけでなく、「心の傷」と「癒し」という普遍的かつ個人的なテーマを大胆なサウンドとともに語り切った点において、現代のポップミュージックにおける意義深い到達点となっている。
全曲レビュー
1. Minor Feelings
Kathy Park Hongの同名詩集を下敷きにした導入曲。
「取るに足らない感情」とされがちなマイクロアグレッションを見つめ返す静かなプロローグであり、パーソナルな痛みが全編の鍵であることを予告する。
2. Hold the Girl
タイトル曲にして、アルバムの核心をなすアンセム。
自己の内なる“少女”=トラウマを抱えた過去の自分を慈しみ、救済へと導くことを主題とする。
ゴスペル調のクライマックスは、まるで天に祈るような清らかさと力強さを持つ。
3. This Hell
カントリー・ロック調のアップテンポな楽曲で、地獄のような現実の中で“選ばれし友人たちと踊り続ける”というポジティブな挑発を含んだ1曲。
ゲイ・アイコンやポップカルチャーの引用を交えながら、LGBTQ+コミュニティへの愛と誇りを高らかに表現している。
4. Catch Me in the Air
母との関係をテーマにしたバラード調の楽曲。
不安定な過去と、その中でも支えとなった母の存在に感謝と困惑を交えて歌う。
ギター主体のサウンドが、浮遊感と親密さを両立させている。
5. Forgiveness
赦しという重いテーマに挑んだミッドテンポのナンバー。
裏打ちされるのは、自らが抱える罪悪感と、他者を赦せない心のしこり。
静かながらも深く沈み込むような構成で、リリックの重みが引き立っている。
6. Holy (Til You Let Me Go)
宗教的な象徴を大胆に用いた楽曲。
キリスト教的抑圧と、それを乗り越える解放の瞬間が、ビートとボーカルに緊張感をもたらす。
“I was innocent when you said I was evil”というフレーズが象徴的。
7. Your Age
インダストリアルなサウンドとビットクラッシュされたリズムが印象的なトラック。
年齢差・権力差のある関係における支配と支配される構造を、怒りと苦悩の視点から描いている。
8. Imagining
Y2Kスタイルのエレクトロ・ポップとUKガラージが融合した、クラブユースなナンバー。
現実と妄想の境界が曖昧になる心理状態を描写し、混沌とした音像がそれを象徴する。
9. Frankenstein
「私は誰かに作られた存在なのか?」という問いかけと共に、自我の断片性を表現した曲。
Mary Shelleyの古典に重ねながら、現代のアイデンティティの複雑さを浮かび上がらせている。
10. Hurricanes
ポップ・ロック的なスケール感を持つ、感情の解放ソング。
自らを壊す衝動=ハリケーンに身を委ねることで、逆説的に自我を確かめようとする。
11. Send My Love to John
アコースティックギターを中心とした静謐なバラード。
息子をゲイであるがゆえに拒絶してしまった移民の母の視点から書かれており、悔悟と愛の再確認が胸を打つ。
実話を基にしているとされ、静かで強い一曲。
12. Phantom
“本当の私はどこ?”という問いをテーマにした繊細なポップ・バラード。
愛に溺れることで自己を失っていく過程を、幻影(Phantom)という言葉に託している。
13. To Be Alive
人生の苦悩を経た末に見出した、生きていることそのものへの賛歌。
アルバムの締めくくりにふさわしい、晴れやかで感動的なポップ・ソングであり、長い旅路の終わりと新たな始まりを感じさせる。
総評
『Hold the Girl』は、Rina Sawayamaというアーティストが、自らの過去と向き合い、その痛みを“物語”として結晶化させたセラピューティックなポップ・アルバムである。
本作における彼女の音楽は、ジャンルを超えて多彩な声色と物語を編み出しながらも、終始一貫して「癒し」と「再生」という主題を抱え続けている。
このアルバムの素晴らしさは、ポップ・ソングの持つ力を最大限に信じているところにある。
Rinaは決して難解な表現には逃げず、むしろ誰もが抱えうる痛みや喪失を、煌びやかで力強い音楽に変えていく。
それは一種の“音楽的儀式”であり、聴く者にとってもまたカタルシスの場となる。
また、Rinaのヴォーカルは、前作以上に感情の揺らぎを捉えており、シャウトから囁きまでの振れ幅を自在に操るその表現力は圧巻。
特に『Hold the Girl』や『Send My Love to John』では、リリックとボーカルが完全に一致し、聴き手の心に深く刺さる。
このアルバムは、単なるサウンドの集積ではなく、Rina自身の人生の“記録”であり、“告白”であり、“祈り”なのだ。
そして、その祈りは、同じように孤独や痛みを抱える多くの人々へ向けられている。
その意味で、『Hold the Girl』は2020年代のポップにおける極めて重要な一作であり、Rina Sawayamaのキャリアにおける精神的中核をなす作品と位置づけられる。
おすすめアルバム
- Kacey Musgraves / Golden Hour
カントリーを軸にしたパーソナルな癒しのアルバム。ジャンルの垣根を越える点で共鳴。 - Troye Sivan / Bloom
LGBTQ+の視点と感情を繊細に描くポップ作。『This Hell』との精神的な接点あり。 - Florence + the Machine / High as Hope
内省と回復を描いた壮麗なバラード群。ボーカルの表現力でも類似点がある。 - Hayley Williams / Petals for Armor
トラウマと自己再構築をテーマにしたソロ作品。感情の微細な表現が魅力。 - AURORA / The Gods We Can Touch
宗教性と人間性を交差させた神秘的ポップ。『Holy』の文脈と共鳴する構成。
歌詞の深読みと文化的背景
『Hold the Girl』というタイトルそのものが象徴的である。
“少女”とは、Rina自身の過去の姿であり、社会の中で抑圧された存在でもある。
アルバムを通じて彼女は、その少女を“抱きしめる”ことで、過去に起きた傷や喪失をただ癒すのではなく、声を与え、物語として生き返らせている。
とくに『Holy (Til You Let Me Go)』における宗教的抑圧の描写、『Your Age』における年齢差による支配構造の告発などは、Rina自身の人生やLGBTQ+コミュニティへの共感を深く反映している。
また『Send My Love to John』では、当事者ではなく“加害してしまった側”の視点を描くことで、赦しの複雑さを繊細に提示している点が秀逸である。
『Hold the Girl』は、Rina Sawayamaがアジア系ディアスポラ、女性、クィアとして生きてきたことの“記憶と解釈”であり、
それをエンターテインメントの中に昇華した類まれなるポップ・ドキュメントなのだ。


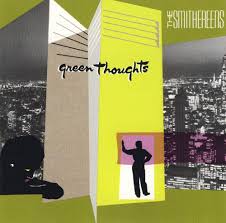
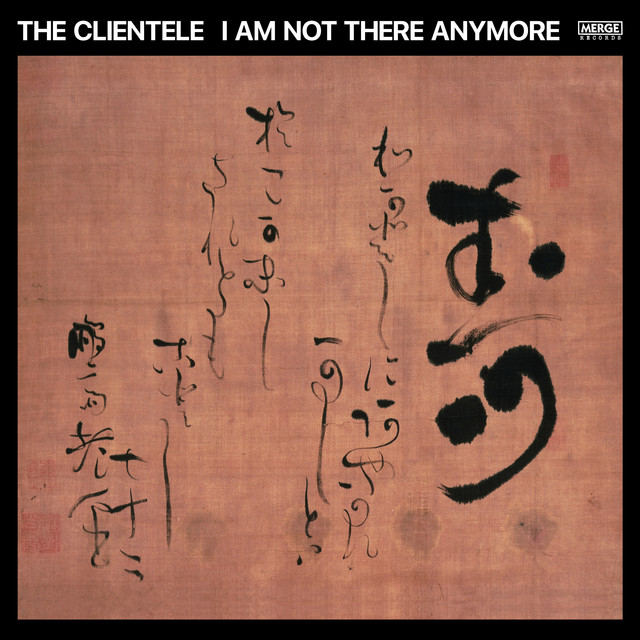
コメント