1970年代のアメリカン・ポップス/ロックシーンを語るとき、ひときわユニークな存在感を放っていたのが**ハリー・ニルソン(Harry Nilsson)**である。
ビートルズのメンバーから「アメリカ最高のシンガーソングライター」と絶賛された逸話は有名であり、その評に違わぬ美しいメロディメイキングと独特の声質、そして時に奇抜なアレンジセンスで、多くのリスナーを魅了してきた。
一方で、ジョン・レノンとの破天荒な交遊録や大胆な実験精神も相まって、一筋縄ではいかないミステリアスなアーティストとしての顔を持ち合わせていたのがニルソンの魅力でもある。
アーティストの背景と歴史
ハリー・ニルソンは、1941年にニューヨークで生まれた。
幼少期は複雑な家庭環境下で育ち、経済的にも苦労する時期が長かったが、音楽の才能には恵まれており、独学でピアノや作曲の基礎を習得。
やがてロサンゼルスに移り住み、銀行のコンピュータ関連の仕事をしながら、余暇を使ってデモを録音・提供する生活を送っていた。
その作曲力が認められ、1960年代中頃にはフィル・スペクターやモンキーズなどに楽曲を提供するようになり、少しずつ音楽業界での評価を高めていく。
そんな中、1967年のアルバム『Pandemonium Shadow Show』が、ビートルズのジョン・レノンやポール・マッカートニーの耳に留まり、二人が「お気に入りのアーティスト」と公言したことから一躍注目の存在に。
さらに1969年にはフレッド・ニール作の「Everybody’s Talkin’」(映画『真夜中のカーボーイ』で使用)をカバーし、これが大ヒット。
ニルソンの透き通るハイトーンボイスと繊細な表現力が全米に広く知られるきっかけとなった。
1970年代に入ると、「Without You」の世界的大ヒットを筆頭に、シンガーソングライターとしても円熟期を迎える。
しかし一方で、ジョン・レノンとの狂騒的な夜遊びやアルコール・薬物問題などもあって、活動が不安定になる時期が増えていく。
それでも才能自体は枯れることがなく、子ども向けアニメーションのサウンドトラック制作など意欲的な試みも行い、晩年まで唯一無二の音楽世界を貫き通した。
音楽スタイルと特徴
1. 美しいメロディとファルセットを活かすボーカル
ニルソンの楽曲を語る際に、まず触れないわけにはいかないのが、その卓越したメロディメイキング力である。
ポップ、ロック、ミュージカル、ジャズなど多様なスタイルを吸収しながら、情感に訴える旋律を軽やかに紡ぎ出す。
さらに、哀愁を帯びたファルセットや澄んだ高音域を活かした歌唱は、時に子どもらしい無垢な響きを持ち、一瞬にして聴く者を物語の世界へ引き込む魅力を持っていた。
2. 遊び心と大胆な実験
その一方で、ニルソンは常に“型破り”を好み、遊び心や実験性が垣間見える作品を残している。
時には完全なアカペラ・アルバムを制作したり、ひとつの曲の途中でスタイルを激変させるなど、予測不能な展開を仕込むこともしばしば。
これは彼のユーモアセンスと職人気質が結びついた結果であり、単なる“ヒット志向のポップソングライター”には収まらない独自のポジションを築き上げる要因となった。
3. 熱狂と破滅のはざまで
ニルソンのキャリアには、ジョン・レノンとの派手なセッションや夜遊び、そしてアルコール問題など、激動のエピソードがつきまとう。
これらはしばしば彼の音楽活動に影を落とす結果となり、コンサートツアーをほぼ行わない姿勢も含め、ファンからの評価や商業的成功を阻む要因ともなった。
しかし、逆にこの“ライブをほとんどやらない”方針と、スタジオでの完璧主義的な作業を組み合わせることで、ニルソン独特の“職人的な美意識”が生まれたとも言える。
代表曲の解説
「Everybody’s Talkin’」(『Aerial Ballet』収録、1968年)
フレッド・ニールのカバーとして有名だが、映画『真夜中のカーボーイ』で使用されたことでニルソン自身のバージョンが大ヒット。
アコースティック・ギターと、ニルソンの高音が澄み渡るように響くボーカルが印象的で、アメリカのフォーク/ポップシーンにも強くアピールした。
「Without You」(『Nilsson Schmilsson』収録、1971年)
もともとはバッドフィンガーの楽曲だが、ニルソンがカバーして大ヒットし、グラミー賞を受賞。
劇的なメロディと、ニルソンのボーカル表現が見事に融合し、ラブソングの定番として今なお多くのアーティストにカバーされ続けている。
切ない感情を爆発させるようなハイトーンボイスが耳に強く残る。
「Coconut」(同じく『Nilsson Schmilsson』収録、1971年)
「Without You」と同じアルバムに収録されているが、雰囲気は一転してコミカル&トロピカルな一曲。
同じ声の持ち主とは思えないほどの多彩な表現力を見せる好例で、ノリの良いリズムに乗せてユーモラスに歌い上げる。
ニルソンの遊び心とポップセンスが集約された楽曲だ。
「Jump into the Fire」(『Nilsson Schmilsson』収録、1971年)
同じアルバムのもう一つの名曲。
エネルギッシュなロックサウンドに乗せて、シャウト気味のボーカルが炸裂する。
ニルソンのポップなイメージを覆すような激しさで、ライブ映像がほとんど残っていないことが惜しまれるほどのパワフルさを誇る一曲。
アルバムごとの進化
『Pandemonium Shadow Show』
(1967)
まだ無名だったニルソンの名前を一躍広めることになった事実上のデビュー作。
ビートルズのカバー「You Can’t Do That」を取り入れるなど、当時からビートルズとの深い交流があったことを示唆する。
ポップセンスとインテリジェントなアレンジが散りばめられ、後の作品への予感が詰まったアルバムだ。
『Harry』
(1969)
「Everybody’s Talkin’」のヒットで広く知られるようになった時期の作品。
フォークやポップを基盤にしつつ、ジャズやソウルの要素も垣間見える。
柔らかな歌声と、どこか物哀しい雰囲気が共存する独特のサウンドを形成している。
『Nilsson Schmilsson』
(1971)
最大のヒット作で、代表曲「Without You」「Coconut」「Jump into the Fire」を収録。
様々なジャンルを縦横無尽に行き来しながら、ニルソンのボーカリストとしての才能とソングライター/アレンジャーとしての実力が頂点に達した。
商業的にも批評的にも大成功を収め、彼のキャリアを象徴するアルバムとして現在も高く評価されている。
『Son of Schmilsson』
(1972)
『Nilsson Schmilsson』の続編的な位置づけで制作されたが、より自由奔放なアプローチが増し、賛否両論を呼んだ。
ジョン・レノンがゲスト参加するなど話題性は十分だったが、その内容は実験性と奇妙なユーモアに富んでおり、初期のポップ路線を期待した層からは少々戸惑いの声もあった。
『Pussy Cats』
(1974)
ジョン・レノンをプロデューサーに迎え、二人の“悪友”ぶりが全面に表れた作品。
レノンが多量のアルコールやドラッグの問題を抱えていた“失われた週末”時代と重なり、レコーディング現場も混沌としていたと言われる。
出来上がったアルバムは雑多な印象を与えつつも、ロックンロール・カバーなどを通じてニルソンの奔放さが伝わる内容になっている。
まとめ
ハリー・ニルソンのキャリアは、まるで“音楽の天才”の明暗を凝縮したようなドラマを持つ。
美しく練り上げられたメロディと、巧みなアレンジセンスにより、ポップチャートをも制するヒットを放つ一方で、型破りの実験や破天荒な生活に走り、早々にライブ活動を放棄するなど常識にとらわれない行動を取り続けた。
しかし、彼が残した曲の数々には“職人技”としか言いようのない緻密な作曲力と、時に子どもが遊ぶような自由奔放な発想が共存しており、どこを切り取ってもニルソン独特のオーラを放っている。
「Without You」などの名バラードを聴けば、その美声とドラマチックな構成に胸が締め付けられるし、「Coconut」や「Me and My Arrow」のようにコミカルな曲に触れれば、ニルソンのイマジネーション豊かな世界が垣間見える。
ロックやポップの枠を軽々と乗り越え、“音楽の楽しさ”を貪欲に追求したこの孤高のシンガーソングライターは、今なお多くのファンを持ち、後進のミュージシャンたちを刺激し続けている。
その足跡をたどれば、人間臭さとクリエイティビティに満ちた“音の冒険”に思わず微笑んでしまうはずだ。

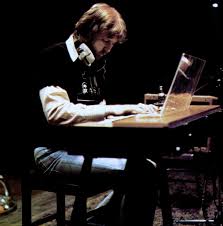



コメント