
発売日: 1980年12月8日
ジャンル: サウンドトラック、シンフォニックロック、スペースロック、シンセポップ
- 概要
- 全曲レビュー
- 1. Flash’s Theme
- 2. In the Space Capsule (The Love Theme)
- 3. Ming’s Theme (In the Court of Ming the Merciless)
- 4. The Ring (Hypnotic Seduction of Dale)
- 5. Football Fight
- 6. In the Death Cell (Love Theme Reprise)
- 7. Execution of Flash
- 8. The Kiss (Aura Resurrects Flash)
- 9. Arboria (Planet of the Tree Men)
- 10. Escape from the Swamp
- 11. Flash to the Rescue
- 12. Vultan’s Theme (Attack of the Hawk Men)
- 13. Battle Theme
- 14. The Wedding March
- 15. Marriage of Dale and Ming
- 16. Crash Dive on Mingo City
- 17. Flash’s Theme Reprise (Victory Celebrations)
- 18. The Hero
- 総評
- おすすめアルバム(5枚)
- 制作の裏側(Behind the Scenes)
概要
『Flash Gordon』は、1980年公開の同名映画のサウンドトラックとして、クイーンが全編を手がけたアルバムである。
彼らにとって初の本格的なフィルムスコアであり、ロックバンドによる映画音楽というジャンルの可能性を拡張した先駆的な試みでもあった。
ディノ・デ・ラウレンティス制作によるこの映画は、アメリカン・コミック由来のSFヒーローもの。
そのカラフルでキッチュな映像世界に対し、クイーンはシンセサイザーとギターを駆使して、未来感とパルプ感の同居する独自の音像を作り上げている。
この時期、バンドはすでに『The Game』でシンセサイザー導入を開始しており、その延長としてこのサウンドトラックはシンセとロックの融合を加速させた。
収録曲のほとんどがインストゥルメンタルで、映画のセリフや効果音を取り込んだコラージュ的構成が特徴。
その中で「Flash’s Theme(通称 “Flash”)」がシングルヒットを記録し、作品全体において唯一の明確な楽曲らしい楽曲として、世界的な知名度を得ることとなった。
従来のクイーンのアルバムとは大きく異なるが、80年代以降のサウンド志向、シンセ導入、視覚的演出との統合といった流れを見据えた重要作であり、サウンドトラックというジャンルに対するクイーンのアプローチが凝縮されている。
全曲レビュー
1. Flash’s Theme
「Flash! Ah-ah! Savior of the Universe!」という冒頭のフレーズがあまりにも有名な、アルバム唯一のフルボーカル曲。
ヒーロー讃歌としての力強さと、SF感溢れるシンセ・エフェクトの融合が見事で、映像と一体化したテーマソングの典型例となった。
2. In the Space Capsule (The Love Theme)
ロジャー・テイラー作によるシンセ主体のロマンティックなテーマ。
恋愛シーンを彩る優雅な旋律が特徴で、メカニカルな音色が逆に人間の感情を際立たせている。
3. Ming’s Theme (In the Court of Ming the Merciless)
ブライアン・メイ作。冷酷な支配者ミンの登場を告げる荘厳かつ不穏な楽曲。
パイプオルガン風の音色と重厚なギターが、宗教的な威圧感を醸し出す。
4. The Ring (Hypnotic Seduction of Dale)
催眠状態に陥る場面を描いた、アンビエントに近い実験的トラック。
環境音とセリフが重なり、音楽というより“音による編集”という趣が強い。
5. Football Fight
フレディ・マーキュリー作。映画内のアメフト風アクションシーンに合わせたファンキーな楽曲。
シンセとパーカッションが軽快に絡み、クイーンらしい遊び心が詰まった一曲。
6. In the Death Cell (Love Theme Reprise)
再び「In the Space Capsule」の旋律が姿を現すバリエーション。
シーンの緊迫感と愛の悲哀が同居する、映像と音のリンク性が高いトラック。
7. Execution of Flash
緊張感のある構成で、劇中の“処刑”をテーマにしたサスペンス的インスト。
心拍音に似たパルス音と無機質なシンセが、死の恐怖を演出する。
8. The Kiss (Aura Resurrects Flash)
ミスティックな雰囲気とシンセパッドが美しい、再生と奇跡のテーマ。
タイトルどおり“キスによる蘇生”というロマンチックかつ神秘的な場面を想起させる。
9. Arboria (Planet of the Tree Men)
緑の惑星“アルボリア”の描写。幻想的な空間音響が展開され、木々のざわめきを思わせる音が印象的。
ディープなシンセアンビエントがSF的世界観を強調する。
10. Escape from the Swamp
逃走劇を描いたアクション・インスト。ブライアンのリフが短く挿入され、緊張感のある展開が連続する。
11. Flash to the Rescue
「Flash’s Theme」のモチーフが再登場。英雄の登場を祝うような構成で、ギターとシンセの重奏が爽快。
複数の場面をつなぐ“モンタージュ音楽”的要素が強い。
12. Vultan’s Theme (Attack of the Hawk Men)
テイラー作のパワフルなマーチ風ロック。
空飛ぶホークマンたちの襲撃を音で再現しており、エネルギーに満ちた場面転換的トラックである。
13. Battle Theme
重厚なシンセとギターによる戦闘テーマ。
クラシックな戦争映画を想起させる構成と、クイーン流のエピック感が融合している。
14. The Wedding March
メンデルスゾーンの「結婚行進曲」をロックアレンジした異色曲。
荘厳さと皮肉が同居し、映画のシーンに独特な異化効果を与えている。
15. Marriage of Dale and Ming
異文化的な儀式の不穏さを表現したミニマルな一曲。
ハーモニウム風の音が場の空気を支配する。
16. Crash Dive on Mingo City
盛り上がりを見せる終盤の突入シーン。テンポとエフェクトの変化がめまぐるしく、クライマックスへの導線を担う。
17. Flash’s Theme Reprise (Victory Celebrations)
勝利のファンファーレとともに「Flash’s Theme」が再登場。
ヒーローの物語が完結し、テーマ音楽の再帰的使用により聴き手にカタルシスを与える。
18. The Hero
本作の実質的なエンディングテーマ。
メイのギターとフレディの歌声が再び交錯し、短くも力強くアルバムを締めくくる。
総評
『Flash Gordon』は、クイーンのディスコグラフィーの中でも特異な位置にある作品でありながら、バンドの音楽的な柔軟性と映像志向の高さを証明する一枚である。
通常のアルバムとは異なり、楽曲ではなく“場面”や“映像”を主役とした構成であり、そのため一曲ずつが映画のワンシーンのように機能している。
セリフやSEを積極的に取り込む手法は、ポップス文脈から見れば異質だが、映画音楽としては実験性に富んだ手法と言える。
その中でも「Flash’s Theme」や「The Hero」のように、クイーンらしいロック・アンセムのエッセンスが時折挿入され、聴き手にバンドの存在を強く印象づける。
また、80年代初頭という時代の空気を反映したシンセ・サウンドの導入と、空間を意識した音作りは、当時の音楽の最先端をクイーン流に吸収した結果とも言える。
本作は映画を観たことがなくても楽しめるが、映像と共に聴くことでその意図がより明確になるという意味で、視聴覚一体型の体験を前提とした作品でもある。
純粋な音楽アルバムとしてというより、**クイーンによる“音響的映画作品”**として捉えるべき傑作なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Vangelis / Blade Runner (Soundtrack)
SF映画とシンセサウンドの融合という観点での代表作。 - Pink Floyd / Obscured by Clouds
映画用に制作された音楽ながら、バンドらしさを保ったアルバム。 - Tangerine Dream / Sorcerer (Soundtrack)
シンセ主体の幻想的サウンドと映像音楽の融合を極めた作品。 - David Bowie / Low
インストゥルメンタルと歌物が混在する構成、未来感ある音作りにおいて類似点が多い。 -
Jean-Michel Jarre / Oxygène
音響による空間演出に長けた電子音楽の金字塔。クイーンの実験的側面と響き合う。
制作の裏側(Behind the Scenes)
プロデューサーのディノ・デ・ラウレンティスは当初、ロックバンドの起用に難色を示していたが、クイーンのライブを観て一転。
「これは映画を超える音楽だ」と発言したという逸話がある。
クイーン側も、従来のサウンドトラックとは異なる“ロック・オペラ風”のアプローチを模索し、映像と音を並列で考える大胆なスタイルを採用した。
さらに映画中で実際に使われたセリフやSE素材を直接取り込んでアルバムに構成したことで、映画そのものを“音”で追体験できる形式に昇華させた。
このアプローチは、のちのMTV時代やサウンドコラージュ文化を先取りする、クイーンならではの映像感覚に満ちている。
ただの挿入歌ではなく、音楽が映画と“対等な主役”となった瞬間——それが『Flash Gordon』という作品の真の価値なのだ。


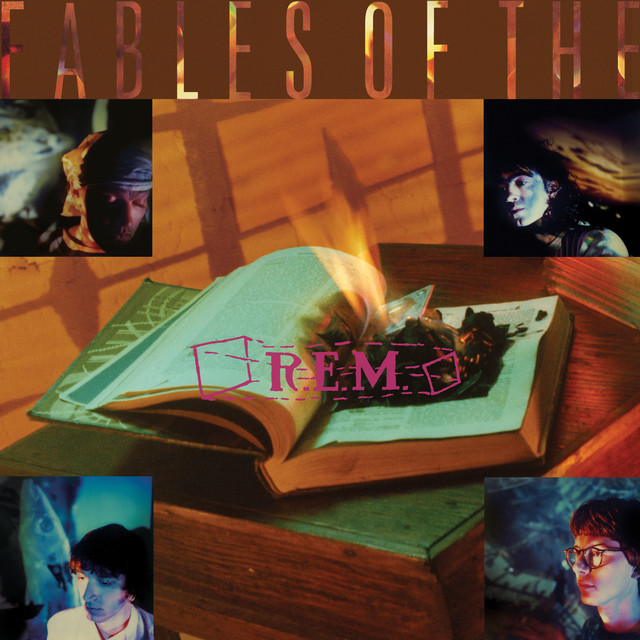
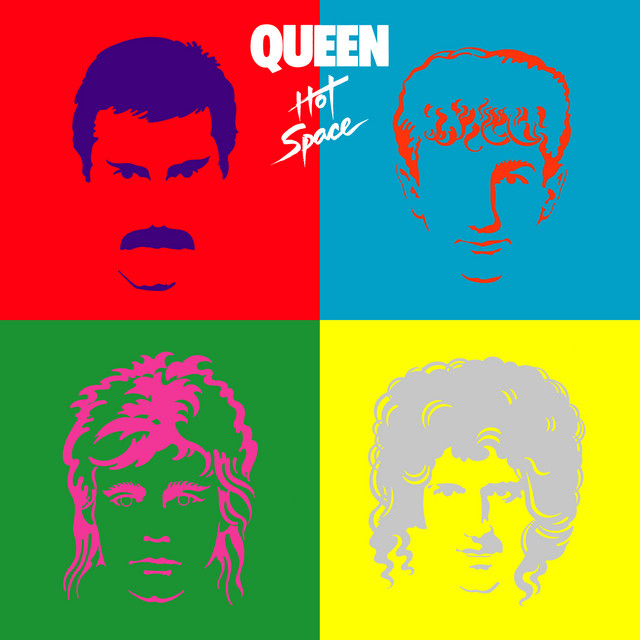
コメント