イントロダクション
The Clashのギタリスト、ミック・ジョーンズがクラッシュ脱退後に始動させたBig Audio Dynamite(以下B.A.D.)。
その音楽は、単なるパンクの続編ではなかった。
サンプリング、ヒップホップ、レゲエ、ファンク、ダンス・ビート――あらゆるジャンルを再構築し、1980年代のロンドンの混沌と未来を音で描き出す。
B.A.D.の音は、まさに「音の爆弾」そのものであった。
バンドの背景と歴史
1983年、The Clashを事実上解雇されたミック・ジョーンズは、自らの音楽的野心を新たな形で具現化すべく動き出す。
1984年、映像作家でもあるドン・レッツとともに結成したのがB.A.D.である。
デビュー作『This Is Big Audio Dynamite』(1985)では、当時としては斬新だったサンプリングとスクラッチを大胆に導入。
映画のセリフ、ニュース音源、効果音などを駆使し、音楽がコラージュ的に再構成されていくさまは、まさにビートのモンタージュだった。
その後のアルバム『No.10, Upping St.』(1986)では、旧友ジョー・ストラマーとの共作も実現。
90年代初頭にはB.A.D. II、さらに単なるBig Audioとして再編を繰り返しながら、時代に応じた音楽を発信し続けた。
音楽スタイルと影響
B.A.D.の音楽を一言で形容するのは難しい。
彼らはパンクの反骨精神を根に持ちながらも、それをダンスフロアへ持ち込むことで“進化”させた存在である。
その鍵となったのが、レゲエとダブ、そしてヒップホップの導入だった。
ジャマイカ系イギリス人であるドン・レッツの感性も加わり、リズムとビートの重視、さらには政治性をも持った音楽が展開される。
加えて、サンプラーやドラムマシンなど当時最先端の機材を導入し、“バンド”という概念すら拡張していった。
ビートルズからエンニオ・モリコーネ、スパゲッティ・ウェスタンからブレイキング・ニュースまで、あらゆるカルチャーが音の素材として吸収されていく。
代表曲の解説
E=MC²
名作映画のセリフをサンプリングし、電子音とファンクビートが融合する実験的ナンバー。
ニコラス・ローグ監督の映画『The Man Who Fell to Earth』『Performance』などから引用されたフレーズが、音の中で幻影のように浮かび上がる。
“It’s all just a little bit of history repeating”というフレーズに象徴されるように、過去と未来を繋ぐタイムトラベル的楽曲。
The Bottom Line
B.A.D.の名刺代わりとも言える初期の代表曲。
ループするベースラインとスクラッチ音、語りかけるようなヴォーカルが絶妙に絡む。
クラッシュ時代とは異なる、都市の夜を思わせるクールなビート感が際立っている。
Rush
B.A.D. II名義でリリースされ、全米チャートを賑わせたキャッチーな一曲。
The Who「Baba O’Riley」やサンダークラップ・ニューマンなどのフレーズを引用し、ロックとダンスの橋渡しをするような構成が特徴。
リフレインされる “Rhythm and melody” のフレーズが、彼らの美学を端的に示している。
アルバムごとの進化
『This Is Big Audio Dynamite』(1985)
サンプリングとビートの洪水。映画的構成とパンクの精神が溶け合った革新的デビュー作。
当時の音楽業界では“早すぎる”とすら言われた。
『No.10, Upping St.』(1986)
クラッシュ時代の盟友ジョー・ストラマーが共同プロデュース。
より緻密なアレンジとロック色を強め、政治性とメッセージが濃くなる。
『Tighten Up Vol. 88』(1988)
ヒップホップ要素が強まったポップな作品。
タイトルはレゲエのコンピレーションへのオマージュで、B.A.D.らしいユーモアとスタイルが炸裂。
『Megatop Phoenix』(1989)
バンドの音楽的到達点とも言えるカオティックな名作。
サイケ、ダブ、ニューウェイブが交差し、まるで情報の渦の中を旅するような一枚。
『The Globe』(1991)【B.A.D. II名義】
ダンス・ビートを押し出したアメリカ向けのサウンド。
“Rush”や“James Brown”など、ラジオヒットを意識した構成で、世界的知名度を高めた。
影響を受けたアーティストと音楽
クラッシュ時代から根差していたレゲエやダブの影響に加え、ヒップホップの走りであるグランドマスター・フラッシュやアフリカ・バンバータのビート感。
また、映画やニュースなど視覚文化もB.A.D.にとっては重要な素材であり、音楽以上にカルチャー全体からの影響が強い。
影響を与えたアーティストと音楽
彼らのスタイルは後のゴリラズ、プライマル・スクリーム『Screamadelica』期、ブラー『Think Tank』期、さらにはThe StreetsやLCDサウンドシステムにも連なっていく。
ジャンルを横断し、音の編集を一つの“表現”として用いた先駆者として、B.A.D.の影響は確かに現在に息づいている。
オリジナル要素
ドン・レッツの映像感覚とミック・ジョーンズのソングライティングが融合したことで、B.A.D.は音楽というよりも“総合メディアアート”に近い表現体へと進化した。
ライブでも映像と音を同期させる先駆的な試みを行い、ステージという場を拡張する発想をいち早く提示した。
また、ミック・ジョーンズはバンド活動と並行して数多くの若手バンドとコラボレーションを行い、“長老”としてシーンを育てる存在にもなっていた。
まとめ
Big Audio Dynamiteは、クラッシュの延長線上ではなく、まったく新たな可能性を模索した音の開拓者である。
サンプリング、映像、ジャンル混交――それらすべてを駆使して、ロンドンという都市のリアルと夢を音楽に変換してみせた。
“ポストパンク”という言葉では語り尽くせない、越境するセンスと精神。
B.A.D.の遺した音は、今も時代の先を照らし続けているのかもしれない。

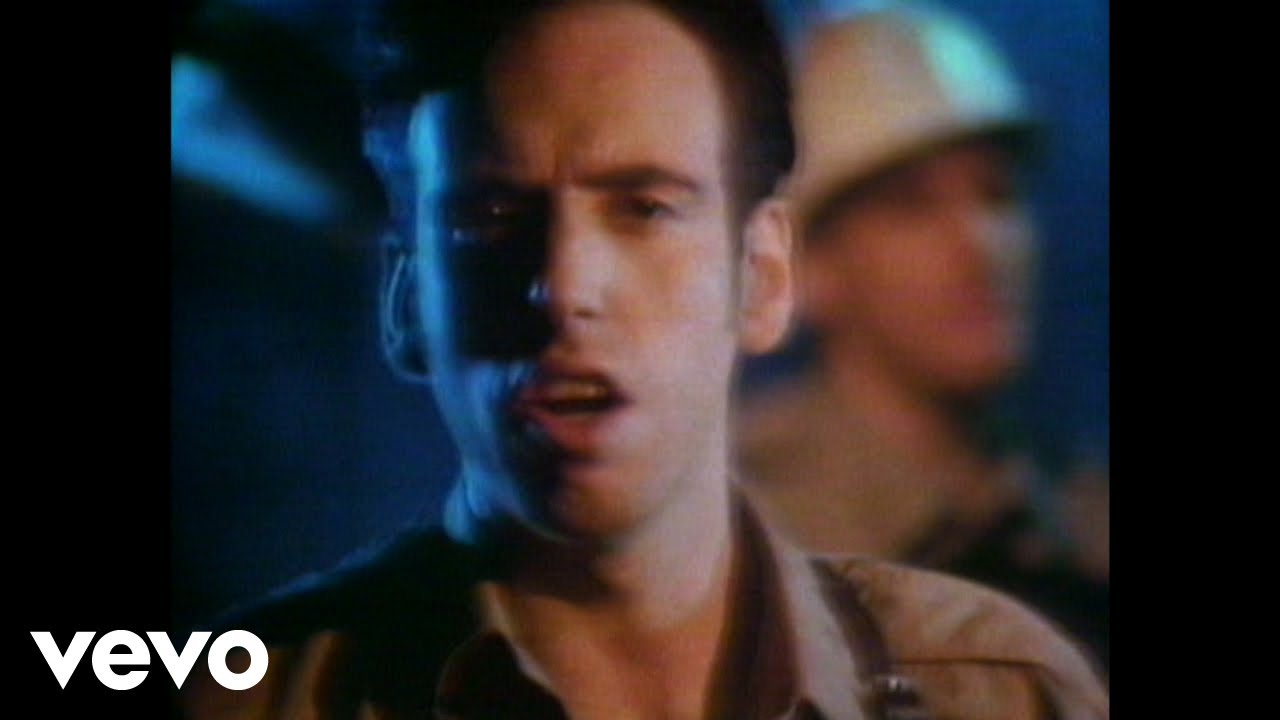



コメント