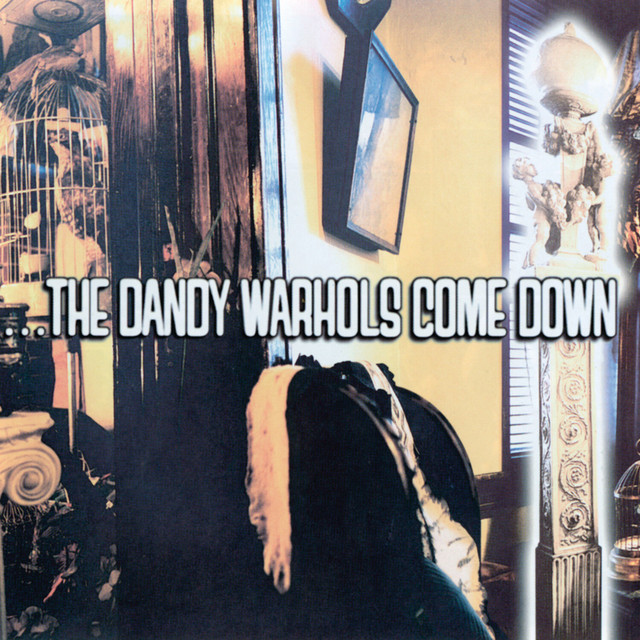
1. 歌詞の概要
「Be-In」は、The Dandy Warholsのセカンド・アルバム『…The Dandy Warhols Come Down』(1997年)のオープニング・トラックであり、全曲の中でも最も大胆にサイケデリックな世界を展開する楽曲である。タイトルの「Be-In(ビー・イン)」とは、1960年代のヒッピー文化において行われた「Sit-In」や「Love-In」と同様の言葉遊びで、集会や祭りのような精神的・政治的な集まりを意味している。つまり、この曲はある種の“意識の共同体”や“感覚の解放”をテーマとしていると考えられる。
歌詞は極めて断片的で、明確なストーリーや叙述はなく、むしろ音と言葉がひとつの陶酔感を作り出すための素材として用いられている。反復されるフレーズとドローン的なサウンド、ディレイを効かせたギターのうねりによって、リスナーは楽曲の構造を超えた“感覚の渦”に巻き込まれていく。そこにあるのは、意識と現実の境界を超えて漂うような、不思議な没入体験だ。
2. 歌詞のバックグラウンド
The Dandy Warholsが『…The Dandy Warhols Come Down』で目指したのは、ローファイで荒削りだったデビュー作からの脱却と、よりコンセプチュアルでサイケデリックなアプローチへの進化であった。「Be-In」はその野心を象徴する楽曲であり、実に7分以上にも及ぶ長尺のトラックでありながら、シングル向けの構成やキャッチーなメロディとは完全に決別している。
タイトルの「Be-In」は、1967年のサンフランシスコで開催された「Human Be-In(ヒューマン・ビー・イン)」という集会から着想を得たとされる。そこではLSD、東洋思想、反戦運動などが交錯し、人々は音楽と意識の拡張を通じて新たなコミュニティを築こうとしていた。The Dandy Warholsはその精神を90年代的にアップデートし、オルタナティブ・ロックの文脈で再構築したのだ。
この楽曲はまた、ライブにおける定番のオープナーとしても機能しており、そのドローン的な導入部が、聴衆を“儀式”のような空間へと導く。彼らにとっての「Be-In」とは、演奏の前段階としての“音の門”でもあるのだ。
3. 歌詞の抜粋と和訳
Come on down, Be-In now
降りてこいよ、今ここで「Be-In」しようYou know it’s all around you
もうすでにそれは、君のまわりにあるんだBe-In now
今ここで、存在するんだ
このフレーズは、非常に抽象的でありながらも、“今ここ”という感覚を強く呼びかけてくる。“Be-In”とは、ただそこに“いる”ということの肯定であり、時間や社会から解き放たれた“瞬間の純粋さ”を意味しているとも言える。
※歌詞引用元:Genius – Be-In Lyrics
4. 歌詞の考察
「Be-In」という言葉は、能動的な“する(Do)”ではなく、受動的な“ある(Be)”という状態に重きを置いている。これは、近代資本主義社会が要求する「生産性」や「計画性」とは真逆の価値観であり、むしろ「ただ存在することの美しさ」や「意識の解放」といったカウンターカルチャー的な思想を内包している。
この曲では、“メッセージ”があまりにも希薄であるがゆえに、むしろ“音そのもの”が語り出す。反復されるリフ、エフェクトの波、脱構築されたリズム――それらがひとつのサイケデリックなマントラとなってリスナーを包み込む。
また、コートニー・テイラー=テイラーの歌い方は、歌というよりも“呟き”や“導き”に近い。彼は物語を語るのではなく、“今ここ”という感覚を音を通して提示しているのだ。これは60年代の精神的な“トリップ”と、90年代以降の脱構築的なポストモダン思考の融合とも言えるだろう。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Tomorrow Never Knows by The Beatles
サイケデリック音楽の原点とも言える実験的かつ神秘的な楽曲。 - Hallogallo by Neu!
ドイツのクラウトロックが生んだ、トランス状態に誘うインストゥルメンタル。 - Venus in Furs by The Velvet Underground
退廃と官能、意識の浮遊感を音で描いたロックの金字塔。 - Only Shallow by My Bloody Valentine
ノイズと美のはざまに立ち、時間の感覚すら歪めるシューゲイザーの傑作。 -
You Set the Scene by Love
サイケデリックな詩性と構成美が際立つ、60年代の終わりを告げるような楽曲。
6. 音楽としての“儀式”が始まる場所
「Be-In」は、The Dandy Warholsの音楽が単なるポップでもロックでもなく、むしろ一種の“儀式”であることを象徴するような楽曲である。これはリスナーを踊らせる曲ではなく、“変性意識の場”へと導く曲だ。始まりも終わりも曖昧な構造、言葉の意味を超えた音の連なり、そしてただ“存在する”ことの肯定――それはまさに、60年代サイケデリアの現代的な再解釈と言える。
The Dandy Warholsはこの曲を通して、聴く者に“脱構築された自我”の状態を提示している。「Be-In」とは、その場に“い続ける”ということ。どこかへ向かうのではなく、ただそこにあるということ。それは、現代社会が忘れかけた“感覚の解放”そのものである。
つまり「Be-In」は、バンド自身の“美学宣言”であり、聴く者にとっては、意識の深部を旅するための“音のゲートウェイ”なのだ。目を閉じて、ただそこに身をゆだねればいい――すべては、その瞬間に始まる。


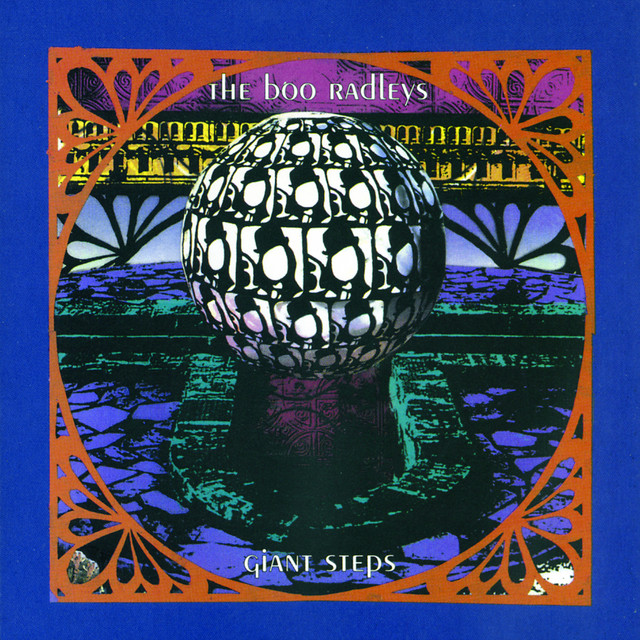
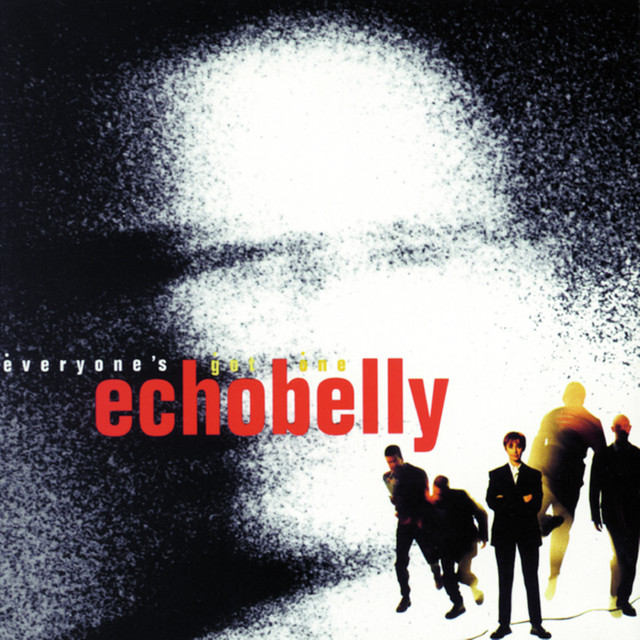
コメント