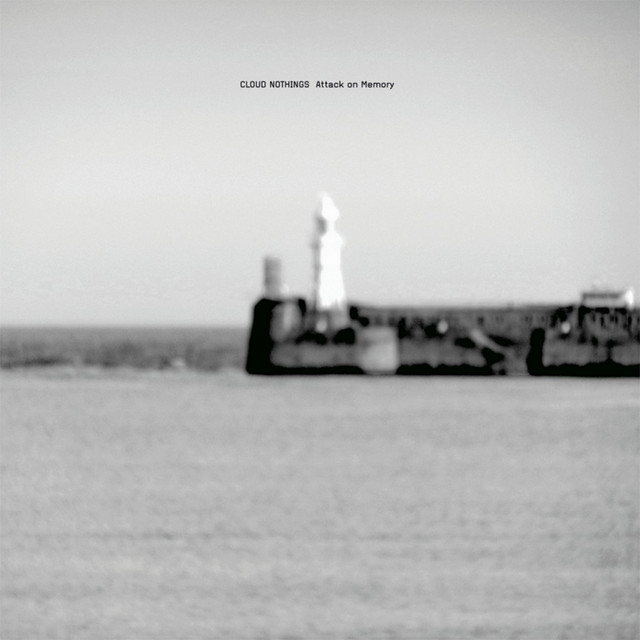
発売日: 2012年1月24日
ジャンル: ポストハードコア、インディー・ロック、エモ、ノイズ・ロック
概要
『Attack on Memory』は、アメリカ・オハイオ州クリーブランド出身のインディー・ロック・バンド、Cloud Nothingsが2012年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、バンドの転機を象徴する決定的な一枚である。
前作『Cloud Nothings』(2011)は、ティーンエイジャーの衝動とローファイな宅録サウンドが光るパワーポップ的作品であったが、本作ではサウンド、テーマ、演奏すべてにおいて劇的な変貌を遂げている。
プロデューサーに迎えられたのは、スティーヴ・アルビニ。Pixies、Nirvana、Shellacなどを手がけた伝説的エンジニアであり、その生々しく剥き出しの音像が、Cloud Nothingsの新しい暴力性をあますところなく引き出した。
本作のタイトル『Attack on Memory(記憶への攻撃)』は、バルディ自身が過去の自分の音楽を“甘すぎた”と否定的に捉え、その記憶に反逆する決意表明であると語っている。
その結果生まれた音楽は、エモ、ポストハードコア、ポストパンクの衝動を飲み込みながら、驚くほど鋭利でスリリングなバンド・サウンドへと昇華された。
荒れ狂う感情、反復されるリフ、叫びともつぶやきともつかないヴォーカル。
ここにあるのは、若さの喪失に抗いながら自我を構築していく過程そのものであり、2010年代USインディー・ロックの金字塔として今も語り継がれている。
全曲レビュー
1. No Future / No Past
重く沈んだピアノとスロウなギターから始まり、徐々に緊張が高まり爆発する構造は、従来のCloud Nothingsにはなかった壮絶な演出。
「No future, no past」――未来も過去もいらないという叫びは、過去の自分自身への断罪であり、バンドの再出発を告げるにふさわしいオープナーである。
2. Wasted Days
9分を超える大曲。反復するギターリフ、断片的なヴォーカル、そして中盤の長いインストパートは、まるでSonic YouthやSlintの系譜を思わせる。
「I thought I would be more than this」――この自己否定的な一節が、アルバム全体の心情を象徴している。
反復と爆発、沈黙とノイズの対比が、まさに“記憶との戦い”を音にしている。
3. Fall In
前2曲の重苦しさを引き継ぎつつも、よりコンパクトでキャッチーなトラック。
アップテンポでありながら、歌詞には「落ちること」「迷うこと」が描かれており、タイトルの“Fall In”には二重の意味が込められている。
4. Stay Useless
本作中もっともポップな印象を持つ楽曲であり、シングルカットされたナンバー。
「I need time to stay useless」という逆説的なフレーズが、現代の若者の無力感を鮮やかに切り取っている。
パワーポップとポストパンクの中間をいく、絶妙なバランス感覚が光る。
5. Separation
インストゥルメンタルながら、バンドとしての力量が爆発するトラック。
3分弱の中にエモ、ノイズ、ポストハードコアのエッセンスが凝縮されており、“言葉にならない感情”を音だけで伝える力を証明している。
6. No Sentiment
タイトル通り、感情を否定するかのようなドライな展開。
ギターは鋭く、ドラムは暴力的。叫ぶようなボーカルも一歩引いており、“突き放すことによる表現”がなされている。
本作中もっとも冷徹な楽曲である。
7. Our Plans
かつて思い描いた“計画”が崩れ去ったことを静かに語るような楽曲。
淡々としたリフが反復される中、ヴォーカルがわずかに感情を取り戻す瞬間が印象的。
静けさと疲弊の中に宿る美しさが際立つ。
8. Cut You
アルバムの締めくくりにして、最も直接的に“他者への怒り”が描かれる一曲。
「I miss you because I like damaging stuff」――恋しさすら破壊衝動に変換される。
ドラムとギターの激突がそのまま感情のぶつかり合いになっており、最後まで生々しいまま終わる。
総評
『Attack on Memory』は、Cloud Nothingsが**“甘さ”を脱ぎ捨て、自意識と怒りを剥き出しにした決別のアルバムである。
ここには、かつての青春的ローファイの影はほとんどない。
あるのは、爆発しそうな衝動、言葉にできない苛立ち、そして未完成なままの自我——つまり、まさに10代の終わりと20代の始まりにある混乱の感情そのもの**である。
スティーヴ・アルビニによるプロダクションは、各楽器の生々しさと録音現場の空気感を際立たせ、まるでリスナーがスタジオの中に入り込んだかのような臨場感を与える。
全体として、構造はシンプルながらも、反復と衝突、静と動のバランスが緻密に設計されており、まさに“ポストハードコア以後のロック”の在り方を提示した作品といえるだろう。
本作によってCloud Nothingsは一気に注目を集め、Pitchforkなどの主要メディアからも絶賛されることとなる。
そしてこのアルバムは今なお、“記憶に攻撃する”ことを恐れない全てのリスナーにとってのアンセムであり続けている。
おすすめアルバム(5枚)
- Fugazi – The Argument (2001)
ポストハードコアの知性と激情が融合した金字塔。バンドとしての姿勢に共鳴。 - Slint – Spiderland (1991)
静寂と爆発、ポストロックと語りの原点。『Wasted Days』に通じる構成美がある。 - Drive Like Jehu – Yank Crime (1994)
複雑なリフとテンションの高いボーカルが特徴。Cloud Nothingsの熱量と親和性が高い。 - Parquet Courts – Light Up Gold (2013)
ローファイと知性の融合。『Stay Useless』的なバランス感覚が近い。 -
METZ – METZ (2012)
同年リリース。ノイズと衝動の塊。Cloud Nothingsの爆発的な側面にシンクロ。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Attack on Memory』は、シカゴのElectrical Audioスタジオでわずか4日間で録音された。
エンジニアはもちろんスティーヴ・アルビニ。彼の信条どおり、オーバーダブなし、クリックなし、ほぼ一発録りでの録音が行われた。
ディラン・バルディはこのアルバムについて、「誰でも聴ける音楽ではなく、自分の中にあるものをむき出しにしてぶつけた作品」だと語っている。
バンドとしての連携もこの時期から格段に向上し、個人の宅録プロジェクトから本格的な“バンド”への脱皮がここで遂げられた。
つまり、『Attack on Memory』は音楽的にも精神的にも、Cloud Nothingsにとっての**“第一章の終わりと第二章の始まり”**を象徴するアルバムであり、そこには“自分自身の記憶に対してどう立ち向かうか”という問いが鳴り響いているのである。


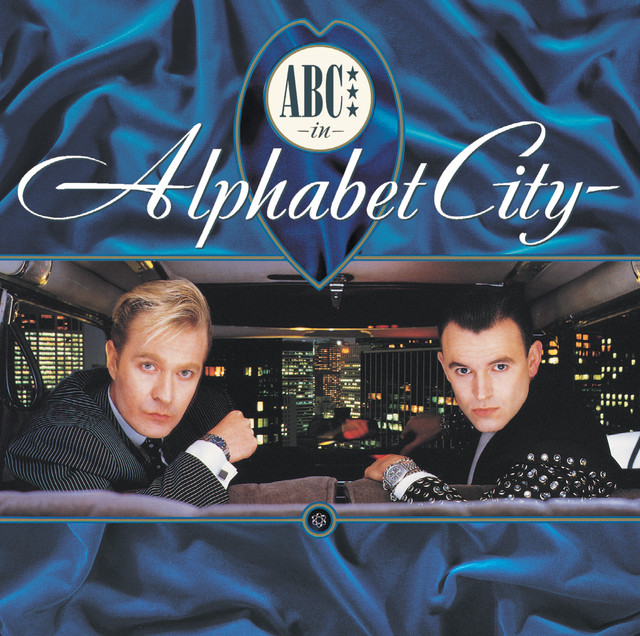
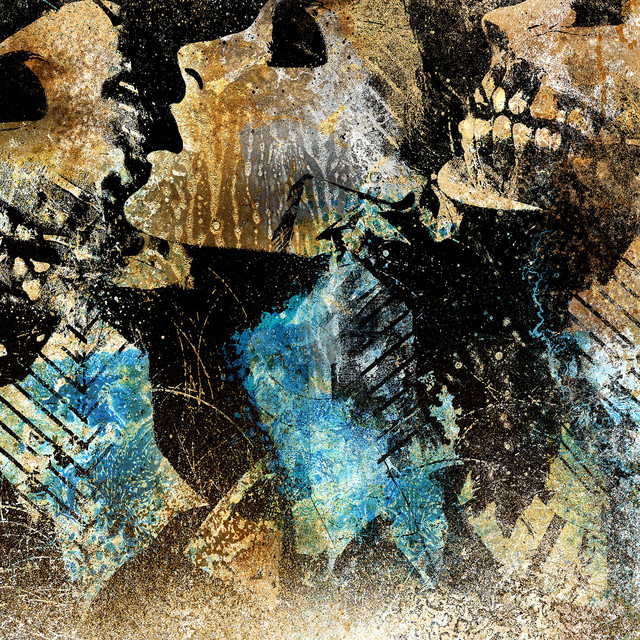
コメント