
1. 歌詞の概要
「All Apologies」は、Nirvanaが1993年に発表したアルバム『In Utero』に収録された楽曲であり、カート・コバーンの内面をもっとも静かに、そして痛ましく表現した一曲として高く評価されている。彼の死の直前にリリースされたこともあり、この曲はしばしば“遺書”や“魂の解放”のように受け取られることがある。
この楽曲には、明確な物語や出来事が描かれているわけではない。だが、そこには不安定な自我、自己否定、外部からの期待と自己像との乖離、そしてそれでも“他人を傷つけたくない”という切実な感情がゆったりと流れている。「What else should I be? All apologies(僕は何になればいいんだ?ただ謝るばかりさ)」というサビのラインは、カートが抱えていた“世界に対する申し訳なさ”と“自分という存在への懐疑”を象徴する言葉となっている。
声高に叫ぶわけではない。むしろ静けさと繰り返しによって、感情は内側から滲み出るようにして伝わってくる。まるで“崩れ落ちそうな魂”の声が、そのまま音楽として鳴り響いているかのような印象すらある。
2. 歌詞のバックグラウンド
「All Apologies」は、カート・コバーンが1990年から1993年にかけて書き上げた楽曲で、彼の妻コートニー・ラヴと娘フランシス・ビーン・コバーンに捧げられているとされている。『In Utero』の収録バージョンでは、チェロ奏者カーラ・アズールが参加し、曲に深い哀しみと温かみのある層を加えている。
当初、カートはこの曲を「ただのポップソング」として語っていたが、のちのインタビューでは、よりパーソナルで内省的な意味合いが込められていることを示唆している。「何かを後悔しているわけではないけれど、すべてが僕のせいのように感じることがある」といった発言もあり、この曲が彼にとっていかに“個人的な声明”であったかがわかる。
また、1993年の『MTV Unplugged in New York』でのアコースティック・パフォーマンスは、彼の死後に特別な意味を持つようになった。バンドの激しさが抑えられたその演奏では、カートの声とギター、そして沈黙が、彼の内面の深淵をよりはっきりと浮かび上がらせている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
“What else should I be?
All apologies”
僕は他に何になればいい?
結局は謝ってばかりさ“What else could I say?
Everyone is gay”
他に何を言えばいい?
みんなが同じに見えるよ“I wish I was like you
Easily amused”
僕も君みたいになれたらよかった
簡単に笑えるような人間に“In the sun, in the sun I feel as one
In the sun, in the sun
Married, buried”
陽の光の中で、ひとつになれた気がした
陽の光の中で
結婚して、埋葬されるんだ
引用元:Genius Lyrics – All Apologies
これらの行は、カートの抱える“他人との距離感”や“自分になれなさ”を静かに、しかし刺すように描いている。特に「I wish I was like you」は、カート自身の異質さと、それに対する羨望と絶望が入り混じった一節だ。
4. 歌詞の考察
「All Apologies」は、Nirvanaの他の曲と比べても特に静謐で、内省的な空気をたたえている。怒りではなく、諦念。絶望ではなく、消耗。それはカート・コバーンという人間の、あまりにも繊細で壊れやすい“心の温度”そのものだ。
「What else should I be?」という問いかけは、社会や周囲の期待に対して、「僕はこれ以上どうすればいいのか?」と悩み続けてきたカートの姿を象徴している。この言葉は、従順さでも反抗でもなく、ただ“理解されないことへの疲労感”として響く。
また、「Married, buried(結婚して、埋葬される)」というラインは、人生の祝福と終焉を並列に描くことで、幸福の裏にある喪失や死への予感を示唆している。この短いフレーズの中に、愛と死、希望と絶望の両極が同居しているのだ。
チェロの音色とともに繰り返される「In the sun」という言葉は、いわば“ほんの一瞬の安息”の象徴ともいえる。だがその光すら、完全な救済にはならない。その哀しみが、最も美しい旋律とともに漂っている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Hurt by Nine Inch Nails / Johnny Cash
内面の痛みと自己否定を、静かに、しかし深く歌い上げた曲。特にジョニー・キャッシュ版は、老いと死を目前にした告白として共鳴する。 - No Name #5 by Elliott Smith
センシティブな自我と社会からの乖離を描く歌。ナイフのように鋭く、それでいて淡々と心に入り込んでくる。 - Black by Pearl Jam
愛と喪失の記憶が混じり合う、エモーショナルなバラード。感情を吐露するような歌詞と表現が「All Apologies」と響き合う。 - Teardrop by Massive Attack
メランコリックで無機質なビートに、人間の孤独と愛情が滲む名曲。音と言葉の隙間から感情が立ち上がる点で近しい。
6. 静けさの中に刻まれた、最後の祈り
「All Apologies」は、Nirvanaのディスコグラフィの中でも特に“終わりの歌”としての気配をまとっている。声を荒げることなく、ただ静かに、誰にも届かないかもしれない言葉を繰り返すことで、カート・コバーンは最後の祈りのようなものを音楽に託したのだろう。
彼は完璧であることを求められたが、それに応えることができず、自分の“欠落”と“申し訳なさ”に苦しんだ。「All Apologies」は、その苦悩の最も静かな形であり、音楽という手段をもって彼が世界と和解しようとした、最後の試みだったのかもしれない。
この曲が終わるとき、世界は何も変わっていない。だが聴く者の胸の奥には、どこか風のように、ふと“やさしい痛み”が残っている。それこそが、カート・コバーンがこの世界に残した、最も美しいノイズなのだ。


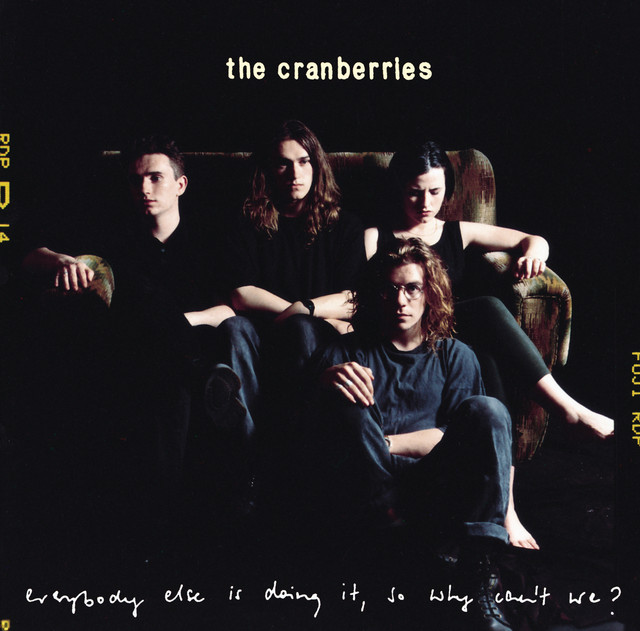

コメント