
発売日: 2002年9月30日
ジャンル: パワー・ポップ、ブリットポップ、オルタナティヴ・ロック
2. 概要
『Life on Other Planets』は、イギリスのロック・バンド Supergrass が2002年に発表した4作目のスタジオ・アルバムである。
デビュー当時のやんちゃなブリットポップ青年から、ソングライティングを磨いたバンドへと変化した彼らが、70年代ロックへの憧憬と、自分たちのキャリアの総決算的なモードを交差させた作品なのだ。
本作は、キーボーディスト Rob Coombes が初めて正式メンバーとしてクレジットされたアルバムでもある。
彼は天体物理学の学位を持ち、レコーディング・スタジオに自前の望遠鏡を持ち込んで惑星観測をしていたと言われる。
バンドは南仏コート・ダジュールでの“ワーキング・ホリデー”中に、フランスのラジオ局 Nostalgie を聴きながら、Carl Sagan の宇宙ドキュメンタリーを見まくった体験からインスピレーションを得ており、ライナーノーツでは Sagan や『銀河ヒッチハイク・ガイド』の著者 Douglas Adams にも謝辞を捧げている。
アルバム・タイトルの“Life on Other Planets”というフレーズは、こうした宇宙趣味と逃避願望の混ざり合いから生まれているのである。
録音は2001年10月から2002年3月にかけて、ロンドンの Mayfair Studios、Heliocentric Studios、そしてウェールズの名門 Rockfield Studios で敢行された。
プロデューサーには、当時 Beck や Air などを手がけていた Tony Hoffer を起用。
前作『Supergrass』(1999)のセルフ・プロデュースでは勢いがやや削がれたと感じていたバンドは、外部プロデューサーを導入することでテイクを短く保ち、過度な分析に陥らないようにしたという。
音楽的には、70年代ブリティッシュ・ロックへの“ツアー”と形容されることが多い。
グラム・ロックの The Sweet や Marc Bolan、Electric Light Orchestra、Paul McCartney & Wings などへの露骨なオマージュが散りばめられつつ、Supergrass 本来のスピード感とユーモアが貫かれている。
批評では、デビュー作『I Should Coco』の奔放さと、『In It for the Money』の音楽的緻密さを理想的なバランスで融合させた作品、と評された。
チャート面では、イギリスのアルバム・チャートで最高9位を記録し、ノルウェーやオーストラリアなどでも上位にランクイン。
レビュー・アグリゲーターの Metacritic では74点と、概ね好意的な評価を得ている。
一方で、一部の批評家からは「アイデア過多でフォーカスに欠ける」「B面集のように中心がぼやけている」といった指摘もあり、その“楽しさ”と“散漫さ”が同時に語られる作品でもある。
2000年代初頭のギター・バンドを俯瞰すると、Blur はワールド・ミュージックやエレクトロへ、Radiohead はポスト・ロック〜電子音響へ、Oasis はクラシック・ロック志向を強めていた時期である。
その中で Supergrass は、あえて70年代の大衆的ロック・マナーを全面的に掘り起こしつつ、90年代ブリットポップ世代の感覚で再構成してみせた。
『Life on Other Planets』は、単なるレトロ趣味ではなく、“自分たちの歩んできた10年”を、70年代ロックの言語を借りて書き換えたセルフ・ポートレートのようなアルバムなのだ。
3. 全曲レビュー
1曲目:Za
幕開けを飾る「Za」は、いきなり宇宙遊園地のようなサウンドが広がるロック・チューンである。
Bowie「Changes」を思わせるピアノ・リフに、Mick Ronson ばりの分厚いギターが重なり、“70年代グラム・ロックの記憶”が一気に立ち上がる。
歌詞はミニマルで、「時間は誰も待ってくれない/だから今夜を楽しもう」という享楽的なメッセージに集約される。
“Face, such a beautiful face / But time waits for no one / So why don’t we get it on” といったラインに象徴されるように、「明日どうなるか分からないなら、今ここで騒ごう」という、Supergrass らしい刹那的な生の肯定がある。
アルバム全体のコンセプトである“宇宙”と“エスケープ”を、最初の数分で提示してしまう力技のオープナー。
奇妙なコーラスやエフェクト処理された声も含め、ここで“地球からちょっと離れた場所”へ連れて行かれる感覚を作り出している。
2曲目:Rush Hour Soul
続く「Rush Hour Soul」は、一転してガレージ・ロック色の強いナンバーである。
タイトなビートとジャリジャリしたギター・リフの上で、Gaz Coombes が畳みかけるように歌うスタイルは、60年代末のブリティッシュ・ロックの更新版のようでもある。
タイトル通り“ラッシュアワーの魂”を歌うこの曲では、混雑した都市生活のストレスと、そこでくすぶる欲望が同時に描かれているように思える。
出勤前のいら立ちも、恋の高揚も、渋滞も、全部ごちゃ混ぜにして2〜3分に圧縮した感じだ。
構成的には、1曲目「Za」で広げたサウンドスケープを、再びギター・ロックの現場に着地させる役割を担っている。
ここまでで、Supergrass が“コンセプト・アルバム”ではなく、“楽しいロック・アルバム”として宇宙ネタを扱うつもりなのだと分かる。
3曲目:Seen the Light
「Seen the Light」は、エルヴィス風の歌い回しと、ゴスペル/グラム・ロック風の高揚感が特徴的な楽曲である。
Gaz はここで、意図的に Elvis Presley のモノマネに寄せた発声を使っており、誇張されたロックンロールのパロディとしても機能している。
タイトルの “光を見た” という言い回しは、宗教的な啓示を意味すると同時に、“ロックに目覚めた瞬間”のメタファーにも読める。
ミュージック・ビデオでは、宗教的トランス状態の人々とロック・コンサートの観客がモンタージュされ、“信仰”と“ロックの熱狂”が同じ身体の動きを引き起こすことが示されている。
サウンド面では、ピアノとギターのリフがシンプルに刻まれ、サビでコーラスが一気に持ち上がる構造。
アルバム前半の中で、もっともストレートな“アンセム”として機能し、続く「Brecon Beacons」の混沌に向けてテンションを上げる。
4曲目:Brecon Beacons
「Brecon Beacons」は、ウェールズの山岳地帯の名前を冠した、スカ〜パンク寄りのキレ味鋭い曲である。
エルヴィス調から一転、ここでは Marc Bolan を思わせる鼻にかかったボーカルで、微妙に不穏なメロディを歌う。
ビートはアップテンポで、ギターがオフビートを刻むことでスカっぽい跳ね方を生み出している。
その一方で、ベースとドラムはパンク的に突っ走り、短い時間の中に“山中ホラー映画”のようなドタバタと狂気を押し込めている印象だ。
歌詞のディテールは抽象的だが、“人気のない高原で何かおかしなことが起きている”という気配だけが濃密に残る。
ここで一度現実感覚がぐにゃりとゆがみ、アルバムの“異世界感”が加速する。
5曲目:Can’t Get Up
「Can’t Get Up」は、タイトル通り“起き上がれない”感覚をめぐる中速ナンバーである。
グラム・ロック風のギターと、ふくよかなオルガンが絡み、夜通し遊んだ翌日の倦怠と、まだどこかで続いているパーティーの残り香が同居する。
歌詞では、身体的なだるさと、精神的な停滞感が二重写しになっている。
「やるべきことは分かっているのに、ベッドから出られない」「時間だけが過ぎていく」といった感覚は、アルバムのテーマである“現実からの逃避”とも呼応している。
前半のピーキーな曲の連続から少しテンポを落としつつ、エモーショナルなコード進行で流れを繋ぐ、重要なブリッジ曲である。
6曲目:Evening of the Day
「Evening of the Day」は、カントリー・ロックとブルーズをブリティッシュ流に解釈したような、ゆったりした楽曲である。
Small Faces 的な英国ロックの渋みと、B.B. King 風ブルーズのエッセンスが混ざり合い、そこに再び Elvis 風のボーカルが乗る。
歌詞の中には、Spinal Tap の楽曲「All the Way Home」への直接的な引用が仕込まれており、ロック史へのメタ的なユーモアも健在だ。
一部の批評では“アルバムの勢いを中断させる冗長な曲”と評されることもあるが、くすんだ夕暮れの空気をたっぷり吸い込ませるという意味で、ここでの減速には意義があるように思える。
中盤に配置されたこの曲は、前半の宇宙遊園地的なハイから少し降りて、
“日常の黄昏時”へとリスナーを引き戻す役割を果たしていると言えるだろう。
7曲目:Never Done Nothing Like That Before
「Never Done Nothing Like That Before」は、1分台で駆け抜けるショート・チューン。
Mick Quinn がリード・ボーカルを取ることで、アルバム全体の空気が一瞬だけ違う方向にひしゃげる。
曲自体は、ほとんどパンクに近いスピードとストロークで突き進むが、
タイトルにある二重否定(Never / Nothing)は、Supergrass らしい茶目っ気を感じさせる。
歌詞の内容はさほど重くなく、「こんなの初めてだぜ」という勢いをそのまま曲にしてしまったようなノリだ。
センチメンタルな「Evening of the Day」の後に、あえてこうした短距離走を挟むことで、アルバム後半のテンションを再起動させている。
8曲目:Funniest Thing
「Funniest Thing」は、軽やかなメロディと、さりげないコード進行の妙が光るポップ・ソングである。
イントロから続くギター・アルペジオとオルガンの絡みが、どこか60年代ポップの甘さを漂わせる。
タイトルの“Funniest Thing(いちばんおかしなこと)”は、皮肉を含んだ言い回しとして機能している。
人間関係のすれ違いや、予想外の展開に対する戸惑いを描きつつも、そのすべてを“おかしな話だよな”と笑い飛ばそうとする視線がある。
前曲のショート・パンクから、再びメロディアスな世界へ滑り込むクッション的な配置でもあり、
ここからシングル曲「Grace」へと流れ込むことで、アルバム後半のポップサイドが開花していく。
9曲目:Grace
「Grace」は、アルバムを代表するシングル曲であり、Supergrass らしいキャッチーさが凝縮された名曲である。
ガツンとしたピアノとギター、T. Rex を想起させるグルーヴ、そして“Save your money for the children”という忘れがたいコーラスが、2分少々の中にぎゅっと詰め込まれている。
曲の着想源は、レコーディングを行っていたスタジオのオーナー Chris Difford(Squeeze)の娘、Grace だと言われる。
彼女が“子どもたちのためにお金を貯めて”と書かれた貯金箱を振りながらスタジオに現れ、そのフレーズを Danny Goffey が酔ったテンションでピアノに合わせて歌ったことが、曲作りの出発点となった。
歌詞としてはかなり突飛な出自だが、結果として“子どもたちのためにお金を取っておけ”というラインが、
不況や将来不安が漂っていた当時の空気と、妙にリンクするポップ・フレーズとして機能してしまっている。
ミュージック・ビデオでは、10歳の少女がバンドを“プロデュース”するというシュールな設定で、曲の子ども的想像力を視覚化している。
10曲目:La Song
「La Song」は、タイトル通り“ラ・ラ・ラ”という無意味音節を効果的に使った、ルーズなロック・チューンである。
アメリカ西海岸を思わせるロードムービー的なムードと、ブリティッシュ・ロックの泥臭さが同居している。
歌詞では、どこか遠くへ向かうドライブの情景と、そこにこびりつく虚無感が描かれる。
“どこか別の惑星みたいな場所へ行ってしまいたい”という、アルバム・タイトルに込められた逃避願望が、ここではより地上寄りの形で表れていると言える。
終盤へ向けてテンションを少し落としつつ、エコーのかかったギターやキーボードが、宇宙空間のような奥行きをつくり出す。
ラスト2曲への“助走”として、ゆるやかに浮遊感を高めていく配置だ。
11曲目:Prophet 15
「Prophet 15」は、ゆったりとしたテンポの中で、奇妙なヴィジョンが描かれるサイケデリック寄りの楽曲である。
タイトルはシンセサイザーの名機 Prophet-5 を連想させるとともに、“預言者”のイメージも重ねているようだ。
サウンド的には、Paul McCartney & Wings の「Let ’Em In」を思わせるオープニング・フレーズやコード感があり、
そこにスペイシーなエフェクトやコーラスが重なることで、70年代後期のソフト・サイケ〜ポップのムードが再構成されている。
歌詞では、車の中で“オスカー・ワイルドやジョン・ベルーシ、チェ・ゲバラの霊が訪ねてくる”ような幻覚的シーンが描かれると評されており、
歴史上の異端者たちが、ハングオーバー気味の若者の頭の中を行き来するような奇妙なイメージを喚起する。
アルバム終盤で最も“別の惑星感”が強い曲であり、ラストの「Run」に向けて、意識をゆっくりと宇宙側へ押し出していく役割を担っている。
12曲目:Run
ラストを飾る「Run」は、Supergrass にしては比較的長尺の、壮大なエンディング・トラックである。
グロッシーなハーモニーと“にょろにょろした”シンセ・エフェクトが折り重なり、70年代のスペース・ロック〜アート・ポップの要素を圧縮したようなサウンドが展開する。
曲が進むにつれ、ノイズとコーラスが渦を巻き、最後にはループするシンセ・フレーズだけが残る。
このループは、オープニング「Za」の導入部を思わせるもので、アルバム全体を一つのサイクルとして閉じる仕掛けになっている。
“走れ(Run)”というタイトルは、単なる逃避だけでなく、“この奇妙な時代を駆け抜けて生き延びろ”というニュアンスも含んでいるように聞こえる。
宇宙的なエフェクトとロック・バンドとしてのダイナミズムが最後にもう一度交錯し、
リスナーは“別の惑星”から現実世界へ半歩だけ戻されたところで、アルバムを聴き終えることになる。
4. 総評
『Life on Other Planets』は、Supergrass のキャリアの中でも、最も“ロック史を遊び尽くした”作品と言ってよい。
デビュー作『I Should Coco』の暴走する若さ、2作目『In It for the Money』の音楽的成熟、3作目『Supergrass』の少し落ち着いたオルタナ感――そのすべてを抱えたまま、70年代ブリティッシュ・ロックの文脈に飛び込んだアルバムだからである。
プロダクション面でのポイントは、Tony Hoffer の存在だ。
彼はバンド自身が“セルフ・プロデュースでは細部にこだわり過ぎてしまう”と感じていたところを、少ないテイクでサクサクと録らせ、
勢いと荒さをあえて残したミックスにまとめている。
その結果、細部には無数の音ネタ(鳥の声、SE、コーラス、奇妙なシンセ)を詰め込みながらも、体感的には爽快なロック・アルバムとして聞けるバランスが生まれている。
音楽的には、“70年代ブリティッシュ・ロックのツアー”という評がまさに的確だろう。
Bowie〜Ronson 的ギター、Sweet や T. Rex 由来のグラム感、ELO のようなポップ・オーケストレーション、Paul McCartney & Wings のメロディ・センス、さらにはカントリー・ロックやスカ、ゴスペルまで。
それらが単なる引用にとどまらず、Supergrass というバンドの“地声”と自然に混ざり合っていることが、このアルバムの強みである。
同時に、批評家が指摘するように“アイデア過多でフォーカスに欠ける”側面も否めない。
「Evening of the Day」や「Brecon Beacons」のように、アルバムの流れを意図的に崩すような曲が挟まれており、
一枚通して聴いたとき、統一されたストーリーよりも、寄せ集めの短編小説集に近い印象を受ける人もいるだろう。
しかし、その“散漫さ”こそが、Supergrass というバンドの魅力と地続きでもある。
90年代の彼らは、ブリットポップ・ムーヴメントの中でも、特に“ふざけながら名曲を書く”ことに長けた存在だった。
『Life on Other Planets』は、その美徳を大人な形に伸ばそうとして、あちこちに飛び火した結果生まれた、奇妙にカラフルな作品なのだ。
2002年というタイミングも重要である。
ブリットポップのピークから数年が経ち、UKロックはフラットなギター・ロックとポスト・パンク・リバイバルへ向かいつつあった。
そんな中で、Supergrass はあえて“宇宙”や“70年代”を前面に出し、ロックの歴史全体を遊び場にするスタンスを選んでいる。
その姿勢は、同時期の The Flaming Lips『Yoshimi Battles the Pink Robots』が見せたサイケデリックでポップな宇宙観とも、どこか緩やかに共振しているように思える。
また、アルバムのテーマを“エスケープ”と捉えると、歌詞の読み解き方も変わってくる。
「Za」や「Rush Hour Soul」の享楽、「Grace」の子どもじみたキャッチフレーズ、「Prophet 15」の幻覚的なビジョン、「Run」のスペース・ロック的エンディング。
どれも、21世紀初頭の現実――テロ以後の不安定な世界情勢や、不況の影――を直接歌うのではなく、
“別の惑星”という比喩を通して、地球から少しだけ距離を取ろうとする試みのようにも読める。
結果として、『Life on Other Planets』は、Supergrass のディスコグラフィの中で、
もっとも“遊び心とロック史趣味が全開になった大人のポップ・アルバム”として位置づけられる。
後の『Road to Rouen』や『Diamond Hoo Ha』で、よりシリアスなトーンやストレートなロックへと振れていく前に、
一度だけ、自分たちの好きな音楽とバンド史を全部混ぜてみせた、そんな“お祭り盤”なのだ。
2023年には最新リマスター&未発表デモ/ライヴ音源を追加した3CD/アナログ盤として再発され、
当時見過ごされていたディテールやソングライティングの質の高さが、改めて評価されつつある。
ブリットポップ黄金期の影に隠れていた一枚が、20年越しに“Supergrass らしさの凝縮盤”として再発見されているのは、とても示唆的である。
5. おすすめアルバム(5枚)
- In It for the Money / Supergrass(1997)
よりシリアスなソングライティングと、凝ったアレンジが評価された2作目。
『Life on Other Planets』で再び70年代色を強める前に、Supergrass がどのように大人のバンドへ成長していったのかを知るうえで欠かせない。 - I Should Coco / Supergrass(1995)
デビュー時の爆発的な若さとパンク的スピード感に満ちた一枚。
『Life on Other Planets』で見られるユーモアや“ふざけた真剣さ”の源流を体感できる。 - Yoshimi Battles the Pink Robots / The Flaming Lips(2002)
同じ2002年リリースの“宇宙×ポップ”アルバム。
SF的世界観とエレクトロ〜サイケを組み合わせ、非現実的な物語で現実を遠回しに描くという意味で、『Life on Other Planets』と通じる部分が多い。 - Hunky Dory / David Bowie(1971)
ピアノが前面に出たグラム期以前の名作で、「Za」周辺のピアノ・ロック感のルーツとしても聴き比べて面白い。
Life on Other Planets が Bowie キュレーションの Meltdown で初披露されたことも含め、象徴的な参照元と言える。 - Electric Warrior / T. Rex(1971)
Gaz のボーカル・スタイルや、アルバム全体に漂うグラム・ロックのノリを遡るならこの一枚。
「Grace」や「Brecon Beacons」に感じられる T. Rex 的グルーヴの“本家”として、セットで聴くと輪郭がよりはっきりする。
6. 制作の裏側
『Life on Other Planets』の制作は、バンドにとって“旅のようなソングライティング”の集大成でもあった。
メンバーはヨーロッパ各地の家や別荘に数日ずつ滞在し、ミニディスクに大量のデモを録音しては持ち帰る、という方法で素材を溜め込んでいったという。
その中から“変なコメディ曲”や“意味不明な断片”を淘汰し、10曲に1曲くらいの割合で現れる“宝石”を拾い上げた、とメンバーは振り返っている。
レコーディング・スタジオとして選ばれた Rockfield は、Queen『A Night at the Opera』や Oasis『(What’s the Story) Morning Glory?』など、数々の名盤が生まれた場所として知られる。
そこに、ロンドンの Mayfair、Heliocentric といったスタジオを組み合わせることで、
都会的な洗練と田園的な開放感、両方の空気を持つサウンドが実現している。
プロデューサー Tony Hoffer は、録音中にテイクを重ね過ぎないよう、バンドに“短期決戦”を強いた。
彼ら自身も、「もしセルフ・プロデュースを続けていたら、無駄に細部をいじり続けていたはずだ」と語っており、
外部プロデューサーの導入によって、90年代的なラフさと2000年代的な音像の緻密さが、絶妙なところで止まっている。
さらに面白いのは、アルバムのコンセプトが制作環境そのものに影響を与えている点だ。
Rob Coombes の望遠鏡は、単なる趣味の道具ではなく、スタジオの外に広がる夜空を日常的に意識させる装置だった。
南仏で聴いた Nostalgie の古いポップスや、Carl Sagan の宇宙ドキュメンタリーは、録音の合間のBGMとしても流れていたと言われる。
つまり、『Life on Other Planets』は、“宇宙がテーマだから宇宙っぽい音を足した”アルバムではない。
むしろ、日々の制作環境に宇宙や70年代ポップスが自然に入り込み、その空気がそのまま曲の構造やアイデアに染み込んだ結果できた作品なのだ。
その“スタジオの空気ごと録音した”ような感覚が、20年以上経った今も、このアルバムをどこかフレッシュに聴かせているのかもしれない。
8. ファンや評論家の反応
リリース当時、『Life on Other Planets』には概ね好意的なレビューが寄せられた。
AllMusic は“音楽制作の楽しさに満ちたアルバム”として高評価を与え、Blender や Entertainment Weekly も、そのキャッチーさとレンジの広さを称賛している。
一方で、NME や Q、The Guardian などの一部英国メディアは、
“エネルギーはあるがアイデアの焦点が定まらない”“B面集のように中心が見えない”といった辛口のコメントも残している。
Metacritic の平均スコア74という数値は、その“高評価と軽い失望の入り混じり”を反映したものと言えるだろう。
ファンの間では、長らく『I Should Coco』や『In It for the Money』の陰に隠れた“通好みの一枚”という位置づけだったが、
2023年のリマスター&拡張版リリースをきっかけに、再評価の機運が高まっている。
デモ音源やライヴ・テイクをまとめた3枚組仕様によって、この時期のバンドの創作量とアレンジ・センスの豊かさが、より立体的に見えるようになったからだ。
今あらためて聴くと、『Life on Other Planets』は“ブリットポップ残党”の一枚ではなく、
90年代〜2000年代のUKロックを繋ぐハブとして、なかなかユニークな立ち位置にいることが分かる。
宇宙趣味と70年代ロック愛、そしてSupergrass 特有の悪ふざけとメロディ・センス――
そのすべてがカラフルに同居するこのアルバムは、2020年代の耳でこそ楽しめる“タイムカプセル”なのかもしれない。
参考文献
- Wikipedia “Life on Other Planets” (作品概要、制作背景、楽曲解説、評価)
- Discogs “Supergrass – Life On Other Planets” (トラックリスト、クレジット)
- PopMatters “Supergrass: Life on Other Planets” (楽曲解説、歌詞のトーン)
- Drowned in Sound “Album Review: Supergrass – Life On Other Planets” (批評的評価、「Evening of the Day」へのコメント)
- Tower Records 特集 “Supergrass『Life On Other Planets』リマスター盤” (2023年再発情報)
- Wikipedia “Grace (Supergrass song)” および関連インタビュー(楽曲背景、Chris Difford の娘 Grace にまつわるエピソード)
- Loudersound “the story of the lost Supergrass album that led to their split” (制作プロセス回想、デモ制作の証言)


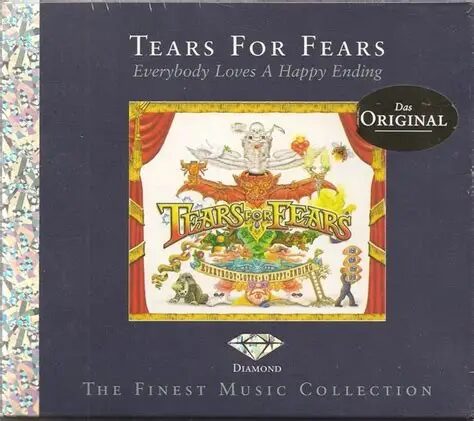
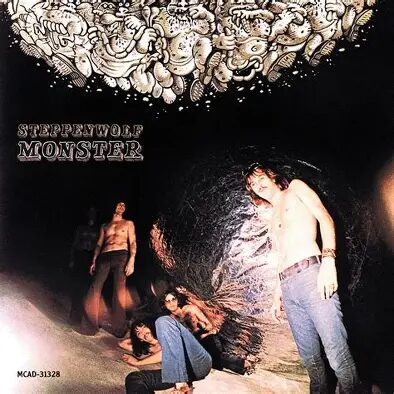
コメント