
発売日: 2014年4月15日
ジャンル: オルタナティブ・ロック、ダーク・ソウル、アート・ロック
概要
『Do to the Beast』は、The Afghan Whigsが16年ぶりにリリースした復活作であり、過去の血と記憶を引きずりながらも、静かに牙を研ぎ澄ませた“成熟の獣”のようなアルバムである。
前作『1965』(1998年)から長い空白を経て、グレッグ・デュリ率いるバンドがサブ・ポップに戻ってきたという点だけでも話題性は十分だったが、本作は“再結成アルバム”にありがちな懐古ではなく、むしろ過去との断絶と対峙”を描く異質な復帰作となった。
バンドの核であるグレッグ・デュリとリック・マクコリス以外の主要メンバーは不在となり、その意味では“Afghan Whigs的精神の再構築”というべき内容。
音楽性も、かつてのソウル・ロックとはやや距離を置き、より映画的、冷たく抽象的なアレンジと構成が特徴的である。
“獣に対してなすべきこと(Do to the Beast)”という謎めいたタイトルは、内なる衝動と向き合う暴力的な精神のメタファーとして読み解ける。
全曲レビュー
1. Parked Outside
歪んだギターと重たいビートで幕を開ける攻撃的な一曲。
“外に停められたまま”というタイトルが、不安と焦燥のメタファーとして響く。
2. Matamoros
ラテン・パーカッションとダークなベースが交錯するサイケなロック。
“マタモロス”はメキシコ国境の町であり、欲望と暴力が交差する場として描かれる。
3. It Kills
静けさと哀しみを湛えたバラード。
“それは殺す”という直接的な言葉の裏に、喪失と赦しの物語がにじむ。
4. Algiers
映画の主題歌のようなスロウナンバー。
ニューオーリンズ風の空気に乗せて、逃避と再生の物語が語られる。
5. Lost in the Woods
シネマティックな弦とピアノが彩る本作の核となる曲。
“森に迷い込む”という喩えが、心の迷宮を象徴している。
6. The Lottery
攻撃的でグルーヴィーな中盤の起点。
“くじ引き”という不条理な運命を引き当てる男の悲哀。
7. Can Rova
インストゥルメンタル要素が強い短編的トラック。
緊張感と空白の美を内包した中継的役割を果たす。
8. Royal Cream
タイトルの甘さに反して、内容は内面の崩壊を描くダーク・ファンク。
権力と欲望、虚栄の苦味が滲む。
9. I Am Fire
スロウ・バーナー的構成で、激情を抑えつつじわじわと燃え上がる。
「俺は火だ」という宣言が、自己破壊と創造を同時に意味する。
10. These Sticks
フィナーレにふさわしい重厚なバラード。
“棒(スティック)”という抽象的なイメージが、過去の記憶や支配の象徴として立ち上がる。
総評
『Do to the Beast』は、The Afghan Whigsというバンドの“亡霊のような再来”であり、生き延びてしまった者が語る物語のように、沈黙の裏に多くを抱えた作品である。
再結成アルバムにありがちな懐かしさや過去の再演ではなく、本作ではむしろその過去とどう折り合いをつけるか、どう裏切るかという問いが中心に据えられている。
そのため、過去作にあったソウル的な高揚感やエロスは控えめになり、より冷たく、抑制された、しかし内側で燃え続ける衝動が作品全体を支配している。
グレッグ・デュリのボーカルは年齢とともに深みと翳りを増し、歌詞はより抽象的で詩的に。
“復活”というよりも“別の次元での再構築”と呼ぶべき、異形のロック作品なのである。
おすすめアルバム
- Nick Cave and the Bad Seeds / Push the Sky Away
静かな語りと内面的緊張の構築が共鳴。 - Mark Lanegan / Blues Funeral
重たくスモーキーなロックと霊的なソングライティング。 - Queens of the Stone Age / …Like Clockwork
再起における不穏な美学の表現に共通項あり。 - Swans / The Seer
破壊と再生、音による儀式的構成が似ている。 - Wovenhand / Refractory Obdurate
宗教的なモチーフとダーク・アメリカーナの統合。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Do to the Beast』は複数の都市(ロサンゼルス、シンシナティ、ニューオーリンズ)で断続的に録音され、バンドの空白期間を象徴するような“場所と時間の分断性”をサウンドにも反映している。
また、参加メンバーの多くはかつての正式メンバーではなく、グレッグ・デュリのプロジェクト的色合いが濃い構成となっている。
それでも“Afghan Whigs”という名前を冠したのは、音楽ではなく“魂”の持続が重要なのだという信念の現れだったのかもしれない。
『Do to the Beast』は、傷を癒すでもなく、開き直るでもなく、ただ“獣と向き合う”ことでしか先へ進めなかった男たちの、ひとつの静かな闘いの記録である。



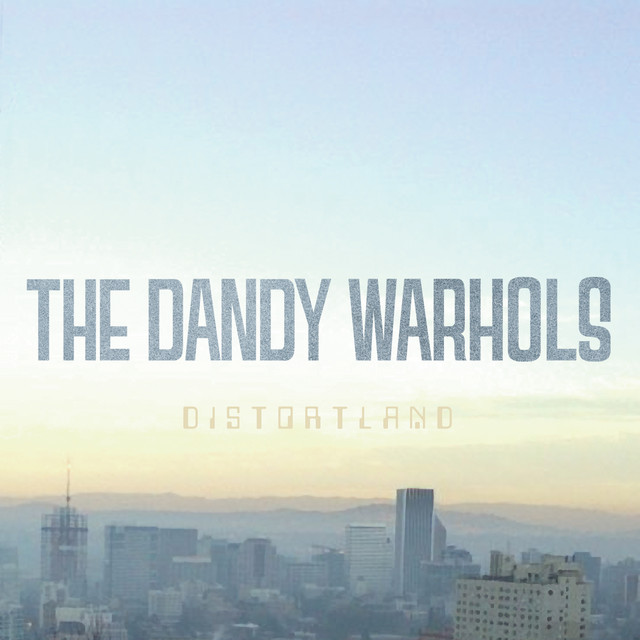
コメント