
発売日: 1984年9月24日
ジャンル: シンセポップ、ニューウェイヴ、ブルー・アイド・ソウル
概要
『How Men Are』は、Heaven 17が1984年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、政治性、感情性、そして音楽的実験精神のバランスが大きく振れた“過渡と拡張”の作品である。
前作『The Luxury Gap』の成功によって得た商業的余裕と音楽的自信を背景に、本作ではより複雑で野心的なアレンジ、そしてシリアスなメッセージ性が打ち出されている。
アルバムタイトルの『How Men Are(男たちはこうなのだ)』は、男性性、権力構造、社会的役割といったテーマを内包しており、その表現はときに辛辣で、ときに哀切を帯びている。
また本作からは、ポップな装いの裏に、テクノロジーと人間の関係性、マスコミュニケーション、階級格差といった問題意識がより強く意識されるようになった。
サウンド面では、アナログシンセだけでなくオーケストラ、生ドラム、ゴスペル・コーラスなどアコースティック/有機的な要素の導入が顕著であり、それにより人間的温度とテクノロジー的冷徹さの対比が一層浮き彫りになっている。
全曲レビュー
1. Five Minutes to Midnight
アルバムの幕開けを告げるダークなナンバー。
“真夜中5分前”というタイトルは、冷戦下の緊張や社会崩壊への危機感を象徴。
不穏なビートと緊迫感のあるサウンドは、80年代の終末感を見事に捉えている。
2. Sunset Now
本作のリードシングル。
夕焼けというイメージが、終焉と解放を同時に示す。
ソウルフルなメロディと淡いコーラスが印象的で、バンドの中でも特に“歌”を重視した作りになっている。
3. This Is Mine
バンド史上もっともソウルフルでエモーショナルなトラックのひとつ。
自らの所有とアイデンティティを主張する歌詞は、貧困や差別、個の尊厳といったテーマと密接に結びついている。
ストリングスとゴスペル・コーラスの導入により、劇的な効果が生まれている。
4. The Fuse
実験的な電子音と不協和音が散りばめられた、前衛的アプローチの楽曲。
“導火線”というタイトルの通り、社会や感情の爆発寸前の状態を暗示している。
構造としてはかなり複雑で、聴き手に緊張を強いるタイプの一曲。
5. Shame Is on the Rocks
カリブ的なリズムと冷ややかなヴォーカルが絡むミディアム・チューン。
“恥は崩れた岩の上にある”という詩的な比喩が、倫理や道徳の流動性を示唆する。
ダンサブルでありながら、どこか虚無的な空気が漂う。
6. The Skin I’m In
本作の中でもっとも内省的で静謐なトラック。
“この皮膚に包まれた自分”という自己認識をテーマに、人間のアイデンティティに関する深い問いを投げかける。
ミニマルな構成と繊細なボーカルが心に残る。
7. Flamedown
恋愛をテーマにした希少な楽曲。
しかし“燃え落ちる炎”というタイトルが示す通り、関係の終焉と感情の焦土を描いている。
バラード調の構成だが、シンセの音色はどこまでも冷たい。
8. Reputation
グレン・グレゴリーの演劇的なボーカルが光るアップテンポ曲。
“評判”という社会的な評価が、人間をどう変えてしまうのかを描いた風刺的ナンバー。
中毒性のあるリフとアイロニカルな歌詞が好対照。
9. And That’s No Lie
9分を超えるアルバムのハイライト。
構成は複数のパートに分かれ、シンセポップ、ソウル、エレクトロファンクが折り重なる組曲的展開。
“そしてそれは嘘じゃない”という繰り返しが、真実と虚構のあわいを示す。
Heaven 17の音楽的野心とスケール感が最もよく表れた楽曲のひとつ。
総評
『How Men Are』は、Heaven 17がポップアイコンから“社会を問うアーティスト”へと大きく舵を切った作品である。
サウンド的にも、冷たいシンセから人間的な要素(ストリングス、コーラス、ジャズ的リズム)へと拡張し、エレクトロとソウルの橋渡しを果たす音像が完成している。
その一方で、アルバムにはどこか“過渡的な混沌”も漂っており、前作『The Luxury Gap』の完成されたポップ性と比べると、曖昧さや葛藤をあえて音楽に反映させたような構成になっている。
そこには、“男たちはこうなのだ”という冷めた観察と、なお人間性への希望を捨てない視線が同居している。
『How Men Are』は、社会的・政治的テーマを内包しながらも、感情と詩性を絶妙に絡めた、80年代シンセポップの思想的頂点のひとつであり、複雑な美しさを秘めた問題作である。
おすすめアルバム(5枚)
-
Talk Talk / The Colour of Spring (1986)
電子音と人間性の融合。構成美とスピリチュアルな奥行きが共通。 -
Ultravox / Lament (1984)
シンセポップから感情表現へと向かう転換点を刻んだ名作。 -
Japan / Gentlemen Take Polaroids (1980)
冷たい美学と耽美的構成の極致。『How Men Are』と響き合う。 -
Thomas Dolby / The Flat Earth (1984)
実験性とポップ性、内省と文明批評のクロスオーバー。 -
Orchestral Manoeuvres in the Dark / Dazzle Ships (1983)
ポップと政治、電子音と社会実験の野心作。



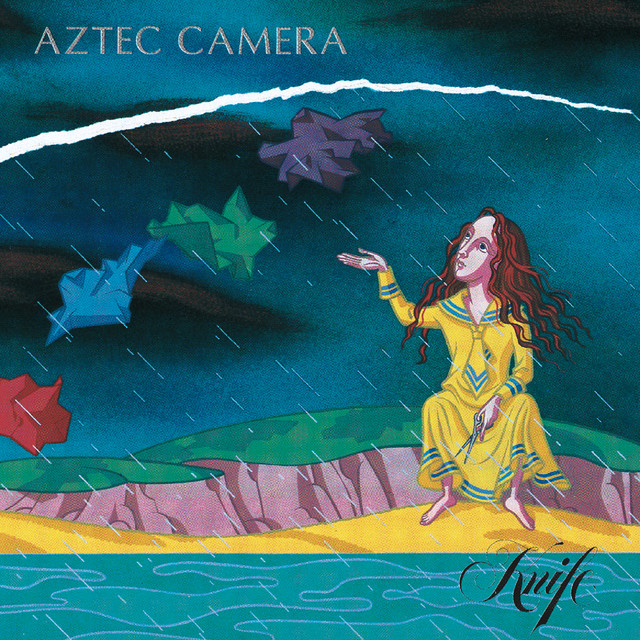
コメント