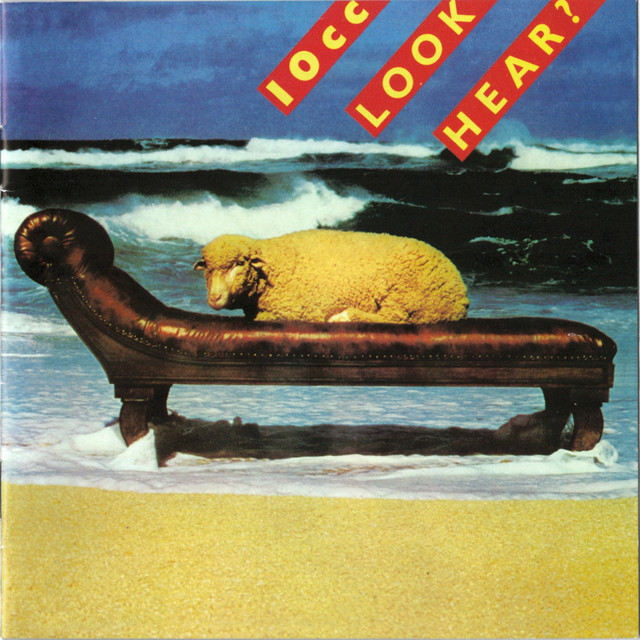
発売日: 1980年3月28日
ジャンル: ソフトロック、アートポップ、ニューウェーブ
音楽と視線のすれ違い——迷走か再出発か、80年代への戸惑いが刻まれた10ccの過渡期作
『Look Hear?』は、1980年にリリースされた10ccの7作目のスタジオ・アルバムであり、70年代の黄金期を越えて初めて向き合う“時代の変化”と“自己の再定義”が刻まれた一枚である。
前作『Bloody Tourists』で世界を巡る視線を描いた彼らは、今作ではより個人的・内省的なテーマと、時代のサウンドトレンドへの応答に重きを置いている。
とはいえ、本作は10ccにとってやや迷いの見える作品でもある。
グールドマンが私生活の事情で制作から一時離脱していたこと、メンバー間の緊張感、そしてポップスの文脈に突如として現れた「ニューウェーブ」の衝撃など、制作背景には複数の要因が重なっている。
アルバムタイトル「Look Hear?(見てる?聞いてる?)」という挑発とも問いかけともとれる二重の表現は、リスナーとの距離感やコミュニケーションの変化を象徴しているかのようだ。
全曲レビュー
1. One-Two-Five
オープニングを飾るのは、ダンスブームを皮肉るニューウェーブ調のアップテンポナンバー。
「One-Two-Five」とはディスコのBPMを指しており、躍らされる現代人への風刺と、スチュワートらしいクールなアレンジが融合している。
2. Welcome to the World
観光者的視点を継続したようなユーモアソング。
明るく軽快なメロディに隠されたアイロニーが、世界の表層化を風刺する。
3. How’m I Ever Gonna Say Goodbye
パーソナルな別れを描いた穏やかなバラード。
アレンジは控えめながら、スチュワートの感情の機微が丁寧に描かれている。
4. Don’t Send We Back
アフリカ系ディアスポラへの言及を思わせるタイトルだが、実際は難民・追放・帰属をめぐる寓意的内容。
リズムのアクセントとコーラスの使い方に10ccのセンスが光る。
5. I Took You Home
恋愛の期待と現実のズレをシニカルに描いたラブソング。
メロディラインは美しく、ポップスとしての完成度は高い。
6. It Doesn’t Matter at All
本作中もっとも美しいバラードのひとつ。
別れを肯定するような諦念に満ちた歌詞と、メロウなサウンドの調和が心を打つ。UKチャートでは小ヒットを記録。
7. Dressed to Kill
女性への欲望と恐れがテーマのダークなナンバー。
サウンドはややAOR寄りで、ギターの艶やかな響きとヴォーカルの陰影が印象的。
8. Lovers Anonymous
10ccらしいひねりの効いたアイデアソング。
恋愛依存症者の自助グループというコンセプトをコミカルに扱いながら、実は深い孤独感が滲む一曲。
9. I Hate to Eat Alone
孤食をめぐるセンチメンタルなミドルテンポ曲。
ユーモラスな視点とささやかな哀愁のブレンドが、かつての10cc節を思い出させる。
10. Strange Lover
10ccの得意とする“ねじれたラブソング”。
幻想的なアレンジと変拍子が、愛の不確かさを音楽で表現する。
11. L.A. Inflatable
アルバムのクロージングは、ハリウッド文化の虚構性を描いた幻想的な一曲。
インフレータブル(空気で膨らむもの)という語感が、中身のない憧れや偶像性を示唆している。
総評
『Look Hear?』は、10ccが70年代から80年代に差しかかる中で直面した、音楽的アイデンティティの揺らぎと再構築の試みである。
明確なコンセプトや鋭い風刺はやや後退し、より内向的でパーソナルな楽曲群と、当時の音楽シーンへの手探りの対応が見て取れる。
しかしそれゆえに、このアルバムには「時代の狭間に立つ者たち」の不安定さと誠実さが刻まれている。
派手さはないが、聴き込むほどに複雑な感情が滲み出てくる、いわば“沈黙の中に佇むポップ”とも呼べる作品だろう。
10ccを知る者にとっては、その“過渡期の肖像”として興味深く、また穏やかな夜にじっくり耳を傾けたくなるような一枚である。
おすすめアルバム
-
Roxy Music『Flesh + Blood』
80年代初頭の移行期に生まれた、美と迷いの記録。 -
Steely Dan『Gaucho』
アーバンで洗練されたサウンドと虚構のテーマが重なる。 -
Prefab Sprout『Swoon』
ソフトかつ知的なポップの進化系。 -
Paul McCartney『McCartney II』
実験とポップが交錯するポスト70s的ソロ作。 -
Split Enz『True Colours』
ニューウェーブとメロディの融合。迷いと発明の同居を感じさせる。


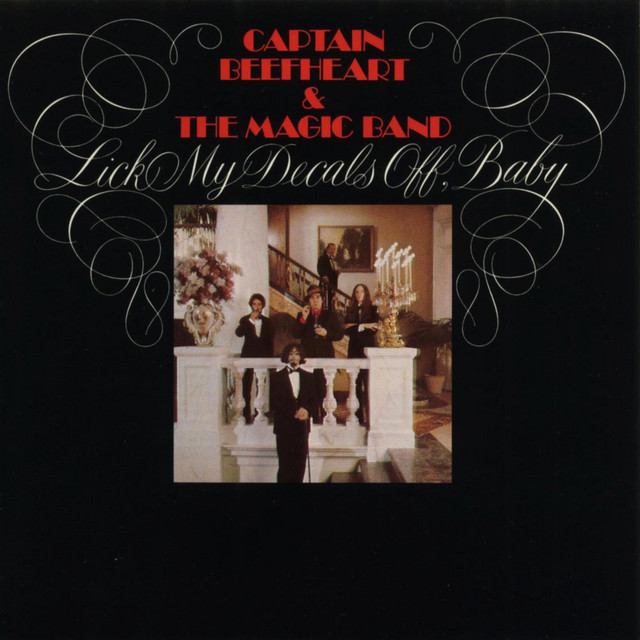
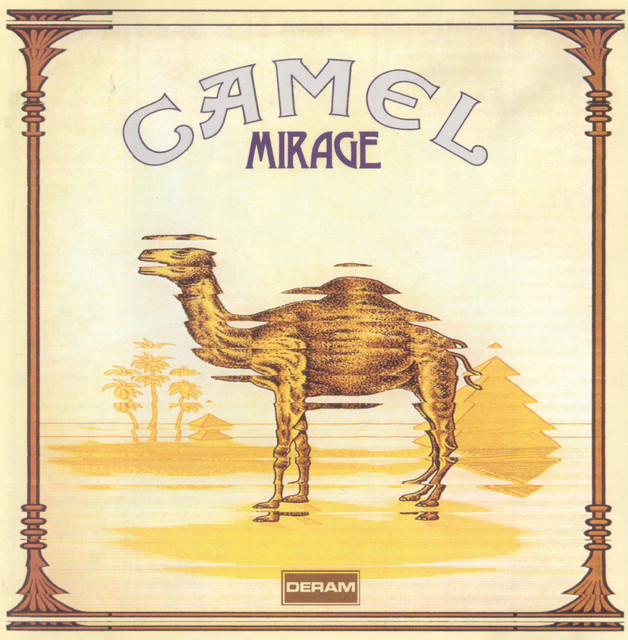
コメント