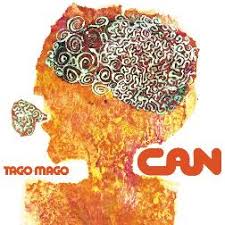
1. 歌詞の概要
『Oh Yeah』は、1971年のアルバム『Tago Mago』に収録された楽曲であり、Canの美学と哲学が見事に凝縮された一曲である。冒頭で逆再生された声が響き、その音像だけで聴き手の意識は日常から乖離し、不思議な感覚へと誘われる。そこから始まる「Oh yeah」という反復は、シンプルでありながら、まるで呪文のような効力を持っている。
この曲の歌詞は明確なストーリーを語るものではなく、イメージの断片が連なっていくような構成をとっている。夢の中の記憶、現実と幻想のあいだに揺れる感覚、自我の解体と再構築——それらが音と声によって暗示される。Damo Suzukiのボーカルは、歌うというよりも、感情の波をそのまま音として放出しているかのようであり、意味ではなく音の“質感”が主役となっているのだ。
2. 歌詞のバックグラウンド
『Oh Yeah』が収録された『Tago Mago』は、Canの実験性が最も色濃く表れたアルバムとして知られている。Damo Suzukiが加入し、即興性と非言語的な表現が全面に押し出されたこの作品は、クラウトロックというジャンルを定義づける重要作でもある。
『Oh Yeah』は、A面後半の楽曲であり、直前の『Mushroom』の緊張感と黙示録的なムードを引き継ぎながらも、よりリズミカルで身体的なグルーヴを導入している。この曲の特筆すべき点は、冒頭のボーカル・パートが完全に逆再生されていることで、時間と記憶の感覚が一瞬で揺さぶられる。この音響的仕掛けは、単なるノイズや演出ではなく、「音楽における時間の方向性すらも問い直す」というCanの実験精神を象徴している。
3. 歌詞の抜粋と和訳
引用元: Genius
Oh yeah, oh yeah, oh yeah
ああ、そうだ、そうだよ、そうだ
Aah ha aah ha, oh yeah
アーハ、アーハ、そうだよ
She’s so fine, she’s so fine
彼女はなんて素敵なんだ、なんて素敵なんだ
Oh yeah, oh yeah
そうだ、そうなんだ
歌詞は極めて断片的で、意味を持つというよりも、音の響きとリズムに身体を委ねる感覚が強い。反復される「Oh yeah」という言葉は、意味を超えて感覚を喚起する“音のパルス”として機能している。
4. 歌詞の考察
『Oh Yeah』の歌詞には、従来の「意味を伝える言葉」としての機能はほとんど存在しない。むしろCanは、言葉そのものを音楽の一部として扱っており、意味から解き放たれた音がどれほどの力を持ちうるかを探求している。
たとえば、「She’s so fine」という一節も、特定の女性を描写しているというよりは、陶酔の中で発せられる“感覚そのもの”に近い。これはリスナーの内的感情と共鳴し、言葉にならない想いを音に託す行為ともいえるだろう。
また、「Oh yeah」というフレーズの反復は、肯定とも陶酔とも、あるいは無意味さの中にある自由とも受け取れる。意味が明瞭でないからこそ、聴き手は自由に解釈し、その時々の感情を映し出す鏡のようにこの音に向き合うことができる。
冒頭の逆再生パートは、時間の流れを逆転させ、意識の始まりを非現実の中に置くという演出でもある。Canは音によって「記憶の歪み」や「時間の再構築」を試みているのであり、その効果は直感的にリスナーの身体へと伝わる。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Vitamin C by Can
よりファンク色が強く、同様に反復とリズムの魅力に満ちた代表曲。 - Hallogallo by Neu!
反復的なビートと空間性の中に、無意識の流れを感じさせるトランス的な一曲。 - The End by The Doors
夢と現実、死と性をテーマにした詩的長編。『Oh Yeah』の内面的旅路と共振する作品。 - The Belldog by Brian Eno & Cluster
退廃的で幻覚的な音世界の中に漂う、美しくも寂しげなトーンが印象的。
6. 音の反復が導く“感覚の自由”
『Oh Yeah』という曲は、Canの美学を象徴するような“音による自由”の宣言である。反復されるドラム、うねるベースライン、そしてDamo Suzukiの非言語的なヴォーカルは、聴き手に思考を捨てさせ、ただ音に身を委ねることを促してくる。
このような構成は、ミニマルミュージックや先鋭的なクラブ・ミュージックの先駆けでもあり、Canの作品がいかに時代を超えて先見性を持っていたかを示している。時間を逆行させ、言葉を反復し、意味を脱構築する——それは音楽が内面の無意識と交差するための手段でもあるのだ。
Canの『Oh Yeah』は、思考と身体、意味と音、理性と夢の狭間に立ち現れる、唯一無二の音響彫刻である。そこにあるのは明確な答えではなく、揺らぎと感覚。そしてその揺らぎの中に、私たちは“自由”の気配を嗅ぎ取ることができるのかもしれない。



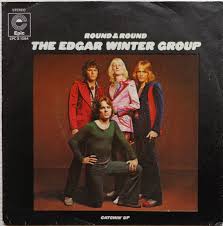
コメント