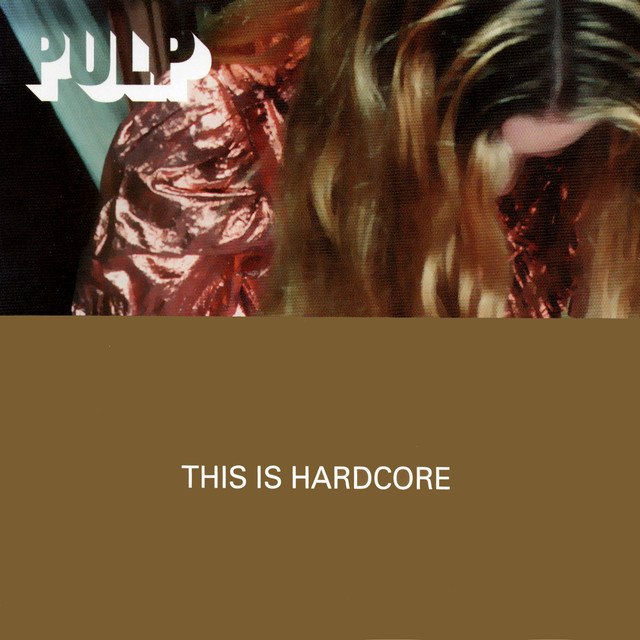
1. 歌詞の概要
「This Is Hardcore(ディス・イズ・ハードコア)」は、1998年にリリースされたPulp(パルプ)の同名アルバムのタイトル曲であり、ジャーヴィス・コッカーが名声の果てに辿り着いた**“終末的ポップソング”**にして、バンドのキャリアの中でも最も挑戦的かつ耽美的な楽曲のひとつである。
タイトルにある「ハードコア」とは、もちろん音楽ジャンルとしてのハードコア・パンクではなく、ポルノグラフィーの「ハードコア」、つまり“隠しようのない剥き出しの欲望”を意味している。だがこの曲は、性的な直接描写をなぞるのではなく、むしろ**ポルノのように消費され、廃れていく存在としての“自分”**をメタファーとして用いて、芸能界、性、自己の虚無を同時に描いている。
曲中でジャーヴィスは、まるでキャリアの終焉を予感する老いたポルノスターのように、自嘲と疲労、興奮と諦念を交錯させながら「これが“本番”なんだ」と告げる。
だが“本番(ハードコア)”とは何か? それは名声か、性的快楽か、消耗か――その答えは曖昧なまま、不穏なストリングスとねっとりしたビートの中で沈み込んでいく。
この曲は、ただの性的メタファーではない。
それは**「見られること」に生きる者の終着点**であり、Pulpというバンドがブリットポップという祭りの後に見つけた、最も苦い真実なのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
1995年の『Different Class』で国民的バンドの地位を手にしたPulpだったが、フロントマンのジャーヴィス・コッカーはその名声に強い違和感と疲弊を覚えていた。
表舞台に出れば出るほど、私生活が消耗し、誰かの理想像にすり替えられていく――
『This Is Hardcore』というアルバム全体は、そうした**“見られること”の恐怖と中毒性**をテーマにした作品であり、その中心に据えられたのがこのタイトル曲である。
楽曲のアレンジにはScott Walker的な耽美主義や映画音楽的スケールが色濃く反映されており、特に冒頭の不協和音とホーンセクション、ダークで官能的なストリングスが聴き手に強烈な不安感を与える。
ミュージックビデオでは、古びた映画館や撮影セットの中をさまようジャーヴィスの姿が描かれ、人生そのものが“撮影”の繰り返しであるかのような虚無感が演出されている。
つまり、「This Is Hardcore」はジャーヴィス・コッカーによる**“名声ポルノの告白”**であり、そこに映し出されるのは快楽でも成功でもなく、人生の裏側に滲む影と、その影に酔ってしまった者の肖像なのだ。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「This Is Hardcore」の印象的な歌詞を抜粋し、日本語訳を添える。
You are hardcore, you make me hard
You name the drama and I’ll play the part
君は“ハードコア”だ、だから僕は興奮する
君がドラマを用意するなら、僕はその役を演じよう
It seems I saw you in some teenage wet dream
I like it when you do that stuff to me
君の姿を見たことがある気がする、10代の性的な夢の中でね
君が僕にあんなことをしてくれるのが、たまらなく好きなんだ
It’s the eye of the storm
It’s what men in stained raincoats pay for
But in here, it is pure
Yeah, this is hardcore
それは嵐の中心
汚れたレインコートを着た男たちが金を払って手に入れるもの
でもここでは、それは純粋なんだ
そう、これが“ハードコア”なんだよ
(歌詞引用元:Genius – Pulp “This Is Hardcore”)
4. 歌詞の考察
「This Is Hardcore」の歌詞は、欲望の場面を演出する側と、それに巻き込まれる側との境界線を曖昧にしながら、消費と演技、そして認識の不協和を描いている。
“君がドラマを用意するなら、僕が演じよう”という一節に象徴されるように、語り手は“主体”ではなく“演者”であり、その行動は他者の期待に基づいている。
それはまさにポルノ産業における“快楽の演技”の構造そのものであり、ひいてはエンターテインメント業界やポップスターという存在の虚構性を示している。
この曲で語られる「快楽」は、純粋な情熱ではない。それは演出され、商品化され、終わりのあるものだ。
ジャーヴィスはその“終わり”を知ってしまった側として、「This Is Hardcore」という一種の“遺言”を残しているのだろう。
また、“これがハードコアなんだ”という断言には、これが現実なんだ、これが大人になるってことなんだ、という冷徹な認識が潜んでいる。
そしてそれは、セックスの話であると同時に、人生そのものの話でもあるのだ。
(歌詞引用元:Genius – Pulp “This Is Hardcore”)
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- The Fear by Pulp(from This Is Hardcore)
不安と現実逃避をめぐる静かな独白。“ハードコア”の後に残る感情を描いた姉妹曲。 - Fitter Happier by Radiohead(from OK Computer)
人間性を失った生活の機械化を描いた短編。芸能と虚無の構造的類似を感じさせる。 - Perfect Day Elise by PJ Harvey
快楽と暴力の境界をにじませた官能的トラック。“消費される女”というテーマが呼応する。 -
Sleep to Dream by Fiona Apple
感情を“声”で武器化するフェミニスト的ポップ。支配と自由の構造に対抗する力強さをもつ。
6. 名声、欲望、そして終わり――すべてが演技になった世界で
「This Is Hardcore」は、Pulpというバンドが**“ポップの裏側”そのものを歌った数少ないアーティストであることを決定づけた作品**である。
それは成功の頂点に立った者だけが見られる景色であり、
そこで見えるのは栄光ではなく、人間としての虚ろさと、消費されることへの依存である。
この曲のタイトルが“これが本番だ”であることは、皮肉にも聞こえるし、真実にも聞こえる。
それはカメラが回り続ける限り、私たちはずっと“演じ続けなければならない”という残酷な現実なのだ。
そしてそれを自覚した語り手が、なおも“演じてみせる”その姿に、
私たちは気味の悪い共感と、どこかしらの美しさを見出してしまう。
これがハードコア――
これが人生という舞台の、もうひとつの幕開けなのかもしれない。


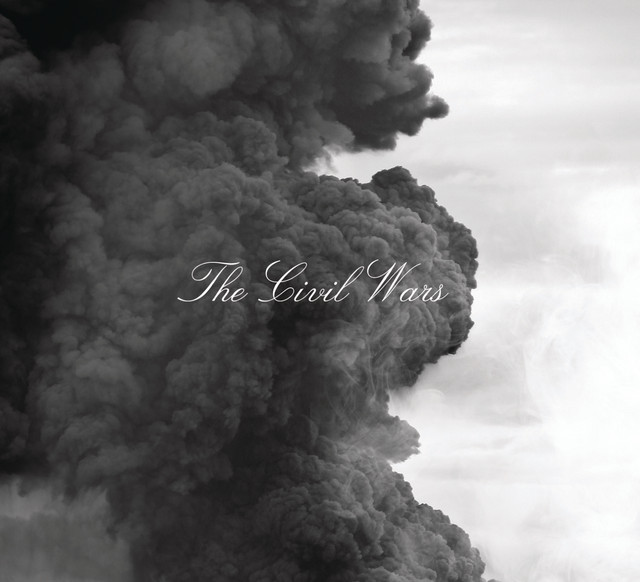
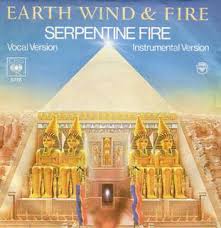
コメント