
1. 歌詞の概要
「Woman in Chains」は、Tears for Fearsが1989年に発表したアルバム『The Seeds of Love』に収録された壮大なバラードであり、フェミニズム、人間の抑圧、ジェンダーの役割への鋭い問いかけを内包した、異例のスピリチュアル・ポップソングである。
曲のタイトルにある「鎖に縛られた女(Woman in Chains)」という表現は比喩的であり、社会の中で抑圧されてきた女性たちの姿を象徴している。しかしこの曲は、単なるジェンダー批評にとどまらず、男らしさを強制される男性の苦悩にも目を向けており、「自由とは何か」「優しさを抑えることが強さなのか」といった本質的なテーマを静かに、だが確かに提示している。
デュエットの形でフィーチャーされたのは、アメリカのソウルシンガー、オレッタ・アダムス。彼女の力強くも繊細な歌声が、抑圧に抗う女性の声そのものとして響き、楽曲に深みと説得力を与えている。
2. 歌詞のバックグラウンド
この曲の構想は、バンドの中心人物であるローランド・オーザバルが、フェミニズムについて深く考えるようになった時期に生まれた。彼はインタビューで、「自分が育った家庭には女性の存在がなかった。だからこの曲は、母性や優しさ、女性性の抑圧について書いたんだ」と語っている。
当時、1980年代後半の社会はまだ保守的な価値観に支配されており、「女性は家庭にいるべき」「男性は感情を見せてはいけない」というステレオタイプが根強かった。この曲は、そのような社会構造が人間の本来の感情や可能性を縛っていることへの批判なのである。
また、楽曲のサウンド面でも極めてユニークで、当時Phil Collinsがドラムを担当。彼の叩くロータム中心のダイナミックなビートが、楽曲のドラマ性を高めている。繊細なピアノとストリングス、オレッタのゴスペル的なボーカル、ローランドの内省的な声が重なり合い、まるで一篇の叙事詩のような構成となっている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に象徴的なフレーズを紹介する(引用元:Genius Lyrics):
You better love loving and you better behave
“愛すること”を愛するべきだし、従順であるべきなんだろう
Woman in chains, woman in chains
鎖に縛られた女──そう、鎖の中の女なんだ
Well I feel lying and waiting is a poor man’s deal
横たわって待つことなんて、貧しい者がすることさ
And I feel hopeless when the hunger starts to rise
そして、飢えがこみあげるたび、僕は絶望を感じる
You better love loving or you don’t love at all
本当に“愛する”ことを知らなければ、それは愛ではない
繰り返される「woman in chains」という言葉は、ただの物理的な束縛ではなく、“感情や可能性の抑圧”を象徴する詩的なメタファーである。
そして、それを描写する語り手もまた、社会的役割に疲れ切った男性であり、この曲が描くのは“性別を超えた抑圧と解放”の物語なのだ。
4. 歌詞の考察
「Woman in Chains」は、ポップミュージックとしては非常に珍しいテーマ──フェミニズムとジェンダー構造への疑問を真正面から扱っている。しかもそれを、教訓的に語るのではなく、詩と音楽の力で静かに染み込ませていくように描いている。
女性に向けられた「You better behave(お行儀よくしてろ)」という命令口調は、社会が女性に課してきた規範や期待を象徴しており、それに対して“自分を解放しようとする女”の姿が、オレッタ・アダムスの歌声を通じて表現される。
だが、この曲は決して女性だけの歌ではない。
男性の視点からも、“強さを装わねばならない”“感情を見せてはいけない”という苦しみが描かれており、「I feel hopeless when the hunger starts to rise」というラインには、愛されたいのに愛し方がわからない男性の孤独が滲んでいる。
だからこそ「Woman in Chains」は、ジェンダーという構造が、性別を問わず人間を抑圧するものであることを鋭く描いている楽曲であり、愛と解放のテーマを普遍的なものへと昇華しているのだ。
(歌詞引用元:Genius Lyrics)
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- This Woman’s Work by Kate Bush
女性の身体的・精神的苦悩を詩的かつ劇的に描いた、フェミニズムの名バラード。 - Freedom! ’90 by George Michael
自分らしさを貫くことの苦しみと喜びを描いた、自己解放のアンセム。 - I Am Woman by Helen Reddy
1970年代のフェミニズムを象徴する、力強くも優しい自己肯定の歌。 - Fast Car by Tracy Chapman
貧困、性別、愛情、自由──すべての境界線を越えて、人生を変えようとする女性の歌。 - Strong Enough by Sheryl Crow
女性の内なる強さと脆さを対比させた、静かながらも強靭なラブソング。
6. “愛するためには自由でなければならない”:抑圧の鎖を断ち切る詩と音
「Woman in Chains」は、1980年代後半という時代の中で、非常に勇敢かつ誠実に“ジェンダーと愛の本質”を問いかけた楽曲であった。
それは、フェミニズムの旗を振るのではなく、人間の魂が本当に自由になるにはどうすればいいのかという、より根源的な問いを音楽に乗せて提示している。
ローランド・オーザバルの声は内面の苦悩を、オレッタ・アダムスの声は抑圧からの解放を、フィル・コリンズのドラムは内側から湧き上がる怒りと希望を──それぞれが異なる“声”となり、ひとつの叙情詩を完成させている。
この曲が鳴り終わったあと、心に残るのは痛みだけではない。
そこには、“もっと優しくなりたい”“もっと自由でありたい”という、人間としての最も深い祈りのようなものが静かに燃えている。
「Woman in Chains」は、その静かな炎のように、今なお私たちの心を照らし続けているのだ。


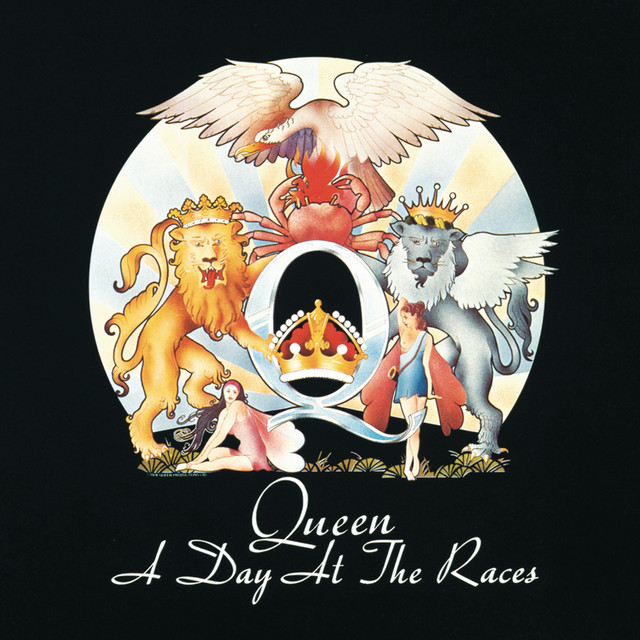

コメント