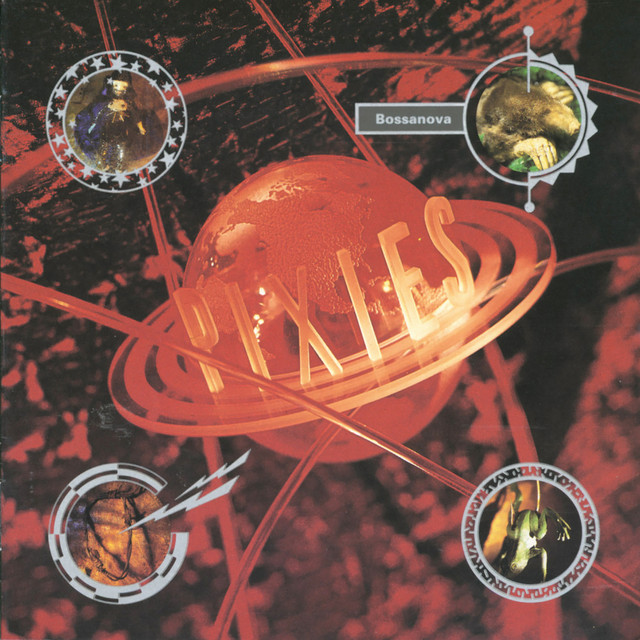
1. 歌詞の概要
「Velouria(ヴェルーリア)」は、Pixiesが1990年にリリースした4作目のスタジオ・アルバム『Bossanova』からの先行シングルとして発表された楽曲であり、同バンドのディスコグラフィにおいて最も“メロディックでロマンティック”な曲のひとつとされている。
タイトルにある「Velouria」という名は架空の人物であるが、その響きには柔らかさ、親密さ、そして神秘性が宿っている。歌詞全体は、ある種の“超自然的な存在”に対する賛美、あるいは崇拝にも近い感情を描いており、Pixiesにしては異例の、明確な恋愛のニュアンスを帯びている。
とはいえ、そのロマンスは決して甘いものではない。むしろ、オカルトやSF、神話といった幻想的な要素が入り混じり、Pixiesらしい超現実主義が色濃く表れている。聴き手は現実と夢の境界が曖昧になるような浮遊感の中に、Velouriaという名の“謎の女神”の姿を追いかけることになるのだ。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Velouria」は、Pixiesにとって初の全英トップ40入りを果たしたシングルであり、そのキャッチーで厚みのあるメロディは、バンドの新たな進化を象徴するものとして評価された。
本作が収録されたアルバム『Bossanova』は、Pixiesの前作『Doolittle』に比べてリバーブ感が強く、宇宙的なサウンドスケープが特徴となっている。そのため「Velouria」も、どこか宇宙空間に放たれたラヴソングのように響く。ギターは重層的でサーフロックの影響を色濃く受けており、反復するメロディとダイナミクスの波が、リスナーを心地よいトランス状態へと導いていく。
Black Francis(フランク・ブラック)はこの曲に関して、「ヴェルーリアは空想上の女性であり、地底王国アガルタのような神秘的な場所に属する存在」だと語っている。これはニューエイジ思想やオカルティズムに通じる発想であり、単なる恋愛の対象というよりも、神話的で異次元的な存在として描かれている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「Velouria」から印象的なフレーズを抜粋し、その和訳を添える。
引用元:Genius Lyrics – Pixies “Velouria”
Hold my head / We’ll trampoline / Finally through the roof
僕の頭を抱いて 僕らはトランポリンみたいに飛び跳ねて ついには屋根を突き抜ける
On to somewhere near and far in time
時のどこか、近くて遠い場所へと飛び出す
Velouria, Velouria
ヴェルーリア、ヴェルーリア
We will wade / In the shine of the ever
僕らは永遠の光の中を歩いていく
We will wade / In the shine of the ever
永久の輝きに包まれながら
Velouria
ヴェルーリア
4. 歌詞の考察
この曲の魅力は、何よりもその“曖昧さ”にある。
語り手はVelouriaという存在を呼びかけ、彼女と共にどこか異次元的な空間へと旅立とうとしている。歌詞に現れる「trampoline」「roof」「shine」「ever」などの語彙は、物理的な現実から飛び立ち、幻想世界へと昇華していく感覚を強調している。ここにあるのは、愛の告白というより、存在そのものへの祈りに近いものだ。
「Velouria」が誰なのか、あるいは何を象徴しているのかは語られない。しかしその不確かさがかえって、聴く者の中に多様な解釈を生み出す。彼女は恋人かもしれないし、神話の女神、死者、あるいは“もう戻れない過去”そのものかもしれない。
また、「shine of the ever(永遠の輝き)」という表現には、時の流れを超越するようなイメージがあり、ここでもPixiesがしばしば扱ってきた“永遠と刹那”“聖と俗”という二項対立が浮かび上がる。
「Velouria」は、Pixiesの音楽にしては珍しく、内面の深層へと降りていくのではなく、上昇する、昇天するような志向を持っている。それは、グラウンドから跳ね上がって天井を突き抜けるような感覚——つまり、現実から逃げるのではなく、そこを突き抜けてどこか違う次元へと進むような、ポジティブな変容の物語でもあるのだ。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Havalina by Pixies
『Bossanova』のラストを飾る、静かなトランス状態に誘う楽曲。アメリカ南西部の風景と夢想が溶け合う名曲。 - Under the Milky Way by The Church
天体的なイメージと甘いメロディが絡み合うドリームポップの名曲。「Velouria」と同じく、地上と宇宙の狭間にいるような感覚を味わえる。 - There Is a Light That Never Goes Out by The Smiths
若さ、逃避、死への憧れをロマンティックに歌い上げた、オルタナティヴ・ラブソング。Pixiesの幻想性とモリッシーの詩情が交錯する。 - Cherry-coloured Funk by Cocteau Twins
言葉が意味を越えて響く感覚、そして女性的な神秘性という点で、「Velouria」とも深い共鳴を感じさせる。
6. “神話のようなラブソング”という可能性
「Velouria」はPixiesにとって異色でありながらも、極めて本質的な楽曲である。
そこには彼らの音楽に一貫して流れるテーマ——境界の曖昧さ、夢と現実の接続、宗教的な神秘性、そして身体性——が静かに、しかし明確に刻まれている。
この曲が示しているのは、単なる“恋”ではない。むしろそれは、ある種の精神的存在に対する崇拝、時間を超えてつながる何かへの希求、そして現実を乗り越えた先にある“存在そのものの美しさ”を巡る詩なのだ。
Pixiesが持つ荒々しさやグロテスクな魅力とは対照的に、「Velouria」は彼らの“天上の側面”を象徴する。そしてそれは、彼らがただ破壊と混乱のバンドではなく、詩的で美しく、魂の深淵に手を伸ばすような音楽も紡ぎ出すアーティストであったことを、静かに証明している。


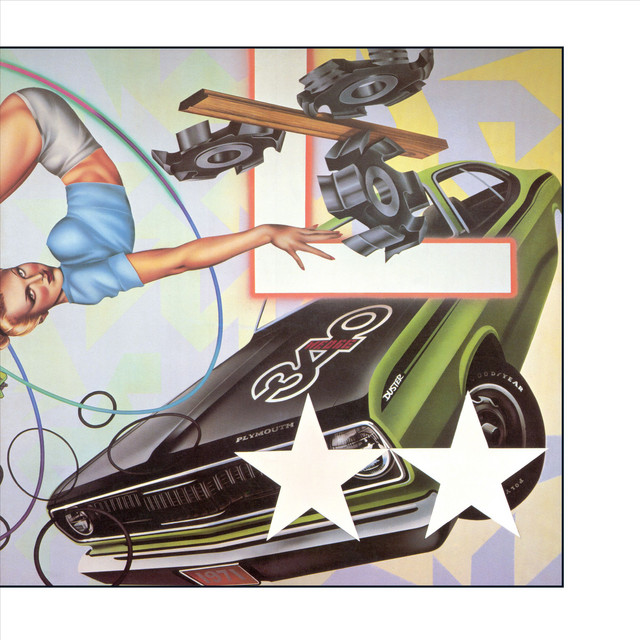

コメント