
発売日: 2012年5月28日
ジャンル: ポストパンク、オルタナティヴ・ロック、エクスペリメンタル・ロック
概要
『This Is PiL』は、Public Image Ltd.(PIL)が2012年に発表した通算9作目のスタジオ・アルバムであり、20年ぶりの完全新作としてファンの前に姿を現した“帰還と再定義”のアルバムである。
1992年の『That What Is Not』以来沈黙を続けていたPILは、ジョン・ライドンのテレビ出演やSex Pistols再結成などを経て、2010年代に突如として活動を再開。
タイトルの「This Is PiL(これがPILだ)」は、名刺のような直接的フレーズであると同時に、「これまでのPILとこれからのPILの橋渡し」を宣言する言葉でもある。
ライドンは自身のレーベル「PiL Official」から本作をリリースし、音楽的にもパーソナルにも完全なコントロールを取り戻した。
サウンドは、初期の実験性と後期の構築性を融合させたハイブリッド。
ギター、ダブ、語り、ノイズ、そしてライドン独特の“説教とも叫びともつかぬヴォーカル”が縦横無尽に交差し、「まだこの男は音で闘っている」と実感させる内容になっている。
全曲レビュー
1. This Is PiL
アルバムは、タイトルをそのまま冠した自己紹介的ナンバーで幕を開ける。
まるでスローガンのように「This is PiL」と繰り返しながら、重くうねるベースとシャープなギターがサイケデリックに展開。
自己定義=“声としての存在”を打ち出す。
2. One Drop
本作のリードシングルで、ライドンがジャマイカ育ちだった過去を背景に描いた、パーソナルでリズミカルな一曲。
「We are the ageless / We are teenagers(俺たちは年を取らない、ずっと10代だ)」というフレーズが、過去と現在をつなぎ、パンクの精神を更新する。
ダブ風味と語り口が融合したPILらしさ満載の楽曲。
3. Deeper Water
6分以上に及ぶディープでサイケデリックな展開を持つトラック。
“深海”という比喩を通じて、内省と再生のテーマがじわじわと浮上する。
ライドンの声は語りに近く、空間的なサウンドスケープが心地よい。
4. Terra-Gate
“Terra=大地”と“Gate=門”が組み合わさった造語的タイトル。
環境問題、政治的分断、地球的規模の閉塞感といった現代的トピックを背景に、怒りというより“観察者の視点”で語る。
ギターの断片的リフと、ダブ的な音処理が印象的。
5. Human
もっともストレートに“人間であること”の複雑さを歌ったトラック。
「I’m not animal, I am human」と繰り返すフレーズが、ライドンの“文明と野性”に対する持続的関心を表す。
シンプルだが、存在の本質に踏み込む哲学的楽曲。
6. I Must Be Dreaming
夢と現実の境界が崩れるような、リズムのゆらぎとボーカルの揺らぎが特徴的なナンバー。
反復的なビートとライドンの曖昧な語りが、夢の中の会話のような印象を与える。
“脱構築されたポップソング”のような異質さが魅力。
7. It Said That
断片的な情報、ニュース、噂、SNS時代の言語環境に対する批判的トラック。
「It said that…(〜と言われた)」という受動態で語られるフレーズが、情報の不確かさと信憑性をテーマにしている。
語りと音が、情報の混沌を音楽化する。
8. The Room I Am In
最もミニマルかつ不穏な空気を放つトラック。
タイトル通り、“自分が今いる部屋”の閉塞感や内面世界を描いたような音像で、まるで音のインスタレーションのよう。
ライドンの声はささやきと怒鳴りの間を行き来する。
9. Lollipop Opera
アルバム中もっとも実験的かつ遊び心に富んだナンバー。
“ロリポップ・オペラ”という意味不明なタイトルに反して、サウンドは非常に攻撃的で、断片的な構成が脳内ループを誘発する。
ライドンの奇声と反復がトランス的。
10. Fool
皮肉と自己分析が交錯する、自虐と批判が入り混じったナンバー。
「I’m a fool, but I’m your fool(俺はバカだ。でもお前のバカだ)」というフレーズが、悲しみと誇りを同時に帯びる。
ギターはシンプルながら、エモーショナルな深みがある。
11. Reggie Song
レゲエではなく“Reggie”という男についての歌。
パーソナルな語りと、第三者への眼差しが重なり、社会と個人の関係性を内省的に描く。
ダブのリズムとギターの絡みが魅力。
12. Out of the Woods
“森を抜け出した”というタイトル通り、アルバムの締めくくりとして象徴的な楽曲。
闇や困難の時代を抜け、ようやく言葉と音を取り戻したかのような、ある種の再生感が漂う。
ラストの余韻が非常に美しい。
総評
『This Is PiL』は、Public Image Ltd.が20年の沈黙を破って提示した“自己証明のアルバム”であり、ジョン・ライドンという存在の進化と持続を見事に刻んだ作品である。
初期の混沌、80年代の構築性、90年代の怒り――それらすべてを経て、ライドンは静かな強度とともに戻ってきた。
本作は、過去の“音の破壊”とは異なり、むしろ“音の関係性”と“言葉の余白”を大切にしたアルバムである。
それゆえ、劇的ではない。だが、聞き込むほどに奥行きが現れる音のドキュメントとして、極めて誠実な表現がここにはある。
“これがPILだ”という言葉には、音楽的な挑発も、商業的な野心もない。
ただ「自分たちはまだここにいる」という生存の意思が込められている。
それだけで十分なのだ。


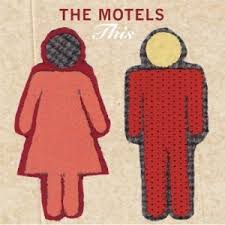

コメント