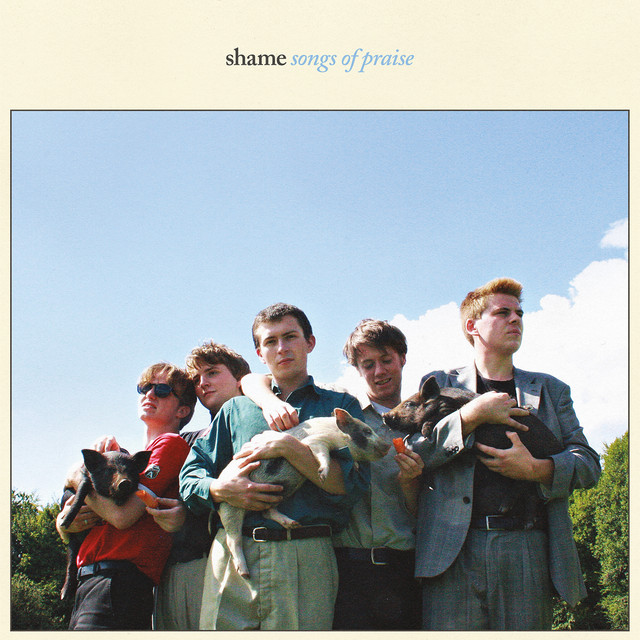
発売日: 2018年1月12日
ジャンル: ポストパンク、インディーロック
⸻
概要
『Songs of Praise』は、Shameが2018年に発表したデビュー・アルバムであり、現代ポストパンク・リバイバルの中核を担う作品として評価されている。
このアルバムは、ロンドン南部出身の若き5人組が、ポストパンクの伝統に90年代オルタナティブの鋭利さを重ね、攻撃的で不穏なエネルギーをぶつけた意欲作である。
バンドは10代から一緒に活動を始め、かの「Queens Head」というパブを拠点にライブ活動を重ねていた。
そのDIY精神と、どこか若気の至りのような激しさが、初作ながら骨太な統一感と圧倒的な熱量を生んでいる。
アルバムタイトルは、BBCの宗教音楽番組『Songs of Praise』からの皮肉的引用であり、音楽の中身はむしろ暴力的で、現代イギリス社会の鬱屈や怒りが剥き出しである。
Gang of FourやThe Fallといったポストパンク先駆者たちの影響を色濃く受けながらも、カタルシスを重視した曲構成、痛快なユーモア、そして社会への冷笑が交錯し、バンド独自のアイデンティティが立ち上がる。
Brexit後の閉塞感、若者のアイデンティティの危機、デジタル化の虚無。
こうした文脈を背景に、Shameは「怒り」の感情を生き生きとしたサウンドに昇華してみせた。
⸻
全曲レビュー
1. Dust on Trial
重厚なギターとカオスな構成で幕を開ける本作の序章。
宗教や制度に対する諷刺を孕んだ歌詞は、すでにバンドの姿勢を明確に提示している。
「裁かれる側と裁く側」という構造への不信感が叫ばれる。
2. Concrete
反復されるフレーズ「And the weight is concrete」が印象的。
愛と退屈、期待と幻滅という二項対立を軽妙かつ鋭利に描く。
トーキングスタイルのボーカルとリズムの突進性がクセになる。
3. One Rizla
アルバムの中で最もポップでキャッチーな楽曲。
「I’m not much to look at, I ain’t much to hear」という自己否定的な一節が逆に開き直りとして響き、アンセム的な力を持つ。
思春期的な不安と開き直りが同居する、象徴的な1曲。
4. The Lick
パフォーマンス重視のバンドの性質がよく現れた挑発的な曲。
ミッドテンポの反復に乗せて、現代社会の「無意味さ」に対する苛立ちが浮かび上がる。
言葉遊びと皮肉に満ちた歌詞は、The Fall的でもある。
5. Tasteless
刹那的でノイジーなギターが引っ掻くように走るナンバー。
「自己表現は無意味か?」という命題を問うような構成で、若者の自己喪失感が色濃い。
短くも強烈なインパクトを残す。
6. Donk
ノイジーなインストゥルメンタルに近い構成で、実験的な一面を見せる。
歪んだサウンドが狂騒的なカオスを生み、アルバムの中盤で一種の錯乱を演出する。
7. Gold Hole
暴力的なビートと挑発的な歌詞が衝突する楽曲。
快楽と退廃、ナルシシズムと他者軽視といったテーマが混在する。
冷笑的な視線と挑発的な語り口が、Shameの本質を示している。
8. Friction
躁的なリズムとシャウトが織りなす爆発的なエネルギー。
社会と自分との摩擦=frictionをテーマに据え、他者との衝突の必然性を肯定するかのような構成である。
9. Lampoon
ギターのうねりとメランコリックなメロディが交錯する中編的ナンバー。
憂鬱さと怒りのグラデーションを描くアレンジが美しく、バンドの表現力を感じさせる。
10. Angie
ラストトラックにして最も内省的。
個人の痛みや喪失感が、怒りではなく静かな諦念として描かれる。
荒々しかったアルバムの流れに一瞬の静寂を与える、エモーショナルな幕引きである。
⸻
総評
『Songs of Praise』は、ポストパンクの語法を引き継ぎながら、それを現代の社会と個人のフラストレーションに接続することで、新しい命を吹き込んだ作品である。
荒削りで衝動的なエネルギーは、ロックの原初的な魅力を思い起こさせるが、それだけで終わらない知性と構成力が見て取れる。
楽曲は短く切れ味がよく、どのトラックにも無駄がない。
しかしその中で、怒りと諷刺、虚無と希望、対立と調和といった二項対立が常にせめぎ合い、聴く者を揺さぶる。
ボーカルのCharlie Steenは、若さと疲弊、傲慢と無力感を同時に体現する存在として、アルバムの重心を担っている。
バンド全体が1つの塊のようにうねる演奏もまた、感情の爆発を支えているのだ。
2010年代後半のUKインディーシーンは多くのポストパンク・リバイバルバンドを輩出したが、その中でもShameは、鋭利なリリシズムと熱量の高さで頭ひとつ抜けていた。
その理由をこのアルバムは如実に示している。
政治や社会への不信、アイデンティティへの問い、愛と不安と諦念。
それらを「ポップ」とは真逆の方法で叫ぶ彼らの音楽は、まさに時代の傷そのもののようにも思える。
耳をつんざくようでいて、どこか切実な美しさを感じさせるこのアルバムは、2010年代のロックを語る上で欠かせない1枚なのだ。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- IDLES『Brutalism』
社会的怒りと暴力的ビートが交錯するUKパンクの現代形。 - Fontaines D.C.『Dogrel』
ダブリン発、文学的リリシズムとポストパンクの新たな融合。 - The Fall『This Nation’s Saving Grace』
皮肉と実験性を併せ持つポストパンクの礎とも言える一枚。 - Savages『Silence Yourself』
ミニマルでタイトな構成と女性的怒りの表出が魅力。 - Protomartyr『Relatives in Descent』
アメリカ版Shameとも言える知的ポストパンクの傑作。
⸻
8. ファンや評論家の反応
『Songs of Praise』は、イギリスの音楽メディアを中心に高い評価を受け、特にそのライブパフォーマンスの再現性や一貫したトーンが称賛された。
NMEやThe Guardian、Pitchforkなど主要メディアは、本作を「若者の怒りを正当に音楽化したアルバム」として位置付けており、デビュー作としては異例の注目度を獲得した。
日本国内でも、ポストパンク系リスナーの間で静かな熱狂が広がっており、特に「One Rizla」はSNS上でもアイコニックな楽曲として語り継がれている。
ライブハウスの熱気をそのまま封じ込めたようなサウンドは、ライブバンド全盛の今の時代において、再評価が進む可能性が高い作品である。



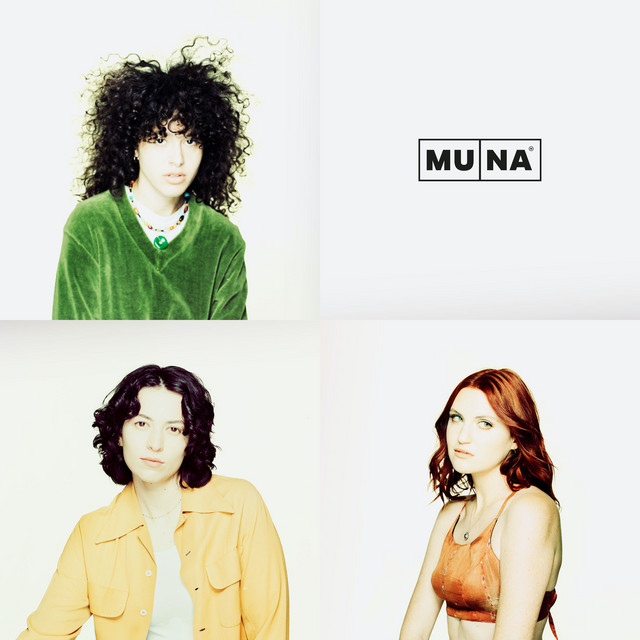
コメント