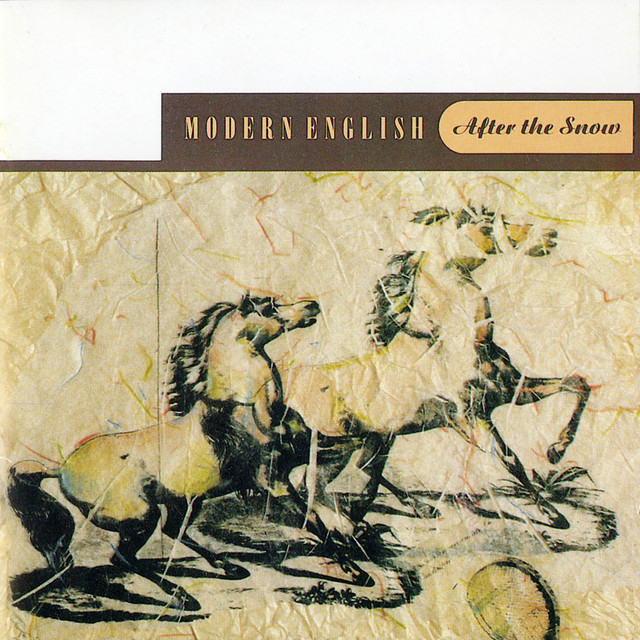
1. 歌詞の概要
「Someone’s Calling(サムワンズ・コーリング)」は、Modern Englishが1982年にリリースしたセカンド・アルバム『After the Snow』の冒頭を飾る楽曲であり、バンドがポストパンクの重苦しさからよりメロディアスで透明感あるサウンドへと転換したことを象徴する一曲である。
タイトルが示す通り、本曲の核にあるのは「呼びかけ」であり、それは文字通りの電話や声であると同時に、無意識下からの衝動、遠くから響く予感、あるいは内なる声をも示唆しているように感じられる。歌詞は一貫して断片的で明確な物語性を持たないが、その分、曖昧な焦燥感や、距離のある関係性、理解されない孤独といった感情をじわじわと浮かび上がらせていく。
音楽的には、軽やかなギターとリズミカルなシンセが絡み合うニューウェイヴらしいアプローチを取りながらも、どこか冷たく、感情を突き放すような印象がある。開放的でありながらも、常に“何かが失われている”感覚が漂う、知的で感覚的なポップソングである。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Someone’s Calling」は、『After the Snow』という作品の新たな音楽的スタートを象徴する一曲である。前作『Mesh & Lace』(1981)でポストパンクの鋭さと不穏を打ち出していたModern Englishは、このアルバムでメロディ志向と内省性を併せ持つ“美しい疎外感”という新境地に踏み込んだ。
作詞のロビー・グレイは、直接的な社会批評よりも、都市生活における漠然とした不安や人間関係の空白、内面の揺らぎといったテーマに関心を向けていた時期であり、この曲もその文脈の中に位置づけられる。
「誰かが呼んでいる」という言葉の反復は、外からの干渉や警告のようでもあり、自分の内面が“何かを知ってしまった”ことへの葛藤のようでもある。モダン・イングリッシュの特徴である「感情の輪郭を曖昧にしたまま、感覚的に語る」スタイルがこの楽曲ではとりわけ冴えている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
(引用元:Genius Lyrics)
Someone’s calling in the night / Someone’s calling in the night
誰かが夜のなかで呼んでいる——繰り返し、誰かが
A voice is talking in my head / And I’m not sure what it said
僕の頭の中で声が話している でもそれが何を言っているのか、はっきりとはわからない
Someone’s calling / Something’s wrong
誰かが呼んでいる——何かがおかしい
Someone’s calling me away / Someone’s calling me to stay
どこかへ行けと呼ばれている 同時に、ここに留まれとも言われている
このように、歌詞は非常に簡潔かつ反復的であり、語り手の混乱や揺れ動く感情を直接的ではなく象徴と矛盾によって描写している。“離れろ”と“留まれ”が同時に聞こえてくるという状況は、まさに都市の孤独や現代人の葛藤を象徴するものであり、正しさのない選択肢の中で宙吊りにされている存在の不安がにじみ出ている。
4. 歌詞の考察
「Someone’s Calling」は、明確なラブソングでもなく、政治的メッセージがあるわけでもない。だがそこには、“意味の空白”を生きる者のリアリティがある。
誰かの声がする。けれど、それが何なのか、どこから来たのかもわからない。もしかするとそれは自分自身の声かもしれないし、無意識の衝動かもしれない。“自分のことを自分がわからない”という感覚は、ポストモダン的な孤独の象徴であり、この曲はそれを、ロジカルではなく感覚のレベルで聴き手に浸透させていく。
繰り返されるフレーズ、あいまいな主語、そして行き場のない命令形。これは、現代に生きる人間が日々感じる不安の輪郭そのものだ。出口のない感情が、突き放されたようなクールな演奏と重なり、かえって聴く者の心に染み入ってくる。
サウンド面では、ギターの煌めきとシンセのレイヤーが印象的で、明確な展開が少ない中で、浮遊感と閉塞感を同時に醸成している。この矛盾した感覚こそがModern Englishの美学であり、後のドリーム・ポップやシューゲイザーに繋がっていく感性の源流でもある。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Careful by Television
日常のズレや異物感を鋭く描きながら、どこか詩的で洗練されたサウンドに昇華したポストパンクの隠れた名曲。 - Atmosphere by Joy Division
重さを感じさせない静けさと絶望感の融合。呼びかけと孤独が共存する楽曲。 - Temptation by New Order
感情の浮き沈みをダンサブルなリズムに乗せて描く、矛盾に満ちた恋と欲望の詩。 - If You Leave by Orchestral Manoeuvres in the Dark
別れの予感と残された感情を、映画的な美しさで包み込んだ80sバラッド。 - Into the Light by Siouxsie and the Banshees
光へ向かう衝動と、そこに潜む怖れの両方を、妖しく魅惑的な音で表現。
6. 曖昧な声に耳を澄ますとき
「Someone’s Calling」は、Modern Englishがまだ“何かに向かって変わりつつあった”時期の作品であり、
その不安定さや曖昧さこそが曲の魅力であり、真実でもある。
誰かが呼んでいる。けれど、それが誰なのかも、何を求めているのかも、はっきりとはわからない。
それでも、その“呼びかけ”に耳を澄ますしかない。
なぜならその声は、自分の中にある何かを指し示している気がするからだ。
この曲は、明確な答えがない世界において、“問い”そのものの美しさと苦しさを描く音楽である。
そしてそれは今も変わらず、静かに、しかし確かに——私たちの耳元で、呼び続けている。


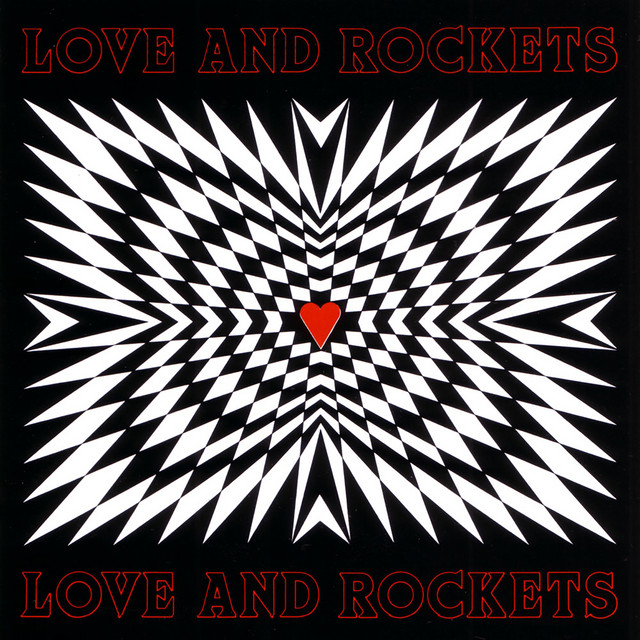
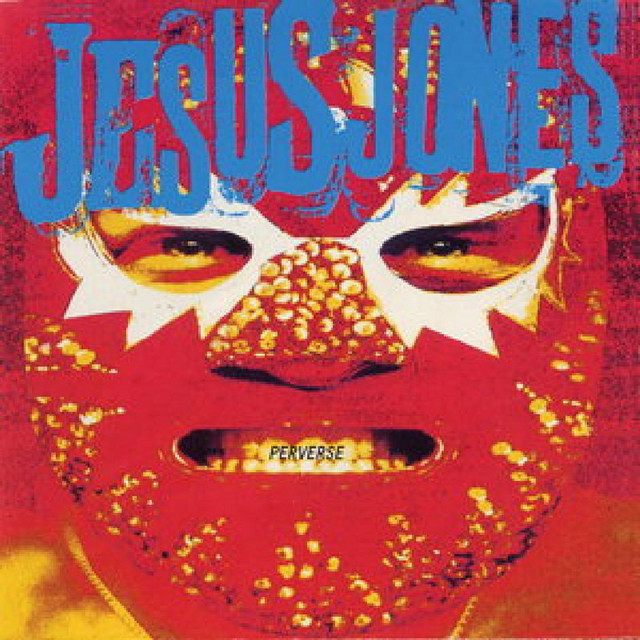
コメント