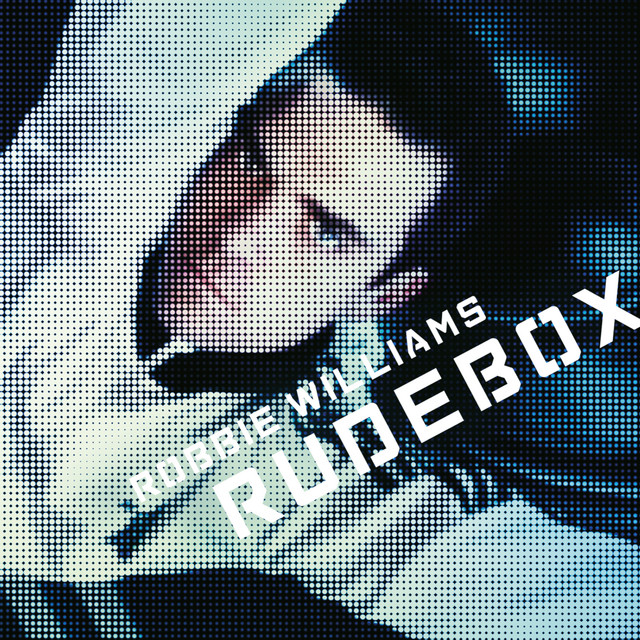
発売日: 2006年10月23日
ジャンル: エレクトロ・ポップ、ヒップホップ、ダンス・ポップ、シンセ・ポップ
概要
『Rudebox』は、Robbie Williamsが2006年に発表した7枚目のスタジオ・アルバムであり、彼のキャリアにおいて最も型破りで実験的な“問題作”にして、“挑戦作”でもある。
本作では、従来のポップ・ロックやバラード路線を大きく逸脱し、80年代シンセ・ポップ、ヒップホップ、エレクトロ・ファンクといった要素を大胆に導入。
音楽的には、Pet Shop Boys、Mark Ronson、William Orbitらとのコラボレーションにより、ダンサブルかつアンダーグラウンド感のあるサウンドを構築している。
タイトル曲「Rudebox」に象徴されるように、本作はロビーが“ロックスター”ではなく“ストリートの語り部”を演じるような構造を持ち、パフォーマーとしてのイメージを意図的に裏切る構成となっている。
商業的には前作『Intensive Care』の成功から一転して評価が分かれたが、その過激なリスクテイクと遊び心、そしてロビー特有の自己解体的なユーモアは、現在では再評価が進みつつある。
全曲レビュー
1. Rudebox
タイトル曲にして、エレクトロ・ヒップホップの混合物のような異色作。
ベースの効いたミニマルなビートに乗せて、ロビーが半ラップ的に自身の“箱=世界”を開陳。
そのダサさすらもアートに昇華した、クセになる先制パンチ。
2. Viva Life on Mars
80s風のスペース・ポップ。
デヴィッド・ボウイへの間接的オマージュを感じさせるSF的サウンドと、虚無と希望を往復するリリックが独特の浮遊感を生む。
3. Lovelight
Lewis Taylorのソウル曲をカバーした、洗練されたエレクトロ・ディスコ。
クールなヴォーカルと光を反射するようなシンセが、アルバム中もっとも“踊れる”一曲。
4. Bongo Bong and Je Ne T’aime Plus
Manu Chaoの2曲をマッシュアップした実験的カバー。
オーガニックなリズムとエレクトロの融合、フランス語と英語の混在という多国籍感が光る。
リリー・アレンとのデュエットも印象的。
5. She’s Madonna (feat. Pet Shop Boys)
“マドンナのような女は一人しかいない”というリリックに、愛と憧れと皮肉が混じる。
Pet Shop Boysとのコラボにより、洗練されたシンセ・ポップの真骨頂に仕上がった名曲。
まさにこのアルバムの隠れたハイライト。
6. Keep On
ファンキーなベースラインとコール&レスポンスが楽しい、ストリート感覚溢れるトラック。
“やめんなよ”というフレーズが力強く、ロビーの陽気さが前面に出ている。
7. Good Doctor
80年代TVドラマのようなチープなシンセに乗せて繰り広げられるユーモラスな語り。
ドラッグと狂気の比喩を含むカオティックなトラックで、混沌と享楽の象徴でもある。
8. The Actor
“演じている自分”への自己言及的ナンバー。
静かな語り口で、裏表のある人生を冷ややかに描く。
本作中もっともダウナーで詩的な瞬間。
9. Never Touch That Switch
エレクトロ・パンク的なサウンドで、“自爆スイッチを押すな”という不穏なテーマが浮上。
音の暴力性と内面の危うさが一体化した、サイケデリックな一曲。
10. We’re the Pet Shop Boys
My Robot Friendによるオリジナル楽曲を、Pet Shop Boysと共にロビーがカバー。
多層的なオマージュとパロディが交差する、“ポップ・アートとしての自覚”が光る実験作。
11. Burslem Normals
ロビーの故郷Stoke-on-Trentへの郷愁と皮肉を混ぜたトラック。
日常の陰影を描いたリリックとミニマルなサウンドが不穏に絡む。
12. Kiss Me
Stephen Duffy時代の曲をセルフ・カバーしたローファイ・ポップ。
ニュー・ウェイヴと80sの感触をまとう、甘く儚い一曲。
13. The 80s
“1980年代という記憶のカプセル”を、語りと回想で辿る異色トラック。
パーソナルな記憶とカルチャーアイコンが交錯し、回想という名のヒップホップ詩になっている。
14. The 90s
前曲の続編として、今度は90年代の自分――すなわちTake That時代を赤裸々に回顧。
ストレートな告白の中に、懐かしさと後悔が交差する。
15. Summertime
サイケ調のビートに乗せて語られる、緩やかな退廃とユートピア願望。
ラストにふさわしい、脱力と希望が同居した余韻のある曲。
総評
『Rudebox』は、Robbie Williamsが自らの“ポップ・スター”像を解体し、実験音楽家/ナレーターとしての自我を露呈した異色作である。
リスナーの好みを問わず、初聴では“裏切られた”と感じる者も多かったが、その大胆なジャンル越境、自己風刺、そしてDIY的感性は、ポップ・アーティストとしての成熟を示す重要な一歩とも言える。
商業的には波紋を呼んだが、Robbieが“予定調和を拒否し、混沌の中に飛び込んだ”という姿勢そのものが、このアルバムの最大の価値である。
今振り返れば、これは彼なりの“音楽でのエスケープ・ルーム”であり、キャリアの最深部に置かれた最も正直なポートレートなのかもしれない。
おすすめアルバム(5枚)
- 『Yes』 / Pet Shop Boys(2009)
『Rudebox』の知的ポップ路線に通じる洗練と遊び心が共鳴。 - 『Reality Killed the Video Star』 / Robbie Williams(2009)
本作の実験性を経て、再びポップに回帰した続編的な一作。 - 『Discovery』 / Daft Punk(2001)
80sへの愛と未来的エレクトロを融合させた名作。『Rudebox』と通じる精神性。 - 『Night Work』 / Scissor Sisters(2010)
セクシュアルかつシンセティックなポップセンスが似ている。 - 『Songs About Girls』 / will.i.am(2007)
ヒップホップとエレクトロの実験的融合という点で同系統。
ビジュアルとアートワーク
ジャケットでは、ネオンブルーの光に包まれたRobbieが、無機質かつクールな佇まいで写っている。
まるで“デジタルの仮面をかぶったロボット”のようでもあり、人間味と人工性の交差点に立つ現在の彼を象徴する。
『Rudebox』とは、その名の通り、“不恰好な箱”に詰め込まれた彼自身のラフでリアルな断片なのである。


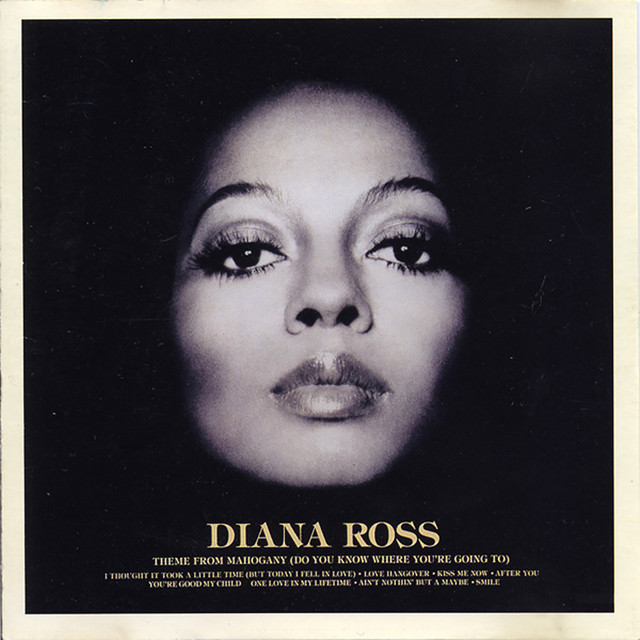

コメント